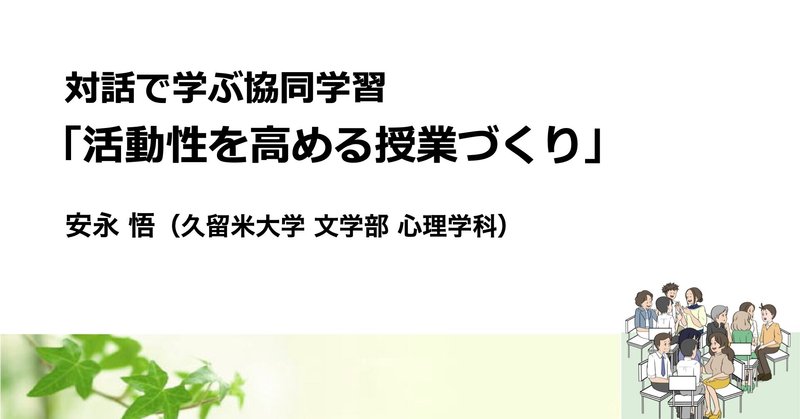
第2回 グループの編成と配置 (その4) 学生を信じて任せる
第2回「グループ編成と配置」(その3)に対する参加者からの返信が届きましたので紹介します。この返信に対する私のコメントは次回(その5)で掲載します。
*
第2回(その4)は引き続き千葉中央看護専門学校の玉木弘美が担当します。安永先生からの(その3)拝読しました。はっとするご指摘をいくつかいただき、本校の3人で話し合いました。そこでの新たな気づきは次の3つです。1つめは「学生の主体性を育てる機会を奪っていた」、2つめは「教員がグループ活動の『失敗』や『つまずき』を恐れていた」、そして3つめは「教員が『学生の主体性を育てたい』といいながら、学生の力を信じて学生の主体性に任せることができていなかった」ということです。
〇 学生の主体性を育てる機会を奪っていた
第2回(その2)で紹介したグループワークのルールですが、約10年前に始め、学生全員が主体的に、生き生きと参加できるようにと考え、学生の反応を見ながら毎年修正を重ねてきました。また学生への説明のしかたも練ってきました。数年前から現在の内容に落ち着き、継続して使用しています。安永先生から「学生が育てばルールの見直しを学生に任せ、最終的には自分たちで作ったルールを、教師がいなくても学生たちが主体的に守れるように」という助言をいただきました。学生を修正に参加させず、教員がとらえた学生の反応を一方的に教員が解釈し修正していたことに、はっとしました。学生がグループワークのルールづくりに主体的に取り組む機会を教員が奪っていたんだ!と気づきました。目が覚める思いをしました。
学生のためにという私の思いは独りよがりの押し付けだった、と気づきました。
〇 教員はグループ活動がうまくいかないことを避けたかった
今までは、当然のように、グループ活動が円滑に進むように、そして教員の期待通りの成果を得るために、グループ編成をおこなっていました。これはつまり、学生の予想外の発想や学びを恐れ、教員が安心できる編成です。
円滑なグループ活動のために、まずメンバーの中心となるリーダーシップの取れそうな学生、話し合いを活性化してくれそうな積極的な学生、確かな知識を持ち、方向性がズレないようリードしてくれそうな学生などを軸に、成績の良し悪し、積極性の有無などバランスよくと考えメンバーを編成していました。しかしそれは、学生の能力を成績やコミュニケーション能力、積極性といった教員の視点のみで決めつけていたといえます。ここには、はじめから成熟したグループを編成するのがよい編成だという思い込みがあり、未熟なグループを育てるという意識が教員に不足していました。
〇 何を学ぶのか、どう成長するのか押し付けていた
学生独自の考えや思考よりも、教員の「学んでほしいこと」「成長してほしい姿」が強すぎると「指導・助言」という名目で、あれこれと学生に指示を出し、考えを誘導しがちです。学生の考えをテーマからずれている、的外れであると感じ、否定的なメッセージを出していた可能性があると思い当たりました。
これまで、学生が教員の意図を汲み取り、教員の期待するいわゆる「正答」を探して、「答え」るのではなく「応え」ようとする場面がしばしばありました。これではグループ活動が生き生きとするはずがない、と気づきました。学生は「学びたい、学びが楽しい」という内的動機づけではなく、「教員に指導されるから、叱られるから」という外的動機づけで学習させられていたのだ、失敗を恐れ、失敗を避ける学生を育ててしまっていたのだと思いました。
〇 学生を信じることができていなかった
安永先生は「学生一人ひとりが担当課題を深く学ぶという責任感と、学んだ内容を仲間と共有する責任感をつよく意識することが大切」とおっしゃっています。私たちは、深く学ぶ責任と学びを共有する責任を学生が意識できるようにと想定していなかった(=信じていなかった)、そして、責任を感じて行動できる学生は、教員から見て「優秀な学生」だけと思い込んでいました。学生の変化や成長の可能性を信じることができていなかったのです。安永先生がおっしゃっている「あなたはグループにとって無二の存在である、といった事実を的確に伝え」るためには、教員が学生の力を信じていなければ決してできない、と気づかされました。
そもそも、学生を信じることとはどのようなことかを、以下のようにはき違えて捉えていたのかもしれません。学生に任せると、教員の予想外の考えや方法を示すことがしばしば起こります。その予想外の内容に、教員は「そこまで考えることができたのか」という驚きや喜びがもたらされることもあります。しかし、到達目標と方向性がズレる、低い到達度で学生が満足してしまうなど、教員が頭を抱えてしまうことも起こります。学生に任せてこのようなことが起こると、指導計画に不足があったのではと、教員が自分自身に落胆します。学生に任せてうまくいかなかった経験が「学生に任せること=無計画」という思いこみにつながっているような気がしました。
〇 グループワークを成功させるためではなく、グループを成長させるために
学生の力を信じ、学生に任せることを意識していくためには、教員にどのような力や姿勢が必要かを、今一度考えてみました。
1つは、学生の予測不可能な成長や、予想外の成長を学生とともに楽しめる力です。教員の計画通りの結果になることに縛られず、生き生きとしたグループ活動から得るものを大切にしていけたらと思います。どこのどなたの言葉かは忘れてしまいましたが、「生き生きとした生活には、失敗や衝突がつきもの」という言葉を思い出しました。失敗を「悪」とはとらえず、成長の過程であるととらえたいです。
もう1つは、教える、指示するだけの存在ではなく、失敗や衝突に学生自身が向き合い、乗り越える力があると考え、学生に伴走していく姿勢です。教員の期待通りにグループワークを成功させるのではなく、失敗や衝突の体験を肯定的にとらえ、グループを成長させることを大切にしていきたいです。
1年生の臨地実習が始まったところですが、個々の学生だけでなく、グループを育てることを意識してみました。自分が得た学びや感動を仲間と分かち合うこと、悩んだことについて互いに相談し意見を聞くこと、学習不足の点はひとりで取り組まず仲間とともに調べることを具体的に「提案」しました。教員に従うのではなく、自分たちにとって必要だと思ったら試みてほしいと伝えました。今までの実習指導では、「指示」をしていたので、学生たちは「教員の提案を受け入れるか否かは自分たちが判断する」ということに、はじめは戸惑った様子でした。そのため「今あなたたちが学びたいと感じていることと、教員が学んでほしいことが必ずしも一致するとは限らない。学びたいときが一番深く学べる最も良いタイミングなのでは?」と投げかけました。
その結果、教員の指示がなくても、自分たちで何を学ぶのかを考え、生き生きと学習するようになりました。自分たちだけの力で行き詰まりを感じると、教員に助けを求めに来ましたが、極力、解は示さず、調べる方法や新たな視点を提案するにとどめました。学生も、自分たちで学ぶことに喜びを感じている様子で、ヒントやアドバイスを求めては来るものの、「正解」は求めることが減ってきました。この学生はつまずくのではないか、手厚い学習支援が必要ではないか、と予測を立てて臨地実習指導に臨みましたが予想外の展開でした。学生自身に互いに影響を与え合い、変化・成長する力があるのだと改めて実感することができました。学生個人を育てるという視点から、グループを育て、仲間と共に育つ場を設けることの大切さを実感しました。
ここで、グループ活動での失敗は衝突を肯定的にとらえて、と述べましたが、安永先生の「学生がどの程度の課題に取り組んでいるのかを、科目を越えて把握しておくこと」の大切さを述べていらっしゃいます。科目を越えてグループ活動を行っているので、学生にとって、科目ごとに学習の場があることになります。教員によって失敗や衝突の許容範囲が異なると、戸惑ったり混乱したりする学生がいそうです。教員の顔色をうかがい、注意されることや評価されることを気にして生き生きとしたグループ活動に支障が出そうです。この点について、安永先生の助言をいただけたらと思います。よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
