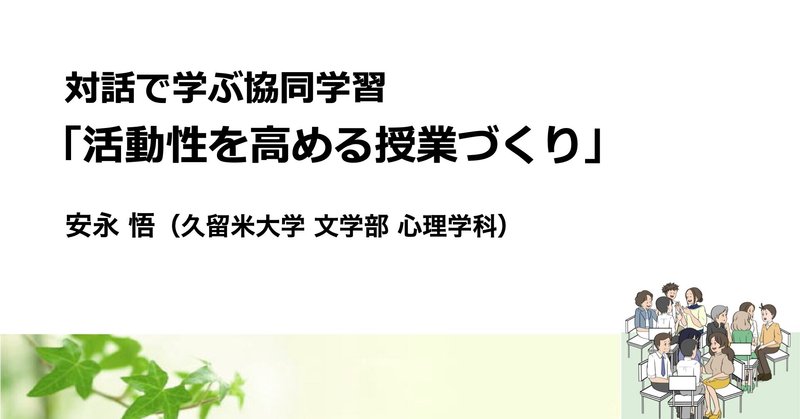
第2回 グループの編成と配置 (その2) 全員が参加できるグループを編成する
第2回「グループの編成と配置」(その1)に対する感想と質問が、参加者から届きました。この原稿に対する私の回答は次回(その3)で掲載します。
*
第2回は千葉中央看護専門学校が担当します。今回の担当は玉木弘美です。教員歴は17年目になります。担当は「精神看護学」です。正解がない問に悩み、考え続ける力を育てたいと考えています。この数年は学校評価を担当し、学生による授業評価が軌道に乗るよう尽力しています。また、自主的に「校内に花を活ける係」になり、花を通して教員としてだけでなく、人として日頃から学生と言葉を交わすことを心がけています。
第1回のセッションを拝見し、東京都立広尾看護専門学校のお二人の先生と同じように目からうろこ、という体験をさせていただきました。第2回でも新たな気づきを得る喜びを発見できたらいいなと思っております。
今回のテーマの「グループ編成と配置」について本校の担当3人で話し合ってみました。話し合う過程で日頃自分が何を考えてグループワークをおこなっているのか、振り返りました。その内容を安永先生に見ていただきアドバイスを頂けたら嬉しいです。
〇学生の背景は多様に、興味関心は同質に
安永先生は、異質なグループにより他者への理解が進み視野が広がる、とおっしゃっています。私たちもグループを編成するときは、年齢や性別、社会人経験、学力、コミュニケーション能力(発言力や調整能力など)の視点から同質のメンバーにならないよう、グループを編成します。多様な経験をもつ学生が集まったほうが、さまざまな視点や立場からの意見や質問が出るので学びも深くなると考えています。
ただ、低学年でグループワークの経験が少ない場合、自分の発言を否定されるのではと不安を抱いている学生が少なくないため、自分の興味や関心のあるテーマで集まれば、多少自信をもって発言しやすいのではないかとも考えています。そこで、グループワークでの到達目標は大きな(抽象的な)ものにしていますが、その大きなテーマをどの現象(小テーマ)から掘り下げていくのかは学生が選択できるようにしています。同じ興味関心のテーマで集まるため、モチベーションの差が減り、いわゆる「お客様」のような学生が生じにくいようです。また、教員がテーマを振り分けるのではなく、学生が選択するという自己決定のプロセスがあると自己責任の意識も生まれ、グループワークの過程で困難が生じても、やり遂げる、という意思をもちやすいのではないかと感じています。
以下に、1年生対象の科目「精神看護学概論」でおこなうグループワークの到達目標と学生が選択するテーマおよび期待される学びを示しておきます。
◇到達目標:日本の精神医療・看護の現状について、その背景と今後の
課題を明確にする。
◇学生が選択するテーマ: A 繰り返される精神科病院の事件
B 長期入院 C 自殺
◇期待される学び:
① 偏見や差別の背景および、患者・家族への影響を理解する。
② 精神医療・看護のマンパワー不足の原因と改善の手立てを考える。
③ 患者・家族・社会それぞれの思いやニーズを理解する。並行して、思いを
満たすこと、ニーズが充足されることの難しさを知る。
④ 上記の①~③を踏まえ、患者、家族、社会が看護師に期待しているもの、
看護師の責務は何かを考える。
〇全員が話し合いの場を安全であると感じ、生き生きと学べる場にしたい
私の授業「精神看護学」では下に示す「グループワークのルール」をA4判用紙に印刷し全員に配布します。徹底しています。
★グループワークのルール
1. 何を発言しても良い。ただし、根拠や理由も伝える。倫理的に適切か考え
責任をもって発言する。非難はしない。非難されない安心感をもてるよ
う、互いに配慮する。
2. 誠意をもって聴く。発言者の発言を途中でさえぎらない。
3. 「お喋り」ではなく「話し合い」をする。
4. 反対意見もきちんと言う。
5. 途中で考えが変わっても良い。
6. 全員が発言する。話すだけ、聞くだけにならない。メンバー全員が均等に
発言できるよう、全員が努力・配慮する。
学生には、緊張しやすい人や自信のない人も発言しやすいように、誰の意見にも参加者が耳を傾けることができるように、多様な意見を出せるように、とルールの目的を説明しルールを意識した話し合いを促しています。学生からは、非難しない、途中で意見が変わってもよいというルールがあると安心して発言できるという感想が多く聞かれ、一定の効果があると感じています。
それでも、話すことが好きな学生に発言が偏ったり、成績が良く自信のある学生の意見にメンバー全員が賛同し異なる意見や反対意見が出ないまま、活性化せず終わってしまうことも起こっています。事前の説明だけではうまくいかない、グループワークを展開しているときにも何か適切な支援ができないものか、そもそも与えるテーマに問題があるのか……悩むところです。
〇グループの再編について:ポジティブな意味の再編を効果的に行いたい
グループと、グループメンバーの成長をさらにステップアップさせるため、または所属していたグループの能力を新グループで新メンバーに伝授するための(ジグソー学習のようなイメージです)グループ再編をしたい、と思いますが、タイミングや方法、学生への説明など具体的な手段を考えようとするとなかなか難しいものがあります。
私のおこなっているグループワークでは、該当単元の1コマ目で数十分、2コマ目90分を当てています。授業時間以外の放課後にも自主的に2~3回程度集まって学習しているようです。テーマに関する意見交換のほか、調べる方法、まとめ方や発表の方法についても話し合っています。
短時間の話合いのグループ、何かを達成するグループ、それぞれの学習効果や教員の配慮すべきこと等について安永先生のアドバイスを頂けると嬉しいです。短時間の話し合いから、何かを達成する(作り上げる・到達する)話合いへのつなぎ方というか、それぞれの利点を課した教育ができたらいいなと思っています。
その他、困難を感じる要因の1つに、他教員も、それぞれ自分の授業でグループワークを行っていることが挙げられます。学生は授業科目ごとに異なるグループに所属しています。同日に別グループでグループワークをこなさなければならない日も少なくありません。科目によってグループメンバーが異なるので「頭が混乱する」という言葉をしばしば耳にします。科目ごとにグループ単位で取り組む課題を課せられることあり、放課後に集まる日程調整だけでも学生は疲弊しているようです。その中でグループを再編しようとすると、新メンバーとの関係を構築することなどにエネルギーを費やしてしまい、グループでの学習を楽しむ余力が減ってしまっているように思います。
教員間で話し合い、すべての科目で同じグループ編成にするという案も出ましたが、科目ごとに目標が異なれば、教員の意図も様々になり、なかなかうまくいっていない現状です。
安永先生の、グループ替えの際の学生への説明については、とても納得できました。グループを再編するときだけでなく、グループ活動が終了するときに、しっかりとクロージングを行い、学生が自分の、グループの成長や課題を整理できるようにしたいと強く思いました。教員が肯定的なフィードバックをおこない、達成感や協同学習の楽しさを再確認できる機会を作りたいと思いました。
〇座席やスクリーンの位置:環境について考えてみました
本校はすべて可動式教室なので、制約は少なく恵まれた環境であると思います。机とスクリーンの配置はもちろん、スクリーンに何が映っているか、教室の明るさ、時計の有無、教室に窓の有無なども影響があるように感じます。また、教員の立ち位置や学生との距離、教員の声の質や大きさ、マイクの使用の有無で学生に教員の指示の伝わり方や集中力、緊張感など様々な影響があるように思います。
特に、グループワークを行う教室の広さとは関連があると感じています。本校は教室の他、図書室や情報処理室も同じ棟にコンパクトにまとまっているので、授業時間中もグループごとに場所を選んで話し合うことが可能です。1つの教室でガヤガヤと話し合うことと比べ、他グループの声や動きに左右されにくく、自分たちのグループの活動に没頭しやすいようです。反面、このように恵まれた環境ですが、他のグループの話し合いの様子や進捗状況から刺激を受ける機会は乏しくなります。また、教員は各場所をラウンドしますが、話し合いの過程を把握することに限界があります。
学生が話し合いに没頭できる環境を生かしつつ、教員の目の届かないところ(目の届かない時間)で起こっている学生の学びや成長をどう把握するか、安永先生はどのようにお考えか伺えたらと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
