
マーケティング発想の基本「鳥の目、虫の目、魚の目」(ライオン:オーラルケア時代の記憶)
マーケティングだけでなく、ビジネスの基本として、多角的に市場を捉えることが重要である。商品やサービス、その顧客など対象に密着する視点「虫の目」、市場や周辺、さらには生活全般といった俯瞰した視野で眺める「鳥の目」、そして、時間の流れ、流行といった歴史的観点から眺める「魚の目」(”うおのめ”でない、さかなのめである)。
最後の「魚の目」、時系列で変化を捕まえたり、歴史的視点で潮流を把握するということを言っているのだが、これが意外と難しいと思う。企業で仕事をしていた時を思い出しても、自社の自事業の歴史を紐解くといっても、しっかりとしたデータベースがなかったりする。マーケティングや営業は、終わりのないPDCAの繰り返しだったりするから、次の世代に向けて、記録を残すという発想が薄かったりする。特に、失敗については隠したくなるのが人情である。
とはいえ、変化の激しい時代のマーケティングでは、潮流を読めないと致命的とも言える。ビジネスマンが歴史小説や歴史書に詳しい人が多いのは、そういう理由かもしれない。かくいう自分も、若い頃に読んだ「歴史からの発想(堺屋太一著)」はバイブルのように読み返していた。
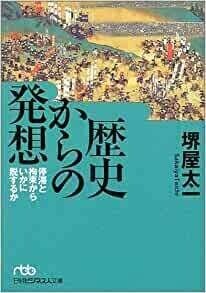
少し古い話になるが、1990年代前半、私がライオン(株)でオーラルケア事業部に所属していた時、「魚の目」を使って、市場や生活者の変化を探り、新しい戦略を立案していた時の資料を紹介しながら、何を考えてきたかを紹介してみたい。
カテゴリーの歴史を探れ
オーラルケア事業部に異動する前、リサーチ部門、当時は市場情報部という部署にいたのだが、そこで業務のかたわら、カテゴリーの歴史をまとめていた。資料が残っているので、紹介してみる。



こんな具合である。ネタ元は社史や業界紙、マーケティング本などであり、1960年代という日本のマーケティング創生期からの整理だったので、比較的シンプルな歴史なのかもしれない。「○○時代」とか「△△の戦い」などと自分勝手ではあるが、市場環境や競争戦略について考察をしていた。1980年後半の花王の「アタック」(コンパクト洗剤)発売以降、マーケティングでは後塵を拝していたこともあり、「魚の目」から逆転のヒントや機会を窺いたいという気持ちだったように思う。資料を集める時に通った社史編纂室で見つけた本で、コピーを今でも大事に持っているのは「花王対ライオン市場戦争(近藤礼一著)」である。
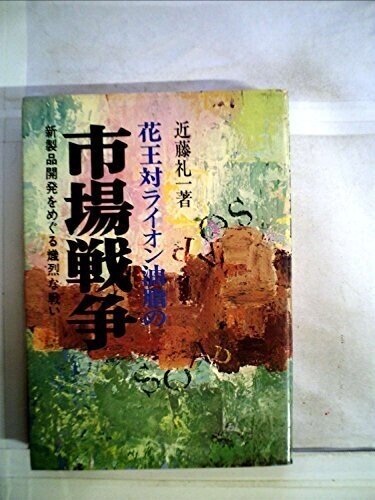
さて、オーラルケア事業に異動した際、事業部長も一緒に変わったため、現状を打破する中長期戦略を立案しようということになり、数名で中長期戦略チームを作ることになり、そこで戦略立案を担当した。
まさに、先に出したハミガキ市場歴史の「魚の目」視点を生かす場を与えてもらったのである。ライオンは今でもそうだが、オーラルケアではリーダーの地位にある。当時もそうではあったが、1970年代にハミガキシェア70%を超えた独占状況から1980年に入ると右肩下がりとなり、自分が異動した1993年頃にはシェア45%位になっており、社内的には危機感を強めていたのである。1970年代のシェア70%って、独占禁止法に触れそうな勢いだったわけである。
歴史を作ったポイントを探れ
1970年代のライオンのオーラルケアは、4大セグメント戦略を展開し、ニーズ毎にブランドを配し、盤石の布陣を完成させていた。マーケティングの本でも割とよく紹介されている。代表的なものとして、「実践ブランドマネジメント戦略(平林千春著)」を挙げる。そこに出ているライオンのハミガキのブランド構図を次に示す。

ハミガキに関するニーズを大きく、美白、歯周病(実は歯周病というコトバを広めたのはサンスターGUMであり、当時ライオンは歯槽膿漏とカテゴライズしていた)、虫歯、そして口臭の4つのケアである。それぞれ、ホワイト&ホワイトライオン、デンターライオン、クリニカライオン、エチケットライオンというブランドを発売し、それぞれのニーズをライオンブランドで席捲したのである。
まさに1980年代までは、「4大セグメント時代」と呼んでよかった。ところが、1990年に入ると、花王「クリアクリーン(ツブが歯垢を落とす)」、サンスター「G・U・M(殺菌で歯周病予防)」といった新製品が登場して、4大セグメント戦略にほころびが生じ始める。先の歴史年表で見ると、「新概念登場」と分析している。4大ニーズでは括れない切り口が登場している。”歯垢除去”や”殺菌”というキーワードが、その新概念と言えるかもしれない。(今ではオーラルケアの当たり前になっているが、、、)
歴史の変曲点を見極めろ
そんな中、オーラルケア市場に黒船がやってくる。サンギ「アパガード」である。当時のハミガキでは破格の高価格設定で、「芸能人は歯が命」という飛び道具のようなキャッチフレーズで、いきなり10%を超えるシェアを奪い取っていった。ここでの新概念は、”パーソナルで高価格”ということだったかもしれない。

ライオンの先人が打ち立てた「4大セグメント」に綻びが生じたことを実感したわけであるが、そうは言っても、この4大セグメント戦略は本当にすごい戦略だったと感じているのが、アパガードという化け物商品の勢いを20%を超えさせずに食い止められたことである。新興勢力とは言っても、アパガードは美白を訴求していて美白セグメントに位置づけられ、その壁がそれ以上の浸食を防いだと私は思っている。攻撃力は失っても、防護力はまだ十分有していた戦略だったと振り返りたい。
さて、歴史から何を学んだか、それを次にどう生かすかが戦略となるわけであるが、自分たちの作った「4大セグメント」戦略が通用しなくなってきたという分析の上、次を攻める切り口を探すことが必要となる。
前の歴史を踏まえて次の歴史を描け
我々が考えた次の青図(ブループリント)を示す。

従来の4大セグメントが市場を横に展開するニーズ分類で作られたものだったと解釈し、これからの時代は、縦に立体的に階層的に市場が進化すると予測して、下から「ベース市場」「+α市場」「ニューバリュー市場」と命名し、ライオンの主戦場が「ベース市場」だったものを、これからは上の市場攻略を目指すものとしたのである。
実際に、その後、市場は縦方向に大きく動いていったと思う。その中でライオンも、「ミクロクリーン」「キシリデント」「クリスタ」「デンターシステマ」「クリニカアドバンテージ」「クリニカNEXTSTAGE」「デントヘルス」「NONIO」といった縦に進化させる新商品を導入していくこととなったのである。
当時を振り返ると、「魚の目」で市場や生活者を分析することで、それまでの強みであった自社のヨコの戦略の限界を読みとり、時代がタテ方向に移行していると分析することで、事業の方向をヨコ→タテへと変換させることができたかなと思っている。最後に、戦略の視点の変化を訴えたシートを貼っておく。(古い話で恐縮でした!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
