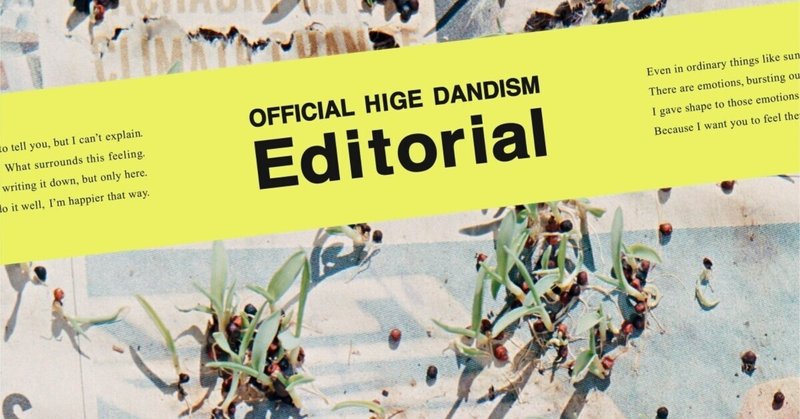
Official髭男dism / Editorial

邦楽ウィーク5日目。今を時めくOfficial髭男dism(ヒゲダン)の「Editorial」を聴いてみます。名前は当然知っていますが、きちんと聴くのは初めて。
Official髭男dism(オフィシャルひげだんディズム、英: Official HIGE DANdism)は、日本の4人組バンド。2012年に大学のサークル仲間を中心に結成され、2015年にインディーズデビュー。2018年、インディーズアーティストとして初の月9ドラマ(コンフィデンスマンJP)の主題歌「ノーダウト」を手掛け、ブレイクします。その後メジャー(ポニーキャニオン)に移籍し、破竹の快進撃を続けています。
先日、かなり久しぶりにカラオケに行きました。そこで何曲も歌われて、メロディ展開が大仰でなかなか盛り上がり感があるなと思って興味を持ちました。めまぐるしい展開ながらしっかり歌えるメロディがあるし、実際に履歴を見たらかなり歌われている。2021年のJ-POPの中心に位置しているバンドの一つでしょう。それでは聞いてみます。
活動国:日本
ジャンル:J-POP、ポップ・ロック
活動年:2012年ー
リリース:2021年8月18日
メンバー:
藤原聡(ボーカル・ピアノ)
小笹大輔(ギター・コーラス)
楢﨑誠(ベース・サックス・コーラス)
松浦匡希(ドラムス・コーラス)

総合評価 ★★★★☆
メロディが良かった。やはり盛り上がる。なんというか北欧的、欧州的な次々と盛り上がる、マイナーコードとメジャーコードが移り変わる曲が多く、サビが長く続く、というか、ヴァース、ブリッジ、コーラスと間断なく盛り上げ続ける、上昇していくような曲が多い。単発の印象に残るサビ、というより、1番、2番全体で盛り上がっていくというか。コーラスが長くてかなり展開していくような曲が多い。
個人的にはこういう展開はドイツやフィンランドのメタルバンド(ビーストインブラックとか)のメロディ展開にも近いものを感じた。音像は全然違うのだけれど、メロディ展開的には好み。まぁ、スティーヴィーワンダー(に影響を受けたと本人たちは言っている)と言われたらそうなんだけど…なんか盛り上げ方がパワーメタル感があるんだよなぁ。音のコテコテっぷり、音数が多い感じがそう感じさせるのかもしれない。
あと、編曲もけっこう凝っている。なんというかプログレ的な楽器隊の絡み合いもあって、ちゃんとバンドサウンドになっている。惜しいところは音響がやや一本調子なところ。全部ボーカルが主体になりすぎていて、けっこう実験的なこととか楽器隊のアレンジが凝っているのに後ろの方に収まっている。もうちょっと実験的な音響の曲もあってもいいのになぁ、音の隙間と重ねるところのダイナミクスを増やしてもいいのになぁ、とは思ったりもした。とはいえ、とても良質で流石多くの人に受け入れらるだけの魅力を感じたし、聞いていて心地よかった。カラオケで歌いたくなる気持ちが分かる。歌えたら気持ちいいだろうなと思う。コーラスに至るまでのメロディの流れがよくできていて、且つ、長時間かけて盛り上がっていくから気持ち良い。
M1. Editorial ★★★★
アカペラ、オートチューンで補正されたロボットボイス的なハーモニーからスタート。エレクトリックゴスペル、日本人的な端正なハーモニー(たとえばハーレムの黒人によるエネルギー溢れるゴスペルに比較して)をさらに電子化して音を精緻に整えた感じ。あまり聞いたことがない音(ありふれていない)で、アルバムのオープニングとして期待が高まる(ゴスペラーズとか、そのあたりにはあるのかもしれないがあまり聞いていないので個人的に新鮮)。イントロで、アカペラだけの小曲。
M2. アポトーシス ★★★★
さすが、プロダクションがいい。一つ一つの音がしっかり粒が立っている。オリヴィアロドリゴが使う落ちていくような、落下音のようなデジタルなベース音が使われている。ただ、あそこまで落下感が強くはないが。解放感があるボーカルライン、短調と長調を行ったり来たりする。面白いメロディ。いかにもJ-POPなのだけれど、こういう音程移動はなかなか珍しいよね。世界的に見ると、、、コード展開の感じがフィンランドが少し近いだろうか。ただ、裏声が混じるのはどこから来たのだろう。もともとブリティッシュトラッドって声を急に裏返したりするんだよね。それがブルーアイドソウルに変わっていって、それがJ-POPにも影響を与えたのだろうか。ニグロアメリカン、黒人音楽系の裏声とは違う、影響は受けているけれど、J-POPはそこから直接ルーツはなく、UK経由なんじゃないかなぁ。ニューウェーブとかの時代。うーん、それともUSのブラックコンテンポラリーなのかなぁ。両方だろうか。話を曲に戻そう。裏声も多用しながら展開していくJ-POP的壮大なバラード。ただ、音はいろいろと遊び心があってシンセの音や、変拍子っぽさもありプログレッシブロック的な音像になっている。これも北欧プログレ、シンフォ系プログ的なアレンジといえばそうだなぁ。フラワーキングスあたりが使いそうなシンセ音、ややレトロなシンセ音が後半ずっとなっている。これ、ジョンアンダーソンが歌えばYESっぽくもなるかも(追記:インタビューを見たら”スティーヴィーワンダーからの影響”とあった、ああ、そっちか、じゃあソウルからも直接なのか)。
M3. I LOVE... ★★★★☆
この曲は聞き覚えがあるな、音作りは前曲とほぼ同じ、やや変拍子というかジャジー、シンフォプログレ的なビート、そこにボーカルが乗る。うーん、最近のYESというかトレヴァーホーン? バグルス的な感じがある。シンセ音とビートのバランスかなぁ。ちょっと音は軽め。だけれど、バンドアンサンブルは意外と凝っている。音作り的にちょっとボーカルが前に出すぎている(個人の好み)的な気もするが、違和感まではない。ちょっとヴォコーダーで加工された声、節回しが入る。こういう節回しを入れるのは日本的アイデンティティでいいと思う。丁寧に上昇していくメロディ。
M4. フィラメント ★★★★☆
ギターサウンド、ディレイがかかった空間的なギターのシーケンスから四つ打ちのビートが出てくる。四つ打ちはやはりプリミティブなダンス感覚がある。うーん、もうちょっとディストーションというかノイズがあればいいのになぁ。メロディは高揚感があるのだけれど、ちょっと物足りなさはある。(メジャーデビューしてしばらくして漂白された)バンプオブチキンみたいな感じもあるな。そういえば、藤原基央のメロディセンスは最初は衝撃だった。天体観測は凄く新しい感じがしたものだ。あの頃からJ-POPのメロディは変わっていったかもしれない。サビが長い、というか、ヴァースからブリッジ、サビに向かってずっと盛り上げていく、みたいなつながりのあるメロディというのは新鮮だった。この人のメロディセンスにも近いものがある。ヴァースからずっと盛り上げていく。この曲はハードロック的なアレンジだったらカッコいいだろうになぁ。
M5. HELLO ★★★★☆
ちょっとロックテイストの強まった曲。ただ、シンセのキラキラ目の音がメインになってくる。ボーカルが入ると弾む、ソウルな感じ。ああ、スティーヴィーワンダー感といえばそうだな、マイケルジャクソン(オフザウォール以前)でもいい。コーラスに入るところでマイナーコードを入れるのはうまい。フィンランドのビーストインブラック的な、「サビのメロディが長い間展開していく」感じがある。これ、サウンドスタイルをメタルにしたら盛り上げる曲になるぞきっと。まぁ、別にヒゲダンがやらなくてもいいのだろうけれど。うーん、メロディには北欧ポップス感があるなぁ。そういえばフィンランドは「フン族」のフンからフィンが来ている。ハンガリーもそう。あのあたりは語圏が日本とも共通しているんだよね。何か音楽的琴線も近いものがあるのだろうか。北欧ポップスといえばABBAだが、ABBAはスウェーデンだからちょっと違うんだよね。もちろん影響はあるのだけれど、フィンランドのセンスは好き。で、このバンドにはフィンランド的なものを感じる。ああ、後半のメロディ展開もいいなぁ。ちょっとバンドサウンド、バックの演奏が今一つダイナミックさに欠けるのが惜しい(今までの曲では一番ダイナミズムがあるが)。
M6. Cry Baby ★★★★☆
ハキハキしたリズム、しかし、いろいろ書いているが予想よりはバンドサウンド。各楽器のアレンジも凝っているし、最初にプログレッシブロック感がある、と書いたが、そういうバンドアンサンブルの妙はしっかりある。そこまでスリリングではなく、だから”最近の”YES、なのだけれど。70年代、80年代の鬼気迫るインタープレイではなく、編曲は凝っているけれどどこかイージーリスニングポップ的なYESの絶妙なバランスの感じ(というか、ヒゲダンを聴く層がどれだけ”最近のYES”といって音像を連想するのだろう、と書いていて思った)。なお、メロディ展開はこちらの方がはるかにスリリング。厚みのあるシンセ音が空間を埋めている、けっこうベースも暴れている。サービス精神あふれるいいメロディ、丁寧に丁寧に、長いサビで盛り上げていく。ドラマティック。
M7. Shower ★★★★
アコースティックな音像だが、ビートは変わらず弾むような、ソウル、ポップソウル的なビート。激しい上下移動を繰り返すボーカルメロディ。この辺りはカラオケ文化というか、「歌うことの技巧性」と「歌うことでの気持ちよさ」を感じさせる。こういう曲って歌えると気持ちいいよね。こういう激しい音程移動が心地よい、と感じるのは中央アジアに共通する感覚な気がする。一番顕著なのはトルコポップスとJ-POPだと思っていて、音程移動が激しい。トルコはさらに節回しも独特だけれど。日本はいわゆる”こぶし”は排除される方向で、声は素直に、ロック的に、あるいはソウル的に伸ばすことが流行している。この辺りはグローバルポップの影響だろう。コードが次々と変わっていく。
M8. みどりの雨避け ★★★★
電車が走る音、AMラジオ的な音質のメロディ、そしてアコースティックなバンドコンボが入る。ちょっと郷愁的な、ジャズコンボ的な音像。これはベースの低音が効いている。音数が少ないからだな。シンセが空間を埋めない分、ベースの低音が支えている。ゴスペル的コーラスが入ってくる。けっこう音を足すなぁ。もうちょっとシンプルなまま行く曲があってもいい気がするが。この辺りはUKの感覚にも近い。Take Thatとかも音数めちゃくちゃ盛るしね。サービス精神なのだろう。けっこうUSはスカスカの曲はスカスカのまま行ったりする。一つ一つの音のキャラクターが立つ、というか。こちらはさまざまな音が入っていて、それはそれでゴージャスな感じはする。
M9. パラボラ ★★★★☆
静か目のヴァースからどんどんどんどん盛り上がっていく曲、コーラスに至っては四つ打ちになる。ベタだがここまでの加速具合がすごくてテンションがあがる。これは編曲がうまいな。でも、これ歌メロだけ聞くとパワーメタルというか、メタルの音像にしたらめちゃくちゃ正統派パワーメタルだよね、歌い上げるし。なんというか欧州ポップス、北欧メタル(フィンランドメタル)感が凄い。別に、まったく、影響は受けていないと思うのだけれど、何か似たルーツなのだろう。脳内でツインリードとザクザクしたギターリフを補完するとゴリゴリのメタルになる。なんだろう、ドイツ的でもあるのかなぁ。ドイツだから、クラシック、中世以降のクラシックの中心地で(シェーンベルグみたいな無調、不協和音になる前の時代)、そこで大仰に盛り上げていく手法、クラシック、オペラ的なコード進行やメロディセンスがルーツなのだろうか。歌のメロディだけで集中力を持続させる、気を引き付けるような構成になっている。その分メロディは展開が早い。
M10. ペンディング・マシーン ★★★★★
最初、盛り上がるアカペラのコーラス、ここからディスコサウンドに。ベースが効いている。ハキハキしたコーラス。ループするシーケンス。ノリが良い曲。ボーカルが熱量を増してくる。これは軽やかな音像があっている、浮ついた、上昇感のある、ひたすら中高音に音域が集まっている感じが曲に合っている。ベースは効いているが低音を効かせるよりは弾む感じが強い。個人的には一番テンションが上がった曲。
M11. Bedroom Talk ★★★★
お、雰囲気を変えてバラード、ブルージーなリズム。ブルージーといっても上田正樹とかやしきたかじんとか、ああいう関西バラード的なある程度軽やかなリズム。ポップブルース。
M12. Laughter ★★★★
ややグランジーな、けだるいギターサウンド。とはいえ、かなり後ろの方で鳴っていて、ボーカルが主役。シューゲイズのようにギターサウンドが前面に出てくるわけではない。これ、アルバム全体としてはかなり曲調もバラエティに富んでいるのに、音響が全部ボーカル主体になりすぎているのがちょっと惜しい。もう少し曲によってメリハリがあってもいい気はするけどなぁ。J-POP、ヒットソングの範疇でもう少し冒険はできる気もする。これだけ演奏が凝っているのに勿体ない気もする。まぁ、ラジオとかメディアで流れたときのバランスとか、他の曲との整合性を考えると仕方がないのかもしれないけれど。どの曲もクオリティは高くメロディもアレンジもいいのだけれど、音響的にややワンパターンで流れていってしまう。その「流れていく」ということを重視しているのだろうから的外れな指摘かもしれないが。
M13. Universe ★★★★☆
ピアノとボーカル、弾むようなボーカル。ところどころユニゾン、シンコペーションが入る。きらびやかなショー、エンターテイメント間のある音。丁寧にアレンジされたビッグバンドな音像。派手できらびやか。
M14. Lost In My Room ★★★★
しっとりした、ギター弾き語り的な。ジャックジョンソン、いや、瑛太の香水、といった方が通りがいいか。ああいうタメがあるギター弾き語りでよく使われるタメのリズム(香水よりはだいぶテンポが遅いが)。コーラスでは裏声になり浮かび上がる。浮遊感がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
