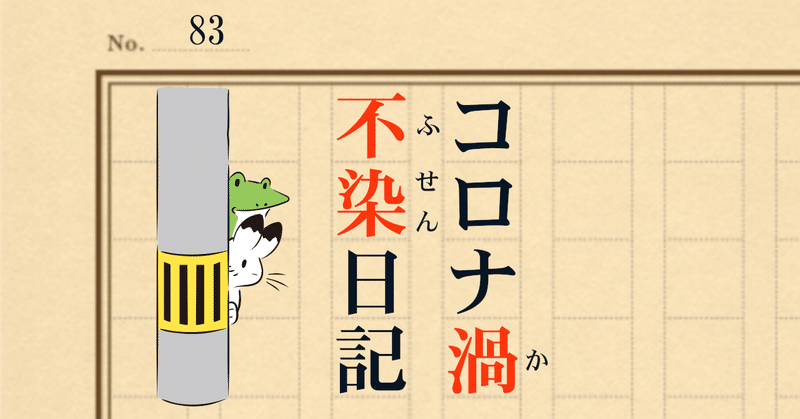
コロナ渦不染日記 #83
十二月十九日(土)
○朝一番で、姪うさぎのおむつを換え、妹うさぎが朝食をとる間、抱いて、あやす。たまに、片頬をあげて、ニヒルに笑うのであるが、当然、彼女に「笑い」の意味などわかっておらぬ。それでも、笑うのは、まわりの存在がそうしているからである。とするならば、妹うさぎの家庭は、なんだかんだで笑みを見せることができる家庭であると推測できる。そのことが嬉しい。
○姪うさぎをあやし、妹うさぎの話を一方的に聞きながら、相棒の下品ラビットと手分けして家事をこなすと、もう昼になっている。巣穴ちかくのパン屋でパンを買い、交代で食べたあたりから、眠けが襲ってきた。部屋にひきあげ、布団にくるまる。
次に気がついたのは、日が暮れる直前であった。
○もうじき、クリスマスである。例年は、ぼくと下品ラビットの二匹で、ささやかに祝うようなかたちになっているので、彼のためのクリスマスプレゼントのめあてをつけに、浜に出かける。
○ひとりで浜を歩いていると、いろいろなことが思い出される。それは、このあたりの予備校にかよっていたからである。駅前の立ち食いそば屋でコロッケそばを食べたり、ゲーセンの裏路地にたむろしたり、カラオケではしゃいだり、CDショップの「交流ノート」で仲良くなった、同世代の若者たちと、市民センターの一室を借りて、勉強会とは名ばかりの、うかれた時間をすごしたものだ。
○特に、CDショップの交流ノートは、その店が、当時はやっていてた、あるゲームのロケ地になっていたこともあり、そのゲームが好きな老若男女が集まって、年齢や性別を超えたコミュニティができあがるきっかけとなっていたことからも、わすれがたい。ゲームのファンが集まるようなノートだから、いわゆる「イラスト交流ノート」ともなっていて、なかにはなん人か、同人誌を作成して配布しているものもいた。とうぜん、オフ会なども行われた。ぼくも、そのオフ会に参加して、同人誌に参加したり、コスプレイヤーの女の子にかた思いをしたりしたのだった。
あれはその年のクリスマスだったろうか、ぼくは、意中の、コスプレイヤーの女の子をなんとか口説き落として、一対一のデートにまでこぎつけたのだった。(もはやとおい時のかなたの出来事で、どこへいってなにをしたかすら覚えていないが)精いっぱいめかしこんで待っていると、その女の子は、赤いダッフルコートの前を、ぴっちりとめた姿で現れた。そして、物陰にぼくを誘うのである。ドキドキしながらついていくと、彼女はおもむろにコートの前を開けて、したに着ていたコスプレ衣装を見せて、こう言ったのである。
「ぜんぶ洗濯しちゃって、これしか着てこられるものがなかったんだ」
いまでも、どうにも解釈をしかねる、不思議な、しかしそれだけに忘れがたい思い出である。
結局、その女の子とはうまくいかなかったので、千に一つも、脈があったとは思えないが、万に一つくらいは、好意のあらわれであったとは思っていたい欲目が、いまもあさましく残っているのだろう。
○昼食に、駅前の立ち食いそば屋で、思い出のコロッケそばを食べた。記憶にある、じゃがいもだけの安コロッケではなく、コーンやにんじんの刻んだのが入っている、野菜コロッケに変わっていた。あのころのコロッケはもう戻らない。

○結局、これはというものは見つからず、プレゼント探しは、来週に持ち越しということにした。
○本日の、全国の新規感染者数は、二九八九人(前週比-四八人)。
そのうち、東京は、七三六人(前週比+一一六人)。
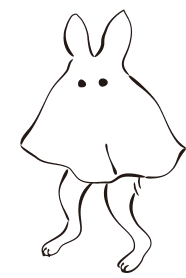
十二月二十日(日)
○野田サトル『ゴールデンカムイ』二十四巻を読む。
前巻にひき続き、終盤にむけて、各陣営の確認や再編成が行われる巻で、物語的におおきな動きはない。しかし、この巻のなかほどにある、主人公「〈不死身の〉杉元」の過去のシーンは、もしかすると、この作品の根幹をゆるがしかねないほどのおおきな動きであった。簡潔に述べれば、このシーンで行われるのは、主人公のひとりである「〈不死身の〉杉元」の、行動原理の再設定である。しかも、物語が変化を内包するものである以上、必然的におこる再設定ではなく、すでに語られた事実を改変しての「再設定」であり、いわゆる「あとづけ設定」である。
この手の「実はこうだった」は、通常、慎重に行わなければ、物語が瓦解する危険性すらある。もちろん、野田サトル氏と制作陣は、そこは慎重に行なっているが、では、なぜそんな危険をおかしてまで、このような再設定を行うかといえば、それはこの物語の背景に決定的な要素として横たわるもののひとつであるところの「杉元の一家を襲った悲劇」が、二〇二〇年という年に起こった、「新型コロナウィルスの流行」とかさなるものだからである。
○『ゴールデンカムイ』の主人公のひとりである、「杉元佐一」は、日露戦争の地獄を生き延びて、〈不死身〉の二つ名でよばれる陸軍兵士である。その出兵には、一家を結核で亡くして、彼ひとりが生きのびたのであるが、結核の流行をおそれた当時の人々がとりうる、精いっぱいの感染流行防止策として、生家を焼かれ、「病気者を出した家の生き残り」として、村に居場所がなくなったという理由がある。軍隊以外に行き場がなかったのだ。
二十四巻で、ある人物に、この冒険の目的を問われ、杉元が思い出す過去は、この「人を死なせる感染症」が存在する世界で、苦しみながらも生きていかなければならなかったときであり、そうした苦闘のさなかにふりしぼられる「なけなしの勇気と抵抗」を、「不死身」として位置づける。
この物語が語られ始めた二〇一四年には、「結核に感染して家を焼かれ、村八分にされた」という杉元の過去は、「明治〜大正時代に軍隊に入った人物の悲劇的な背景」として、妥当なものであるという以上のものではなかったように思う。当時には、六年後に世界的規模の流行となる、新型ウィルスの感染など、予見しえなかったはずである。だが、そういう時代になったいまだからこそ、この設定は、語られるべきであるし、再設定される必要がある。
いま、この時代に、この物語を読むひとは、すべからく、杉本とおなじく、「自分は不死身だ」と自分に言いきかせる人々だからである。しかも、それは、自分のためではなく、自分が背負い、守りたいと願う、愛する誰かのためなのである。
○夜は岬に移動し、イナバさんと飲む。クリスマスカラーの鍋をつつく。

○本日の、全国の新規感染者数は、二四九一人(前週比+一〇七人)。
そのうち、東京は、五五六人(前週比+七六人)。
参考・引用文献
イラスト
「ダ鳥獣戯画」(https://chojugiga.com/)
いただきましたサポートは、サークル活動の資金にさせていただきます。
