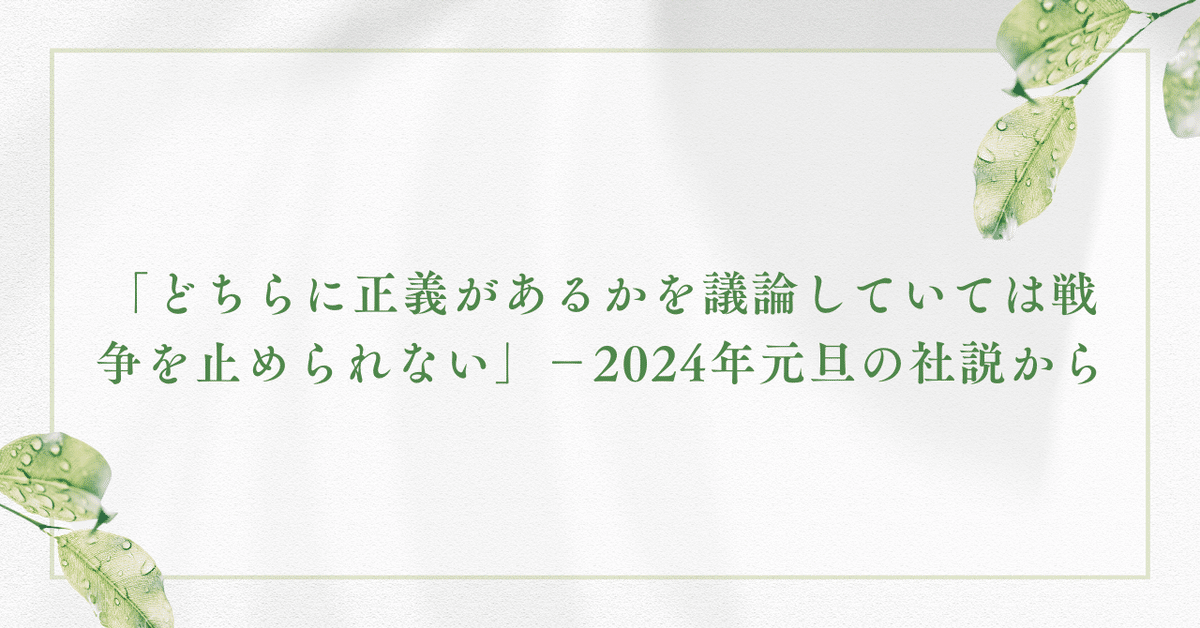
「どちらに正義があるかを議論していては戦争を止められない」ー2024年元旦の社説から
2024年元旦の全国紙5紙のうち4社が国際政治をテーマとしました。印象に残った部分を切り抜きました。
日経新聞は対話の重要性を強調しました。
”ウクライナでの戦争の出口は見えずもうすぐ2年になる。昨年10月、イスラム組織ハマスのイスラエルへの越境攻撃で始まった紛争も越年した。これらは、ある日突然、武力で平和な日常が破壊され、戦闘が始まると、簡単には収拾できなくなる現実を世界に見せつけた” として”問題が多いほど首脳間の対話の重要性は増す”
いったん紛争が始まれば長期間に及ぶとの分析を朝日新聞は紹介しています。
”スウェーデンのウブサラ大学の分析によれば、冷戦終了後に着実に減りつつあった武力紛争は、2010年を境に増加に転じた。直近の集計では世界で進行中の紛争は187に達している。いったん起きた紛争は8~11年続くことが多いという。”
”2010年といえば、米国はオバマ政権の1期目。リーマン・ショックによる不況が尾を引き、米国の対外政策が一気に内向きに転じた年である。パックス・アメリカーナ(米国による平和)の陰りは隠しようもない”
”冷戦後の国際秩序は根底から揺らぎ、「警察官」を失った世界は不安定化した。抑え込まれてきた緊張関係や、先進諸国から忘れ去られていた地域紛争が、相次いで「着火」した。”
紛争に対して国際社会はどう対応すべきなのか。以下は毎日新聞からです。
”思想家の内田樹氏は「どちらに正義があるかを議論していては戦争を止められない。いかに停戦し、死傷者を減らすかが最優先だ」と指摘する。国際社会に求められているのは一人でも多くの命を救うための迅速な行動である。”
”国連大使を務めた後、国際司法裁判所(ICJ)裁判官・所長として国家間紛争の法的処理の任にあった小田和恒氏は「国家の武力ではなく、国際世論が規範的な『力』となるには、国際組織が強くならなければいけない」と説く。”
”国家の暴走に歯止めをかけるのは「法の支配」である。戦争によらずに紛争を解決するICJの権限拡充が必要だ。国連総会と事務総長の関与強化も求められる。病院攻撃の全面禁止を検討すべきだ。”
読売新聞は日本の取るべき対応について次のように指摘しました。
”他国と一度も戦火を交えたことはなく、軍事的な脅威を与えたこともない。防衛力の強化でも、自衛と脅威の抑止、国際平和への貢献という目的を厳守してきた。”
”そうした実績を踏まえて、平和の大切さ、人命の尊さを世界に訴え、休戦、停戦、そして平和の回復と新しい秩序作りを呼びかけることが、日本の使命であろう。”
また、産経新聞は次のような見解を示しました。
”平和のため抑止の努力が欠かせない。それには日本が国際情勢に能動的にかかわる必要がある。”
”強烈な個性のトランプ前大統領が当選すればウクライナでの戦いがロシア優位へ一気に傾くかもしれない。日本の安保環境の激変もあり得る。次期大統領が台湾防衛の強い意志を示すのか、日本や台湾が前面に立ち防衛するよう促す「オフショア・バランシング」に傾くのか。後者であれば−そして日本が中国に従属したくないなら−日本は米核戦力の日本配備や核共有、核武装の選択肢を喫緊の課題として論じなければならなくなる。”
一方、東京新聞は気候問題や自民党の政治資金パーティーの裏金問題を採り上げ、米国上院議員を務めたジェームズ・クラークの格言を伝えました。
”「今」の世代が欲望を満たし、便利さを享受するために、病んだ地球を押しつけられることになるのは「未来」の世代で、「今」の世代がコストを最小化、利益を最大化できる代わりに、「未来」の世代が損害や賠償に苦しむー。子孫の視点に立って考えるなら、こんな理不尽な話はありません。”
”<政治屋(ポリティシャン)は次の選挙を考え、政治家(ステーツマン)は次の世代を考える> ”
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
