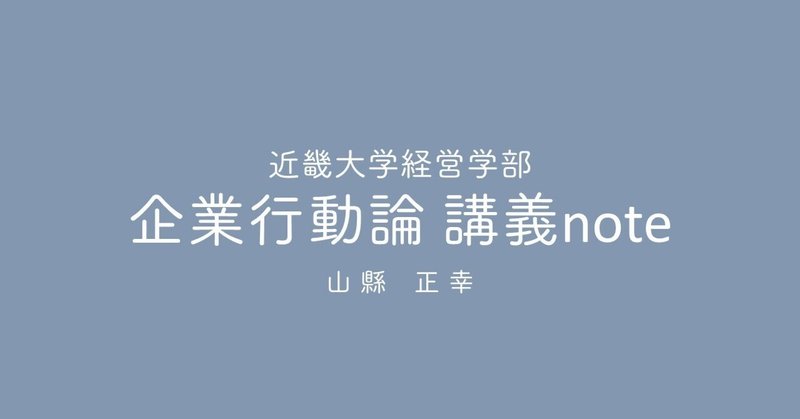
企業行動論講義note[05]「ひとは、一人だけで何かをなしとげることは難しい:協働するとはどういうことか」
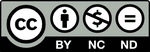
この内容は、第1講の〈その5〉もしくは第2講〈その2〉に当たります。講義の進み具合で変動します。
なお、このnoteはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス「表示-非営利-改変禁止」です。
みなさん、おはこんばんちわ。やまがたです。
今回は、[04]「よりよい交換を実現するためには、どうすればいいのか:発見プロセスとしての競争」の続編です。
前回の講義noteでは、価値創造を実現 / 成就する際に〈競争〉が生じるということについて、お話ししてきました。競争って、たしかに大変です。けれども、それゆえにこそ新しい意味や価値を生み出します。
では、〈競争〉のなかで「よりよい交換」を含んだ価値創造を実現 / 成就しようとするとき、何が必要になってくるのでしょうか。
一つは、企業者的姿勢(entrepreneurship)*です。これについては、後の講義で採りあげます。
* entrepreneurshipという言葉は、「起」業者能力とか「起」業者的姿勢というように「起業」というニュアンスで用いられることが少なくありません。ただ、企業行動論の講義においては必ずしも会社を立ち上げるということに限定していません。むしろ、今まで見出されていなかった〈意味〉や〈価値〉を描き出し、それをモノやコトなどへとカタチにしようとする姿勢を、「企てる」というニュアンスを大事にしたいので〈企業者的姿勢〉という言葉をあてています。
もう一つが、〈協働 cooperation〉です。ここまでの講義noteでもお伝えしてきましたが、人間は自分だけで生きることはできません。この講義の言葉でいえば、一人だけで欲望を充たすことはできないわけです。
この協働こそ、企業行動論をもちろん含む経営学にとって、もっとも重要なテーマであり、概念の一つです。経営学の歴史のなかで、協働についてはものすごく数多くの議論が展開されてきました。それを、ここですべて見ていくことはできません。
これからする説明のベースになっているのが、バーナード(Barnard, C. I.)です。
ちなみに、この『経営者の役割』、決して読みやすい本ではありません。が、私が一冊だけ絶対に読むべき経営学文献を挙げよと言われれば、ためらわずにこれを挙げます。経営学に関心のある方は、また経営学を学んでいる学生さんは、ぜひ一度は読んでみてほしいなと思います。
前置きだけで、1000字近くになってしまいました。では、本題に入りましょう。
なぜ、ひとは協働するのか。
これについては、すでに述べましたが、簡単です。
ひとは、一人で自らの欲望を充たしきることはできない
からです。
たとえば、24時間営業のコンビニエンスストアを考えてみましょう。いかにオーナーさんが体力・気力・知力・胆力に充ち満ちていたとしても、一人で発注や品出し、棚卸、レジ打ち、掃除などをすべて担うことはできません。しかも、24時間連続365日などということは不可能です。となると、そのコンビニエンスストアを一緒に動かしていってくれる人と協力していく必要があるわけです。
そう考えると、協働をひとまず以下のように定義できます。
【協働とは】
人間が、単独ではできないことに関して、他の人と目的を共有して、資源や能力、活動を提供しあい、共有された目的を達成しようとする営み。
ここで大事なことは、「人間は不完全かつ非完結な存在である」こと、そして「人間はそれぞれ独自(ユニーク)の存在である」こと、この2点です。だからこそ、人間は協働するのです。
協働の目的と個人の動機
さて、先ほどのコンビニエンスストアを引き続き事例として考えてみましょう。コンビニの場合、オーナーは自分だけでできない仕事をしてもらうために、アルバイトやパートで働いてくれる人を募集します。
働いてくれる人たちは、もとからそのコンビニを発展させるというようなつもりはないかもしれません。むしろ、そっちのほうが普通でしょう。お給料が欲しいから働きにきたと考えるほうが自然です。ただ、そのためにはコンビニエンスストアでのさまざまな仕事を担うことを、目的として共有するわけです。
オーナーも自分が持っている土地を収益が得られるように活用したいというのが、その人自身の欲望であるなら、別にコンビニエンスストアを営む必要はないかもしれません。しかし、コンビニエンスストアを営むときには、それを目的として設定することになるわけです。
つまり、オーナーとアルバイトやパートはコンビニエンスストアを営むという点で目的を共有しているわけですが、同時に、それぞれに個人的な欲望を抱いています。バーナードは、この個人が抱く欲望を〈動機〉と呼んでいます。
じつは、協働において大事な点に、
協働の目的≠個人の動機
というのがあります。バーナードは、この点をかなり強調しています。協働の目的と個人の動機が一致するほうが、どちらかといえば稀で、一致している場合を〈チーム〉と呼びます。スポーツなどの場合に〈チーム〉と呼ぶのは、本来の意味にあっているわけです。
さて、協働の目的と個人の動機が別物であるとするなら、個人が協働に参加するとき、協働の目的が達成されることも重要ですが、個人の動機も充たされなければ、その個人は協働に参加しようとは思わないでしょう。
この点をバーナードは協働の有効性 / 協働の能率という概念で説明しています。簡単に言えば、前者は「どれだけ協働の共通目的が達成されたか」の度合いであり、後者は「協働に参加する個人の動機がどれだけ充たされたか」の度合いです。協働を持続させようと思うと、どちらかだけで考えることはできません。しばしば、後者を無視して協働を持続させようとする発言を聴くことがありますが、これはきわめて大きな間違いです。
その点を念頭に置いて、バーナードは個人から協働への参加・貢献を獲得する際に、「個人の動機を変化させる」か、あるいは「協働の成果を個人に分配する」という2つの方法を示しています。「個人の動機を変化させる」というのにもいろんな方法がありますが、たとえば協働の共通目的への共鳴度を高めることで、「お給料ももちろん大事やけど、この仕事をやることが、自分にとって意味がある」という姿勢へと変化させるケースが考えられます。一方、「協働の成果を個人に分配する」ので一番わかりやすいのは、お給料でしょう。もちろん、それ以外にその企業や団体などで協働することで、個人の能力や知見などが高められるというような場合も含まれます。
協働体系と組織
さて、バーナードの議論を一つひとつたどっていくのは、ひじょうにおもしろいのでいくらでも続けたくなるのですが、それをやってると何万字あっても終わりません(笑)
ここもすごく重要なところなのですが、ごく簡単にだけ。
バーナードは協働体系(coöperative system)と組織(organization)を明確に分けています。協働体系とは、企業や学校、政党、クラブやサークルなどのように、一般的に「組織(体)」と呼ばれている存在です。したがって、そこには参加するメンバーがいて、人々のあいだに特定の関係性があり、必要な物的資源があり、必要な資金が準備されています。
それに対して、組織とは「2人以上の人々の意識的に調整された活動や諸力の体系」(訳書76頁)と規定されています。バーナードは、組織を物理学における「重力の場」や「電磁場」のような概念的構成体と捉えています。つまり、活動や諸力がつながりあって(動いて)いる状態を組織と呼んでいるのです。
この概念規定は、きわめて重要です。なぜなら、別の論文でバーナードは顧客も組織に活動や諸力を提供するメンバーの一員として捉えているからです。これは最近のビジネスの実践において注目されている〈エコシステム〉という考え方と、きわめてよく似ています。
今回、企業行動論を履修してくれている近畿大学経営学部の学生さん、とりわけ私の講義に初めて接する2回生のみなさんは、以下に書いてる内容について「なんのこっちゃ」って感じるかもしれません。でも、ここは山縣自身が最近めちゃくちゃ関心を持ってて、もし仮に山縣ゼミに入ってみたいとか考えてくれてる方がいたら、ちょっとお付き合いください(笑)
山縣(&山縣ゼミ)は、ここ数年、サービスデザインという価値創造のための考え方&方法を学びつつ、企業さんとコラボさせてもらって、それを実践的に活かすということをやっています。その基礎になるのが、〈サービスドミナント・ロジック〉っていう考え方です。
ここでは、顧客(お客さん)もまた単に受け身の存在としてではなく、価値創造を担う主体(アクター)の一人として位置づけられています。
このように、価値創造の担い手を企業だけでなく、そこにかかわりあうさまざまな活動主体(ステイクホルダーとか、アクターとか言います)もまた、同じように価値創造の担い手であるとみる考え方は、バーナードや、その源流にいるニックリッシュたちによって提唱され、その後あまり顧みられることもなく、今になって新たな価値創造の考え方として再生しつつあるのです。
企業という協働体系
さて、先ほど協働体系という言葉を出しました。この講義の「主人公」でもある企業も、協働体系の一つです。では、企業という協働体系は、どのような目的を共有しているのでしょうか。
もちろん、これは企業によって異なります。個々の企業がそれぞれにおいて共有する目的は企業理念や、最近ではPurposeというかたちで示されます。
ただ、企業という存在全般という点で見た場合、どう説明できるでしょうか?
ここで、講義note[03]を思い出してください。
ここで、私はビジネスとは「価値を創造すること」であると書きました。つまり、他者が抱き、しかもその人が自分自身で充たせない欲望を、何らかの効用給付を創出することで充たし、それによって対価を得るという営み、これがビジネスなのです。
このビジネスを担う協働体系こそが、企業なのです。したがって、この講義ではひとまず企業を価値創造を共有目的とする協働体系と位置づけます。
ただ、これだけでは企業とはどういう存在であるかを説明したとは言えません。少なくとも、不十分ではあります。
そこで、次回からはいよいよ「そもそも、企業とはどういう存在なのか」という2nd Stepに進んでいきます。
おわりに:実践性の強い経営学で抽象的な思考を鍛える意味。
ここまで、きわめて抽象的な話を続けてきました。もうしばらく続きますが、こういった抽象的なレベルで思考できるようになると、実践にも大いに活かせるようになります。実際、優れた経営者の方々って、みなさんが考えている以上に、抽象的な思考にものすごく優れてはります。たとえば、山縣ゼミで一緒にコラボさせてもらっている八尾市の木村石鹸工業株式会社の社長である木村祥一郎さんは、実践はもちろんのことながら、それを支える思索も、ものっすごく魅力的な方です。
抽象的な思索だけで実践ができるわけではありません。しかし、抽象的な思索なしの実践は、往々にして思いつきや行き当たりばったりに終わってしまうケースが少なくありません。せっかく、企業行動論を履修してくださってるんですから、ぜひ実践をよりいきいきしたものにするためにも、抽象的な思索を少しでも習慣づけてもらえればうれしいなって、願っています。
ということで、また次回に。
ばいちゃ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
