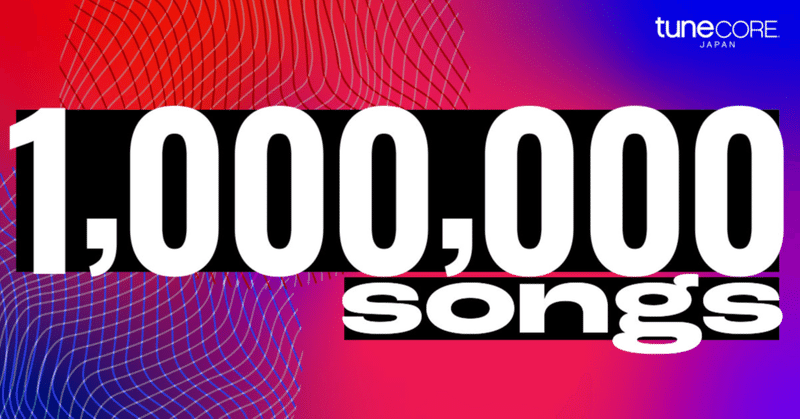
それでも「メジャーデビュー」したい君に〜「デジタルとグローバルの時代」の活動ビジョン
この投稿には反響をいただきました。「メジャーデビュー」はすでに形骸化していて、世間体が保てる以外にアーティストにとってのメリットは少ないばかりか、既存のレコード会社と「専属実演家」契約を安易に結ぶことは、アーティスト生命を危機にさせるリスクがあるという警笛は、音楽関係者の皆さんに広く知っておいていただきたい事実です。
CD販売を軸とする「レコードビジネス」からサブスクでの配信を軸に「録音原盤ビジネス」に変わっている今は、「デジタルとグローバル」を優先してアーティスト活動の戦略を考える必要があります。日本レコード協会加盟各社も、デジタル時代にアーティストとフェアな関係性を築くためには、専属実演家契約のテンプレートの全面見直しが必須だということを正確に認識していただきたいです。
3つのレイヤーでアーティスト活動をイメージしよう
さて、害悪を指摘するだけでは、後ろ向きなので、この「デジタルとグローバル」時代に、レーベルとはどう付き合うのがよいのか、アーティスト向けのアドバイスをまとめようと思います。
どんな風にアーティスト活動をするのか長期戦略を考えるときに、少し視座を高くして、こんな風に整理してみることをオススメします。一言にまとめると、
3つのレイヤーを数年単位のフェーズで乗り換えていくイメージ です。
順を追って説明しますね。
3つのレイヤーというのは、「グローバルメジャー」「ドメスティックレーベル」「DIY(アーティストダイレクト)」の3種類です。
1)グローバル3社との契約
ユニバーサル、ソニーミュージック、ワーナーミュージックの3社は、規模、資本力が図抜けたグローバルに拠点を持つレーベルです。以前は、BMGとEMIと5大メジャーと言われていましたが、合併して3社になりました。国にもよりますが、3社を足すと7割近くのシェアがあります。
面白いもので、歴史的に見て、時代を先取りするのはインディレーベルで、それをメジャーが買収することでシェアを維持していくという流れが続いているようですが、それが音楽ビジネスのダイナミズムにもなっています。
彼らは世界市場での売上を基準にアーティストを見ますので、日本人アーティストがグローバルにメジャー契約を取るのは、かなり難易度が高いでしょう。でも、いつかはこのフィールドで戦うのだという目標は持ってもらいたいなと思います。

気をつけたいのは、日本でソニーやユニバーサルと契約してもグローバル市場へのアクセスパスを手にしたことにはならない場合が多いということです。欧米法人窓口のグローバル契約でなければ、日本市場しか視野に無いないことが普通です。
日本のレコード業界は国内市場のみを対象に発展してきたので、海外でのマーケティングのノウハウがなく、グローバル3社も日本の音楽家の作品のグローバルヒットには積極的に取り組む例はほとんどありませんでした。
4〜5年前からその空気は変わってきているように感じています。大手3社と契約のチャンスがあったら、日本以外の活動のプランニングも契約前に出してもらいましょう。契約前に何も言わなければ、日本市場以外は後回しになるのが普通です。
2)DIYで活動する
Do it yourself型でアーティストとパーソナルマネージャーだけでも、かなりのことに挑戦できるようになりました。音楽リサーチ会社MidiaReserchによると、デジタル市場の2020年における「Artist Direct」の比率は6.3%で、2019年の5.8%から増加しています。

DIY型アーティストの活動支援については、2012年から始まったTuneCore Japanの貢献が非常に大きいですね。配信楽曲も100万曲を超えました。日本では大手レーベルに伍する売上シェア(TuneCoreの場合はアーティスト還元金額)を誇っています。瑛人「香水」、yama「春を告げる」、川崎鷹也「魔法の絨毯」、Tani Yuuki「Myra」などもTuneCoreを使って配信された楽曲だそうです。誰でも手軽に配信できる環境になっています。
ブレスリリースを出していましたので、興味のある方はどうぞ。
アーティストから見ると自分たちでやるのが利益率が高いのは、当然ですね。配信売上の約50%の原盤印税が手に入ります。それとは別に著作権印税も12%程度あります。英国は15%になるなど、著作権印税料率も上昇傾向なので、受け取り方法を真剣に検討するべきです。
既存の音楽出版社と契約して受け取る方法ももちろんありますが、デジタルサービスだけを考えるのであれば、欧米で流行している「アドミニストレーション型」サービスを使うのが、料率的には圧倒的に得です。音楽出版権は作詞作曲者と折半というのが長年の業界慣習ですが、アドミン型エージェントの相場は10〜20%です。
この辺のことがよくわからないという人は、下記の参考投稿をチェックしてみてください。
音楽活動のスタートはDIYから始まりますが、様々な経験をして、ブランディングやネットワークを手に入れたら、最後はDIYに戻ることになるのが今の時代のアーティスト活動だと思います。
これからの音楽ビジネスの最初ユニットは、セルフマネージメントできるアーティストと、音楽ビジネスを理解したマーケターのチームだと思っています。今年から「音楽マーケティングブートキャンプ」を始めたのは、日本の音楽界の最大のペインである「音楽マーケター」を育成するためです。継続して続けながら、アーティストとマーケターのマッチングなども徐々にやっていくつもりです。興味のある方はご連絡ください。
3)ドメスティックレーベルは、イコールパートナー
2つの間で重要なのが、ドメスティックレーベルとの契約です。日本のレコード会社の人脈や情報は、(まだ)役に立ちます。「害悪って書いてたじゃん?」って言わないでください。これを「メジャーデビュー」と解釈して、手放しでアーティスト活動を預けてしまうと不幸が始まります。
けれども、日本の音楽業界は音楽への愛情とアーティストへのリスペクトが根底にあります。アーティスト側がビジネス構造を理解して、自分の音楽を認めてくれるスタッフと濃密なコミュニケーションを取りながら、従来型の音楽業界、音楽シーンに自分たちの存在を浸透させていくことができれば、アーティストとしてレベルアップできることはたくさんあるでしょう。
彼らは、デジタルとグローバルは(ほとんど)わかりません。これまでやってないからノウハウがないのです。でも、それ以外の領域では長年の蓄積とネットワークがありますから、アーティストが成長する機会を得ることはできるのです。
ドメスティックレーベル契約時の留意点
i) デジタルとフィジカルの条件は分けて結ぶ
ii) 専属開放のガイドラインを定める
iii)海外活動の方針を決めておく
アーティストの状況や音楽性などによって、結ぶべき契約条件はちがってきますので、一概には言えないということは大前提として理解してください。その上で、僕が考える契約時のポイントは前掲の3つです。
i) デジタルとフィジカルの条件は分けて結ぶ
経済的合理性から考えると自然なことです。CD時代は、音楽ビジネスのプラットフォームをレコード会社が持っていましたから、アーティスト活動全体を一つのくくりで契約する「録音専属実演家契約」を結ぶことに合理性がありました。
これから音楽ビジネス(録音原盤ビジネス)の中心は、デジタルサービスです。ここではプラットフォーマーは、Spotify、Apple、Google,Amazon,LINEといったデジタル事業者で、レコード会社は原盤提供窓口を担っているに過ぎません。
以前のエントリーで説明したような、アーティスト印税1%、原盤印税12%みたいなCD時代の相場をベースに、「デジタル分少し上乗せ」みたいな条件は理にかなっていません。
僕が今契約を結ぶとしたら、ベースになる方程式は、
配信事業者からの受取額 ー 窓口手数料 ✕ 分配料率 = アーティスト受領金額
ここから先の料率は、個別の契約条件次第です。僕の感覚もあくまで一例なので、頭の整理のためと思って見てほしいのですが、レコード会社の歴史と熱意に最大限の敬意を評して、こんな数字を入れます。交渉上手の弁護士に言わせたら、「山口さんは甘すぎる」って怒られそうですww
配信売上 ✕ 80%(窓口手数料2割)✕ 分配率 1/2= 40%
ii) 専属解放のガイドラインを定める
レコード会社が求める契約は、必ず「専属実演家契約」です。ここで戦うのは得策でないでしょう。問題は、専属で拘束される内容です。著作権法上の「実演」というのは非常に幅広い概念で、作詞作曲以外のほとんどの音楽家の活動が制約の対象になることになります。
特に、「録音物への固定」というのがレコード会社の生命線なので、そこの専属性は強く求められ、他社と行う際には、専属解放料が要求されることになります(そのために他社との仕事が成立しなくなることもあります)問題はデジタル化によって、「録音物への固定」の範疇もひろくなってしまっていることです。以前なら、コンサートのTV中継は、DVD化などにならない限り専属解放は不要というのが業界慣習でした。これが、デジタル配信になると、専属解放が主張されます。インスタグラムでライブをやるのもレコード会社の許可なくできるということです。
契約時に専属実演契約の解放のガイドラインを話し合って、テキストにしておくことをお勧めします。日本の会社は基本は性善説の信頼関係ベースですから、細かい契約書になっていなくても、口頭の約束ではなく、メールでも良いので書面になっていれば、不誠実は対応をされることは滅多にありません。
iii)海外活動の方針を決めておく
専属実演家契約の範囲は、全世界を求められることが一般的です。ドメスティックレーベルの海外ネットワークは貧弱ですし、ノウハウも確立していませんから、可能なら日本国内だけにしておきたいところです。
国内だけにすると後ろ向きな話になっていく側面もあるので、契約前に日本以外の活動計画を立ててしまうのはいかがでしょうか?日本以外での活動計画を話し合う中で、契約条件を決めていくのです。本気で海外やるなら、ビジネスパートナーも各地に必要になってくるでしょうから、そういうディスカッションをするだけでも有益です。
デジタルサービス上でのプロモーション、マーケティング、ライブ活動の可能性などをプランニングしておくことは、「デジタルとグローバルの時代」に死活的に重要なことです。
他にも、原盤制作費の金額や負担率、契約期間、契約中のリリース曲数、契約終了後の拘束条件(他社との契約はいつから可能か、同一楽曲の再録音は等)、音源以外のコンサートやグッズ、ファンクラブの収益をどうするかなど重要なファクターはいくつもあります。
僕が代表で長年アーティストマネージメントをしてきたバグコーポレーションはセルフマネージメントを期するアーティストのためのメンタリング事業を開始していますので、活用していただければと思います。
アーティスト活動の「フェーズ」別ビジョン
このように、ドメスティックレーベルもビジネスパートナーとして活用しながら、グローバルな、真の意味の「メジャーデビュー」を夢見ながら、利益率が高いDIY活動にいつでも戻れるようにしておくのが、これからのアーティストの長期活動ビジョンです。
レーベルとの契約は、2〜3年が一般的でしょうし、そのくらいの期間は何らかの成果を出すのに必要ですから、3年程度を1つの「フェーズ」と捉えるのが適切でしょう。
フェーズごとに目標設定しながら、クリアーできたらもっと上のステップに、残念ながら成果が上がらなければ、DIYで体制を立て直したり、一定の商業的な成功を収めたら、利益率を上げるためにDIYの時期を設けたり、というのような狡猾さをもった活動ビジョンを持つ時代になっているなと感じています。
前掲の2と3の中間みたいな形もいろいろあるでしょう。レーベル契約のない大手音楽事務所との契約は、まさに中間的なことになるかもしれません。デジタル時代の音楽活動には、多額の資金や大きな組織は、必ずしも必要でもありませんし、有利とも限りません。
頭を使って真剣に考える、ネットにある情報を徹底的に調べる、色んな人にあって話を聞く、誰でもできるアタリマエのことを怠っているアーティストが日本には多いなと思うことがあって残念です。
このエントリーが少しでも参考や刺激になったら嬉しいです。
<参考投稿>
モチベーションあがります(^_-)
