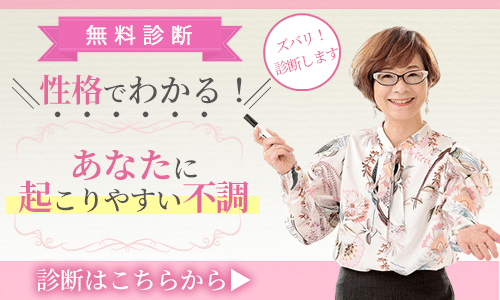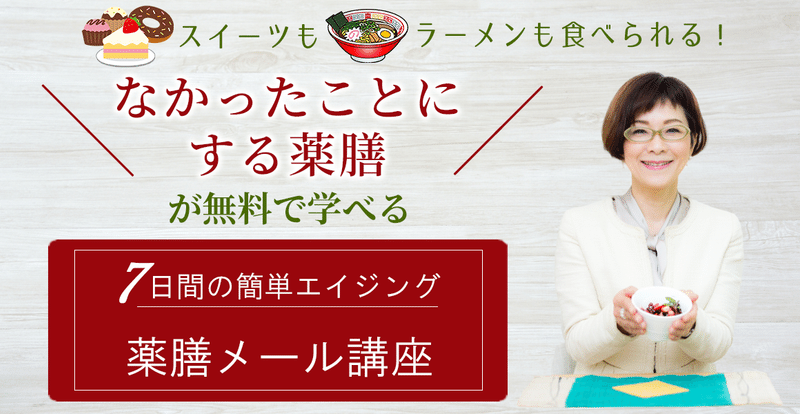秋の初めにおすすめ!冬瓜とあさりとレタスのスープ
秋の初めは、日中の暑さは真夏並みですが湿度が減って乾燥して来ます。
朝晩は涼しくなるので、寒暖差による体調不良や風邪をひくケースが出て来るのがこの頃。
昼間はまだ汗をかくので潤い不足になりがちですが、昼間水分を摂り過ぎると夜の冷えや浮腫みに繋がる、真夏と同じことをしていては良くない時期です。
風邪をひくのは粘膜が十分に潤っていないことも理由の一つになるため、体を潤わせておくことは大切になります。
こんな時は、潤いを補給しても要らない水分はしっかり出して、熱のこもりを冷やす食材がおススメ。
そこで、きゅうりと同じウリ科の野菜、冬瓜を使ったスープのレシピをご紹介します。
冬瓜・あさり・レタスのスープ

材料/
冬瓜280~290g程度(皮と種を含む)、殻付きあさり1パック、豆腐半丁、レタス適宜、生姜少々、だし汁800cc、塩コショウ、オイスターソース適宜
作り方/
1. 冬瓜は皮を剥き、種とワタを取り除いたら食べやすい大きさに切る。
2. あさりは砂抜きしておく。殻をこすり合わせて洗いボールに入れておく。豆腐を切り、洗ったレタスは適当な大きさに手でちぎっておく。生姜は皮ごと薄くスライスして千切りにしておく。
3. 出汁の中に生姜とあさりを入れ沸騰させて殻を開く。そこに冬瓜、豆腐を入れて冬瓜が柔らかくなるまで煮る。最後にレタスを入れてひと煮立ちしたら塩コショウ、オイスターソースで調味して完成。

これくらいの量で280gです。

皮を剥き、種とワタを除いたところ。

皮はなるべく薄く剥きます。少し緑が残る程度に。
材料の性質と効果
■冬瓜
ウリ科の冬瓜は、キュウリなどと同じく体にこもった熱を冷ます性質です。
必要な潤いを補い、浮腫みの原因になる要らない水分は排泄させる効果があります。
ほとんどが水分と言うところもきゅうりと共通です。味が淡泊なためいろいろな料理に馴染み使いやすい野菜ですね。
■あさり
体を冷やす性質です。「血」と潤いをアップさせる陰陽で言えば陰の食材。
海から獲れるものは「陰」のパワーを持つので、女性(陰)には嬉しい食材です。調味料として使うオイスターソース(牡蠣のエキス)も同様です。
殻付きで調理をすることも大切で、殻の重さは下に降ろす、鎮めるという効果があるとされるので中医学では「血」不足によるイライラを鎮めると言う意味で、あさりはメンタルを落ち着かせる食材の一つになります。
■豆腐
潤わせる働きのある白い食材の一つ、豆腐も体を冷やす性質です。
大豆たんぱくを豊富に含みイソフラボン効果とにがりのカルシウムも含まれます。アミノ酸スコア100。
これは、含まれるたんぱく質の量と必須アミノ酸の割合がすぐれているということ。どんなにたんぱく質が多く含まれた食材でも必須アミノ酸が少なかったり、そのバランスが悪いとたんぱく質の栄養価が少なくなります。
アミノ酸スコアは100を超えるものは全て「アミノ酸スコア100」と表示されるため、豆腐は栄養価の高いたんぱく質食材と言えますね。
■レタス
高原野菜のレタスも水分豊富な体を冷やす性質です。
必要な水分は補い要らない水分は排泄させるので夏には積極的に食べたい野菜です。
カリウムが豊富なため利尿効果に繋がります。
殆ど栄養がなさそうに見えますが、薬膳では血めぐり効果も謳われています。レタスが!!です。
栄養学的には、β-カロテン、ビタミンCなどの他、カリウム、鉄分などのミネラル、食物繊維がバランスよく含まれるため、血めぐりアップ(活血作用)整腸作用などが言われるのですね。
冷やし過ぎないように食べることを考える
秋の初めは、まだ暑さが真夏並み。
日中に体の熱を冷ましたり汗で失った水分を補いながら要らない水分を排泄させるには、すいかやきゅうりでも良いのです。
けど、朝晩は冷えて来ますよね?
なので、冷やし過ぎずに食べることを考えます。
そこで使うのが生姜。
生の生姜は発散させる効果が高いですが、火を入れて使うと温める効果が高くなります。そして皮ごと使うと温め過ぎを緩和させることができるのです。
生姜はじっくりお腹から温めたい時は、皮を剥いた状態で蒸して乾かした乾姜を。普段、炒め物などに使う生姜は程よくお腹を温めて食材の冷やし過ぎを緩和させることができると考えてください。
夏から秋の変わり目はグラデーションで食事を変える
陽の季節から陰の季節に変わるこの時期。
長い湿気のあった時期から空気も変わり、体の状態も変わります。
夏から秋の変わり目は暑さと、汗で失った水分補給の両面を考えながらも夜は冷えることも忘れずに、冷やしすぎずに潤い補給を考えた料理を作ってくださいね。
※このスープは暑い日の日中には、生姜を入れずに作っていただいても良いです。
【関連記事】
性格からわかる、起こりやすい不調とおすすめ食材を無料でお知らせします。
下のバナーからお答えください。
なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座を配信中です。下のバナーをクリックしてお申込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?