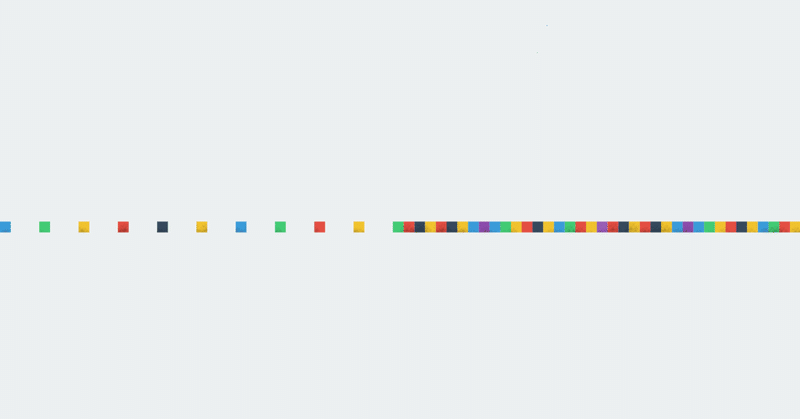
モノの流れに身を置いている
数年前に、「はたらく細胞」というアニメが流行った。
一時期ではあちこちでみかけた気がするので、かなりヒットしていたのだろう。僕も、流行っているときにサブスクで見た。
内容としては、体内で働いている細胞たちを擬人化して、実際にどういうことをやっているのか、というのを解説したものだった。細かい内容は忘れてしまったが、それなりにクオリティが高い作品だったように記憶している。
印象的だったのは、体内で「はたらく細胞」たちは、何かを運搬していることが非常に多い、ということだった。主人公(?)の赤血球も、常に台車のようなものを押して何かを運んでいる。

もちろん、外敵と戦う役割の細胞もたくさんあるのだが、そういったものは全体の母数からすると少数で、大部分は「何かを運ぶ」細胞である、というのが印象的だった。
*
現実世界では、「モノの動き」というのはさほど意識しない。それは、僕ら自身に足があり、移動することができるので、モノを取りにいくことができるからだ。そして、どこにどういったものが供給されるのかは、社会全体でシステム化されているので、迷うことが少ない。
たとえばおなかが空いたからコンビニに行けば、食べ物を買うことができる。当たり前だが、コンビニでは自然に食べ物が湧いてくるわけではなくて、コンビニ側が適正な商品を仕入れ、さまざまなルートを経由して運ばれてくる。「はたらく細胞」たちのように、一個一個台車で運ばれてくるわけではないが、なんらかの流通経路を経て運ばれてくる。
最初に入った業界がたまたま物流業界だったので、商品の流通には関心がある。というより、一応専門家だ。「はたらく細胞」で示されていた通り、極端な話、生きるということは、物流の中に身を置くことだと思う。
ちょっとした災害などで物流が寸断されると、人は生きていけない。モノが足りなくなって、すぐに死んでしまう。しかし、その「物流」の組み立ては、モノをA地点からB地点に移動させれば済むといったような単純なものではなく、いろんな人がそこに携わり、必要な場所に必要な量が届くような複雑な仕組みが作られている。
物流のことを考えるとき、たまに「商社不要論」を聞くことがある。商社というのは要するに卸売業のことだが、モノを右から左に動かしているだけで利ザヤを得ている、と批判されている。
しかし、これも物流という機能全体のことを考えると、その必要性がわかる。たとえば自分がラーメン屋を経営していたとする。どこかから食材や資材を仕入れなければならない。もちろん、メインになる麺や具などの原料の調達は、こだわりのところから直接契約してもいいのかもしれないが、たとえば割りばしとか、調味料などといったこまごまとしたものまで直接メーカーと契約したら、ものすごい手間になってしまう。
そういったものは、どこか卸売業者が一か所に取りまとめてくれて、まとめていっぺんに納品してくれたほうが手間がかからないし、コストも抑えられる。最近は、メーカーがそういった卸売業の役割を果たして、自社製品なのにほぼ仕入れ商品、というケースもある。
*
モノの流れを完全に可視化したら面白いだろうな、と思う。メーカーだって、モノを作ってはいるものの、どこかから原料を仕入れ、それを加工して、どこかに卸している。ある意味では、「流通」という大きな流れの一部にすぎないのだ。
とんでもなくミクロな世界が、実はマクロ世界の縮図だというのはよくあることだ。むしろ、「社会」というものが、「人間の体内」のようにミクロなものを模して作られているのではないか、ということさえ思えるのである。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
