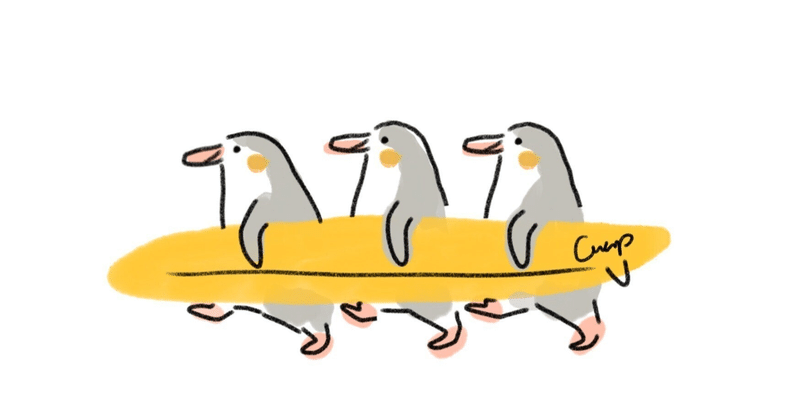
世界の仕組みはツギハギだらけ
世の中のあらゆる仕組みはツギハギだらけだな、とよく思う。悪くいえば行き当たりばったり、よくいえば柔軟。「そのとき使えるもの」「便利なもの」を組み合わせて、現代のあらゆるシステムは成り立っている。
行き当たりばったりに増改築を繰り返されたのが現代である。根本的に仕組みを変えてしまうことで、もっと効率をあげることができるとは思うのだけれど、ドラスティックに変えてしまうといろんなところに影響がおよぶので、なかなか思い切ったことができない、というジレンマもある。
生物の起源はひょっとしたら神が設計したのかもしれないけれど、少なくともいまの生物の仕組みは神が設計したわけではない。言い方は悪いが、進化の過程で適当にいろんなものがでてきて、それで生き残ったものが現生生物、というだけだ。
もちろん、いまの環境で生存できるように最適化されてはいるのだけれど、本当に最適化されているわけじゃない。これが最適に思えても、もっと広い目でみたらさらなるよい方法はあるかも。
物理エンジンを使って、コンピュータの中で進化シミュレーションをしている人がいる。遺伝的アルゴリズムといって、生物の進化のように「うまくいかなかったら消す」「うまくいったら残す」を繰り返して、特定の目的を達成しようとする。しかし、実際にやってみるとなかなかうまくいかない。
こうみると、ツギハギだらけといいつつも、実に巧妙なバランスで成り立っているんだな、と思える。
*
生物の仕組みだと、いきなり仕組みそのものをいじるのは相当難しいと思うので別にいいのだけれど、人間が決めたルールぐらいだったら変更してもいいんじゃないか、と思うことがときどきある。
個人的に一番なんとかしてほしい、と思っているのは「10進法」である。10進法はみんな生まれたときから使っているので全く違和感はないと思うのだけれど、めちゃくちゃ非合理的だと思っている。
10は、2と5でしか割ることができないので、マジで役に立たない。例えば、おまんじゅうを10個もらったとして、3人でそれを分けると、割り切れないので喧嘩になってしまう。4人でもダメだ。
だから欧米では昔から「ダース」という単位を使い、ものの単位は12個で1セット、という考え方があるが、あれは非常に合理的である。2、3、4、6、で割り切れる。5で割ると2.4という中途半端な数になるが、10を3で割ったときの3.333...よりマシだろう。
10進法を使っているのは、人間が10本指だからというのに由来しているらしいが、数学的に非合理なのでなんとかしてほしいものである。試しにネットで調べてみても、「人間が10本指だから」という以上の説明が見当たらなかった。
過去に12進法を使う文化圏もあったようだが、なぜか淘汰されてしまったらしい。
*
10進法の台頭によって日常生活で一番不便さを感じるのは、「時間の変換」である。ご存じのとおり、時間は60をひとつの単位とするため、10進法との相性は悪い。60というのは12の延長線にあるため、つまり12進法の論理だといえるだろう。一年も12か月なので、ここも10進法との整合性が崩れている。
さらには、一週間が7日というのも、旧約聖書に由来しているのかもしれないが、これもあまり整合性がないのでただちにやめてもらいたいところである。365を素因数分解すると5×73になるので、できれば一週間を5日にしてほしい、と思う。
いまのパソコンのキーボード配列の主流であるQWERTY配列なども、昔はタイプライターの性能が悪かったため、あえて打ちにくい配列にした、ということが言われている。これが打ちにくいかどうかはわからないが、日本語入力の場合、「A」の入力頻度はそこそこ高いが、左手の小指で押すことになるため、ここに負荷がかかりすぎている。ctrlなどでも使うため、キーボードを長時間打つと、左手の小指が攣りそうになることがある。
これも、親指シフトなどの最適化された方式があるのだが、あまり主流になっていない。かな入力とかも、慣れたらすごいのだろうか。
*
最適化ということでいうと、ここ最近は音声入力を活用している。最近の僕のnote記事はだいたい7割ぐらいが音声入力によるものである。いったんバーッと5分ぐらいで音声入力してしまってから、手で直していく。直しの時間のほうが長く、10~15分ぐらいかかるのだが、それでもゼロから手打ちするよりはマシだったりする。
惰性で残っている仕組みも、そのうちテクノロジーの進歩によって最適化されることもあるのかもしれない。暦などの影響範囲が大きい仕組みについては期待できないが。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
