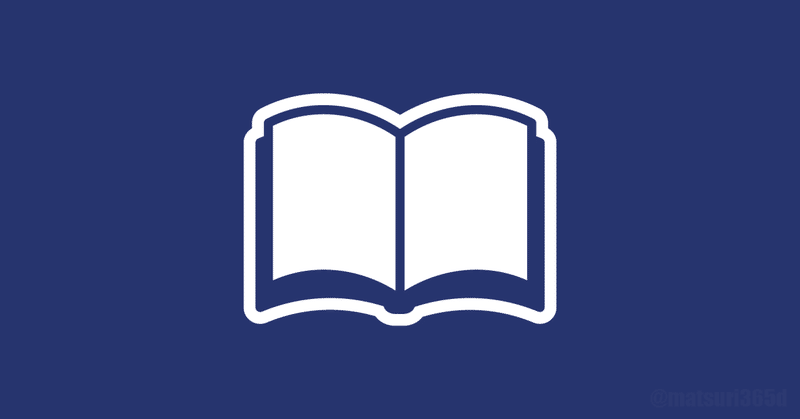
敏腕編集者ってどういう人ですか?
漫画編集者の林士平氏が、ほぼ日で糸井重里とインタビューしている記事を読んだ。
あまり詳しくは存じ上げなかったのだが、そういえば編集者として名前を聞いたことがあるような気がする。少年ジャンプでヒット作を数多く飛ばしている敏腕編集者とのことだ。
確かに作品リストを見てみると名前を聞いたことがある作品ばかりだし、「チェンソーマン」など、自分が好きな作品も含まれている。
*
編集者とはどのような存在なのか、そして、実際にどういう仕事をしているのか? については、一般的には結構謎に包まれている。しかし、たとえば漫画家について描かれた漫画「バクマン。」などを読むと、その片鱗を知ることができる。
「バクマン。」は少年ジャンプが舞台なので、まさにこの働き方なのだろう。しかし、この作品は漫画家サイドから見た作品だし、フィクションなので脚色も多分に含まれているだろう。
冒頭に貼ったインタビューを通じて、編集者としての仕事哲学のようなものが見てとれた。これを読んで感じたことは、編集者というのはわりと個人事業主的な側面があって、統一されたスタイルはないのでは、ということだ。
林士平氏の話す内容は非常に興味深いのだが、それでいてわりと内容としては「普通」な感じがして、それほど特徴的なものはないような気がした。本当にすごい人って、そういうものなのだろうか? 基本に忠実というか。あるいは、言語化できない秘伝のレシピみたいなものがあるのだろうか。
*
漫画編集者の仕事とはどういうものなのだろう。このインタビューを読んで、「客観的に、率直に作品の評価を漫画家に返す」のが一番の編集者の仕事なのかな、と思った。
面白かったら面白いと言い、わからなかったらわからないと言う。判断に困ったら、判断に困ると言う。そういう当たり前のことが、実はけっこう大事なことなのかもな、と。
編集者というのは、漫画を「審査」する立場でもあるし、漫画家を「育てる」立場でもある。しかし、林士平は率直に感想を伝えることで、「読者」であろうとしているのかな、という印象も受けた。
自分がアウトプットしたものを、率直に他人から意見として聞ける機会というのは実はあまりない。ファンであれば肯定的なコメントしかしないだろうし、アンチであれば中傷しかしないだろう。面白いものを面白いと言ってくれ、よくわからないものをよくわからないと言ってくれる存在は、実はかなり貴重なのかもしれない。
率直に何かを感じ、それを言語化するのは結構難しいことだ。僕も奥さんとどこかに外食に行って、何かを食べたとき、その料理の感想を話し合うことがあるが、素直に言語化するのはそれなりに大変である。まず何かを感じ、その理由を探っていき、言語化する、というプロセスをたどるわけだが、それを「作った張本人に返す」のはさらに難易度が上がるだろう。
*
ヒット作を生み出すにはどういうことをすればいいのだろうか。インタビューの中で、担当している漫画家の数について触れられている。連載するレベルの作家が7人で、あとは予備軍だという。総数としては100人ほどだとか。
予備軍の中には、連載なんて夢のまた夢で、訓練生みたいなものまで含まれているのだという。上澄みの7人はいわば「主力」なので、どうしてもそこに注力したくなるが、残りの93人をどう育てていくかが腕の見せどころなのだろう。
実際のところ、ヒットを狙っても、本当にヒットするものなんて1000のうち2つとか3つとかそういうレベルなのだろうから、たくさん作ってたくさん出すしかないのかも。そういう意味では、「敏腕編集者」とは、「マメで、面倒見がよく、作家のタマゴをたくさん抱えている人」ということになるのだろうか。
このインタビューはいろんな側面を引き出しているとは思うが、まだ見えていない部分も当然あるのだろう。本人にさえ、自覚できていないこともあるのではないだろうか。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
