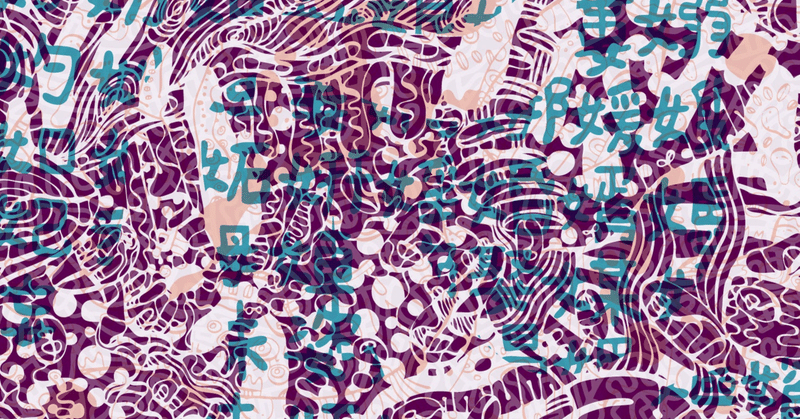
コピーが「刺さる」ことがあまりない
「キャッチコピー」と呼ばれるものがある。商品や広告において、謳い文句や煽り文句などを短い言葉で表現したものである。広告業界にはコピーライターという職種があり、広告をより効果的なものにするため、専門の職業の人が一生懸命、効果的な「刺さる」言葉をつむぎだしている。
広告コピーで、特に優れたものはそれだけで作品性があり、「名作コピー」と呼ばれる。「良い広告コピーを紹介しよう」みたいな動きもときどき見られる。
そうやって紹介されるコピーは、確かに斬新でハッとするようなものもある。が、あくまで個人的な意見ではあるが、しっくりくるものはほとんどない。その場では「うまいなあ」と感心しても、すぐ忘れてしまう。
*
というより、「いいコピー」とはどういうものなのだろうか? 「これは美しい」「これは名作だ」ともてはやされるものが「いい」とされる世界でいいのだろうか? ということである。
「名作」と呼ばれるコピーは、ちゃんとコピーとして機能したかどうか、という観点で選ばれているのだろうか。単に同業者や界隈の人々がもてはやしているだけではないのだろうか。
もちろん、商品が売れまくって、社会現象になったとき、広告は象徴的な存在としてクローズアップされる。しかし、それは広告がすごかったから、というより、商品そのものがもっていたポテンシャルではないのだろうか。穿った見方をすると、「名作コピー」を連発する人もいるが、単に「勝ち馬に乗っている」だけではないだろうか、と。
僕は広告の素人なのだが(広告業界で働いたこともない)、少しコピーについて考えてみる。
*
コピーの役割とは、そもそもどういうものがあるだろう。広告を打つ目的としては、ブランドを認知させたり、イメージを向上させたり、購買行動につなげたり、というものがあると思う。
商品の本質を端的に表現し、それを自分の生活としてイメージしやすいものになっている広告は強い。しかし、そういう「いいコピー」を考えついたとしても、それが記憶に残りコピーとしてちゃんと機能するかどうか、というのはまた別の問題である気がする。
「言葉遊び」的というか、「うまいこと言っている」コピーは(個人的にはだが)あんまり記憶に残らないし、「しゃらくさい」と思う感想のほうが多い。コピーを書く視点で、「おお、これはいいコピーだ!」とそのときは思ったとしても、そのとき限りで忘れてしまったりして、実際にそれが「いいコピー」だったかどうか、というのはわからないのではないか、ということである。
*
日産のCMであった「やっちゃえ日産」とか、高須クリニックの「YES!高須クリニック」というのは、完全に意味不明だし、別に本質を突いているような気もしないけれど、「やっちゃえ」や「YES!」というのは日常的に口にするため、日常生活の中で連動して、ついつい想起してしまう。
こういうものが「いいコピー」とされるかどうかは謎だが、「浸透している」という点においては、「いいコピー」と言えるのではないだろうか。
「いいコピー」になるためには、「引っ掛かり」というか、「ツッコミどころ」が必要なんじゃないか、ということも最近思っている。
中央線の広告に四谷学院という予備校の広告があって、「なんで、私が東大に。」と書かれているのだが、「いや、お前が受験したんやろ」と見るたびにツッコミを入れている。
しかし、そのツッコミが奏功し、バッチリ記憶に残っているので、これも「いい広告」と言えるのではないか、と自分は思っている。引っかかるところがないとそもそも印象に残らないので、「うまいこと言ってんなあ」ぐらいだとすぐに忘れてしまうのだ。
もちろん、「それをもって四谷学院に入りたいかどうか」という観点では、また別の評価になるかもしれないが。
*
広告はあまり好きではないのだが、映画の予告編は好きである。映画の予告は広告ではないかもしれないが、映画館にまた来させようとしている点では広告の一種なのではないか、と思われる。
庵野秀明作品の予告編が好きなのだが、言葉が一切入っていない。こういうのがどうも好きらしいのだ(映画のポスターなどには当然コピーが入っているが)。
こういうのは、コピーがないのに、広告として機能している、ということだろうか。
あと個人的には、コピー単体の言葉よりも歌のほうが染み込みやすい、というのはある。名古屋のご当地CMソングなど、かなり好きなCMは多い。
いい曲である。
*
コピーを書くことを生業とし、全身全霊をかけて制作している人がいるのはもちろんなので、そういう人たちの仕事をどうこう言うつもりはないのだけれど、「いいコピーだ」とされたり、単に商品が売れたというだけでは図れない「何か」があるような気がするのである。
「結果として記憶に残った」ものがいいコピーだと言えるかもしれない。であれば、たとえば10年前のコピーで覚えているものが「いいコピーだ」と言えるのではないだろうか?
もっとも、単に自分がひねくれているだけで、「いいコピー」とされるものに本当に感心し、購買行動にダイレクトにつながっていく人々のほうが世の中としてはマジョリティなのかもしれないが。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
