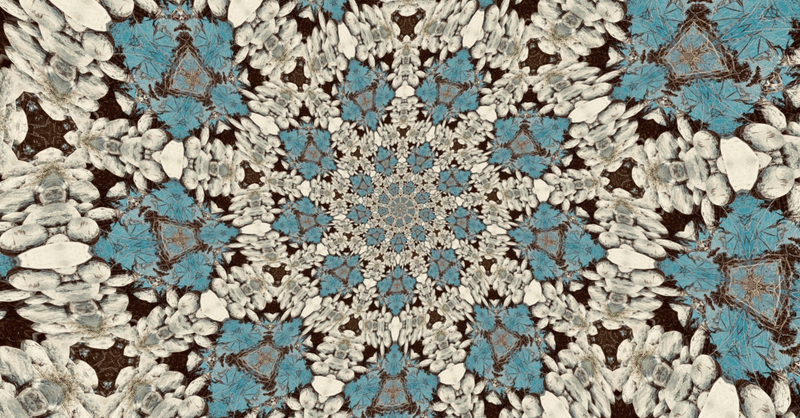
感覚で「いいもの」をつくる人たち
いろんなミュージシャンを好きになっては、そのうち飽きて離れて、時間が経つとまた戻ってを繰り返しているのだが、ここ10年ほどのスパンの中で飽きずに好きなのが米津玄師である。
昔から人気はすごかったが、いまだ衰えることなく、定期的に作品を発表し、映画やドラマなどでも主題歌を担当しており、そこの楽曲でも評価をされている。特に主題歌系は、原作を読み込んでいるのが伝わってくる完成度で、いつもすごいなと思っている。
普通、アーティストの曲はずっと追いかけていると似たような曲ばかり作るようになるので飽きてしまいがちだが、米津玄師は変化し続けているせいか、あまり飽きがこない。新しい曲が発表されても、新鮮な気持ちで聞くことができる。
*
米津玄師の楽曲の良さはどういうところにあるのだろうか? 一言でいうと、「センスがいい」と思っている。そんな単純に言うなと言われそうだが、実際にそう思うのだ。
いい音楽って、そもそもなんなのだろう? というのを最近考える。コード進行はもうだいたいすべて出揃っているし、メロディも組み合わせは有限だ。原理的には、そのへんのコード進行に適当にメロディを載せれば楽曲になるはずだ。
しかし、それで「いい曲」を仕上げる、というのは別次元の話である。人気アーティストは自分なりの「得意パターン」を見つけて、それを量産することで飯を食って行こうとする。しかし、米津玄師は次々に新しいパターンを開拓していき、それがすべていい曲なのだからすごい。だから、「センスがいい」としか言えないのだ。
米津玄師の良さを言語化するのはかなり難しいのだが、僕の意見は、「感覚的で、よくわからない複雑なものを、聞きやすい音楽の形にまとめあげる能力」が卓抜しているように思う。新曲が出るたび、一聴すると普通に曲として聞けるのだけれど、よく聞くとコード進行がめちゃくちゃだったり、むちゃな転調が入っていたり、という無理な展開の積み重ねで構成されていたりする。
しかし、それでちゃんと自然に聴こえてしまうのがおそろしいところだ。音楽的に解説している動画も見たりするのだが、混乱する様子が出ていてとても面白い。
要は、感覚が鋭くて、それがセオリーを超えていく感じが心地いいのだろう。論理ではなく感覚が優先されているので、論理を積み重ねるだけの手法では永遠にそこに到達できない。そこにある種の「天才性」を見るのだろう。
*
論理を超えたところに論理を見出す感じは、将棋の藤井聡太の将棋にも少し近いような気がしている。藤井聡太は、ときに従来の将棋の常識からは大きく外れた手を指すのだが、本人としては自然に指している感じがまたおそろしいのである。
論理の枠の中でものを考えるのではなく、感覚でものをつくり、論理を超えていく。結果として、それでいいものができあがる。それをやってのけているのが面白いのだろう。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
