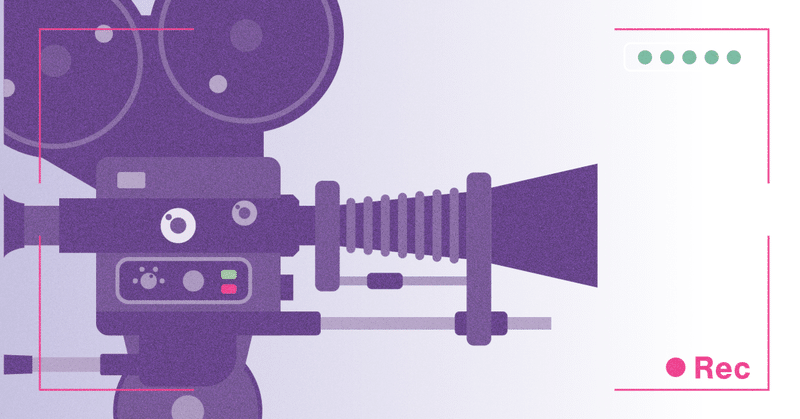
「君たちはどう生きるか」は説教くさい映画なのか?
宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」は、面白かったという感想の人もいれば、つまらなかったと言う人、まだ見に行っていない人など、さまざまな層がある。
まだ行っていない、面白くなさそうだから行かない、という人の理由の中に、「説教くさそうだから」というのがある。確かに、「君たちはどう生きるか」というのは、タイトルだけ見ると、超絶説教くさそうなタイトルではある。
しかし、宮崎駿作品を振り返ってみると、そんなに説教くさそうなものはこれまであったかな? とは思う。強いて言うなら、ナウシカあたりは、「自然を大事にしよう」的なメッセージが強いので、人によっては説教くささを感じるかもしれない。
その点で言うと、本作はタイトルだけ「君たちはどう生きるか」という同名の小説からとっているだけであって、内容がそうだ、というわけではない。実際に見ても、「どう生きようか」と感じた人もいれば、そんなものは考えなかった、という人までさまざまである。
*
作品における説教くささとは何だろうか。というと、要するに作者に明確な思想があって、その思想を押し付けるために作られた作品、ということになるだろうか。プロパガンダ的な映画は説教くさいかもしれない。教育を目的にした作品だったりすると、その傾向は強くあるかもしれない。
今回の作品を見て、なんとなく、高畑勲に対するコンプレックスというか、高畑勲を意識して作られた部分もあるのかな、とちょっと思った。
一般的に見ると、宮崎駿と高畑勲はジブリの二大巨塔だが、両者に対する評価はちょっと異なっている。アメリカのニューヨーク近代美術館に、高畑勲監督の「となりの山田くん」が入っており、芸術面では高畑勲のほうが高い評価を得ているのだ。
東大仏文卒のインテリで、ものすごく教養があり、宮崎駿の師のような存在だった高畑勲。はたから見ると、メガヒットを飛ばして大成功しているように見える宮崎駿に対し、大赤字を出して経営を危ぶませるほどの大コケを喫することもある高畑勲を比べると、宮崎駿のほうが成功しているように見えるのだけれど、本心からすると、「自分のやりたいことを貫き、芸術的にも質の高いものづくりができた高畑さんが羨ましい」という気持ちがどこかにあったのかもしれない。
「ポニョ」のドキュメンタリーで宮崎駿がさかんに言っていたのが、「これまで培ってきた技術の手癖にまかせない」ということだった。何十年もかけてアニメーションを作ってきたので、もはや「いい画」を描くことは簡単だ、と。しかし、そこからあえて外れたものを作らないと、本当の創作にはならない、ということらしい。
つまり、セオリーからあえて外れていくことで、「本当にやりたいこと」を作ろうとしていたのかもしれない。そしてそれは、生涯最後の作品になるかもしれない宮崎駿に対する、鈴木プロデューサーからのご褒美だったのかも。
*
いろんな角度で分析している動画や批評なども読んでいるのだけれど、今回の作品は、あくまで宮崎駿の個人的なフィルムであったことは間違いない。「何も宣伝をしないのが今回の宣伝戦略」などと言われているけれど、完全に個人的なフィルムであれば、そもそも「宣伝する」という行為自体が的外れである。そういう理由で、今回は宣伝をしなかったのかもしれない。
サポート費用は、小説 エッセイの資料代に充てます。
