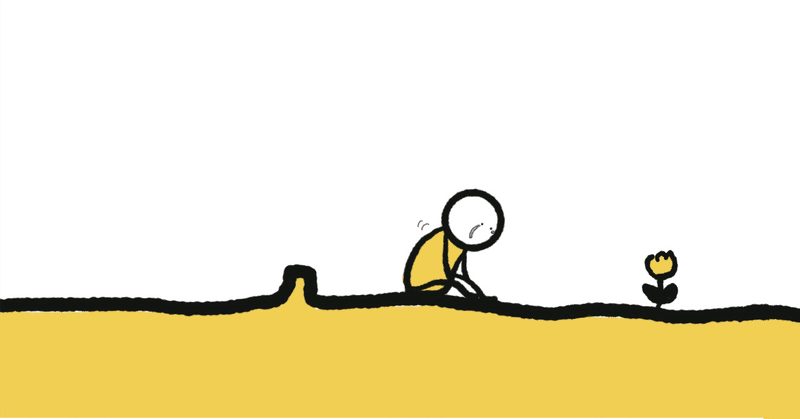
一級建築士学科試験 独学失敗談
こんにちは。やぎ座の人です。
社会人2年目で、令和4年度の一級建築士試験に無事合格し、勉強生活を卒業することができました。
製図試験は一発合格することができましたが、学科試験は1度失敗しています。
お金がなかったので、1度目も2度目も独学でした。
1度目の受験も、割と真面目に半年ほど勉強して挑みましたが、結果は以下の通りで不合格でした。
(令和3年度一級建築士試験の結果)
○計画 14/20
○環境 16/20
○法規 17/30
○構造 17/30
○施工 15/25
◉合計 79/125(合格ラインは87点)
一級建築士試験に合格した今、改めて当時のことを振り返ると、
「この勉強方法ではダメだったなぁ・・・」
と反省することがいくつかあります。
本記事では、私の学科1年目の独学失敗談を紹介したいと思います。
失敗① テキスト選びの失敗
一級建築士の学科試験対策用のテキストは何種類かありますが、それぞれのテキストの特徴を理解して使用することが大切だと思います。
1年目の自分は、当時使用していたテキストの特徴を理解しておらず、試験当日に痛い目を見ました。
1年目に私が使用していたテキストは「スタディング 建築士講座」のテキストです。
この「スタディング 建築士講座」ですが、コンセプトが「合格点をクリアするための最小限の学習を極める」ということで、学習内容も建築士試験に出題する全範囲を網羅するのではなく、出題頻度の高い問題のみを学習して、合格点を目指すというものでした。なので、テキストも網羅的な内容ではなく、ポイントに絞って作られたものでした。
当時の自分はこのコンセプトをあまり理解しておらず、本番で、
「なんか見たことのない問題がたくさんある・・・」
と、結構焦ってしまいました。
内容を絞って学習するというのは、実務経験が豊富な方には向いていると思いますが、実務経験が全くなかった自分にとっては、始めから、あまり向いていない講座だったかなと思いました。
一級建築士の学科試験は、案外単なる暗記では太刀打ちできない問題も多いので、内容を絞って効率的に学習するより、建築の知識を体系的に学べるテキストを、自分には採用すべきだったと思います。
「スタディング 建築士講座」を選んだ理由としては、講座価格が8,8000円と、ギリギリ自分にも出せる金額で、映像授業もついていてコスパがいいと感じたからですが、テキストについては、自分に合ったものを選ぶことが1番大切だと思います。
失敗② 過去問演習が少なすぎた
どんな試験にも共通して言われるのが、過去問演習の重要さです。一級建築士の受験においても、例外なく過去問演習は重要です。
しかし1年目の私は、過去問演習より、テキストの読込を重点的に行っていました。過去問演習も行なってはいたのですが、ただただ問題をさらっと解くだけで、内容の理解に努めていませんでした。
解いた過去問の数も圧倒的に少なかったです。
1年目は「スタディング 建築士講座」に付属の過去問題集を使用していたのですが、付属の問題集だけだと、問題数は以下の通りになります。
○計画 約500問
○環境 約325問
○法規 約500問
○構造 約450問
○施工 約525問
→換算すると過去問4~5年分程度
この演習量だけでは足りず、1年目は、本番で、
「似たような問題は見たことあるけど、答えが分からない。。」
といった現象を多発してしましました。
これを反省して、2年目は過去問演習を増やして、さらに、一つ一つの問題について、内容を深く理解するように努めました。具体的に2年目は、過去問9年分を解いて、同じ問題を繰り返し解きました。(効率的な過去問演習方法については、別記事にも書きたいと思います。)
この結果、2年目の試験では、
「似たような問題見たことある!!」
といった感じで、圧倒的に試験本番での迷いと戸惑いが少なくなりました。
失敗③ 法規を舐めていた
1年目の自分は、一級建築士の学科試験は、ほぼほぼ暗記の試験と思っていました。
法規については、
「法令集持ち込めるなら、暗記しなくていいし楽勝!」
「法令集さえ、しっかり作り込めば余裕!」
と思っていました。
しかしこの考えは大変危険です。
1年目の本番で何が起きたかというと、
「残り時間少しなのに、全然問題が解き終わらない。。
残り10問くらい、全部適当にマークするしかない。。」
と、深刻な時間不足に陥りました。
1年目は、本番の四者択一形式の演習を全くやっておらず、一問一答形式の演習ばかりを行なっていたので、時間の感覚が全くありませんでした。
全ての選択肢を読んでいたら間に合わない。
そんな初歩的なことに本番で初めて気づきました。
法規については、一問一答形式の問題に回答できるのは大前提で、本番で高得点を取るには、どの選択肢で法令集を使うのかを見極める力を身につけることが必要でした。
さらに他の科目もそうですが、法規では、最初に建築基準法のこの問題が出て、次に建築士法が出て〜というような、大まかな出題傾向を知っておくことが大切です。
2年目は、30問の4者択一の問題の解き方を意識して勉強することで、圧倒的に法規の得点力が伸びました。
法規は他の科目と違い、年による難易度のばらつきが少なく、確実に得点源にできる科目かと思います。1年目も、2年目のように、法規で安定して高得点が出せていれば合格ラインに乗っていたので、やはり法規の攻略というのは、一級建築士学科試験で大きく鍵を握るかと思います。
2年目に行った具体的な法規の勉強法は、ぜひこちらの記事をご覧ください。
失敗を活かした2年目の結果
上記の失敗を踏まえて、2年目で勉強方法を変えた結果は以下の通りです。
(令和3年度1級建築士試験の結果)
○計画 16/20 (+2)
○環境 17/20 (+1)
○法規 25/30 (+8)
○構造 26/30 (+9)
○施工 17/25 (+2)
◉合計 101/125(+22)(合格ラインは91点)
1度独学で学科試験に失敗すると、独学では無理なのかな…と、心の折れる方もいると思いますが、冷静に自分のダメだった部分を分析して改善していけば、まだまだ伸び代はあると思います。
私も2年目で大幅に得点力が上がったので、諦めずにチャレンジしてほしいなと思います。今後も一級建築士試験に有益な情報をシェアしたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
