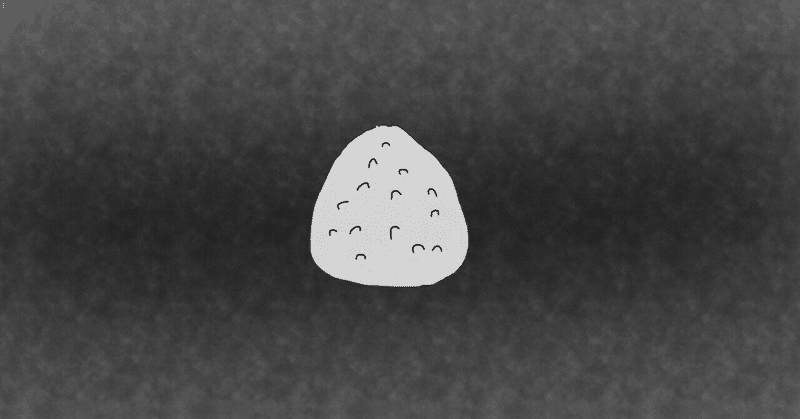
しょっぱくて、何が悪い
以前祖母との思い出を書いたのだけれど、これはその祖母の夫、つまり私の祖父との話。
我が家は共働きだったけれど、夜ご飯はできるだけ家族揃って食べようというルールだった。
大抵父が19時頃に帰ってきて、1時間ほどかけて丁寧な料理を作り、20時半あたりに帰ってくる母を待ってから、いただきますの時間。
当時小学生の自分には、これが結構つらかった。
12時過ぎに学校で給食を食べてから、20時半までのあいだ、お腹が空かないなんてことはない。
姉と兄は、年上なぶん、私より行動の幅や自由が広くて、友達の家に遊びに行ったり、習い事に通ったりしていた。
一方私は、一人で行動するにはまだ危なっかしい年齢だったので、鍵っ子のような感じで留守番をしながら、母が買いためてくれていたスナック菓子が余っていればそれを食べ、夕食までの空腹を凌いでいた。
お菓子があれば、物事はそれで解決する。
食器棚の下の棚がお菓子コーナーになっていたので、こげ茶色のその扉を開けて、とんがりコーンとか、キットカットとか、干し芋とか、何らかあればそれで十分。
あまりにお腹いっぱいになってしまうと、夜ご飯を食べれず怒られかねないから、ほどほどにしないといけない。
でもここで、お菓子のストックがゼロだと、かなり困ったことになる。
まだお小遣いをもらっていなかったから、近所の駄菓子屋さんやコンビニで買おうとしても、大事に取っておいたお年玉の5千円札を切り崩さないといけない。
その5千円札に手を出してしまうことは、当時の私にとって、とても大きなことに感じられた。
どうしようどうしようと考える頭とは裏腹に、空腹レベルは急上昇。
お菓子棚はもちろん、冷蔵庫の中も、冷凍庫の中も、父親のおつまみボックスまで漁ったけど、おやつに食べれそうなものはない。
母から「絶対にだめ!」と口すっぱく言われていたものの、ついに一人でガスコンロを使って、何か作ってしまおうかと思った矢先、祖父がやってきた。
祖父は忙しい両親に代わり、孫の子守り隊員として、よく家に来てくれていた。
紺色で小さい祖父の車が(超安全運転を心がけ、いつでもほぼ最低時速なのではというスピード感だった)、我が家の玄関前の砂利道を、ゴロゴロ音を立てて進んでいく。
「あ、おじいちゃんだ!」と思い、玄関の扉を開ける。
おじいちゃんは「おう、しょうこ、元気かー?」と言う。
私は「そうこ」という名前だけれど、おじいちゃんは「そ」の発音が上手くできず、昔から私のことを「しょうこ」と呼ぶ。
「しょうこじゃない、そうこだもん!」と私は少し拗ねるけど、「ん?しょうこだろ?」と言いながら笑うから、おじいちゃんだけのあだ名として許すことにした。
リビングに入るや否や、私は「ねえおじいちゃん、お腹すいた。なんかお菓子なーい? ガリガリくんとか」と聞く(おじいちゃんはガリガリくんラバーで、よく買ってくれた)。
「ん?今日は何も買ってきてないぞ」と言われ、私はがびーん。
「腹減ったのか?」と聞かれたから、「うん、だって何もないんだもん」と答える。
すると祖父は台所に行き、炊飯器のふたを開けて、冷やご飯が残っていないことを確認。
「じゃあ米食べるか? 塩むすび。」
「えー、おにぎりー? (甘いお菓子が食べたい)」
「じいちゃんが作る握り飯、食べたことないだろ?」
「うん。」
「じゃあ待っとけ。」
そんな会話があって、祖父は白米を炊き始めた。
早炊きモードで、30分ほどだっただろうか。
ほかほかのごはんの匂いが鼻をくすぐって、必死に忘れようとしていた空腹が、待ってましたとばかりの勢いで、再登場。
祖父はまだ湯気がぼうぼうに立ち上る炊飯窯から、しゃもじで大きく一杯、どんぶりにごはんを入れ、濡らした手にじゃりじゃりと塩を馴染ませていく。
どう考えてもやけどしそうな熱さのお米を、塩のついたその手に乗せて、ふっふと浮かせながら、リズミカルに握る。
「ほら、できたぞ」と手渡されたそのおにぎりは、海苔も何も付いていない真っ白な塩むすびで、祖父のこぶしくらいの巨大サイズだった。
待ち望んだ食料を前に、私は熱さも忘れてその巨大おにぎりを素手で持ち上げ、はむっと一口かみしめた。
おいしい、おいしい、おいしい……!
表面にしっかり付いた塩味が、お米をもっと甘くして、具材は何も入っていないけれど、「主食もおかずもお米です」と言わんばかりのお米の存在感。
具材がなくても、甘じょっぱいおにぎりだった。
「おじいちゃん、これおいしい!」
「だろ? 米を食べないとだめなんだ。お菓子ばっかり食べてたら死ぬぞ。人間米を食べないとだめなんだ。」
祖父曰く、そういうことらしい。
我が家では父親が料理することが多かったけれど、京都出身の父は出汁がきいた薄味の料理がベースだったので、普段食べている父の料理と比べると、祖父の塩むすびは法外にしょっぱかった。
ダイレクトな塩分というか、「塩とわかる塩味」という感じ。
でもそれがたまらなくおいしくて、初めてマクドナルドを食べた時みたいな、知ってはいけない味を知ってしまった感覚だった。
父の料理もとてもおいしいので、もうそれは全く別ジャンルということで整理させてもらわないと、父に申し訳なくなる。
でも、とてもおいしくて、何というか体が元気になる味だった。
あまりにもおいしかったから、その後も母に作ってとねだったり、大人になってから自分でも作ってみたけれど、なかなか祖父の味にはならない。
あの時食べた、甘じょっぱさに辿り着かないのだ。
先日姉の結婚式で帰省して、久しぶりに祖父に会った。
披露宴の時、私は祖父の隣の席だったので、だいぶ耳が聞こえにくくなった祖父にも聞こえるように、「この料理はイマイチ」とか「これは食べた方がいいよ」とか、文句混じりの食レポを耳元で伝えながら、2人でぶつくさ話していた。
祖父から「お前は結婚しないのか」と聞かれ、「うーん、私はいいかなー」と答えると、「結婚なんてしなくてもいいんだ。子供なんて、育てるのにお金ばかりかかるし、たまったもんじゃない。会社で偉くなってる女の人は皆子供がいない、お前は社長になればいい」という、若干時代からは怒られそうな自論でアドバイスをくれた。
たぶん、不器用な祖父なりの励ましだったんだと思う。
ついでに言うと、その結婚式の日、久しぶりに私を見た祖父は、第一声で「痩せたんじゃないか? 40kgもないんじゃないか?」と言った。
私が「痩せてないよ。50kg手前はあるよ(事実)」と答えると、「そうか、じゃあそれ以上太っちゃだめだ」と言われた。
おじいちゃんの教え通り、ちゃんとお米を食べて、すくすく育ちますからね。太らない程度に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
