
【小説】また乾杯しよう
「だから中野ちゃんもたまには出ようよ」
いやいや。
私だって、全然外で飲み歩いてないわけじゃない。一緒に行くメンバーが嫌なのだ。大体いまどき、会社で呑み会っていうセンスがもう古い。自分の金と時間を払い出してまで、不特定多数の会社の人と仲良くなりたいって感覚は、最近の若い子には、もう殆ど無いのではなかろうか。
そもそも今どき、オフィスで女性にちゃん付けする人が平気でいるあたりが、もうこの会社はダメだ。
────勿論。そんなことをこの零細企業で言い出しても、なにもはじまらないというのは、私だってわかってる。
私がこの会社で勤めている理由は、恩義のある叔父さんに頼まれて仕方なく、1年だけという約束でパート社員として働きにきているだけのこと。叔父さんには悪いがこの会社には愛着もなにもない。
とはいえ、そんな内心でクールビューティーを気取っている私でも、流石に周囲の空気というものを多少は読む。今回で言えば、先の叔父さんが専務に昇進した記念の懇親会に、私も呼ばれているのだ。これは実に断りにくい。
小さい会社だ。私がどういう縁故でこの会社で働くことになったのかは、殆どの社員の知るところにある。
つまり今、私を中野ちゃん呼ばわりで誘っているうちの課の課長も、そこら辺の「断りづらい」事情を把握した上で、私にこういうことを言っているのだから、少々たちが悪い。
これが都内のそれなりの規模の企業であれば、そもそも私みたいな縁故採用は今どきしないし、こんなパワハラとセクハラのハイブリッドみたいな誘い方をされることもないだろう。もうそこをボヤいても仕方のないところなのだけれど、離婚を機に実家の千葉に戻っている私は、子供もいなかったこともあり、ひとまず何か、フルタイムで働ける仕事に就いていたかった。
────毎日決まった事務仕事で、残業も無い。
いまどきすごい好条件だ。あまり労働意欲の無い私にとって、こうした都合の良い仕事は、ある意味、ここら辺の地方都市でしかもう残っていない気もする。要するに、叔父さんの誘いも、私のそういう足元を見た上での縁故採用なのだ。誰も彼も、優しさの皮を被せて「あなたのため」と言いながら、自分の都合を押し付けてくる。二十歳前から数年続いた結婚生活と、その末の離婚は、人の好意を額面通り受け取ると、痛い目に合うことを教えてくれた。
職場の前任者はそれなりに良くできた人のようだったけれど、妊娠を告げてからあっという間に産休に入ってしまったらしい。その人の代わりに、丁度1年間だけ働ける人を今の会社は探していた。そこに私はあてがわれたというわけだ。
「やっぱり中野ちゃんもたまには出ようよ」
まだ言ってる。 だから、そのちゃん付けは止めてくれないだろうか。
正直、虫酸が走る。顔に出てないかな? うん、今の所、ぎりぎり口角は上がったままで、作り笑顔もたぶん維持出来ている。わたし、えらい。
さて。表情は兎も角、どう穏便に返したものかと、無い頭をひねっていると、思わぬところから声があがった。
「本人、嫌そうにしてるみたいだから、そろそろ勘弁してあげなよ。」
そんな様子を見るに見かねたのか、隣の島にいる他課の進藤課長が、助け舟を出してくれた。
この進藤課長、一見穏やかなナイスミドルだが、何故か周囲からは一目置かれている。彼が喋り始めると周りが聞き耳を立てるのか、急に静かになるために、普段は雑然とした職場でも、この人の声はよく通る。
────でも、その声で私も決意が固まった。
周囲に気を使わせるのは、私も居心地がよくない。叔父の祝いの席でもあるし、今回は顔を立てて出席するとしよう。小一時間程度、適当に愛想笑いをしていれば終わるだけの行事だ。我慢しよう。
「私、今回は出ます。ご存知のように、叔父さんの祝いの席でもありますし。でも二次会は遠慮させてください。」
「無理しなくてもいいんだよ。どうせ大した席じゃないんだから。」
そんな半分ぐらい失礼なフォローを、進藤課長が入れてくれたりもしたけれど、結局、私はその懇親会に出ることに決めた。
思えば私は子供の頃から、ずっと人の顔色ばかり眺めて、自分の意見を決める子だった。親からは、育てやすかったと言われたけれど、私にしてみれば主体性が無いだけの話。
思春期を経て大人になり、子供の頃の主体性の無い自分に嫌気が差したことで、必要以上に人の顔色を伺うことはもうすっかり無くなったけれど、逆に、人に気を遣われるのが苦手になっていた。
それが、周りから見ると、私は気を遣われるほど弱い女じゃない。というアピールになってしまっているらしい。なにやら知人に言わせると、私は「クールな人」と思われているらしい。そんな自身の人物評に違和感はあるけれど、そのイメージに乗っかった方が、社会生活は過ごしやすく、あまり他人に頼らずに今まで生きている気がする。
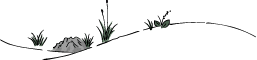
程なく週末がおとずれ、問題の懇親会が開かれることになった。
食事は普通の居酒屋のものだ。しばらく前に作り置いたのか、乾いて油の回った唐揚げに手を伸ばす気はしないし、正直、あまり私の食の好みとは合わないものが、テーブルには並んでいる。
叔父の座るテーブルには、私よりも若い女子社員が配置され、かいがいしく、大皿からサラダを取り分けている。勿論、私はそんなことはしたくはないので、部屋の隅で課のメンバーと同じテーブルにつき、傍からそれを眺めていた。
懇親会は序盤こそ穏やかに進んだが、そこはそれ、スーツを着ていてもおっさん率9割の集団だ。酒が進むにつれ、下品な下ネタが多くなり、2時間の予定を終える頃には、私もすっかり、この場を如何にして抜けようか、ということばかりを考えるようになっていた。
「それでは、ここは一旦お開きにして二次会に向かいましょう~」
すっかり顔を赤くした幹事の声が響く。
意を決するなら今だろう。私は席を立った。
「私はここで失礼します。お疲れさまです。」
「えっ。ほんとに帰っちゃうの? 折角だからもう一軒行こうよ。滅多に中野ちゃんとは呑めないし。」
大きな声で言ったつもりはなかったのに、離れた席に移動していた筈の、うちの課長に目ざとく見つかってしまった。それにしてもその中野ちゃん呼ばわりはホントにどうにかならないのか。
しかも私はあまりお酒が強い方ではない。だから今日呑んだ一杯程度のワインでも、それなりに酔いは回ってしまっている。
そうなれば、私自慢の作り笑顔の精度も、かなり悪くなる。
今の私の顔、大丈夫かな。かなり露骨に嫌な顔してる気がする。まあもういいか。
「今夜は他に予定があるので、失礼します。」
言い切った。私、言い切った。
「いやいや~。たのむよ~。どうせ家に帰ってもやることないでしょ?」
酔ってるとはいえ、いくら私でも、正面からこうも失礼なことを言われると、もう相手をしているのも嫌になる。
もう、無視して帰るか・・
「────よし。それじゃあ俺もその二次会に行くかな。」
突然、進藤課長のバリトンボイスが響き渡る。帰り支度をしている皆の視線が集まっているのを感じる。
「え、進藤課長も二次会に?」
うちの課長が反応した。狼狽えているのは何故だろう。
「ええ。中野さんとは乾杯したいし。中野さんもまた乾杯したいよね?」
えっ? 「また」ってどういうことだろう。またも何も、私は一度も進藤課長とは呑みに行ったことはない。
「あ。は、はい!」
しまった。つい勢いに押されてそのまま返事をしてしまった……
「あー。そうかー。進藤課長と中野さんは呑みに行ったことがあったのか…… な、なんだか無理に誘って悪かったね。二次会は我々だけで行ってくるから大丈夫だよ。」
「えっ? は、はい。」
どうしたのだろう。進藤さんが口を挟んだ途端、うちの課長がものすごく恐縮している。ともあれ、この言いっぷりからすると、どうやら私は二次会に行かずに済みそうだ。
進藤課長に助けられた……のかな?
少しの酔いと、突然の出来事にぐるぐるしながら、小声で進藤課長に礼を言う。
「ありがとうございます。」
「うちの連中もまあ、根は悪くないんだけど酒が入ると、ホラ、ね。」
他の人に気遣いしながらの返答。落ち着いた大人って、こういう人のことを言うのだと思う。
「あの…… 聞いてもいいですか?」
「うん?」
「進藤課長は、どうしてそんなに周りから一目置かれているんですか?」
「うーん。それはね……どうしてだろうね。」
「えーっ。教えてくださいよ。」
好奇心がわいて、自然と笑みになる。 大丈夫、今度は作り笑顔の心配をするまでもなく、心から笑えている。
「それじゃあ、その話は、また乾杯しにいった時にでも。」
「わかりました。約束しましたよ、また。ですね。」
なにかいたずらを考えている時のような顔をして、進藤課長も笑っていた。
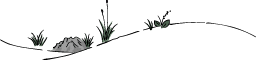
その後、程なく約束の1年は過ぎ。 前任者が産休から戻ってきたことに伴い、予定通り私は退職する運びとなった。
物怖じしない明るい性格で、肉付きの良い、人好きしそうな優しい顔。なんだかこう、幸せが身体からあふれている感じがする人だ。 たぶんこの人は、私なんかよりずっと、ここの職場に向いている。
私はというと、都内での勤務に比べて仕事自体はとても楽だったけど、人間関係が近過ぎるこういった職場は、私の性格には致命的に向いていなかった。1年という歳月は、そんな簡単な事実を確認するには充分な期間であり、私は数ヶ月前から次の就職先を都内で探しはじめていた。
以前はあれほど頻繁に開かれていた、社内の呑み会の類いも、あれ以降、世間ではコロナ禍がはじまってしまい、表向き開かれることもすっかり無くなった。
ちなみにその後、進藤課長が何故ああいう扱い方をされているのかは、新参者の私には解らずじまい。
そもそも人の噂話をするのがあまり好きではない私は、敢えてそれを周囲に尋ねることもしなかった。
けれど、進藤課長への退職の挨拶の言葉だけは、もう心に決めている。
「お世話になりました。また、乾杯しましょう。」
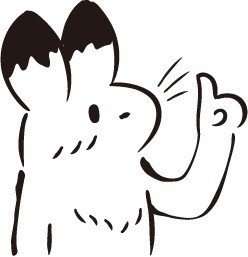
俺はねぇ、饅頭が怖いんだ!俺は本当はねぇ、情けねぇ人間なんだ。みなが好きな饅頭が恐くて、見ただけで心の臓が震えだすんだよ──── ごめんごめん、いま饅頭が喉につっけぇて苦しいんだ。本当は、俺は「一盃のサポート」が怖えぇんだ。
