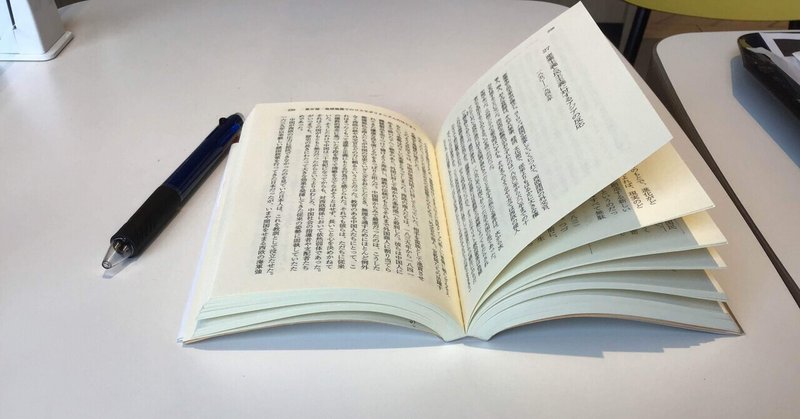
いつかの僕へ
おお…ついに…
読了しました!マックで世界史!
W・H・マクニール『世界史(上・下)』中公文庫
増田義朗 佐々木昭夫 訳
いやー、それにしても長かった……
上下巻合わせて850ページくらいでしょうか。
下巻のカバー裏に、世界の文明の流れをコンパクトにまとめた名著、と書いてあり、いやいやマクニールさんもっとコンパクトに!頼むよ! と…まあ読む前は正直そう思ってましたね。読み終えた今でこそ、よくまとまっていたなあと思いますが。
読み終えるまで一か月以上かかりました。もっとも、この本は高校生のころに買ってちょっと読んで挫折してそのまま放置していたので、買った時から数えると、読み終えるまで十年以上かかったということになります。長い宿題を終わらせた気持ちです…(長すぎる)
でも、まあこれは時間をかけて読む本だと、自分をなぐさめるわけではありませんが、そう思います。学校の授業も時間無制限でずっと先生の話に耳を傾け続ける、なんてことはできませんよね。
たぶん、それと同じです。
この本を、はじめは漫然と頭から読み始めました。やがてしんどくなり、一日一章読もうと決め、決まった時間(ランチ休憩時)に読むようにしました。後半は、産業革命、民主革命(フランス革命)などテーマごとに読むようにし、世界大戦以降はラストスパートで一気に走り切りました。読み方も変えながら、なんとか読破です。
そうそう、どこかのタイミングで「訳者あとがき」を先に読んでおいたのも良かった。分からないところが出て来ても、大きな流れ、著者の歴史観をおさえておくことで、あとから復帰できたり、我慢して読めたり、いろいろと便利なはず。だからこの『世界史』を読み通そうとするつもりなら、まずは上巻で様子を見てから、と言わずに上下巻セットで購入するのをお勧めします。(あとがきは下巻にしかないので。)
マクニール教授によると、
歴史は、ある集団が魅力的な文明をつくりだし、周りがそれを取り入れたり、反発したりして反応をしめす。文明はまたその周囲の反応から影響を受け、あるていど持続する場合は内部からの変革もあって進む。
と、大雑把にいうとこういう感じ。そしてこの史観から、これまた大雑把に、世界史は三つの大きな時期に分けられます。
①紀元前から西暦500年
まず中東に大きな文明ができ、(メソポタミア)その外にギリシャ、インド、中国と文明の焦点が形成されていく時代。
②500から1500年
メソポタミアのような強力な文明の中心地を欠き、新文明もたくさんでき、その相互接触も活発になった時代。
③1500から現代
西ヨーロッパが諸文明間の均衡をやぶり、地球全体に広がり、各地の文化を変容させた時代。
こういうことを先に知っておくと、ずいぶん読みやすくなります。というより、こういうことを知らずにいきなり読み始めるのは、地図もコンパスもなしに航海に出るようなものじゃないかな、と高校生のころの自分に自戒をこめて言いたい気持ちになりました。
高校生の僕はというと、本に読み方があるなんて発想はそもそもなく、ただ頭からケツまで通読することしか考えていませんでした。それしか考えていなかったというより、もはやそれすら考えていなかったと言った方が正確かもしれません。というのは、あのころは、ライトノベルとかゲームとか、読み方を考えずに読めるものしか読んでいなかったから。
あれから月日が流れ、僕もゆっくりではありますが、いろいろ読むようになってきました。小説、批評、文学、哲学、など。いろいろ読むことで、本にもいろいろあるんだなということが、ようやく分かってきたのかもしれません。だったら読み方や読むときの心構えなども、いろいろあって当然だ。
だからこの本はやっぱり、僕が十年かけて読めるようになった本なのかもしれないと、そんな感慨。灌漑ってなんだよ、とふてくされて世界史を投げ出したかつての僕へ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
