
【つの版】ウマと人類史22・絲綢之路
ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。
曹操は烏桓を討伐して移住させ、南匈奴を再編し、ともに騎兵戦力に組み入れて遠征に活用します。のちに鮮卑の大人軻比能は魏の分断工作に遭い、235年に暗殺されました。指導者を失った鮮卑諸部族は、様々に分裂しながら各地に割拠し、魏晋時代を過ごします。ここらで視点を西へ遷し、チャイナとローマを繋いだ「シルクロード」について見てみましょう。
◆絲◆
◆綢◆
魏略西域
この頃、西域諸国はどうなっていたでしょうか。前に「大秦への旅」でやりましたが、『魏略』西戎伝をおさらいしましょう。
氐、貲虜、羌、タリム盆地諸国、大月氏(クシャーナ朝)、大宛(フェルガナ)、安息(アルサケス朝パルティア)、條支(アンティオキア/セレウコス朝)、烏弋山離(カンダハール)、大秦(ローマ)については、すでに見ましたのでやりません。天竺(インド)は飛ばします(いずれインド関連でまとめてやろうかと思います)。大秦の次の記事から見ていきます。
北新道西行、至東且彌國、西且彌國、單桓國、畢陸國、蒲陸國、烏貪國、皆並屬車師後部王。王治于賴城、魏賜其王壹多雜守魏侍中、號大都尉、受魏王印。轉西北則烏孫、康居、本國無增損也。

北新道とは、敦煌の玉門関から北西へ向かい、高昌(トルファン)を経てジュンガル盆地へ入る道です。南道はタリム盆地南部、旧北道はタリム盆地北部を通ってパミール高原を抜けるのに対し、この道は比較的通りやすく、のちの玄奘三蔵もここを通っています。かつてトルファン盆地には姑師国があり、匈奴に服属して交易路を牛耳っていましたが、前110年に漢に敗れ、国号を車師国と改めました。漢はこの国を前後に分割し、のち戊己校尉を置いて統治しましたが、後漢が衰えると放棄されました。魏の頃にも王国は存続しており、魏はその王に印綬や爵位・官位を与えて手懐けています。
そこから北西へ進むと、前漢以来の独立国である烏孫(セミレチエとキルギス)、大宛(フェルガナ)、康居(タシケント、チャーチュ)が連なっています。康居には北匈奴や西匈奴の残党が逃げ込んでいました。
北烏伊別國、在康居北。又有柳國、又有岩國。又有奄蔡國、一名阿蘭。皆與康居同俗。西與大秦、東南與康居接。其國多名貂、畜牧逐水草、臨大澤、故時羈屬康居、今不屬也。
康居の北には北烏伊別国、柳国、岩国、奄蔡(阿蘭)などの国々があり、みな康居と習俗は同じで、西は大秦(ローマ帝国)に接しています。その国は名貂が多く、水や牧草を追って遊牧し、大きな澤(アラル海やカスピ海)に臨んでいます。かつては康居に従っていましたが今は独立しているといいます。このうち最後の奄蔡/阿蘭は、ローマの史料でいうアオルソイ/アランにあたり、イラン系遊牧民サルマタイの一派です。
『史記』大宛列伝や『漢書』西域伝によれば、奄蔡は康居の西北二千里に在る行国(遊牧部族)で、習俗は康居と同じく、弓を扱う者は10余万います。また果てしない大きな澤に臨んでおり、これがおそらく北海ではないか、と記されています。『後漢書』西域伝には「奄蔡国改め阿蘭聊国」とあり、アオルソイとアランが合体したアラノルシイをいうようです。『魏略』にいう柳國とは阿蘭聊国が分かれて伝わったものでしょうか。
呼得國、在蔥嶺北。烏孫西北、康居東北。勝兵萬餘人。隨畜牧、出好馬、有貂。堅昆國、在康居西北。勝兵三萬人、隨畜牧、亦多貂、有好馬。丁令國、在康居北、勝兵六萬人、隨畜牧、出名鼠皮、白昆子、青昆子皮。此上三國、堅昆中央。俱去匈奴單于庭安習水七千里、南去車師六國五千里、西南去康居界三千里、西去康居王治八千里。
呼得は呼掲の写し間違いで、烏掲とも書かれ、のちのウイグルないしオグズのことです(これら自体が単に「部族」を指しますが)。烏孫の西北で康居の東北だと、タラスの北のチュイ川流域やその北、バルハシ湖以北の平原でしょうか。堅昆(クルグズ)はミヌシンスク盆地の住民ですが、康居の西北であれば呼掲の西で、丁令は康居の北にあるといいます。しかし堅昆はこの三国の中央にあるともいい、どうも方向がおかしいですね。だいたいカザフスタンの平原に、馬や鼠はともかく貂はいません。
また堅昆等の三国は、かつての匈奴単于庭である安習水(安昆水=オルホン川)から7000里、南の車師六国(トルファン)から5000里、西南の康居の国境から3000里、西の康居王の都から8000里離れているとあります。1里が434mとするとそれぞれ3038km、2170km、1302km、3472kmにもなりますが、カラコルムから3000kmも離れればウラル山脈かシベリアの彼方です。
そこで例によって5倍誇張とすれば、カラコルムから1400里(607.6km)北は、バイカル湖西岸のイルクーツク。トルファンから1000里(434km)北はアルタイ山脈。タシケントから1600里(694.4km)北東はバルハシ湖。チュイ川から600里(260.4km)北東もバルハシ湖です。すなわち、丁令はバイカル湖付近、堅昆はミヌシンスク盆地とアルタイ山脈、呼掲はバルハシ湖の北に割拠し、モンゴル高原西部を北から取り囲んでいるわけです。これらの国からは貂などの毛皮や金属資源がもたらされ、各地へ輸出されました。

或以、爲此丁令即匈奴北丁令也、而北丁令在烏孫西、似其種別也。又匈奴北有渾窳國、有屈射國、有丁令國、有隔昆(堅昆)國、有新梨國、明北海之南自復有丁令、非此烏孫之西丁令也。
ここは魏略が混乱しており、「匈奴の北の丁令と烏孫の西の丁令は別である」としています。ややこしいことに丁令とは「テュルク」の音写で、やがてテュルクを名乗る諸部族がユーラシア大陸の各地へ大拡散していきます。とするとすでに烏孫の西にはテュルクが広がっていたのでしょうか。
烏孫長老言、北丁令有馬脛國。其人音聲似雁騖。從膝以上身頭人也、膝以下生毛、馬脛馬蹄。不騎馬而走疾馬、其爲人勇健敢戰也。
烏孫の長老が言うには、北丁令に馬脛国がある。その人々の音声は雁に似ている。膝から上の身体と頭は人で、膝から下には毛が生えており、馬の脛と馬の蹄である。彼らは馬に騎乗せず、疾走することは馬のごとく、勇敢で好戦的である。
『山海経』海内経によると、北海の内に幽都の山があり黒水が出ています。そこには色が黒(玄)い禽獣が住まい(五行で黒・玄は北に配されます)、大玄の山、玄丘の民、大幽の国、赤脛の民、そして釘霊の国があります。その民は膝から下が毛に覆われ、馬の蹄があって善く走るといいます。これは魏略の馬脛国の伝説とほぼ同じです。ウマ娘の国でしょうか。釘霊とは丁令や丁零と同じで、やはり「テュルク」のことです。
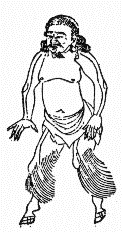
またヘロドトスによれば、アルギッパイオイ(ウラル山脈西麓の民)の言い伝えに、山々の彼方には山羊の脚を持つ人間が住むといいますから、釘霊国の民とはこれと同源の伝説でしょう(白鳥庫吉も指摘しています)。プリニウスの『博物誌』にも「インド東部の山奥にはサテュロス(山羊の脚と角を持つ精霊)がおり、非常に敏捷で捕まえられない」とあり、他にも山海経に出て来るのとよく似た怪物・怪人種たちが並べ立てられています。
特に有名なのが、頭がなくて胴体に顔があるブレムミュアエ/アケファロイ(頭なし族)です。山海経の刑天にそっくりですが、たぶん「彼らには頭(首領)となる者がいない」「頭(首領)を殺しても戦い続けた」という伝説を額面通りに受け取った結果、こんな怪物が生まれたのでしょう。
ケンタウロスはギリシア神話に登場する怪物で、ギリシア北方のテッサリア地方に住み、馬の首の代わりに人間の上半身が生えている姿で有名ですが、古くは馬の脚を持つ人間として表現されたこともあったようです。インド神話のキンナラ(緊那羅)という半神的種族も半人半馬の姿をしており、いずれも騎馬遊牧民の姿を怪物化したものでしょう。
短人國、在康居西北。男女皆長三尺、人衆甚多。去奄蔡諸國甚遠。康居長老傳聞常有商度此國、去康居可萬餘里。
短人国は康居の西北にある。男女はみな身長が3尺(70cm)しかなく、人口は甚だ多い。奄蔡などの諸国から遥か彼方にある。康居の長老が伝聞するところでは、この国と常に商取引があり、康居から1万里の彼方だという。
プリニウスの『博物誌』やギリシア神話にも見える小人族の国です。インドやリビア(アフリカ)の奥地にあるともいいますが、タシケントから1万里=4340kmも北西へ行くとスカンジナビア半島の真ん中あたりで、5倍誇張とみなして2000里=868kmならアラル海のほとりです。このあたりで人口が多いというのであれば、アラル海の南部にホラズムがあります。
ホラズム(フワーリ・ズム、低地)には非常に古くから定住民がおり、ゾロアスター教の聖典『アヴェスター』やアケメネス朝ペルシア帝国のダレイオス1世によるべヒストゥーン碑文にも見えます。河川がアラル海に注ぐ肥沃な土地で、交易も盛んでした。ソグディアナやフェルガナと同じく東イラン系の住民がいましたが、これを短人国というのは「土地が低い」というのを「住民の身長が低い」と間違ったのでしょう。よくあることです。
『魏略』西戎伝の記述はここまでで、後は評が続いています。しからば、ギリシア・ローマなど西方諸国からは、中央アジアやチャイナはどのように見えていたのでしょうか。
絲綢之路

西暦150年頃、エジプトの地理学者クラウディオス・プトレマイオスが記した『地理学(ゲオグラフィア)』では、すでにアフリカとユーラシア大陸の相当部分が判明しています。しかしカスピ海から東は非常に大雑把で、スリランカ(タプロバネ)がやたら大きくなっています。

ガンジス川の彼方、インドシナ半島らしき「黄金の半島」の東には「マグヌス・シヌス」という大きな湾があり(トンキン湾でしょうか)、その北にシナエ(Sinae)、すなわちチャイナがあります。166年には大秦王安敦(ローマ皇帝アントニヌス)の使者がベトナムまで来ていますから、エジプトからアラビア海・インド洋を通ってチャイナに到達する「海のシルクロード」はすでに存在していました。では、陸路はどうでしょうか。

イラン高原・インド・シナエの北には山脈が連なり、広く「スキティア」と総称されています。カフカースの北、マイオティス湖(アゾフ海)とカスピ海の間には「アジアのサルマティア」とあり、黒海北岸はヨーロッパのサルマティアということになります。その東、ヴォルガ川の彼方には「イマウス山脈(ヒマラヤ/パミール高原)のこちら(西)側のスキティア」がソグディアナの北にあり、さらに東に「イマウス山脈の彼方(東)のスキティア」があって、その東に「セリカ(Serica/Serika)」があります。
絹を英語でシルク(silk)といいますが、これはギリシア語セーリコス(serikos)、セール(ser)に遡ります。絹は古代西洋には産出せず、遥か東方から外国の商人が運んでくる珍しい織物でした。ギリシア人は彼らをセレス(Seres)といい、その国をセリカ(絹の国)と呼んだのです。チャイナでは絹織物を古く絲(上古音slɯ)と呼んだため、これが西方へ伝わってセール、シルクとなったのです。古テュルク語では絹織物をtorkoと呼び、モンゴル語に入ってtorgo、チベット語でdarとなっています。
最も古くは、紀元前5世紀末にペルシア王に仕えたギリシア人医師クテシアスが『インド誌』でセレスについて触れ、「驚異的な長身と長寿の人々」と記しています。紀元前後、ローマ帝国の地理学者ストラボンもセレスの長寿について触れており、またバクトリア王国の国境はセレスやプリュノイ(Phrynoi、パミール高原の住民か)に接するまで広がっていたと記録しています。崑崙山の仙人や西王母の話が伝わったのでしょうか。
アウグストゥスの頃の詩人ウェルギリウスは「セレスでは森の木の葉から羊毛のような繊維をとる」と歌っており、ストラボンも絹のことを「樹皮からとるもので綿に似ている」としています。絹がチャイナからギリシア・ローマまで伝わったのはセレウコス朝やパルティアを介してでしょう。
ストラボンと同じ頃、ローマの地理学者ポンポニウス・メラは「セレスの地はアジアの最も東にあり、南のインドと北のスキティアに挟まれている」と記しました。彼らは雪や蛮族、野獣のために道が塞がれて孤立しており、沙漠のある場所に品物を置いて距離をとり、別の者たちがそれを取って代わりの品物を置いていく「沈黙交易」を行うとも記されています。
プリニウスによると、スキタイや野獣の住む東の荒野の彼方にタビスという山脈があり、その向こうに断崖があって、海に臨んでいます。海岸沿いに北東へ進むとセレスという民がおり、森から毛織物を収穫します。その地の鉄はパルティアのものよりも優れており、住民は背が高くて亜麻色の毛髪と青い目を持ち、浜辺で沈黙交易を行うというのです。どうもチャイナ本土ではなく、タリム盆地あたりのコーカソイド系住民を指しているのかも知れません。詩人ホラティウスは「セリカの弓矢の民(Sericae Sagittae)」の語を用いており、中央アジアの騎馬遊牧民としていたようです。歴史家ディオニュシオスも「セレスは、よく知られる織物を生産する国民で、トハロイやプリュノイと同じくスキティア人の一種族である」とします。
1世紀頃には、バクトリアを経てパミール高原の麓の谷を通り抜け、セリカの首都セラ(長安?)に至る通商路がエジプトで知られていました。また海路でシナエ/ティーナイという国に到達するルートも知られていたのです。プトレマイオスはこうした情報を総合して、シナエとセリカを南北に別々に存在するとし、セレスをヘロドトスの伝える遊牧民イッセドネスと同一視しました。伝聞を重ねたためやや奇妙ですが、当時一級の知識人にとっても、チャイナや中央アジアの地理についてはこの程度でした。
◆絹◆
◆音◆
東西の史料のエアポケットめいたこの地域から、やがてエフタルやフンが湧き出してきます。彼らについて見る前に、東へ戻り、南匈奴や鮮卑のその後を見て行きましょう。
【続く】
◆
つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。
