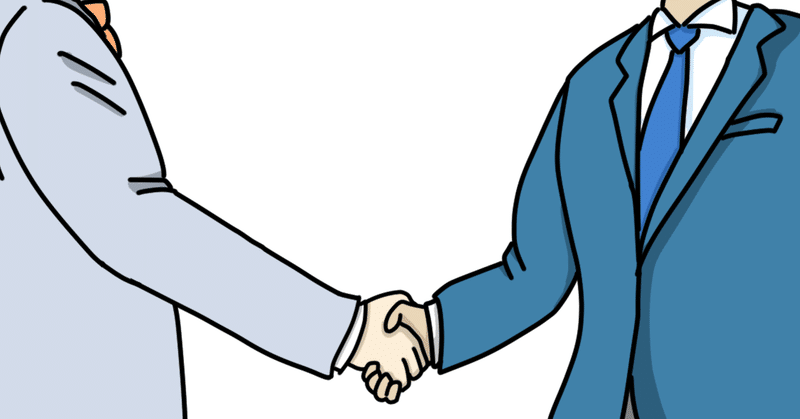
相互の「ズレ」を埋めるビジネス力
おはようございます 渡辺です。週末はとても良い天気でしたね。昼間は半袖、夕方からは長袖みたいな気候が好きです。
週末、方針発表の際に山本さんが紹介していた「無敗営業」 - 高橋浩一 を読みました。
営業だけでなく、採用だったり、仕事におけるコミュニケーションにも応用できることが多いとおもいますので、紹介します!
仕事の成否を分けるのは情報ギャップ
まずですが、仕事の成否を分けるのは、相手と自分の間にある情報ギャップであり、それが相互の「ズレ」につながっていきます。そのため、情報ギャップを埋めるコミュニケーションが相手の理解や信頼獲得につながってくるわけです。
また、営業案件において難易度を「楽勝」「接戦」「惨敗」に分けると、大抵の案件は「接戦」であり、この接戦でいかに勝ち星を挙げるかが、総合的な成果につながっていくわけです。また接戦を3つのパターンに分けるとすると、
a.当社 or 他社
b.今やる必要があるか(一旦保留)
c.内製できないか
の3つとなります。少し違うかもしれませんが、採用だと a.当社 or 他社、b.一旦保留、c.転職をやめる みたいな感じですかね?
このような接戦における心理状態においては、情報が追加されることで、結論が変わるという性質を持っています。例えば、オファーの金額が想定よりも高かったとか、CTOとの面談により、開発部門の雰囲気がより伝わったとかです。
という訳で、明日は「接戦を制する3つの質問」について触れていこうと思います。それでは、10月も本日でおしまいですね。
今週もよろしくお願いいたします!
接戦を制する3つの質問
おはようございます 渡辺です。今日から11月。あっという間に今年もあと2か月ですね。さて、「無敗営業」2日目の今日は、「接戦を制する3つの質問」を紹介します。
「接戦を制する3つの質問」とは、
1.接戦状況を問う質問
2.決定の場面を問う質問
3.裏にある背景を問う質問
の3つになります。
「接戦状況を問う質問」
まず、1つ目の「接戦状況を問う質問」ですが、意外と多くの営業が戦況を把握せず戦っているという事です。限られた時間というリソースを活用するためにも、楽勝なのか?接戦なのか?惨敗なのか?を把握することで、注力すべき案件の優先順位を明らかにすることが重要です。
先ずは、昨日も触れた接戦の3つのパターンのどれにあたるのか?それぞれに応じた対策を打つという事。そのうえで、BANTCHと呼ばれる営業現場で確認すべき6つの事項を漏れなく確認することです。
Budget(予算)
Authority(決裁者)
Needs(ニーズの抜け漏れや優先順位)
Timing(検討や導入のスケジュール)
Competitor(競合)
Human Resource(お客さま側の人員体制)
裏にある背景を問う質問
2つ目の前に、3つ目の「裏にある背景を問う質問」に行きます。こちらは、相手との会話の中で情報ギャップを埋めて、自分の知らない相手の情報や認識を得て、相手の課題解決に役立てていくというものです。
とはいえ、余り関係性が築けていない方とのコミュニケーションにおいて、いきなり切り込むのは気が引けてしまうかもしれません。そこで、一言添える「枕詞」がいくつか紹介されています。
「もし仮にXXXという点がクリアされたら・・」(前提の変更)
「あくまで個人的な意見で構いませんので・・」(回答リスク軽減)
「御社のビジョン実現にお役立ちするために伺いたいのですが・・」(意図の伝達)
これらを上手く活用しつつ、深堀や特定を行いながら、相手の背景を明確にしていくことが重要ですね。
決定の場面を問う質問
最後2つ目の「決定の場面を問う質問」です。これにより、自分たちの強みや価値が明らかになり、「相手は何が決めてで我々を選ぶのか」に対する理解が進んでいきます。
この3つの質問をうまく重ねることで、接戦における勝率があがるようなアクションがとれるようになってくるわけですね。それでは、本日もよろしくお願いいたします!
ズレを解消する「4つの力」
おはようございます 渡辺です。いい天気が広がっていますね。さて、「無敗営業」3日目の今日は、ズレを解消する「4つの力」を紹介します。
昨日触れたとおり、「接戦を制する3つの質問」を中心にPDCAを回すことで、接戦に関する情報が蓄積されることにより、「どう選ばれるか」がブラッシュアップされ、勝ちパターンを築くことができるようになってきます。
もう一方、この本のキーワードでもある、「ズレ」。4つの「ズレ」とそれを解消する4つの力を紹介します。
要件ヒアリングが不十分、情報把握ができていない
→ 理解のための「質問力」不足
担当者としての魅力や価値を感じない
→ 必要される「価値訴求力」不足
意図に沿わない提案をだしてくる
→ 意思決定を助ける「提案ロジック構築力」不足
動きが悪い
→ 段取りを進める「提案行動力」不足
敢えて、「お客さま」や「営業」というワードを排除しているのですが、その分ふだんの仕事にも応用できる内容ではないでしょうか?
「質問力」と「価値訴求力」はコインの裏表で、質問により相手を深く理解すれば、的確な情報提供が行え、その結果として価値提供力があがり、さらに質問をしやすくなります。
このサイクルを回して取得した情報を元に、提案を組み立てる力が、「提案ロジック構築力」であり、忙しくて時間の限られている相手とのやりとりをスムーズに進める力が、「提案行動力」になるわけです。
如何でしょうか?明日は、このグッドサイクルの1つ目「質問力」について掘り下げておしまいにしようと思います。それでは、本日もよろしくお願いいたします!
ピラミッド構造を意識した「深堀り質問」
おはようございます 渡辺です。今日もいい天気が広がっていますね。
さて、「無敗営業」最終日の今日は、ズレを解消する「4つの力」の1つ目「質問力」からピラミッド構造を意識した「深堀り質問」を紹介します。これも営業だけに限らず、仕事の様々なシーンで応用できる力になりますね。
念のため、ピラミッド構造とは、トーナメント表のようなもので、頂点に大きなイシューが置かれ、頂点に近づくほど抽象度が高く、末端に近づくほどより具体化された情報になります。
では、「深堀り質問」4つについて紹介します。短い一言の質問を投げかけることで、相手にボールを戻すことによって、相手の考えを構造化していくようなイメージです。
1.相手の発言内容を明確にする質問
例:「と、おっしゃいますと?」
「人的資本経営が大事なんだよ!」みたいな曖昧なことを相手が言った場合に、言い換えを促す質問です。「要は、今の時代『人』こそが経営の要であって・・」みたいにその人の考えにもう一歩踏み込むことが出来ますね。
2.詳細を引き出す質問
例:「具体的には?」
課題のピラミッドの下段を聞き出す質問です。抽象的な内容からより具体的なアクションに近づいていく質問になります。場合によっては、「そこは、これから」という事もあると思いますが、そんな時は、逆に自分の考え「例えば、こんなイメージですか?」とかをぶつけるとよいでしょう
3.背景を引き出す質問
例:「なぜでしょうか?」
課題のピラミッドの上段を聞き出す質問です。具体的なアクションから抽象的な内容によりに近づいていく質問になります。具体的なアクションを挙げられた時に、その背景を確認していくことが、相手とのズレを無くすのに必要ですね。ストレートに「その背景には何がありますか?」と聞いてもいいですね。
4.網羅感を確認し全体像を捉える質問
例:「他にはありますか?」
課題のピラミッドの横方向を探り、抜け漏れを聞き出す質問です。見落としていそうな情報を探していくことで、具体レイヤーでは、具体的な施策が。抽象レイヤーではそこに至った背景がよりくっきりと浮かびあがってきます。
これらの質問を駆使しながら、時折、言い換えや要約をしつつ、相手の考えを代わりに構造化してあげることが出来ると、with Onemile 頼れる仲間に近づきますね。
如何でしたでしょうか?紹介しきれなかった具体的な内容が他にもたくさん含まれていますので、ぜひ手に取ってみてみてください。
それでは、今週もあと1日。本日もよろしくお願いいたします!
(2022.10.31-11.04)
サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。
