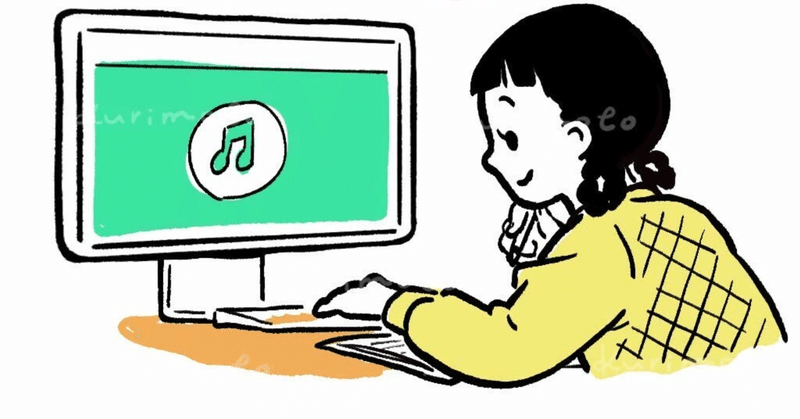
パフォーマンスを左右する「やる気」
おはようございます 渡辺です。4連休を頂きましたが、特に何かをする訳ではなく、いつも通り本を読んだり映画を観たりとと、のんびりと過ごしておりました。
おかげさまで、本は何冊か読めたので、順番に紹介していこうと思います。今週は、「こうして社員はやる気を失っていく」- 松岡保昌 から紹介します。
企業のパフォーマンスを左右するのは「やる気」
基本的には、メンバーがやる気を失わない為に、マネージャーに向けた本ではあるのですが、一般層のみなさんにも参考になりそうなところをかいつまんで紹介します。
本の内容に入る前に、グロースハックのAARRRモデルというのがあるのですが、これを人材にあてはめてみると以下のように表せると思います。
Acquisition:獲得 → 採用
Activation:活性化 → オンボーディング(就業開始。周りとの関係性構築)
Retention:継続 → 社員として活躍
Revenue:収益化 → 成果を上げる
Referral:紹介 → リファラルで知り合いを紹介
+
Churn:離脱 → 退職
(詳しいイメージは、AARRRで画像検索してみてください)
この最初のA以降のパフォーマンスを左右するのが、「やる気」であり、この本では、幾つかの事例を交えながら、先輩や上司の不用意な言動により、「やる気」が下がるかを知ることができます。
また、今の時代「企業力の格差」は、一人一人の「やる気」に起因しています。(本の中では、「モチベーション」という言葉が使われていますが、前の流れを汲んで、敢えて「やる気」で)OCでも大切にしている、メンバーひとりひとりの「当事者意識」こそが、強い会社とそうでない会社を分けるという事です。
という訳で、明日は「当事者意識」についてもう少し掘り下げていこうと思います。それでは、今週もよろしくお願いいたします!
「主体性」が生まれる為の「当事者意識」
おはようございます 渡辺です。今朝もいい天気が広がっていますね。
さて、今日は「当事者意識」について触れていこうと思います。この本には以下のように書かれています。
自ら考えて動く。積極的にチャレンジする。このような行動が習慣化し、それを大切にしている組織に共通する特徴は、社員に「主体性」があることです。(中略)「主体性」が生まれる大前提となるのが、「当事者意識」です。
また、「主体性」に似た言葉である「自主性」との違いについては、
決められたことを率先して行うのが「自主性」であり、
何をすべきか自分で考え、行動し、結果に責任をん持つのが「主体性」
と書かれています。
さらに、どのようにして、「当事者意識」が生まれるのか?これに関しては、
仕事が会社のためだけではなく、
自分のためでもあると心の底から思える時です。
会社における仕事は、会社運営における重要なピースの一つであるわけですが、それをやることが、自分自身の人生やキャリアにおいても、意味や意義があることだと思えることで、「自分事」になってくるわけです。
如何でしたでしょうか?必ずしも、これが「当事者意識」の正解というわけではありません。これをきっかけに、自分が考える「当事者意識」って何だろう?とあらためて、自問自答してもらえると嬉しいです。
それでは、本日もよろしくお願いいたします!
「やりがい」とは?
おはようございます 渡辺です。昨日は、清水さんに教えて頂いたおかげで、月食を観ることが出来ました。442年ぶりってすごい時間感覚ですね。
昨日は「当事者意識」について触れましたが、本日は、仕事のパフォーマンスを向上させる「見えない報酬」である、「やりがい」について考えてみます。「やりがい」について、大きく2つが挙げられていますが、まず1つ目は「仕事の目的」です。
「仕事の目的」
何度となく、事例を出しているレンガ職人の話があります。「ただ、レンガを積んでいる」だけでなく、「生活のため」でなく、「歴史に残る大聖堂を建て、おおくの人が祝福を受けるため」まで昇華させることが出来ると、仕事の意味や意義が変わってきます。3人のレンガ職人はやっている作業は同じはずですが、「やりがい」としては大きく変わってきます。
ABC理論というのがあるのですが、Aが出来事(Activating events)、Bが認知の仕方(Belief)、C が結果的に起こる感情(Consequences)の頭文字をとったものです。
Aという同じ出来事があったとしても、C の感情を引き起こすのは、Bの認知の仕方次第であるという事です。先のレンガ職人にあてはめてみるとこんなかんじですね。
ただ、レンガを積んでる → しんどい
生活のため → 仕方がない
大聖堂を建てる → 名誉なプロジェクトに参加出来て嬉しい
A → B1 → C1、A → B2 → C2、A → B3 → C3 のように、スタートのAは同じでもその受け取り方Bによって、Cが変わってくるという事です。
「承認」「称賛」「尊敬」
2つ目は、「承認」「称賛」「尊敬」です。中々機会もすくないですが、僕自身やっぱり、ほめられると嬉しいものです。またついつい、日々滞りなく業務が進んでいると忘れがちになってしまいますが、逆に滞りなく日々が過ぎていることに改めて、感謝したいと思います。皆様いつもありがとうございます!
ぜひ、みなさんも日々のさりげないやり取りの中でしたり、また直接言うのは気恥ずかしい場合は、ワンマイル賞に投稿するなど感謝を伝え合う事が出来ればと思います。
という訳で、今日は「やりがい」について考えてみました。
それでは、本日もよろしくお願いいたします!
「認知」について
おはようございます 渡辺です。今日も朝からいい天気ですね。
昨日は「やりがい」について触れました。そこでのレンガ積み職人の話における「認知」について考えてみようと思います。
第3者的に、寓話として聞いている分には分かりやすい話ですが、当事者となるとついつい1人目のレンガ職人になってしまうかもしれません。そうならない為に、必要なのが「ゼロベース思考」です。ゼロベース思考とは、今まで自分たちが常識だとおもってきたような、前提や思い込みにとらわれず、ゼロから物事を考えることです。
VUCAと呼ばれるこの時代においては、外部環境は常に変化しています。そこでサバイブしていくためには、過去の成功体験や考え方だけに頼っていては難しいです。思い込みや先入観にとらわれず未来思考で、「本当にそうか?」と問うことが必要ですね。
もう一方で必要な考え方として、「残すべきもの」と「変えるべきもの」の明確化です。自分の根底にある価値観や大切にしたいものコトに関しては、不変の真理として無理に変える必要はないかもしれませんが、一方で変えた方がいいものや、変えるべきものは、1日も早く変えていった方が良いですね。
日々忙しく過ごしていると、ひとつひとつに対し、「本当にそうか?」と問いている暇はないかもしれませんが、たまには立ち止まって、「残すべきもの」と「変えるべきもの」を自分に問うてみる時間を確保していきたいものです。それでは、本日もよろしくお願いいたします!
「やる気」を左右する「幸せの4因子」
おはようございます 渡辺です。いい天気が続いて嬉しいです。
今週は、「やる気」「やりがい」「認知」などについて考えてきましたが、結局のところ幸せに働けることこそが、「やる気」につながってくるかと思います。そこで、最終日の今日は慶應の前野教授による「幸せの4因子」を紹介します。
前野教授によると、「幸せ」は自分でコントロールできるものであり、幸せに影響する要素はたくさんあるが、主なものがこの「幸せの4つの因子」と呼ばれるものになります。
1.「やってみよう!」因子 = 主体性に関する因子
勉強や学びなど、新しいことに挑戦すること、小さなことでもチャレンジすると成功したり失敗することもありますが、結果として成長することにより幸せを感じることが出来ます。
2.「ありがとう!」因子 = つながりと感謝の因子
感謝をする人の方が幸せだし、他人のために何かを貢献できる人ほど幸せを味わうことが出来ます。またつながりは、数よりも多様性の方が幸せにつながるという研究もあるそうです。相似な関係ではなく、弱くても多様な関係を持っている人の方が幸せを感じるそうです。
3.「なんとかなる!」因子 = 前向きと楽観の因子
ポジティブな人の方が、「なんとかなるでしょう」ということでリスクテイクできるので、挑戦もできるということで、第1因子にもつながりますが、確かにいつまでもクヨクヨしているよりも、前を向いていける人の方が幸せな感じがしますね。
4.「ありのままに!」因子 = 独立とあなたらしさの因子
ヒトはヒト、自分は自分。あまり他人とは比較せず、自分自分の好きなことや得意なこと、ワクワクすることを突き詰めていくこと。人の目を気にせず、自分のペースを持っていることが幸せにつながります。
ここまでで気づいたかもしれませんが、幸せを形成するのは、「認知」の仕方であったり、「やる気」「やりがい」を左右するのは、感謝や主体性だったりする訳です。
前野教授はTEDの講義もあるので良かったら見てみてください。
それでは、今週もあと1日ですね。本日もよろしくお願いいたします!
(2022.11.07-11.11)
サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。
