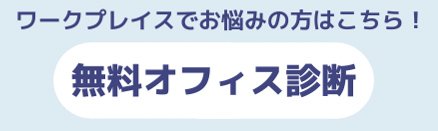今はまだ、変革の通過点。ワークスタイルの変化と、課題への向き合い方について
コロナをきっかけに働き方をガラッと変えられた、HEROZ株式会社さま。もともとは毎日オフィスに出社していましたが、今では業務の大部分を在宅勤務で行っているそうです。一方、コミュニケーション面での弊害を解決するための様々な工夫もされてきました。働き方改革とコミュニケーション対策について、人事部長の桑原さま(写真右)と広報の小林さま(写真左)にお話を伺いました。
HEROZ株式会社
設立:2009年
事業内容:AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用
オフィス:東京都港区芝5-31-17 PMO田町 2階
リモートワークという選択肢ができたことで、今まで見えなかった無駄や負担に気がつけた
── コロナを機に働き方を柔軟にされたそうですね。どのように改革されてきたのか教えてください!
桑原さま:コロナ前は毎日出社が当たり前でした。今のオフィスに移転したのはコロナ前でしたが、メンバー全員が入る広さをしっかり確保していたんです。そんな中、コロナが流行し、在宅勤務を推奨する流れになりました。
小林さま:会社としても、オフィスでの密を避ける必要がありましたし、電車通勤によるメンバーの感染リスクを軽減したかったので、在宅勤務を推奨しました。
桑原さま:第一回目の緊急事態宣言の際に、在宅勤務ができるようにし、推奨しました。その後、感染状況が緩やかになったタイミングで、オフィス勤務を前提としていた働き方を見直し、オフィス勤務か在宅勤務かは個々人が自律的に判断し、併用することを是としました。
小林さま:リモートワークを申請しても、却下されることは基本的になかったため、徐々に在宅勤務の割合が増えていきました。こうした状況を受け、2020年冬ごろに正式に制度として在宅勤務を導入しました。
桑原さま:私は2020年夏に入社したのですが、その頃がちょうど働き方の転換期で。人事責任者として働き方を整える必要があったので、入社後すぐに全社員と面談し、「在宅勤務についてどう思いますか?」というヒアリングをしました。基本的に好意的な意見が多かったですね。中には「寂しい」という声もありましたが、選択肢として在宅勤務があること自体は歓迎されました。

── 徐々に在宅勤務という形に慣れていったのですね。現在はどんな状態ですか?
桑原さま:出社・在宅を選択できるようにしたので、人によって勤務スタイルが大きく違う状況です。出社頻度のルールも、特に設けていません。ほぼリモートワークのメンバーも多いですが、一方で、オフィス出社がほとんどのメンバーもいます。出社しているのは全体の5%くらいです。リモートワークをしている人の方が圧倒的に多いですね。
こうした状況なので、実は、完全にリモートワークに切り替えるか、フルリモート前提で地方採用を行うことも検討や議論も継続して行っているんです。ですが、まだ結論は出ていません。社員にもアンケートをとり、意見をたくさんもらっています。やはり、オフィスをなくすことや、フルリモート前提の採用を増やすことには、慎重な意見が多いですね。一度実施したら元には戻しづらいので、ディスカッションは当面続くと思います。
小林さま:現状は出社とリモートのハイブリッドで、両方のメリットをうまく使う方向性が支持されている気がします。ちなみに会社としては、「働きやすさや仕事に対するコミットの仕方を考えて、自律的に選んでほしい」というスタンスなんです。住んでいる場所や家庭の状況、業務の内容によっても、ベストな働く場所は人それぞれですからね。
桑原さま:リモートワークのメリット・デメリットは、それぞれの価値観や在宅での就業環境、日々のタスク内容などによって変わるものだと思います。たとえば、通勤時間を減らして稼働時間を確保したい日もあるでしょうし、複雑な議論が必要な日は、ホワイトボードを囲んでみんなで集まって話した方がいいと思います。
小林さま:エンジニアは自宅に開発環境が整っている場合が多いので、リモート率が高いです。逆に、コーポレート職は比較的出社していることが多いですね。業務によっては、対面で行った方が効果的なこともありますし。
桑原さま:リモートワークを取り入れると同時にフレックスタイム制も導入したので、決まった時間に全員出社するという「当たり前」がなくなって、働き方の選択肢は増えたと思います。全員が同じ時間同じ場所に集まるという慣習は、ある意味では個々人にも負担があったと思うんですよね。コロナを機に、今まで見えていなかった無駄や矛盾が明るみになったと思います。コロナが収束しても、柔軟になった生活様式やビジネス慣習は、なかなか元には戻らないのでは、とも思います。
小林さま:柔軟になったおかげで、以前の体制だったら仕事を続けられなかった人たちが、退職しなくても良くなりましたしね。育児や介護、病気、怪我などで、画一的な働き方ができなくなることは誰にでもあります。そうした時に、働き方が柔軟であれば、それぞれの状況に合わせて仕事を続けることができます。
桑原さま:いずれにせよ、最終的なゴールは「会社が掲げている目的を達成する」ことです。「同じ時間帯にオフィスに集まる」ことではありません。もちろん、場を共にすることの有意義性も多分あります。ですが、それは目的達成のための手段でしかありません。出社・リモート、それぞれの利点を理解したうえで、今後も併用していきたいです。

一緒に働いている仲間がどんな人なのか、好きなものや苦手なものは何か、分かり合ったチームでありたい
── リモートワークを始めて、良いことがたくさんあったんですね!一方、リモートワークはコミュニケーション方法を工夫しないといけないイメージがあります。普段はどうコミュニケーションをとっているんですか?
小林さま:基本的にはチャットツールを使ってコミュニケーションしています。あとはオンライン会議ツールで行うことが多いですね。チャットツールは履歴が残るので、業務管理面でも良いことがたくさんあります。口頭と違って、ノウハウの蓄積にもなりますし。通知設定もできるので、集中を切らさなくて済みます。
桑原さま:ですが、やはり対面でしか分からないものには気付きづらくなりますね。たとえば、顔色や雰囲気など。自ら発信してくれないと様子を知ることが難しいのが、オンラインのデメリットだと思います。チャットツールでは、対面に比べて雑談も極端に少なくなり、ストレスが溜まりそうだと感じたので、色々と対策を始めました。
── 具体的には、どのように対策されたのですか?
小林さま:いくつかの社内イベントを定期的に開催しています。全社員参加のイベントだと、まず一つ目は、月に一度の全体ミーティングです。オンライン会議ツールを使って、自宅でも参加できるようにしています。案件の進捗やお知らせの共有、いまHEROZがどんなことをしているのかなどをアップデートし、認識を統一することが目的です。
もう一つは、毎月開催している「全社つながりの場」です。リモートワークが根付き始めた2020年の秋ごろから始めた企画で、コミュニケーション促進を目的としています。内容は様々で、テーマを設けて話したり、MVP表彰をしたり。「コロナが収束したら何がしたい?」「おすすめの本は?」といった雑談的なテーマもあれば、「開発したら面白そうなAI技術は?」といった仕事に関連するテーマもあります。
「全社つながりの場」を通じて、普段リモートワークのメンバーと会話ができたことが嬉しかったです。コロナ後に入社したメンバーからも、「普段話さない人のことも知れて、会社との距離が近くなった」という声が挙がりました。
桑原さま:試行錯誤しながら実施してきた企画ですが、メンバーも徐々にオンラインでコミュニケーションをするのが当たり前になってきていると感じています。
小林さま:他にも、任意参加で「勉強会」や「案件共有会」などを月一目安で開催しています。「勉強会」では、エンジニアが研究についての話をしたり、専門性の高いトピックの共有を行います。エンジニア向けのイベントではありますが、他部署からの参加も多く、毎回賑わっていますね。ただ知識を交換するだけでなく、普段見えない専門的な部分を知ることで、部署間の相互理解が深まっています。
「案件共有会」は、エンジニア職・ビジネス職のメンバーが集まり、各案件の詳細について報告・議論する場です。それぞれの目線で案件について話し合うことで、お互いが何を思い行動しているかを共有できる機会になっています。
これらはもともとオープンスペースで集まって開催していたのですが、コロナ後はオンラインで開催しています。
桑原さま:また、コミュニケーション促進を目的とした社員が有志で始めた「交流会」というイベントもあります。とてもフランクな場で、あまりルールは設けず、基本的に何を話してもOKとしています。業務時間外に行う、有志参加のイベントです。趣味を共有したり、研究の発表を行ったり。それぞれのメンバーが持ち味を発揮して、楽しく過ごしています。
小林さま:こうしたイベントについては、定期的に社内アンケートをとり、意見をもらっています。おおむね好評ですが、「テーマによっては話題に入りづらい」「ラフになりすぎると目的を見失ってしまう」という懸念もあります。今後も試行錯誤をしながら、改善し続けていきたいと思っています。社内イベントについては、こちらの記事でも紹介していますので、ぜひご覧ください!
「会社が一方的に働き方を押し付けるのではなく、それぞれのメンバーが自分の働き方について自律的に考え続ける会社でありたい」と話してくださった、桑原さまと小林さま。リモートワークを取り入れて終わりではなく、最善の形を今後も探していきたい、とおっしゃっていました。
さらなるご成長を楽しみにしています。この度はありがとうございました。
(執筆・写真:呂 翔華)
👇ワークプレイスに関するご相談は、こちらをクリック!