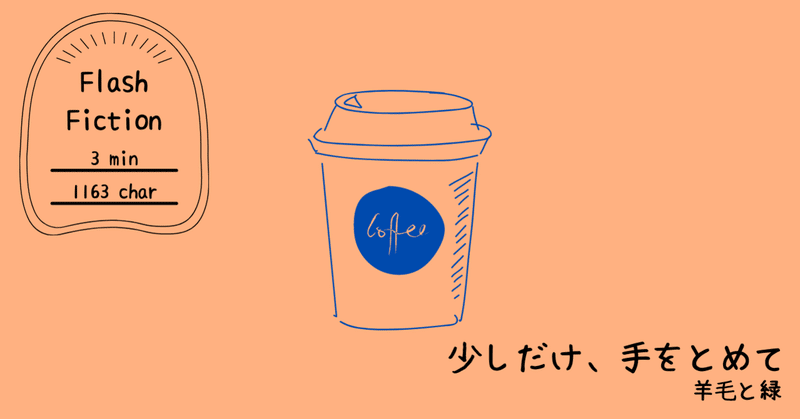
少しだけ、手をとめて
「少しだけでいいから手を止めて一服しようよ。コーヒーでもいれるよ」
「邪魔しないで」
彼はわたしが作業に集中して少しすると、よく邪魔をしてきた。
そのせいでケーキのホイップがうまく固まらなかったこと、いい気分で散歩をしているときに足を止めなければいけなかったことがあった。それほどに暇であるのか、わたしが彼の欲しいときに相手をしてくれる存在であると思っているのか、その都度かんがえさせられてはうんざりしていた。
「まだ彼は子供なのね。好きな人の困る顔が見たいのよ」
「そんなの許されるのは子供のときだけよ。もういい加減大人なんだから」
「まあ、勝手にやってくださいな」
わたしが相談すると、きまって彼女はどうでもいいという風にあしらってきた。わたしの恋愛のどこかに嫉妬でもしたのかと思ったときもあったけど、彼女はただめんどくさかっただけかもしれない。
ただ、まともにとりあってくれる人はほとんどいなかったことはたしかだった。
彼とのおわりは、案外あっけないものだった。彼が実家に帰らなければいけないと言い、一緒に来ないかと誘われたのだけど、わたしが拒んだのだ。考えたけれど遠距離恋愛も嫌だったし、一緒に行きたくないと思ったことで、彼のことはもう好きではないと気づいたことが一番大きな理由だった。
「まあ、あんたがそれでいいって思ったんなら何も言うことはないよ」
「一人の女の恋愛が終わったんだよ。少しくらい慰めてくれてもいいじゃない」
わたしは自分がかわいそうに思えて慰めてほしくて、やけ酒しようといくつも杯を空にした。いい加減、気持ち悪くなりそうだと思ったところで、彼女はわたしの手をとめた。
「まあまあ、ちょっとだけ、ほんの少しだけでいいから手を止めな」
欲しい言葉だと思った。そしてそれは彼がよく使う言葉によく似ていた。
そういえば、ケーキのホイップが出来上がったときには、わたしはすっかり腕が痛くなってしまっていた。意地になって散歩をし過ぎて、靴擦れを起こしてしまった。
ああ、彼はこんな気持ちでわたしをいつも止めていてくれたのだろうか。それは、集中すると行き過ぎてしまうわたしをそっと気遣う言葉だったのであろうか。勝手な解釈かもしれなかったけれど、うんざりしていた彼の言葉は、いつもわたしを大切にしてくれている言葉だったのだろうか。
「ねえ、これって」
「そう聞きなさんな。あんたは頑張り屋さんだからね」
「ありがとうって、ごめんって、まだ聞いてくれるかな」
「それは神のみぞ知るってやつじゃない。でも、ひとつだけわかることはあるよ」
彼女の言いたいことは言われなくてもわかった。わたしは切符を買いに行かなければいけない。一度帰って、落ち着いてから明日にでも出発すればいいのかもしれない。それでもわたしは、少しでもはやく彼に伝えなければいけないことがあった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
