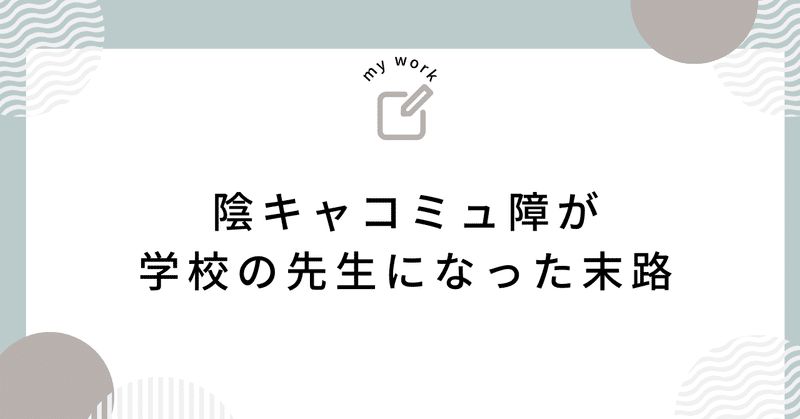
陰キャコミュ障が学校の先生になった末路
こんにちは。
中学校教員をしているあっきーです。
みなさんは、学校の先生にどのようなイメージを抱いていますか?
某Xなどを見ると
学生時代陽キャだった人が教員になってる
教員になる人は学校が大好き
クラスの中心になって行事を盛り上げてた
などなど、いかにも昔は「陽キャ」だった人たちが学校の先生になっている、という声が多いようです。
しかし、私は陰キャでコミュ障。
学校も行事も嫌いでした。
こんな私が実際に学校の先生になってみて変わったことを、今回はお話できたらと思います。

●なぜ学校の先生になったのか
これは半分懺悔なのですが…。
私が教員になりたかった理由は「吹奏楽部の顧問になりたかった」からでした。
今になって考えてみると、自分が中学生の時に吹奏楽コンクールの結果がイマイチだったから、子どもを利用してリベンジしようとしていたのかなと思います。なんと最低!
しかし、人事異動の神様が大いなる力を発揮させたのか、吹奏楽部のある学校に一度も赴任せず、今では吹奏楽の「す」の字もないくらい、吹奏楽部とは無縁の生活を送っています。
陰キャでコミュ障だった私。
中学生のときはスクールカーストの最底辺で、教室では孤立を極める日々。
自分の得意なことを生かせる吹奏楽部だけが、自分の居場所でした。
居場所を追い求めた結果が、教員だったのでしょうね。
●学校の先生になってみて
○「陽キャ」「陰キャ」のくくりに縛られてる場合じゃない
新卒ですぐ、知識がないまま特別支援学級の担任に。
いざ働いてみると、さまざまな困り感を抱えながら学校生活を送っている生徒にたくさん出会いました。
「どう思う?」と聞かれてもどう答えたらいいか分からない子。
誰でもいいからかまって欲しくて、つい暴力的な行動に出てしまう子。
どうがんばってもアルファベットが読めない子。
中には、コミュニケーションが苦手ゆえに、教室で孤立してしまって、特別支援学級にやってきた生徒もいました。
その中で、気付いたことがあります。
教室で孤立してしまっているのは、陰キャだからというわけではないこと。
「陽キャ」だろうが「陰キャ」だろうが、ひとりひとり何かしらに困り感を抱えている生徒がいること。
つまり、教室で孤立してる原因を「陽キャ」だからとか「陰キャ」だからとかで結論づけることは不可能!
だから、子どもをグループとして捉えるのではなく、1人の人格として捉えることが大切なのだと気付かされました。
○陰キャの先生も需要がある
一方、職員室の先生たちは「陽キャ」がとても多い、というのが正直な感想です。
特に、急速な世代交代で20代の教員が一気に増えてきているので、雰囲気が一気に若くなっています。
若い男性教員同士で定期的にバスケットボールやバレーボールをしていたり(!?)、ゲリラカラオケ大会が開催されていたり(!!??)。
「陽キャ」の先生方の多くは、学級担任をもっていて、行事の度にクラスを盛り上げるべくパリピの才能を発揮させています。お祭りが大好きなのだと思います。
しかし、子どもたちの中には行事が好きじゃなかったり、「陽キャ」の雰囲気が好きじゃなかったりする子も当然います。
そんなときに、子どもの気持ちに寄り添えるのは誰なのか。そう、「陰キャ」の教員です。
離島時代に一緒に働いていた貫禄のある先生が、別の学校に異動する時のあいさつでこのようなお話をされていました。
どんな性格の先生も、子どもたちには必ず需要がある。
ある先生が100人の子どもに嫌われていたとしても、1人その先生のことが大好きな子どもがいたら、それだけで立派な需要があるということだ。
その先生とは細々としたトラブルがあったので個人的にはあまり好きではないのですが、この言葉だけは腑に落ちました。
(陰キャの私に向けて言った言葉なのではとさえ思ってしまう…。)
実際、私の周りに集まってくるのは、学校の雰囲気が苦手な生徒が多いです。大体、行事をやる意義か分からないとか、学校独自のみんなでやろうって文化が嫌いとかと言った類の愚痴を聞かされています。
私ならば自分の気持ちを全部受け止めてくれる。
私に話しても多分怒らないで聞いてくれるだろう。
そんな安心感があるから寄ってくるのでしょう。今後も常に謎の安心感を身にまとい続けたいと思います。
○ちょっとだけ自分のコミュ力が上がった
毎日50分の授業をこなし、休み時間も談笑をして関係性作りに励んでいる学校の先生。
嫌でも、コミュニケーションを取る時間がとても長くなります。
そのため、人見知りしがちな私でも中学生程度までの年齢ならば、初対面でも気軽に話ができるようになりました。
今では、公園で知り合った幼稚園児や小学生が「赤ちゃん〜!」と息子に絡んできても普通に会話を続けています。
同世代や上の世代とコミュニケーションを取るのは未だに苦手ですが、気軽に話せる世代ができただけ、大きな成長だと感じています。
●まとめ
陰キャでコミュ障な私が学校の先生になって思ったことは、先生の性格は千差万別でいいんだということです。
つまり、私は私のままでいい!!
それに気付かせてくれたのは、今まで出会った子どもたちと先生たち。
不純な動機で教員になりましたが、同時に大切なことを学ぶことができました。
長時間労働やたくさんの業務量など、教員になってみて大変なことは山ほどあるのですが、教員になったこと自体は全く後悔していません。
陰キャでコミュ障でも先生になれる。
むしろ、ありのままの自分で子どもたちと向き合った方がいい。
教員になって、「自分らしさ」について深く考える貴重な機会を頂いたなと思います。
もし、陰キャでコミュ障だけど教員を目指している人がいたら、ぜひなってください!!
需要、ありまくりです!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
