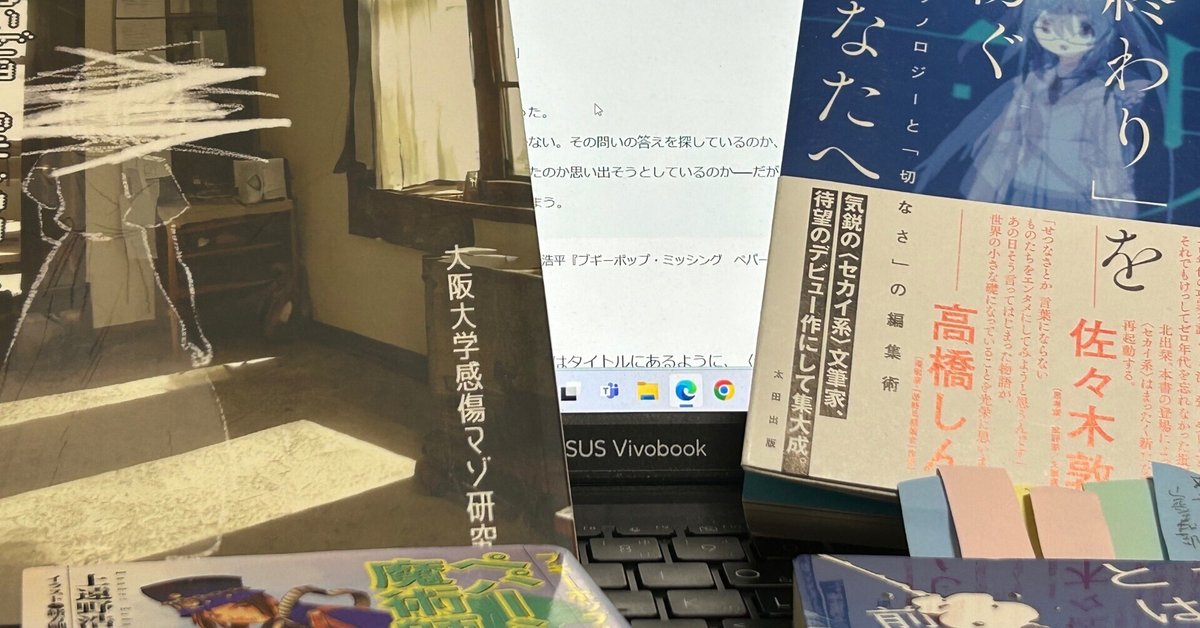
Where Our Decade Is──北出栞『「世界の終わり」を紡ぐあなたへ』書評
「なあ、魔術師──」
[…]
「君は世界をどう思う?」
「…………」
すると、彼は立ち停まった。
少しの間、そのまま動かない。その問いの答えを探しているのか、過去に自分が同じ問いにどう答えたのか思い出そうとしているのか──だが、やはり再び歩き出していってしまう。
はじめに
前島賢『セカイ系とは何か』はタイトルにあるように、〈セカイ系〉という、90年代後半からゼロ年代にかけての、国内サブカルチャーの世界における「文芸」運動を文化史的に解説したものである。以下の説明は、あらゆる言説の中で最も簡潔に、そして明快にこの概念を切り取ったものとしていまなお有効であるように思う。
「『新世紀エヴァンゲリオン』の影響を受け、90年代後半からゼロ年代に作られた、巨大ロボットや戦闘美少女、探偵など、オタク文化と親和性の高い要素やジャンルコードを作中に導入したうえで、若者(特に男性)の自意識を描写する作品群。その特徴のひとつとして作中登場人物の独白に『世界』という単語が頻出することから、このように命名された。命名者はウェブサイト『ぷるにえブックマーク』の管理人、ぷるにえ」
1995年放送の『新世紀エヴァンゲリオン』を始点としたそこにおける史観は、きわめて精細に時代のフレームを捉えていたが、それゆえに〈セカイ系〉という語の限界を指し示すことになった。本書において〈セカイ系〉は何よりもある時代──ポスト・『エヴァ』の時代──においてのみ有効な語として束の間立ち現れ、そしてその終局にあって無化される。140マイルで消失するデロリアンのように、このタームはある時代を駆け、消えた。ある時代の残光。ある時代の消失。そうした性質は、文庫版に書き下ろされた新たなあとがきにおいて、さらに際立っていた。
文庫版あとがきにおいて、すでに半分近くが経過した2010年代(テン年代)の文化に対し、前島ははっきりと敗北宣言を表明する。エヴァンゲリオン新劇場版に、ボーカロイド小説に、「カゲロウプロジェクト」に、前島はすでに自分(の世代のオタク)との離隔を見ていた。「(新時代の文化がなにがしかの文化的価値を胚胎している可能性に触れながら)そうであれば、是非ともこうした新しい物語の魅力を、私のような人間にもわかりやすく伝えてくれる若い論客が生まれてくることを期待して、ひとまず筆を擱くこととする」。それはかつて、テン年代の文化論を早々に記そうとした物語評論家:さやわかの姿勢(『一〇年代文化論』)とは明瞭な対照をなしているが、こちらもまた、逆説的ではあるけれども、ある種の誠実性を獲得していたように思う。
無論、この種の「敗北」は同書のオリジナル、SB新書版における本文からすでに予見されていたことではあった。〈セカイ系〉は売り物にならない。多くが、短編やそれに準ずるボリュームである(とされる)それは本質的に、絶え間ないフランチャイズ・メディアミックスによってコンテンツを拡散させていくライトノベルやノベルゲームとは相性が悪かった。ポスト・セカイ系の思弁であるところの「決断主義」的な傾向を顕在化し、作品を成立させていくことになる西尾維新や奈須きのこは、その文章量、物語のスケールによって、テン年代においてもなお隆盛を極めたが、それは露悪的に言えば、セカイ系の排除によるものであった側面をもつはずだ。
しかしその時代さえも、すでに過去になりつつある。
大長編ライトノベルの多くが完結し(相対的に)コンパクトに物語をまとめるラブコメが顕在化しつつある現在。単巻ライトノベルや骨太な新人賞受賞作がとりわけ注目され、人気を獲得するかたわらで、続刊に対する関心が薄れつつある現在(*1)。
北出栞『「世界の終わり」を紡ぐあなたへ』は、そのような時代の臨界点に出現した批評だった。
*1::ここで筆者が想定しているのは、2018年以降の「このライトノベルがすごい!」選出作品をめぐる一連のムーブメントである。2018年、「この新作がすごい!」部門において一位を獲得した安里アサト『86-エイティシックス-』を筆頭に、その後同部門は多くの、一巻における完結度が高い作品や、そもそも単巻で完結するような作品を見出していくことになるが、前者は一巻の売り上げに比して、続刊の売り上げが振るわない、という状況が相次いでいる。
本書はデジタル・ツールと、それが属し、また強化する情報環境という観点から、改めて90-00年代という「時間」と分かちがたく結びついている側面のある〈セカイ系〉というタームを捉えなおす。そして(詳細は後述するが)そのうえで〈セカイ系〉を「PCのデスクトップ画面にGUI(引用者注:グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を介して触れる中で立ち上がる『半透明』な感覚。それを作品として具現化したもの」と定義する。それは「切なさ」中核に据えつつ、それを無数のパラメーターに貫かれた、予測し制御しうる情感として捉える視点であり、その点において、本書は2020年代批評の画期をなしながら、テン年代という、いまなお批評の座軸が定まっていないかに見えるあいまいなこの十年期に対して、有効な言説を提示することに成功していたように思う。
以下、そのような、本書の胚胎している批評的な可能性を概観し、描出する。そしてそのうえで、一人の〈セカイ系〉消費者としての「ぼく」の態度(アティチュード)を提示したいと思う。だからこの記事は、半分だけ書評ではない。100%の透明度で対象の本をそのままに映し出しながら、他方で不透明に、ソリッドに、一人の書き手としての立場を示す、言わば準(半)透明な言説としてこれはある。それは同時に、ある種の、実存の叫びとしてもあるはずだ。〈セカイ系〉という言葉の連なりが、束の間われわれに許すかにみえる感傷性、「切なさ」。そうしたすべてを記すことこそ、本記事の目的とするところである。
Chapter1.セカイ・「切なさ」・パラメータ(書評パート)
断絶。ある種の思想運動としての〈セカイ系〉を語るうえで、そのタームは何よりも重要であるように思う。前島が言うように〈セカイ系〉は「若者(特に男性)の自意識」と密接に関わっており、なればこそ、その作品世界は他の一切──とりわけ、社会といった「中間項」──がスポイルされたものとして成立してきた経緯をもつ。「きみ」と「ぼく」の関係性の前提条件としての「世界」と「ぼく」の関係性。しかしそれは、常に、断絶として立ち現れてくる。「ぼく」が本質的に世界とは無関係であること。この断絶において、「激しい自分語り」にしるしづけられた自意識は輪郭を際立たせる。
ブロガーの藤原聡紳はセカイ系とそれが属していた文化圏と密接な関係性を有していた作家:上遠野浩平についてのブログの中で、以下のように記している。
「セカイ系作品は、ほぼ間違いなく自己のセカイに対する無力を描くが、自己とセカイとの無関係は描かない。むしろ、セカイと無関係で暮らそうとしても、そんなことは不可能だという認識を描く。キャラクター(と読者)はセカイ全体、ひいては無力感・劣等感にきちんと向き合わねばならないのだ。
[…]
つまり、自己の影響はセカイに及ばないという根本的な断絶の感覚がここ(セカイ系的な特徴をもつ作品の一つ『冥王と獣のダンス』)では書かれる。作品世界という舞台においてすら、キャラクターはセカイに対する影響力を一切もたない無力な存在だ。
この認識を描いてこそのセカイ系と言ってよかろう。僕が中高生のころ読みまくったのはたぶんそれだった。
「根本的な断絶の感覚」と向き合うこと。藤原が言うように、セカイ系の特質はそこにある。そしてここにおいて、断絶の自明性はモノローグによって確保されている。セカイ系が成り立つためには──そして「無力感・劣等感」を強固なものとして提示するには、まずもって語る主体が自明でなければならない。主体という座、モノローグの担い手それ自体が、ほとんど何の留保もなく存在しているということ。そのありかたはやはり、庵野秀明が──『エヴァ』的な思弁が規定したものであった。
『スキゾ・エヴァンゲリオン』において語られた「僕らは結局コラージュしかできない」(*2)(=コピーしかない)という言葉は、氏の創作姿勢、そしてそれ以後の創作のかたちを指し示したものとしてあまりに有名だが、続けて庵野が「オリジナルが存在するとしたら、僕の人生しかない」と発言したことには注目すべきだろう。ただ一つの、固有のものとしての経験。無媒介的・無距離的にわれわれの認識に到来し、一切を規定するものとしての人生の経験。氏はかつてそれを確信していた。すべてが統御されてはじめて成り立つアニメの表象を相対化するかたわらに、人生の相対化は(=普遍性への還元は)不可能である、という確信がある。
*2:庵野秀明『スキゾ・エヴァンゲリオン』49頁
かつて庵野が、そしてのちにガイナックスとして成立するダイコンフィルムの面々が作り上げた『愛国戦隊大日本』は、分かちがたくパロディでありながら、どこにもオリジナルのないもの(=明確な参照元を持たない、「戦隊もの」のパブリック・イメージに対するパロディ)であった。シミュラークルのシミュラークル。オリジナルの喪失。90年代以降、かつてポストモダン状況と呼ばれた状況におけるその種の絶望はしかし、固有の人生を(感傷的に)語るという、心理主義的な態度(アティチュード)によって埋め合わせることが可能なものであった。それは上に引いた庵野の言明において端的に指し示されているし、のちに宇野常寛が『ゼロ年代の想像力』で指摘するように、当時の幻冬舎に代表的な文芸や、テレビドラマの世界において追究された方法論でもあったはずだ。
しかしもはや、そうした「語り手」の自明性は根拠を失っている。北出が指摘するのは、まさにそうした、テン年代における文化状況であった。
主体の消失。レフ・マノヴィッチ(『ニューメディアの言語』)が指摘したような、1995年以降のメディア環境において──そして、ゼロ年代後半以降のスマートフォンの登場以降において──現出するものはそれである、と北出は言う。無論、それは本書のサブタイトル「編集術」が端的に示すように、心理面に焦点を当てた社会評ではない。それは技術論的に想定されうる「位置」をめぐる言明だ。世界を観測し記述する「位置」。その自明性が消失した地平を想定すること。テン年代を始めるためには、まずもってその手続きを踏まなければならなかった。
前島の議論を引きつつ、ゼロ年代の文化運動を簡潔にまとめ、さらに浜崎あゆみや岩井俊二らの仕事を援用しながらセカイ系をさらに(男性中心主義的だ、という批判を裂開させるかたちで)拡張させるところから始まった本書。それは東浩紀の「半透明性」を手掛かりとしながら(*3)、主体の消失から改めて〈いま・ここ〉に繋がる10年の実相を明らかにしていく。この10年。新たな「ぼくら」の10年。それは批評的空白を抱える十年期であった。
*3:東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』におけるもの。ライトノベルやノベルゲームの「文体」を、現実を引き写しつつ、同時に特有の存在様式を提示するような「半透明な」ものであるとした
北出は震災後の国内の情報環境に言及したうえで「新劇場版」シリーズ以降の庵野秀明の仕事を参照しつつ、『シン・エヴァンゲリオン』の終局近くにおけるカットから、以下のようなイメージを抽出する。
「現実とは一切の接点を持たない『どこにもない場所』で、沈黙し青空を見つめるシンジの姿。その視線は、現代の情報環境においてなお『誰でもない誰か』であることにとどまりつつ、同時に『世界の終わり』に向けてメッセージを投じるための道筋を見据えているように思えるのだ」
匿名がデフォルトの、スマートフォン普及以前のインターネットにおいて、語られる言葉はある主体のラベルが張り付くことのない、どこまでも断片的で「独り言」的なものであった。北出はそのようにこの20年を振り返り、そのうえで、常にユーザーが「何者か」として機能してしまう、スマートフォン普及以降のインターネット環境──動員の暴力・憎しみが、寄る辺なき個同士を繋げるプラットフォーム──に抗する可能性を、「匿名性」がまとっていた諸々のイメージの中に見出す。そしてそこにおいて、主体の消失という現象が成立する。
ドイツ・ロマン派の絵画と議論を引きながら、北出はそこにある「終わりなき作品外への遡行体験」を今日的な作品経験に適用する。「世界の果てを前にした人間、の絵を見ている私(も誰かにまた見られていて……)」という経験。それは視覚のみならず、身体イメージも相対化する。ゲルハルト・リヒターの「ガラス」芸術が、のぞき込む主体の鏡像を絶えず攪乱する、そのありかたにおいてもまた、今日的な作品経験が──「タッチパネル上で生まれる切なさ」が──息づいている。そう考えれば、リヒターのガラス芸術の一つが、瀬戸内海に浮かぶ小島(豊島)に寄贈され、日本という「空間」と不可分のものとして存在していることは、決して偶然ではないのかもしれない。
リヒターの「ガラス」に映し出された鏡像のように、主体が、そのイメージが、絶えず攪乱されるということ。断絶感自体が独立して、主体も含めた世界全体が無数の断片となって立ち現れてくるということ。こうした状況を前提として、本書は改めて「編集」に注目する。ばらばらの断片同士を接続させるデジタル・ツール。創作行為を民主化するニューメディア。その可能性を描出する行為は、やがてテン年代、そして〈いま・ここ〉としての2020年代に対する有効な批評へと収斂する。
本記事「はじめに」から繰り返せば、本書における〈セカイ系〉は「PCのデスクトップ画面にGUI(引用者注:グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を介して触れる中で立ち上がる『半透明』な感覚」として、メディア環境によって規定される感覚と不可分のものとしてあり、なればこそ、そこで取り扱われるコンテンツはどれも「それを作品として具現化したもの」だった。
麻枝准が全面的に関わっているプロジェクト『ヘブンバーンズレッド』(=『ヘブバン』)がプレイヤーに提示するような、視覚と触覚の限りない接近が、可視/不可視の対立を無化することで生まれる新たな感覚。それを掬い上げ編纂したものとしての作品、かつて東浩紀が(本書の指摘するものとはやや異なるかたちで)幻視した、創作の主客があいまいに溶け合ったものとしての作品が、ここでは問題となる(*4)。それはまた、メディアの発達によって、見えるものすべてに「触る」ことが可能になった後の世界。その快楽が前面化し覇権的になった世界において、なお、〈セカイ系〉的な切なさを語ることができるか、ということでもある。
*4:『動物化するポストモダン』におけるデータベースと消費の往還関係の中で、消費者はキャラクター・イメージを能動的に補完する。ここにおいて、創作の一部は、消費の一瞬に委託されている。
例えば2007年から開始した『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの第一作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』。本書はその制作に際して行われた「REBUILD」に注目する。1995年放送のテレビアニメ版を構成していた、アナログな実体(≒セル)としてこの世界に残留する「原画、動画、レイアウト(画面の設計図)、背景」(同前、60頁)の断片をデジタル・ツールによって接続すること。それによって、『:序』は成り立っていた。そして本書は、この創作過程自体が、ばらばらの断片たちの断絶を、「編集」によって統合する作業であることを──〈セカイ系〉的な断絶を超克する可能性を秘めたものであることを指摘する。そしてそのうえで本書は、広い射程で、新海誠の作品に、先に触れたような「編集」の可能性と「切なさ」の同居したありかたを見る。
「静止画的な断片性を台詞と音楽のタイムコントロールによってつないでいくこと」(81頁)。2002年に公開された短編『ほしのこえ』に際して批評家から発された反応を引きながら、本書は新海誠の核にある作風をそのように断じる。音楽や声までを含んだあらゆる構成要素が「レイヤー」の重なり、連なりとしてそこにあり、それらが、監督という主体の統御によって接続されること。断絶と接続。こうした整理はまた、「ムービー作家」という、本書が採択したタームの秩序へと合流する。
1986年に設立されたアメリカの映像会社「プロパガンダ・フィルムズ」は、所属の作家がしばしば「MTV世代」と揶揄されたことに象徴的なように、ミュージック・クリップ的な感性と不可分の映像作家を多数擁する集団だった。そして創立メンバーの一人であるデヴィッド・フィンチャーのいくつかの仕事に代表的なように(『ファイト・クラブ』)、そこで培われた表現は後のハリウッド映画を規定していくことになるが、本書はそのような80-90年代的な想像力の、日本における実装として新海誠の仕事を取り上げる。
ミュージック・クリップ。そう聞いてただちに想起するのは『秒速5センチメートル』第三話終盤のシークエンスだが、それ以前から、そしてそれ以後も、新海誠はしばしばそのような表現を採択し、作品の中核に据えてきた。ファルコム時代のオープニング・アニメーションや、『君の名は。』『天気の子』の第一幕プロット・ポイント。あるいは、2016年紅白歌合戦のために編集されたクリップ映像。本書が「AMV(=Anime Music Video)の美学」と呼ぶ、こうした表現と詩情は、繋がるはずのないもの、ばらばらの断片たちを、デジタル・ツールの力と「切なさ」によって接続しているという点で、本書の定義する〈セカイ系〉に沿いながらそれを超克する可能性を秘めている。
そしてその想像力は、NEXONによるスマホゲーム『ブルーアーカイブ』のPVや、動画投稿サイトTikTokにおける脱中心的で脱過程的(*5)な諸々のショート・ムービーへと継承されていったという。そこには『君の名は。』以降の、新海誠という「存在」──国内文化の様相それ自体を規定するシミュラークルの大本──が深く関わっている。
*5:本書が指摘するように、TikTokの表現は「撮影→加工→投稿(→流通)」という、本来いくつかの過程を経なければならない、動画を成立させるプロセスを圧縮し、撮影の中に加工を組み込み、流通速度を加速させている。それはプロセスを「撮影→流通」と単純化できるほどにまで削ぎ落す
テン年代作家としての(『言の葉の庭』以降の)新海誠。しかししばしば、固有名のそぎ落とされた、むき出しの表現、むき出しの「気分」のプール(≒データベース)として見出されてきた存在としての新海誠。そのようなテン年代における氏の受容形態から、析出された詩情がここにはある。
断絶から改めて結ぼれについて考えること。工学的なパラメーターに覆われた文化空間の中で、それでもなお立ち上がる「切なさ」を、〈セカイ系〉を橋頭堡として考えること。本書が採るそのような立場は、ゼロ年代批評において傍流に位置づけられていた技術論を掬い上げながら、テン年代のメインストリームを再定義し、2020年代に侵入するような、意欲的でありながらどこまでも誠実なものだった。
──その誠実さに応えるためには、自分の態度(アティチュード)を包み隠さず表現するほかはない。
だからここからは、書き手としての「ぼく」、セカイ系の消費者としての「ぼく」のことを書こうと思う。そしてそれは、恐らくは根本的な部分で、本書の結論からは離隔する。もう一つのテン年代。否、ゼロ年代。否、2020年代。時にうち捨てられ、時に落ち延び、そしていま・ここにあるオルタナティヴな「なにか」。〈セカイ系〉という言葉の中にひそむそれをこそ、ぼくは捉えたい。
Chapter2.突破を心に終末を唱えよ(延長パート)
「君はどうする?」
その背中に黒帽子がまだ問いかける。最後の問いだ。これに道化は素っ気なく答えた。
「おまえの知ったことか」
本書内でも取り上げられる芸術家ゲルハルト・リヒターの中心的な仕事には、「アブストラクト・ペインティング」と呼ばれるものがある。これはパレット上の絵具の混ざりをそのままキャンバスに投射し、スキージ(へら)で引きのばすことで完成する絵画芸術であり、完成品は歪な線の連なりとしての抽象画として成立する。
その中でも代表的な連作「ビルケナウ」は、現実の写真──ナチス・ドイツ、アウシュヴィッツ=ビルケナウで行われた虐殺の記録だ──を描き写したものに、上から、先に触れたアブストラクトの手法でもって絵具を投射し引きのばしたものだった。現実を覆う凄絶で酷烈な色の連なり、その圧倒的な存在感はしかし、絵に近接することで氷解する。そこにあるのはもはや色ではない。否、そもそも平面ですら、ない。
正直に白状すれば、ぼくは「ビルケナウ」を目にしたことがない。だからこれは喩えとしては実感を欠き、不適切であるのかもしれない。けれど少し前、大阪中之島美術館で開催されていたテート美術館展「光」に展示されていたアブストラクト・ペインティングの一枚を見たとき、ぼくは未だ見ぬ「ビルケナウ」の、その表現の核心を掴んだように感じたのだ。そしてアブストラクトという表現手法それ自体が胚胎する可能性を。
なまきずだ、と思った。そのキャンバスに刻まれていたのは、むき出しのなまきずだった。
スキージは絵画を完成させる過程において、キャンバスを抉る。なればこそ、それは一つの傷を作り得、絶えず平面のスクリーンの「奥」を志向する手法としてある。三次元方向にひらかれた絵画。そのようなものとして。
リヒターは「ガラス」によって無限のフレームアウトを表現するかたわら、そのような極限を描き出して(あるいは描くことを拒んで)いた。それは本書の作り上げる「世界」の「破れ」として──外側として機能するのではないか。そしてまた、「破れ」は一つの問いを析出する。
その表現の極限、現実の極限を、いかにして遇するべきか。そしていかにして理解するべきか、という問いである。これに対し、〈セカイ系〉というタームで応えることはできるだろうか。
結論を述べれば、ぼくは可能であるように思う。しかしそれは、「切なさ」とも「編集」とも別の位置にある。──「冒涜」という位置に。「追懐の冒涜」という位置に。もう一つの〈セカイ系〉の中に蠢くそれらは、リヒター的な「破れ」と響き合うはずだ。
ライターの江永泉は論考「セカイ系、やる夫スレ、『あの花』──2010年代の個人的回想」(『青春ヘラver.5「インターネット・ノスタルジー」』所収)の中で、冷戦の終結や自衛隊のPKO派遣、湾岸戦争といったトピックと絡めながら、90年代後半における初期〈セカイ系〉作品の想像力がまとう戦争文学の影を指摘し、後に登場する、奈須きのこなどの作家による現代伝奇──東浩紀らによって「物語回帰」の「戦争文学」と称された──との間の親和性を見た。
『イリヤ』の中核をなすミリオタ的感性、『最終兵器彼女』における「戦線」の前方/後方の問題(あるいは、片田舎を覆う戦争の気配)、そして〈セカイ系〉定義論争に巻き込まれた有川浩(現:有川ひろ)『塩の街』に端を発する自衛隊三部作(とその発展形として解されうる『図書館戦争』シリーズ)。終末の想像力と戦争のディティールが溶け合ったところに〈セカイ系〉はあった、と。
それはまた宇野常寛『ゼロ年代の想像力』の枠組みとも響き合う。日常それ自体が、すでにして闘争であるかもしれない、というイメージを抉り出した同書にとっての「終わらなさ」──「ループもの」の基底をなす永続の感覚(=終わりなき日常)──とは、すなわち祝祭のことであった、と江永は指摘する。そしてそのうえで、以下のように、怪獣映画とカタストロフィについての批評であるところの、切通理作『お前が世界を殺したいなら』に依拠しながら、〈セカイ系〉の原イメージを描出した。
「セカイ系を特徴づける一つの身振りは内省である。それは怯えゆえの引きこもり、また若々しい無垢性と表裏一体の自己中心性の産物として批判されがちだった。しかし、戦争イメージを踏まえれば、それがどういう想像のモードに抗していたか明確になる。都市や住人が破壊される光景、打ちこわしへの没頭であり熱狂である。
[…]
セカイ系的な思考は、惨禍の光景に眺め入りながら内省的な暴力批判を展開する。梶井基次郎「檸檬」(1925年)に倣っていえば、現に破壊された百貨店の光景を前に、これが爆弾であれと檸檬を置いていた自分の身振りを問い直す内省が始まるのである」
──2010年代の個人的回想』
若さは無垢ではない。内省は自縛ではない。祝祭はすなわち破壊、「世界の終わり」の惨禍でもある。そう宣言する一連の言明はまた、同時代の作品群──〈セカイ系〉の周縁に位置づけられ、独自の存在感を放ち続けてきたとある作品群の活写するものとの間に、強い相関をもつように思う。──『ブギーポップ』シリーズとの間に。
『ブギーポップ』。後に登場する西尾維新に強い影響を与え、時雨沢恵一や高橋弥七郎といった作家たちの原体験として在るこのシリーズを特徴づける、最大のものの一つは「世界の敵」という概念である。
「人間をやめようとしている、世界のすべてを敵に回してでも“突破”しようとする」(*6)存在。それこそが「世界の敵」だ。それはまた別のところでは「未来」に対する志向として見出されていた。すなわち、いま・ここを裂開させる──決定的な「世界の終わり」をもたらす存在として。
*6:上遠野浩平『騎士は恋情の血を流す』
無論、『ブギーポップ』は断続的に、20年以上刊行され続けている(それぞれの巻は一定の独立性を保った作品としてある)シリーズであるため、その概念の指すものは多岐にわたる。それは「生命」そのものに対する根本的な無関心や、世界全体に対する深く昏い恐怖を抱えこんでいる、といったような、認識のレベルでその他すべての世界と隔たっているようなある種のサイコパスとして描かれたかと思えば、植物兵器や怪異のような、茫洋とした実体として描かれることもあった。そしてそうした類型のうちの一つに、少女性と激情、という取り合わせはある。
『ブギーポップ・イントレランス オルフェの箱舟』における「敵」などはその好例だが、議論が煩雑になるためその内容に踏み込むことはしない。重要なのはそこで描かれている、なにがしかの限界、なにがしかの「世界」を突破しようとしている(=世界のすべてを焼き尽くそうとしている)存在の姿が、どこまでも能動的(=反自動的)であるという点である。そこには「突破」への、直接それとは意識されない意志がある。
そうした構造は、先に引いた江永が同じ節の中で触れる、切通理作の著作が主に取り扱う怪獣映画にも見られたものだった。平成ガメラシリーズの最終作『ガメラ3 邪神《イリス》覚醒』において、少女:綾奈は、自分の家族を死に追いやったガメラに復讐するために、怪獣の卵を育てる。その切実な激情は世紀末という、映画が背景にもつ大状況と接続し、やがて古都・京都の炎上というかたちで示される「世界の終わり」へと迫っていく。
『最終兵器彼女』においてちせがまとう「終末」のイメージは、どこか自動的・宿命的なものだった。そこにある否応なさはただちに、われわれにあの「断絶」を想起させる。世界それ自体と、根本的に隔たったところに置かれている自己の実存の輪郭が、ここにおいて際立つ。しかし「世界の敵」は、切通の依拠した怪獣映画的な想像力は、そして江永の批評は、その断絶の「突破」を志向している。リヒター的な「破れ」を。「断絶→接続」ではなく、「断絶→突破」という回路。そこに対する内省的な批判(の意識)。かつてある種の〈セカイ系〉が、それを捉えたいくつかの批評が、そして他ならぬぼくが、切実なものとして捉えていたのは、そうしたありかたに他ならない。
そして江永の論考は、さらにその先へと進む。そしてそこで持ち出されるのが「追懐の冒涜」という概念である。
ジョルジョ・アガンベンが『讀神』において援用した、オーソン・ウェルズによる未完の映画『ドン・キホーテ』における一幕──あるキャラクターが、スクリーン上の女性を救おうとして映画館を破壊するという一幕──に触れながら、江永は「冒涜」をその核にもつオタク・カルチャーを超克する可能性を、その種の「突破」に見出そうとした(*7)。
すなわち、冒涜を冒涜すること。液晶のタッチパネルの向こう側への突破を、志向すること。それは『ドン・キホーテ』がそうであったように、何ら超越としての資格を有さない、空虚な残骸のみをこの世界に生み出してしまう行為なのかもしれない。しかしそれを成り立たせる暴力性は、あらゆるアイロニーを無化しうる。
*7:ここで言う「冒涜」とは猥褻性や俗性のことである。それはコンテンツへの「誠実な」没入を絶えず不可能にするが、その端的な例として江永は『あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない』のパチンコ&スロット化を挙げた。ある世代にとっての、ほとんど暴力的でさえあるようなノスタルジーと、決定的な死の予感すらもが、アイロニカルに分解され流通してしまう「この」現実の残酷性。それを棲み分けや道徳とは別の仕方で遇することの必要性が、ここでは深い葛藤を感じる文体でもって描き出されている
断絶感の「突破」としての暴力。それはいま・ここのわれわれが否応なく生を、生臭く「不気味な」身体を被るのと同様に、否応のないものであるという側面がある。空風のようにこの身体を吹き抜ける怒り、誰に押し付けられたのかもわからない憎悪、嫉妬、そうしたすべて。怨念めいた認識のすべて。生のすべて。その矛先を、他ならぬ冒涜に──激烈な暴力の変奏に──向けるということ。そこから、われわれにとっての愛を立ち上げるということ……
『「世界の終わり」を~』は祈りとともに幕を下ろす。それは未だ見ぬ誰かへの祈りであり、世界最後の瞬間に歌われるような、歌のための祈りでもある。
ぼくもまたそれに倣いたい。冒涜への冒涜が完遂された後の残骸の上で、それでもなお生き続けるために。
ぼくは目をつむる。イヤホンから流れてくる重層的な旋律も、つけっぱなしになっているテレビの音も、今はどこか遠くに聴こえる。そしてぼくは、キーボードから手を放す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
