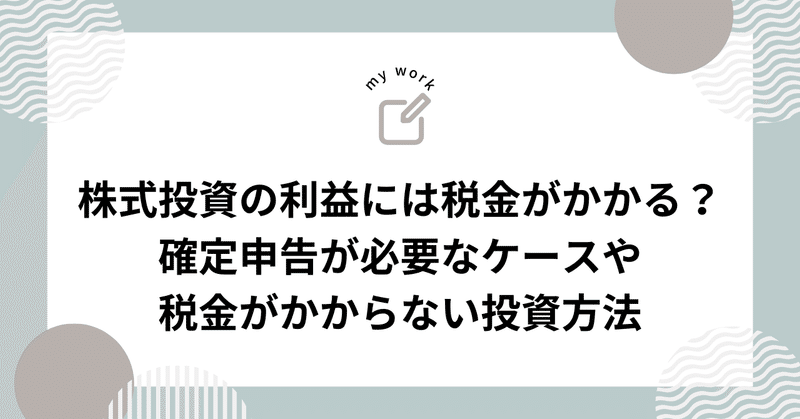
株式投資の利益には税金がかかる?確定申告が必要なケースや税金がかからない投資方法をご紹介!
将来のことを考えると、預金だけでは不安だから投資を始めたいけれど、「投資には税金がかかるって本当?」「確定申告って必要?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。
そこで、今回は株式投資の利益も課税対象になるのか、また税金の支払い方法や確定申告の仕方を解説するとともに、利益が出ても確定申告をせずに済む資産運用の方法をご紹介していきます。
投資をはじめとする資産運用に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
■株式投資の利益には税金が課せられる
まずは、株式投資で得た利益には税金が課せられるのかという疑問にお答えしていきます。
結論として、株式投資では「譲渡益」と「配当金」という2種類の利益に対して、一部の例外を除いてはそれぞれ20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金が課せられます。
・譲渡益にかかる税金
譲渡益とは、株式の取得価格と売却価格の差から生じる利益のことです。
譲渡益を得た場合は、株式投資による所得とその他の所得を分離して税金額を計算し、確定申告を行う「申告分離課税」で納税します。
例えば、10万円で購入した株を12万円で売却して2万円の譲渡益が出た場合、「譲渡益2万円×税率20.315%=税金額4,063円」となります。
・配当金にかかる税金
配当金とは、株式を発行している企業が利益を上げた際に、利益の一部または全部を株主に分配する現金配当のことです。
例えば、1株当たり70円の配当金が支払われた場合、100株保有していれば「70円x100株=7,000円」、300株保有していれば「70円×300株=21,000円」というように株の保有数に応じて配当金を受け取れます。
配当金については、申告分離課税の他、「総合課税」という課税方式も選択できます。
申告分離課税では、所得に関わらず一律15%の所得税が課せられますが、総合課税では所得に応じて5%~45%の間で所得税率が変動します。
加えて、配当控除も受けられるため、所得が一定以下の方は総合課税を選択した方が有利です。
■税金の支払い方法
続いて、株式投資に伴い発生する税金の支払い方法について解説します。
株式投資の利益に対する税金の支払い方法は、自分で確定申告を行う方法と、特定口座の「源泉徴収あり」を選択して税金が自動的に引かれるようにする方法があります。
・特定口座の「源泉徴収あり」を選択する
株式投資に使用できる口座は、一般口座と特定口座の2種類です。
一般口座を選択した場合は、株式投資の損益を自分で計算して確定申告を行わなければなりませんが、特定口座の「源泉徴収あり」を選択すれば証券会社が源泉徴収を行ってくれるので確定申告の手間が省けます。
ただし、特定口座でも「源泉徴収なし」を選択した場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
・自分で確定申告を行う
株式投資で得た利益に対する税金は、確定申告によって納税するのが基本です。
一般口座や特定口座の「源泉徴収なし」を選択した場合は、必ず確定申告を行いましょう。
また、特定口座の「源泉徴収あり」を選択した場合でも、自分で確定申告を行った方がお得になるケースがあります。
■特定口座の「源泉徴収あり」でも確定申告をおすすめするケースとは?

特定口座の「源泉徴収あり」を選択した場合でも、以下のケースに当てはまる場合は、確定申告を行うことで税制上お得になります。
・年間利益が48万円以下の場合
・損失を翌年以降に繰り越す場合
・他の口座と損益通算する場合
・配当金で総合課税を選択する場合
どのようにお得になるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
・年間利益が48万円以下の場合
株式投資による年間利益が48万円以下の場合は、確定申告を行うことで税金が還付されることがあります。
例えば、その他の所得がない専業主婦などは、譲渡益から所得税の基礎控除額である48万円を差し引くことで、課税所得が0円となるため、確定申告をすれば源泉徴収されていた税金が全額戻ってきます。
・損失を翌年以降に繰り越す場合
株式投資で年間損益の合計がマイナスだった場合は、毎年確定申告を行うことを条件に、損失金額を翌年から3年間にわたって繰り越すことができ、その間は税金がかかりません。
・他の口座と損益通算する場合
一般口座や別の証券会社での取引と損益通算をして、源泉徴収税額に過払いがあった場合は、確定申告を行うことで過払い分が還付されます。
また、損益通算の結果、プラスマイナス0もしくはマイナスになる場合、確定申告をすれば税金がかかりません。
・配当金を総合課税にする場合
配当金に対する課税方式を総合課税にすると、税金が安くなることがあります。
総合課税は、課税所得が多いほど税率が高くなる累進課税方式となっているため、所得が一定以下の人は確定申告を行うことで税金が安くなります。
ちなみに、所得税率が15%未満であれば、総合課税を選択して確定申告を行った方がお得になります。
■株式投資の譲渡損益を確定申告する方法と必要書類
株式投資の譲渡損益を確定申告するには、以下の3つの方法があります。
・確定申告ソフトやアプリを使う
・国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する
・紙の確定申告書に手書きする
それぞれの方法を、以下で解説していきます。
・確定申告ソフトやアプリを使う
株式投資の確定申告を手軽に行いたい方は、確定申告ソフトやアプリを使うのがおすすめです。
実際の確定申告書様式に則った入力画面が表示されるので、そこに必要項目を入力することで簡単に申告用データを作成できます。
確定申告が初めての方でも比較的利用しやすいので、申告書の作成に自信がない方にもおすすめです。
作成した書類は、印刷して税務署に持参または郵送するか、e-Taxを利用して税務署に送信します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する
国税庁のホームページ上にある「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして、株式投資の確定申告書を作成することもできます。
確定申告ソフトやアプリのように、画面の指示に従って入力していくだけで簡単に作成できます。
加えて、国が提供しているという安心感があること、自動で計算される納税額をすぐに把握できること、などのメリットがあります。
作成した書類の提出方法は、確定申告ソフトやアプリを使用する場合と同じです。
・手書きをする
税務署に直接取りに行くか取り寄せるなどして確定申告書を入手し、手書きをするという方法もあります。
パソコンやスマートフォンに入力するのが苦手な方に向いていますが、書き損じや計算ミスに注意が必要です。
書き方や計算方法に疑問や不安がある方は、税務署で職員に聞きながら作成することも可能です。
・株式投資の確定申告で必要な書類
株式投資の確定申告をする際は、以下の書類が必要です。
確定申告書 第一表
収入金額や所得金額、所得から差し引かれる金額を記載し、税金を算出します。
確定申告書 第二表
所得の詳しい内訳、医療費控除や社会保険料控除などの所得から差し引かれる控除の内容、住民税、事業税などについて記入します。
添付書類台紙に、源泉徴収票を貼り付けます。
確定申告書 第三表(分離課税用)
譲渡益が出た場合に使用する書類で、株取引の内容を記載します。
確定申告書 第三表を制作するにあたって、先に以下の「株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書」を作成しておく必要があります。
株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書
確定申告書 第三表(分離課税用)の作成・提供にともなって必要となる書類です。
株取引による損益の計算内訳を詳細に記入します。
■株式投資の配当金の確定申告について
配当金に対する税金は、上場株式等の配当で20.315%、それ以外の配当については20.42%の税金が源泉徴収されているので、基本的には確定申告を行う必要はありません。
しかし、確定申告を行った方がお得になる場合は、申告分離課税や総合課税のどちらかを選択し、確定申告を行うこともできます。
総合課税を選択すると、所得によっては税金が安くなることと配当控除が適用されることがメリットです。
控除額は、配当所得とその他の所得を合わせた課税総所得額によって変わります。
ただし、高所得者が総合課税によって確定申告を行うと、源泉徴収額以上に税率が上がって損をすることになってしまいます。
総合課税でお得になる課税所得額の目安は、695万円以下です。
確定申告書に配当金について記載する際は、確定申告書 第二表の「所得の内訳」に、給与所得の源泉徴収票の「支払額」と「源泉徴収税額」の欄に記載されている金額をそのまま転記します。
配当所得の欄には、源泉徴収される前の配当金額を記載します。
また、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「配当割控除額」の欄に、配当金にかかる住民税の源泉徴収額を記入します。
■NISAなら税金がかからず確定申告も不要
株式投資で期待できる利益は、譲渡益と配当金の2種類ですが、どちらもそれぞれ税金がかかります。
また、一般口座や特定口座の「源泉徴徴収なし」を選択した場合は、自分で確定申告を行う必要もあります。
そこで、節税できて面倒な確定申告の必要もない資産運用を望んでいる方は、NISAの活用がおすすめです。
NISAなら、制度の範囲内の取引であれば利益が出ても非課税なので確定申告をせずに済みます。
・新NISAで非課税投資枠が大幅にアップ!
非課税投資枠とは、1月~12月までの1年間に非課税で投資可能な枠のことです。
年間投資額がこの枠の範囲内であれば、売却益や配当金をいくら得ようとも税金が課されることはありません。
これまでのNISA制度では、一般NISAで毎年120万円、つみたてNISAで毎年40万円の非課税投資枠が設けられていました。
また、非課税で運用できる期間は、一般NISAとジュニアNISAで5年間、つみたてNISAで20年間と決められていました。
しかし、2024年1月からスタートした新NISAでは、非課税投資枠が大幅に拡大され、一般NISAで毎年240万円、つみたてNISAで120万円まで無期限で非課税投資ができるようになったのです。
・株式投資と比べてどれくらいお得?
では、新NISAを株式投資と比較するとどれくらいお得になるのでしょうか?
例えば、株式投資では200万円で購入した株式を売却して、20万円の利益を得た場合、「20万円×税率20.315%」で4万6,300円の税金を支払い、結果として手元に残るのは、15万3,700円です。
一方、NISAなら一般NISAで年間200万円分の金融商品を購入しても売却益にかかる税金は0なので、20万円の利益がそのまま手元に残ります。
そのため、NISAは譲渡益に対する節税対策に、ピッタリと言えるでしょう。
・NISAとその他の資産運用を併用するのもおすすめ
NISAでは、1年間の非課税投資枠があらかじめ決まっており、一度上限に達したら翌年までは、それ以上非課税で金融商品を購入することはできません。
また、株式投資の場合、株式を売却して損失が出たとしても他の口座と損益通算を行うことができますが、NISAの場合は損益通算ができません。
NISAは、あくまでも中長期的に保有することを目的として、売買が目的の株はNISA以外の口座を利用するなど、NISAとその他の口座を分けて資産運用を行うのもおすすめです。
・NISAで税金がかかるケース
NISAで配当金を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」という受け取り方を選択する必要があります。
株式数比例分配方式とは、NISA口座を開設している証券会社の口座で配当金を受け取る方式のことです。
NISA口座から購入した株式の配当金や投資信託などの分配金の受け取り方は、この方式以外にも「配当金領収方式」や「登録配当金受領口座方式」など、数種類あってその中から自分で自由に選択することができます。
しかし、「株式数比例分配方式」以外の受け取り方式を選択した場合は、課税対象となってしまうため注意が必要です。
今回は、株式投資にかかる税金や税金の納め方、確定申告の仕方、確定申告が不要な投資方法についてご紹介しました。
短期間で大きな利益を得たいとの考えから株式投資を始める方もいますが、株式投資で得た利益には税金がかかり、利益が大きくなるほど税金も多く支払わなければなりません。
また、確定申告を行った方がお得になるケースを知らずに、特定口座で源泉徴収を受けていると、損をする場合もあります。
しかし、NISAなら非課税投資枠の範囲内の取引であれば税金がかからないため、「確定申告をすべき?」「手続きの仕方は?」などと悩まずに済みます。
投資をしたいけれど税金がかかるのは嫌という方や、面倒な確定申告は避けたいという方は、NISAを活用した資産運用も検討してみてはいかがでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
