
真似をすれば他人のことが分かる?ー読書メモ:『ソウル・ハンターズ−シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』その2
人間と動物。人間/動物。人間 対 動物
「人間」と「動物」はまったく別々のものである・・・のだろうか?
人間は最初から最後までずっと人間であるし、動物もまた最初から最後まで動物である・・・のだろうか?
人間と動物の区別は絶対的・・・なのだろうか?
狩猟者が獲物である動物を模倣するとき
『ソウル・ハンターズ−シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』によれば、シベリアの狩猟民「ユカギール」の狩猟者は、獲物をおびき出し、仕留める時、獲物である動物の「真似をする」という。動物の動き、動物がたてる音を狩猟者が模倣する。
そしてこの、狩猟者が獲物である動物を真似る時、狩猟者は「人間」のままでありながら(つまり動物を狙う狩人としての知覚を保ったまま)、同時に動物のパースペクティブから状況を知覚する。
動物を人間に「例えてみる」のではなく
狩人であると同時に動物のパースペクティブからも状況を知覚する。この時、狩猟者は動物を人間に「喩えて」みているのではない。
『ソウル・ハンターズ』の著者、ウィラースレフによれば、「動物を人間としてみる」、「動物を人間に、喩える」ということは、人間と動物の区別を前提にしている。それはつまり、人間と動物は全く異なる別々のものである、とした上で、人間がその高度な精神の中に、人間に例えられた動物という像を生み出しているのだという考えである。
人間に例えられた動物という像は人間の精神の中のもの、精神が作り出した精神の一部、精神そのものであって、外界の物質的なモノとしての動物そのものとは関係がない。と。これは精神と物質の「デカルト的」区別を前提にした考えである、と。
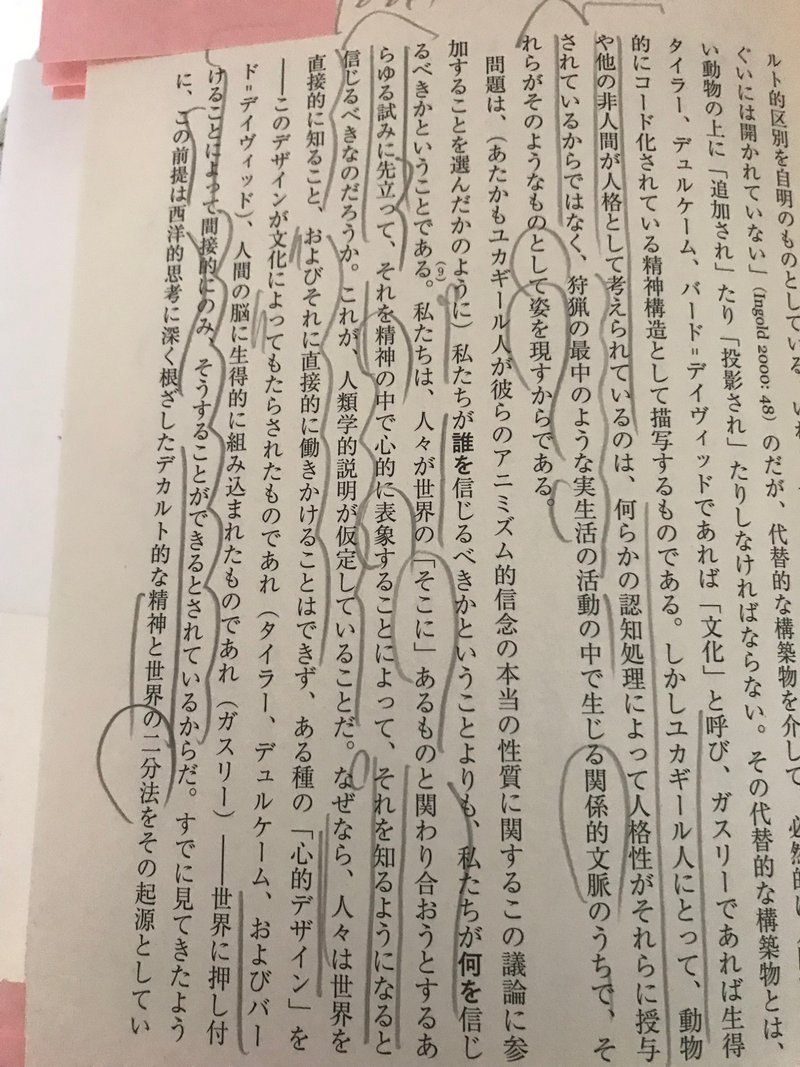
ところが、ユカギールの狩猟者の主観的な体験は、こうした「喩え」という説明の仕方では捉えられないという。
狩猟者の主観的体験は、精神と物質の「デカルト的」区別の絶対性を超えている。そこでは人間は人間としての認知(なによりも動物を獲物として狩ろうという意識と、そのための合理的な行動)を保ちながら、同時に動物の側が狩猟者を見て、感じ、考えていることを動物のパースペクティブからありありと感じ、体験する。
そして、その人間でありながら動物である体験、狩猟者でありながら獲物である体験は、狩猟者が動物の動きを"不完全に”模倣する中で立ち現れてくるという。

「自己」と「他者」の関係を理解するヒントにも
この話は人類学の基本的なものの見方に関わる重要な問題提起であるのだが、人間同士のやり取り、コミュニケーションを理解しようという際のヒントにもなる。
相手を真似る、模倣することで、相手のパースペクティブに似たようなものを実体験する。自分と相手は異ったまま、また自分自身のままでいながら、他者を理解する。
これは人間同士のコミュニケーション、特に、他者が主観的に経験しているであろうことを自分の中でありあり体験したり、そこから他者を理解したりすることの手がかりにもなりそうである。
他者は動物?モノ?!
「デカルト主義」の心身二元論を徹底的に推し進めると、自分以外の他の人間も、動物や、テーブルやガラス瓶、そのあたりのモノと同じになってしまう。
あるいは逆に自他を含めて、すべての人間は「ひとつ」の精神を共有しており、そのために互いに完全に理解できるはずだ、といった議論もある。
前者の想定からすると、結局、他人と分かり合うなんて不可能、という話になり、後者の想定からすると、同じ人間同士なのだから、手放しに、いきなり、なにもせず、わかりあえて当然、ということになる。
前者は自他の「区別」を完全に別々のものと捉え、後者は自他の区別を完全に同じ側のものと捉える。どちらにしても、区別の絶対性を前提としたうえで、その相手がどちら側に居るかでモメることになる。
区別は絶対?
問題は、この区別の絶対性という想定である。
ユカギールの狩猟者と獲物の狩猟という状況における関係と単純に一緒にはできないが、人と人の関係もまた、主観的な体験としては、状況によって、相手のことが分かるような分からないような、部分的に分かるが部分的に分からないような、曖昧でどちらとも区別できないものであったりする。
相手が考えているであることをありありと想起し、感情を一体にできていると感じることもあれば、相手を全く理解不能な機械かモノのように感じることもある。
自他の区別は絶対的なものでない。
同時にこちらでありながらあちらでもある、ということが可能だと、考えたい。
二項対立は「わかりやすい」ようで、返ってわかりにくくすることもある
コミュニケーションとはディスコミュニケーションである、とはよく言ったものだが、コミュニケーションはゼロかイチか、できるかできないかのデジタルな二者択一ではない。
分かるような、わからないような。
分からないようで、なんとなくわかるような。
コミュニケーションは、お互いに伝わったような気がするが、伝わっていないかもしれない、が、とりあえず伝わったということで先に進めそう。というくらいのこととして、「適当」に捉えたほうがいい。
そうし人間同士でも、なんとなくわかったような気になれる鍵は、「不完全な模倣」にあるのかもしれない。
人間同士のこと「あの人になりたい」などと言ってしまえるほど共感できる相手とであったり、逆に「分かりたくもない」と拒絶したくなり相手と遭遇することもあるだろう。
そういうときに、不完全なド素人の芝居の練習とおもって、その相手の身振り、手振り、表情、声、セリフを「演じてみる」というやり方。そうして実際に演じている瞬間に、自分の中に立ち上がってくる知覚。これを冷徹に自分自身のままで観察する。という具合である。
鍵になるのは芝居の不完全性だ。完全に演じている役になりきれない、冷静に恥ずかしいなと思ってる意識こそが、相手に同化しない自分自身の根幹なのであろう。
おわりに
他者の視点を、他者にならず、自分自身のままで居ながらが、同時に体験すること。その鍵は模倣にある、という『ソウル・ハンターズ』の議論、とてもおもしろいところである。
ちなみに、この話は下記に掲載するnoteの続きである。
つづく
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
