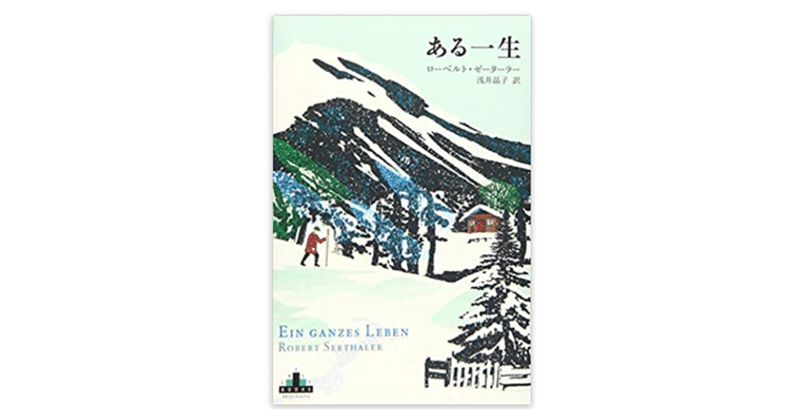
『ある一生』ローベルト ゼーターラー (著), 浅井 晶子 (翻訳) タイトル通り、無名の男の一生まるごとを淡々と描く小説。が心に響く年齢境遇に、自分がなったのである。
『ある一生』 (新潮クレスト・ブックス) 単行本 – 2019/6/27
Robert Seethaler (原著), ローベルト ゼーターラー (著), 浅井 晶子 (翻訳)
Amazon内容紹介
「20世紀初頭、幼くして母を亡くし、アルプスの農場主のもと過酷な労働をしいられて育ったアンドレアス・エッガーはある日、雪山で瀕死のヤギ飼いと出会い、「死ぬときには氷の女に出会う」と告げられる―。生まれてはじめての恋、山肌に燃える文字で刻まれた愛の言葉。危険と背中合わせのロープウェイ建設事業に汗を流す、つつましくも幸せな日々に起こったある晩の雪崩。そして、戦争を伝えるラジオ。時代の荒波にもまれ、誰に知られることもなく生きた男の生涯。その人生を織りなす瞬くような時間。恩寵に満ちた心ゆすぶられる物語。」
ここから僕の感想
無名の男の一生を、老いて死ぬまでをまで淡々と描く、という小説のジャンル、というのが、どうもあるようなのだ。劇的と言えば劇的だし、平凡といえば、平凡な一生を。僕も、この年齢まで生きると、この先、どんな死に方をするにせよ、まずは、人生の主要部分は終わっていて、まずまず平凡に切り抜けて生きてきて、あとはどう老いて死ぬかだけの段階に入った。そんなときに、そういう小説を読んで、「ああ、死ぬとき、自分はどんな風に一生を振り返るのかなあ」などということを考える。ドラマチックに考えれば、自分の人生もなかなかいろいろあったし、平凡と言えば、平凡だったなあと。
小説半ば、戦後ロシアに抑留され、そこから生まれ故郷の村に帰郷した時、主人公は54歳。まあ、今の僕くらいの年齢だ。もうしばらく主人公は長生きするのだが、ひとまず、このときに主人公が人生を振り返る部分を引用する。
「エッガーは自分の子供時代のことを思い出した。学校に通った数年間のことを。当時は目の前に終わりなく延々と続いていた年月が、いまでは瞬きするほど短くはかなく思われる。そもそも、時間はエッガーを戸惑わせた。過去はあらゆる方向に変形して見え、記憶の時系列は混乱し、その形も重さも、奇妙にうつろい続けるのだった。ロシアで過ごした時間の方が、
マリーとともに過ごした時間よりずっと長いにもかかわらず、コーカサスとヴォロシロフグラードの収容所での年月は、マリーと過ごした最後の数日間とほとんど変わらないように思われた。ロープウェイを建設した年月は、後から振り返ると、たったひとつの季節に凝縮される一方、まるで人生の半分を、雄牛をつなぐ棒にうつぶせになって過ごしたよう気がした。視線を地面に向け、小さな白い尻を夜の空に突き出して。」
ここまで、僕も人生を振り返ると、そういう、時間の変形、伸び縮みの感覚と言うのは、たしかにあるなあ。広告のプレゼンに明け暮れた時間は、「ひとつの季節に凝縮される」という感覚はあるなあ。仕事って、人生の時の中の比重でいうと、それくらいの感じなんだよな。
この54歳から先、主人公は、生まれた村をほとんど出ることなく生きるのだが、老いて、死ぬまでの人生もなかなか味わい深い。
この小説の作者ローベルト・ゼーターラーは、僕より若い。1966年生まれで、この小説は2014年に刊行されているから、40代でこの小説を書いている。40代の作者が、70,80歳まで生きて、老いて死ぬ人間の一生まるごとを書こうという思うのはどういうことなのかな。(という疑問は、僕の読書感想を読んでくれている人にはおなじみになりつつある、僕の興味関心なのだ。)
だってね、僕の40代を考えたら、仕事も子育ても真っただ中、大忙しで、「老いる」とか「老いて死ぬ」とかいうのがどういうことかなんて、考えなかったもんな。うちの場合、親も元気で、まだ健在なもので。老いて、死に向かう人間の、心や体の変化と感じ方を、こんな風に書けるものなのかな。いや、この小説だと、40代の小説家が描いているのに、主人公の老年期から死に向かう場面、見事に描けているのだよな。
先月にやった、本読み友達との「昨年読んだ本ベスト3」発表会で、教えてもらった小説でした。同年代だと、やはり、こういう小説が、心に響くのだと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
