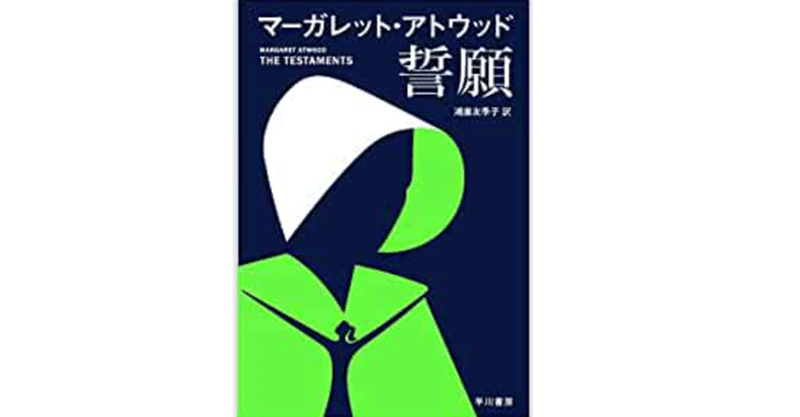
『誓願』マーガレット・アトウッド著 鴻巣友季子訳。なるほど、『侍女の物語』から「著者とこの世界の33年の変化」が、「作品世界内15年の変化」に、こう反映するのか、作品世界観が大転換することに、驚く。そこから、少し脱線しつつ、感想を書きました。
Amazon内容紹介は、ごく短い。
「「道具」であることを、やめた女たちは―『侍女の物語』続篇。ブッカー賞受賞作。」
これ、なんでこんなに短いかというと、内容が、サスペンスなので、ネタバレ厳禁度が、前作『侍女の物語』より、ずっと高い。なので、ばれないように短い。
とはいえ、サスペンス的展開としては、読んでいるうちに「ははーん、そういうことか」と、だいたい、途中で予想はできてくる。
とはいえ、これから読む人のために、ネタバレしないようにしつつ、かつ、あんまり、他の人が論じていない視点で、この小説のことを、前作との対比で、論じてみたいと思う。
鴻巣友季子さんの「あとがき」の見事な分析
その前に、この本、巻末に、作者アトウッドの「謝辞」、訳者 鴻巣友季子さんの「あとがき」、英文学者 小川公代さんの「解説」と、三つの小文がついているのだけれど、前作『侍女の物語』とのコントラストについては、鴻巣さんのあとがきが、きわめて正確に分析、記述されている。引用する。
『誓願』は『侍女の物語』の続篇として書かれたが、ナラティブのスタイルや語り口、物語のトーンや方向性はがらりと変わったと言っていい。違いについては後述するとして、ひとつの独立した物語としても読めるという点は明確にしておきたい。
としたうえで、ちょっと先で、鴻巣さんはこう分析する。
『誓願』には三人の語り手がいる。ギレデアの女性社会の最高指導者である「リディア小母」(正篇では侍女を痛めつける恐ろしい教育係として異彩を放っていた)、地位の高い司令官の娘「アグネス・ジェマイカ」、カナダのトロントで古着屋の夫婦のもとに育った「デイジー」。
(中略)
侍女「オブフレッド」の単独視点で展開していく『侍女の物語』には、俯瞰的視点はもちろん、他者の視点がないため、暗く狭い地下道で進んでいくような閉塞的な不安感と、視野狭窄感を読み手にあたえる効果があった。『侍女の物語』がclousure「とじる」物語であるとすれば、本作『誓願』はrevealing「ひらく」物語だといえるだろう。『誓願』に登場する女性たちは、目を開き、蒙を啓かれ、思考や意識を拓いていく。また、内実が固く秘されていたギレデア国の暗部が、外部の目に開示されていく。
鴻巣さんが、日本のディストピア三選として紹介したもので言えば、前篇『侍女の物語』は、いったい何が起きているのかが分からない、小川洋子さんの『密やかな結晶』や桐野夏生さんの『日没』のような閉塞感がある。
一方、この『誓願』は、全体に、この国と周辺国家で何が起きているのかは、分析的によくわかるように記述されており、見通しがかなり良くなっている。その点、いとうせいこう氏の作品のような、説明的わかりやすさがある。
その世界の中で、主人公たちは、より能動的に、その状況と自分の人生に立ち向かっていく。もちろん、悲惨な状況、悪辣な男性支配層のあり方も、より具体的に描かれていく。それに女性たちが立ち向かっていく、極端に言うと、「痛快エンターテイメント」と言っていいような大転換なのである。
その中身、筋は、ネタバレになっちゃうので書かない。その代わりに、私がここで書きたいことは、鴻巣さんの言う通り、「この作品単体でも読める」のだが、それでもやはり、この二作、両方揃って、「女性を主人公とした小説としての全体性の構造」になっている。二作続けて読んだ方がいいよ、ということについて書いていきます。
人生の「全体性」の視点から、二作の構造を考える
高齢男性である私が、専門でないフェミニズム関連の、こういうことを書くのは、いささか勇気を要するというか、批判覚悟というか、なのだが、書くべき大事なことだと思うので、勇気を奮って書いていきます。問題あれば、ご指摘ください。
この二作を「閉じる」「開く(啓く、拓く)」の対比とする鴻巣さんの分析は、これは慧眼、素晴らしい分析だと思う。のだが、もうすこし、小説の具体的内容に即して二作の対比を見ていきたい。
『侍女の物語』の主人公は、クーデター前のアメリカで、結婚して女児を育てている。クーデター後、女児を連れてカナダに逃れようとして失敗し、女児は奪われ、夫もおそらく連行されるか殺されたか、行方不明になっている。自身は「侍女」として、司令官の子どもを作るだけの「道具」として生きることを強いられている。
原発事故や環境汚染などの影響で正常な子供が生まれにくくなっているギレアデ共和国では、キリスト教原理主義の教義とともに、社会維持の必要上からも、女性は、子どもを産むための道具としての役割にきつく限定されている。女性を産めない女性は、社会的地位に応じて、いくつかの役割に振り分けられているが、多くは「男性と、子どもを産める女性」の世話をする役割に限定されている。ひどい女性差別社会である。
支配層の夫の妻であり、かつ、正常な子供を産めるのが最善であり、そうした「妻」がいちばん上級の女性である。その妻が子どもを産めない時に、代わりに子供を産む役割だけをするのが「侍女」。前作の主人公は侍女である。
他に「マーサ、本作で女中」は、男性支配層と妻と侍女の世話をする子供が産めない女性や、より身分の低い階層の男性の妻「便利妻、本作では平民妻」などがいる。
では、前作で、「侍女」の教育係として登場した「小母」とは何か。それは、クーデター前に知的職業(法曹、医者、学者など)に就いていた、子どもをもう産めない年齢の女性のうち、ギレデアの支配に協力加担して、女性社会全体を管理支配する役割になった人たちであることが、本作で明らかになる。
うーん、だんだんネタバレしそうになってくるなあ。
ここで、僕が問題にしたいのは、
『誓願』の主人公女性三人は、老人となったリディア小母と、若い女性二人。結婚前の、恋愛前の、若い女学生。
後でもう一度、詳細に論じるけれど、とにかく『誓願』の主人公は「男性パートナーとの関係(恋愛とか結構とか性行為とか)からも、妊娠出産育児からも」前後に年齢的に離れた立場に、主人公全員が設定されているのである。女子とおばあさんを主人公とした小説。
それに対し、『侍女の物語』の主人公、オブフレッドは、1人、娘を産み、育てている途中で奪われ、次の子どもの妊娠を役割として与えられる女性。
侍女となった後も、オブフレッドは、司令官とも、その運転手ニックとも、街で検問する若い兵士の視線も、「性的誘惑」として意識する。それは不快なことだけではなく、それに対応する、自らの内部に欲望を意識する。生死の分からない夫への感情もありつつ、同時に、現実に近くにいる男性たちに対し、性的な引力と、自身の存在が男性に性的影響を及ぼすことも意識して生きているのである。
また、奪われた娘に対する様々な思いは繰り返し深まっていく。他の侍女の妊娠出産、自身の次なる妊娠に対しても、「役割」としての嫌悪だけでない、微妙な感情が描かれていく。子供を産み育てることは、社会から強要されれば不快だが、自らの選択としては、彼女にとって、肯定的な体験なのである。
オブフレッドを「子供を産む役割に限定された、差別抑圧される、ディストピアにおける悲劇の主人公」として描いているが、オブフレッドはその環境、限定の中でも「性と男女の駆け引きと性欲と子供を持ち育てることへの愛着や執着」を感じ、考えながら生きる。「生殖年齢にある女性として、心も体もそのように働く微妙な機微」が、きわめて精緻に描写されている。
『侍女の物語』は、女性を極端に差別し抑圧し役割限定する社会システムへの批判にはなっているのだが、同時に、女性の男性パートナーへの感情や性欲や子どもへの愛情といったものは肯定的に描かれていると思う。
一方、『誓願』においては、リディア小母においては、「老いて衰えていく自らの女性性」への、知的ユーモアに満ちた自己観察が、随所にあり、これは、なんとなく、アトウッドが老いた自らの容姿や肉体をどのように感じているのかが投影されているようで興味深い。そのような年齢に達するにつれ、女性は同年齢男性に対し、対等になるどころか、優位に立ち、コントロールしていく。生殖性から距離を置いた老齢の女性である。
対する、二人の若い女性、ギレデアに暮らすアグネスと、カナダに暮らすデイジー、それぞれの社会文化の違いはあれど、男性とか性とか結婚とか、そういうものは、まだあくまで社会や教育や親が与えるイメージが優勢である。やはり、生殖性から距離がある、少女として描かれている。
人間もまた動物の一種であると考えれば、人生は「生殖年齢・期間」とその前後の、3つの時期に分けられる
こういう書き方はすごく批判を受けそうな書き方になるが、人間も動物の一種なので、「恋愛結婚などパートナ―異性と関係性を築きセックスして子供を妊娠出産して育児をする」という期間を、動物、生物で言うところの「生殖年齢・期間」であるといったん、一旦、措く。
(生殖のためだけの存在として、その道具として女性を規定することを、これらふたつの小説は批判しているのだけれど、その年齢期間に、ある比率の男性も女性もが、社会制度として強いられなくても、自由意思で、その役割を果たそうとすることに、少なくとも『侍女の物語』の方は、一定程度、肯定していると思う。)
①「生殖年齢・期間前のアグネスとデイジー」→②「生殖年齢・期間のオブフレッド」→③「生殖年齢・期間後のリディア小母」という、女性の人生の三段階について、置くことができる。
もちろん、成長によって、小説中でも、若い二人は①から②に移行し、結婚や恋愛や性行為に対する抵抗や憧れなどが描かれる。
『侍女の物語』は②の段階にある女性が、極端な役割に限定されたディストピアに投げ込まれた悲劇を描く。
『誓願』は、そうした社会に対して反抗を試みるのは①と③の「前後の期間・年齢」主人公による、という構図になっている。
『侍女の物語』では、②の主人公の独白小説であり、登場人物としても①の若い女子はほとんど登場しない。また、完全な老女もほとんど登場しない。②から③になりかかっている、老い切っていない面倒な存在としての「司令官の妻」が描かれる。
一方、『誓願』においては、ギレデアにおける「妻」や、妻を目指す同級生たち、つまり②の段階にある女性たち、あるいは②に素直に適応しようとする同級生は、批判的に描かれる。無邪気に、考えなしに、パートナーを求め、子どもを作ろうとする女性は、思慮の足りない存在のように描かれる。『誓願』では、侍女は、ほとんど、人格を持った存在としては登場しない。出産で死亡するオブカイルのことを、主人公の1人アグネスは距離を置いて観察するのみである。
『侍女の物語』と、主人公の立場、視点が完全に反転している。
ドキュメンタリー番組「出産しない女たち」
話が飛ぶが、すこし前に、NHKBS世界のドキュメンタリーに、「出産しない女たち」というのがあった。
「出産しない女たち」
「子どもを産むのが女の幸せ」「母性は本能」と世間一般では言われているが果たしてそれは真実なのか。母親にならないという選択を嘆くべきではないと、女性たちが反論する
子どもがいない自分自身をネタにするコメディアンのパフォーマンスと体験談を軸に、作家、助産師、哲学者など女性たちが通説に反論し、子どもを産まなくても幸せになれると主張。人間に生まれつきの母性などないとして、社会がいかに「子どもを持たない女性」の悪いイメージを作り上げてきたのかを指摘する。“母性神話”と社会の押し付けに物申すドキュメンタリー。 原題:[m]otherhood(スペイン 2018年)
①から③にジャンプする。②の生殖期間・段階を選択しない生き方を、女性の主体的選択として肯定する、というテーマのドキュメンタリーだった。もちろん、②の年齢段階で同性、異性のパートナーと関係を築きつつ、「妊娠、出産」はしない、という選択をする人も多い。また、出産はしないが、養子を育てることで「親」になる選択はするなど、②の年齢段階での、人生の選択肢は無限に多様。ドキュメンタリーはそういう多様な例を追いかけていくものである。
その中で、「出産をさせようとする社会的制度的圧力は悪」という社会や男性を批判攻撃すること。そこまではいいと思う。納得できる。が、「出産や育児を何の疑問も抱かずにしている女性も、敵の一部」というくらいに、主張が攻撃的な感じになっていくラディカルなフェミニストが、インタビューを受ける人の1/3くらいいる。見ていて、僕は、ちょっとひいてしまった。
『誓願』の主人公たち、それぞれは、けっして過激なフェミニスト的ではない。
リディア小母の自らの老いへのユーモアある観察眼、カナダの女子中高校生の、デイジーの恋愛や男性に興味があるいまどきの女子らしい言葉、彼女たちは、必ずしもラディカルなフェミニズム丸出しな印象は全く与えない。読んでいて魅力的な女性だし、楽しい小説だ。
しかし、ふと気が付くと、「育児や出産を何の疑問も抱かずに求める女性は、考えが足りない、女性自身の内なる敵」みたいな感触が、この小説にはある。あのドキュメンタリーと同じような感触が。
小説内に、まともな男性の存在が希薄で、幼児性愛など、悪辣な人物の印象の方が強い。
ここ数年の#METOO運動や、小児性愛の男性問題など、この周辺の現実の問題が作品内に反映している。
『侍女の物語』で描かれていた、男性パートナーと関係を継続的に作り、欲望も愛情も感じ、妊娠出産し、子どもを育て、子どもを愛して執着し、という「生殖期間」固有の体験が、『誓願』という小説からはまるごとすっぽり抜け落ちている。この30年間の、現実社会の変化が、作品世界内に、色濃く反映されているようだ。それは、そう気づいてしまうと、男性の私としては、なにか、居心地の悪いような申し訳ないような、いたたまれない気持ちになる。
『誓願』単体で、「女性の、現代の、最も大事な問題を扱った、今、読むべき小説」としてほめたたえられるのは、今のその周辺の問題の論じられ方がそのまま反映しているようで、ちょいと怖い。男性登場人物に悪人しかいない。女性同士の友情や愛情が印象深く数多く描かれる一方、男性で好印象かつ鮮明な印象な人物は、本当に、ごく少数である。(ガースくらい)
小説の終盤で、『侍女の物語』と、『誓願』のつながり方が最終的に明らかにされていく過程で、今、ここまで僕が書いたようなモヤモヤは、実はその多くが氷解するように書かれている。だからこそ、『侍女の物語』から、二作続けて読んだ方がいいと思う。『誓願』だけを読むのとだと、印象はだいぶ大きく変わると思う。
#Amazon
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
