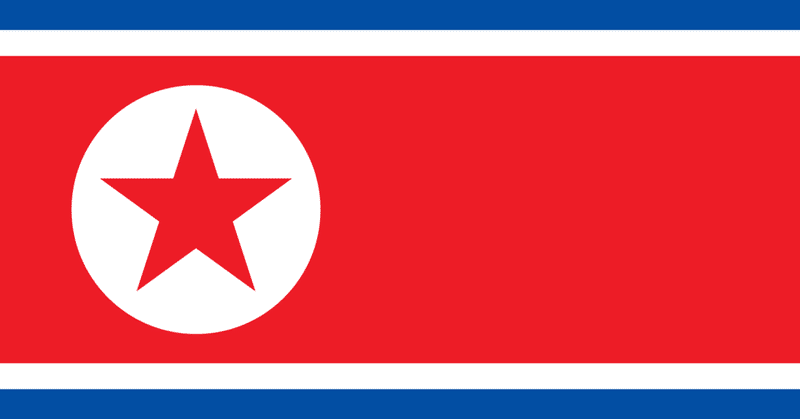
野球朝鮮民主主義人民共和国代表、その素顔に迫る
筆者はKBOファンの日本人であるが、プロ野球ファンになるはるか前から「北朝鮮ウォッチャー」であった。
となれば、おのずと興味は朝鮮民主主義人民共和国の野球に向かう。
かの国の野球は、これまでもさまざまな書籍や論文において論じられてきたテーマであるが、本稿では国立国会図書館に所蔵の『週刊ベースボール』と、韓国のネット記事を主に参照しつつ、野球朝鮮民主主義代表の素顔に迫る。
※特記事項
・朝鮮民主主義人民共和国は、以下「北朝鮮」と表記する
・人物の敬称は省略した
・出典はすべて括弧内に示し、参考文献表を文末に添えた
・出典のうち、『週刊ベースボール』については、巻号ではなく発行年月日を示した
朝鮮半島の野球史~1945年8月15日以前~
フィリップ・ジレット。朝鮮半島の野球史に関心のある人ならば知らぬもののいない名前だろう。朝鮮半島に初めて野球を伝えた人物である(大島 2006:10)。大島の2006年の著作にもあるように、ジレットがソウルの皇城YMCAの総務を務めるかたわら野球を始めた「1905年」が、多くの書籍において朝鮮半島の野球史の出発点とされてきた(大島 2006:10)。
しかし、正岡の2020年の研究では、大島勝太郎の1932年の著作『朝鮮野球史』や大韓野球協会・韓国野球委員会が戦後に発行した『韓国野球史』を参照しつつ、ジレットが1901年または1902年頃に、平壌にグローブとボールを持参してキャッチボールを楽しんでいたということが言及されている(正岡 2020:3)。
1905年に第二次日韓協約によって日本は大韓帝国の外交権を奪い、1910年には日韓併合を行なって朝鮮半島を植民地とした。
これによって大量の日本人が朝鮮半島に移住し、朝鮮人とスポーツで交流した。日本人はサッカーでは朝鮮人チームに歯が立たなかったが、野球では強さを見せていた(大島 2006:12)。
当時の全国中等学校優勝野球大会、いわゆる「夏の甲子園」では、1921年の第7回大会から朝鮮と満州、1923年の第9回大会から台湾で「地方大会」が実施された(大島 2006:12)。また、1927年に始まった社会時野球の大会、都市対抗野球でも朝鮮、中国、台湾の代表が出場していた(大島 2006:20)。1933年に開催された第7回都市対抗野球大会に朝鮮代表として出場し準優勝した「全京城」はほぼ日本人主体のチームであったが、その中で唯一の朝鮮人選手であった李栄敏(イ・ヨンミン)は陸上競技、サッカーにおいても優秀な成績をおさめた万能型の選手で、1925年には京城運動場史上初の「柵越えホームラン」を放つなど、「朝鮮のベーブ・ルース」と称されていた(大島 2006:20‐21)。
「夏の甲子園」と都市対抗野球で朝鮮代表が活躍する中、朝鮮半島北半部の野球事情はというと、「夏の甲子園」の朝鮮半島予選に参加した旧制中学校11校のうち4校、新制中学校39校のうち15校が現在の北朝鮮側に位置していた(正岡 2020:4)。これらの学校のうち、1929年に「夏の甲子園」に出場した平壌中は、初戦で平安中学(現・龍谷大付属平安高校)と対戦し3‐0で敗れたものの、強豪平安中学と互角に渡り合う実力を見せた(正岡 2020:5)。また、平壌高等普通学校からは朴賢明(パク・ヒョンミョン)という選手が頭角を現し、社会人野球の「全京城」のメンバーとしても都市対抗野球に出場したのち、1938年途中に大阪タイガース(現・阪神タイガース)に入団した(正岡 2020:4)。
このように急速に発展を遂げてきた朝鮮半島の野球の歴史は、1945年8月15日に日本が太平洋戦争に敗戦したことによって、一時的に途切れることになった。
北朝鮮野球の歴史~1945年8月15日以降、1988年まで~
1945年8月15日に日本が無条件降伏したのち、朝鮮半島は連合軍によって北緯38度線を境に分割され、南をアメリカ軍が、北をソ連軍が統治した。連合軍軍政期においては、1945年10月3日にソビエト民政庁が、1946年2月8日に北朝鮮臨時人民委員会が、そして1947年2月20日に北朝鮮人民委員会が樹立された。
この間、1946年には「北朝鮮総合体育大会」が開催され、野球が正式種目に含まれていた(正岡 2020:5)。朝鮮民主主義人民共和国が建国されたのは、1948年9月9日のことであったから、それより先に北朝鮮の野球の歴史は新たなスタートを切っていたことになる。
建国以後の北朝鮮野球の動きは未だに明らかになっていない部分が多いが、1960年に開催された全国高等技術学校野球大会の種目に野球が含まれていたこと、60年代から多くの学校に野球部(野球小組)が創設されたこと、そして1966年7月には『軟式野球』という野球の入門書が北朝鮮の群衆文化出版社から出版されたことが正岡の2021年の研究で明らかになっている(正岡 2021:110)。正岡は、この入門書について、北朝鮮が野球の活性化を国の方針として行っていたこと、そして韓国では「日帝残滓」であるとの批判を受けて行われなくなっていった軟式野球を敢えて北朝鮮が普及させようとしたことには、安全かつ安価な道具で行えるメリットがあったことを指摘している(正岡 2021:110)。
1966年には、北朝鮮の野球史と日本の野球史が交錯する一つの出来事があった。かつて東北高校のエースとして活躍したのち大洋ホエールズに投手として入団し、1965年に帰国事業第125次船で北朝鮮の清津市へ渡った元プロ野球選手、波山次郎(尹次郎、ユン・チャラン)が、勤労者大会の第1回大会で清津市代表チームのメンバーとして出場し、5試合を戦って全勝で優勝した(鈴木 2013:178)。このとき、波山自身は4回戦でホームランを打ったことを手紙に書き残しているが、登板したかどうかは定かではない(鈴木 2013:178)。
清津市鉄工所に勤務しながら野球を続けていた波山次郎は、鈴木の2013年の著作によれば、1973年[注:おそらく1974年の誤記?]に、弟の波山鐘煥(尹鐘煥、ユン・ジョンファン)とともに平壌鉄道体育団チームに招集された(鈴木 2013:186)。
平壌鉄道体育団とは、当時の「ステート・アマ」養成機関のひとつで、すべての競技のエリートが集まる体育団であった(鈴木 2013:159)とされているが、実は「平壌鉄道体育団」という名称は他の文献ではあまり見かけない表記であり、鉄道省所属のサッカー、卓球、バスケットボールなど様々な種目を抱えるスポーツ団体としては「機関車体育団」との表記のほうが一般的である。
1974年には、キューバが代表チームを北朝鮮に派遣し、25日間で7試合を行った(正岡 2021:111)。なお、このときのキューバ代表は、6月にキューバを出発し、チェコスロバキアと北朝鮮で試合をした(鈴木 2013:182)ほか、7月には日本を初訪問している。日本では社会人野球の全日本チームや全静岡チームなどと合計7試合を戦った。
鈴木の2013年の著作では、キューバの新聞『グランマ』1974年7月20日号にこの時のキューバ代表の戦いぶりと北朝鮮野球に関する記事が掲載されており、1974年当時は北朝鮮国内に15チームがあり、南浦市には野球場が建設されていたこと、沙里院と平壌で2試合ずつ、新義州で3試合、南浦で1試合の合計7試合が行われたことなどが触れられている(鈴木 2013:184)。
この時の北朝鮮代表は7試合合計で37本の安打を放ち、そのうちの2本がホームランだった(鈴木 2013:184)。ホームランのうち1本は二塁手のキム・ウォンシク、そしてもう1本は投手の波山次郎が放った(鈴木 2013:184)。
このように、鈴木の著作においてはじめてその実体が明かされた1974年のキューバ代表と北朝鮮代表の試合であったが、その後これをきっかけに北朝鮮とキューバの野球交流が活性化した形跡はない。1977年ごろには波山次郎も平壌鉄道体育団を去り、清津市の鉄工所へと戻っていった(鈴木 2013:186)。
正岡の2021年の研究では、北朝鮮の野球に訪れた転機は、1986年にキューバのカストロ議長が訪朝して金日成主席と会談し、その席上で野球をすることを勧めたことだった(正岡 2021:112)とされている。これに応じて、1988年10月に開催された全国人民体育大会の種目に野球が追加された(正岡 2021:112)。
しかし、このカストロ訪朝が北朝鮮野球に与えた影響は、どうやらプラスの要素だけではなかったように思われる。鈴木の2013年の著作では、1980年代から90年代にかけて北朝鮮野球協会の会長を務めた在日コリアンの実業家、鄭原徳(チョン・ウォンドク)が語ったこととして、80年代半ば、しかも内容的にはカストロ訪朝の後と思われる時期の話として、平壌の大同江の河川敷にあった野球場の環境が劣悪であったことや、ユニフォームのズボンがゴムひものモンペのようなものでみすぼらしかったため日本のメーカーに特注したこと、そしてキューバから提供された野球道具が朝鮮人の体格に合わずバットもグローブも重すぎたことや、キューバから派遣されたコーチの指導に選手がついていけずケガをするなどして、コーチがさじを投げていたことなどが明かされている(鈴木 2013:168‐169)。
後述の、北朝鮮代表チームに関する『週刊ベースボール』の報道などでも、「北朝鮮の野球はキューバの影響が強い」とする論調が散見される。しかし、実際には北朝鮮の選手とキューバの野球道具やコーチとの相性は悪く、真の北朝鮮野球の強化は、鄭原徳が個人で日本製の野球道具一式を寄付した(鈴木 2013:169)ことなど、日本との結びつきによってなされたとみるべきであろう。鄭原徳は1987年、1988年の二度にわたって在日朝鮮人選抜野球チームを率いて訪朝したが、キューバへの野球留学の成果などもあって、1988年には北朝鮮の野球のレベルが上がっていたとも語っている(正岡 2021:113)。
「野球朝鮮民主主義人民共和国代表」の軌跡
野球の北朝鮮代表チームが初めて国際大会に参加した時期については、Wikipedia日本語版に記載のある、新潟で開催された「第1回環日本海国際親善野球大会」に参加した1991年とされてきた。このほか、大島の2006年の著作には、先述の朴賢明の末弟にあたる朴賢殖(パク・ヒョンシク)へ取材した内容として、1990年に北京で開催されたアジア競技大会の野球競技に北朝鮮が参加した(大島 2006:88)という主旨の記述があるが、おそらくこれは誤りであろう。少なくとも公式記録上は、1990年のアジア競技大会の野球競技に参加したのは中華民国(チャイニーズタイペイ)、日本、韓国、中華人民共和国の4か国であり、北朝鮮の参加は確認できない。
しかし、筆者の調査によって、1991年の「第1回環日本海国際親善野球大会」でも、1990年のアジア競技大会でもない、別の大会に北朝鮮を代表して野球チームが参加していたことが判明した。
『週刊ベースボール』1989年11月20日号に掲載された、「ピョンヤンにも野球の火が灯る 日本海沿岸諸国での野球大会の開催を目指して」という記事によれば、1989年10月15日から20日にかけ、中国の福州で行われた「二化杯国際棒球大会」に、平壌鉄道省体育団チームが参加していた(著者不明 1989:128)。選手のプレーする姿の写真はないものの、当時のベースボール・マガジン社の社長池田恒雄と、北朝鮮野球協会の書記長の金喜洙(キム・ヒス)、さらに平壌鉄道省体育団監督の金清吉(キム・ジョンギル)が並ぶ記念写真や、池田を囲んでスーツ姿の北朝鮮チームの選手が揃った集合写真などが掲載された。なお、このときの北朝鮮チーム関係者への取材は事前に予定されていたものではなく、当時中国を訪問していたベースボール・マガジン社の池田社長の一行が、平壌鉄道省体育団と上海のホテルでたまたま顔をあわせたのがきっかけであったことを、同社常務取締役の田村大五が『週刊ベースボール』1989年12月4日号に掲載の「白球の視点」で明かしている(田村 1989:24)。なお、この記事に掲載された写真では、金清吉監督は左胸にハングルで「朝鮮」と書かれたパーカーを着ており、ユニフォームのズボンは縦縞であった。したがって、後述する記事でカラー写真で紹介された代表ユニフォームとは異なるデザインのものであったと考えられる。
パーカーの「朝鮮」の文字や、レベルや規模はどうあれ「二化杯」が「国際大会」であったことを考えると、この時の平壌鉄道省体育団チームは「事実上の北朝鮮代表チーム」と言えるだろう。
ちなみに、このとき平壌鉄道省体育団を率いた金清吉は、「第1回環日本海国際親善野球大会」でも北朝鮮代表チームの監督を務めたほか、東京の上野出身で、十条の朝鮮学校を卒業したのち1961年に帰国事業で北朝鮮に渡った人物であると鈴木の2013年の著作で紹介されている(鈴木 2013:156)。
1974年にキューバ代表と対戦した平壌鉄道体育団、そして1989年に「二化杯」に参加した平壌鉄道省体育団は、いずれもおそらく鉄道省所属のチーム、すなわち「機関車体育団」であったと考えられる。
「二化杯」は、中国、日本、そして北朝鮮のチームが2回総当たりのリーグ戦を戦った。そのスコアを、先述の『週刊ベースボール』の記事に沿って示す(著者不明 1989:128)。
平壌鉄道省体育団 18‐0 日本航空
中国二化 2‐11 平壌鉄道省体育団
中国二化 18‐6 日本航空
平壌鉄道省体育団 9‐0 日本航空
平壌鉄道省体育団 13‐2 中国二化
日本航空 5‐14 中国二化
平壌鉄道省体育団は、4試合を戦って全勝で優勝した。完封2試合、4試合合計の失点がわずかに4点、1試合あたりの平均得点は12.75点、投打ともに他の2チームを圧倒した。このときの試合については、今後日本航空(JAL)側に資料が残っていないか問い合わせてみたいと考えている。
この「二化杯」に関する『週刊ベースボール』の報道は、韓国球界でも話題となった。『週刊ベースボール』1989年12月4日号の「白球の視点」では、平壌鉄道省体育団に『週刊ベースボール』の愛読者の選手がいたこととあわせて、かつて大阪タイガースに在籍しのちに北朝鮮に渡った朴賢明の末弟で、1989年当時KBOの審判委員長を務めていた朴賢植が、チーム内の最長身の初老の男性の写真について、生き別れの兄(おそらく三番目の兄の朴賢民)ではないか?と指摘して話題となっていたことを、共同通信を引用しつつ報じている(田村 1989:24)。
1990年7月に北朝鮮はアジア野球連盟に加盟し、同年8月2日には、国際野球連盟(IBA)の40番目の会員として正式に加盟した。実は国際野球連盟においては北朝鮮は比較的「古参」にあたる。
そして、同年12月15日から28日にかけて、鄭原徳の招待でIBA会長のロバート・スミスとIBA副会長の山本英一郎が平壌を訪問した(鈴木 2013:163)。
山本は『週刊ベースボール』1991年1月28日号に「日本野球連盟副会長」の肩書で手記を寄せており、IBA加盟後には上層部の命令で北朝鮮国内の10の大学に野球部の新設が決まったことや、1992年までに4000人規模の新球場の建設が予定されていること、ナショナルチーム候補選手A組の練習をスポーツオリンピックセンター内のグラウンドで見学したことなどを綴っている(山本 1991:126)。記事には、のちに新潟へ派遣される代表チームと同一のデザインのユニフォームを着た選手たちと一緒に山本が写っている集合写真も掲載されている。その一方で、山本の記述には「彼の地に野球が再スタートしたのは1987年とのこと」(山本 1991:126)という不正確な内容もみられる。なお、このとき山本が設計図を見た新球場は、鄭原徳の資金提供によって計画が進められていたものだったが、北朝鮮側が別の用途に資金を流用するなどしており、結局頓挫した。この顛末は鈴木の2013年の著作に詳しい。
『週刊ベースボール』の歴史において、もっとも北朝鮮野球が大々的に取り上げられたのは、1991年6月10日号であろう。
ノンフィクション作家の工藤美代子が北朝鮮を訪問して北朝鮮代表チームを取材した特別寄稿「ピョンヤンで出会った『男のスポーツ』」という記事では、「第1回環日本海国際親善野球大会」に向けて特訓をしている北朝鮮代表チームについて、平均年齢が21~22歳で、そのほとんどが大学生であったことが紹介されている(工藤 1991:106)。また、北朝鮮の野球ブームについて、野球がオリンピックの公式種目となり、アジア代表の出場枠が1992年のバルセロナ大会では2枠、1996年のアトランタ大会では3枠となることを受けて北朝鮮、中国、ソ連が野球に力を入れていることが要因であると工藤は指摘している(工藤 1991:106‐107)。工藤が取材をした1991年時点では、国から十万ドルの国家予算がおりて、国内11の大学に野球部が創設され、さらに50校もの中学校で軟式野球が始まり、野球のルールを解説するテレビ番組も放映されていた(工藤 1991:107)。
工藤は、北朝鮮代表チームの練習を取材した感触として、レベル的には日本や韓国、台湾のアマチュアに遠く及ばないが、その真剣さと気迫に圧倒されたと綴っている(工藤 1991:107)。また、北朝鮮の野球関係者が「わが国では、他の国が五年かかるところを、少なくとも二年半でなしとげるのです」と語っていたことや、本稿で先述したスタジアム建設計画にも触れており、北朝鮮野球の急速な発展に感銘を受けた様子が窺える(工藤 1991:107)。
このとき工藤が取材した選手は、エース右腕の柳英吉(リュ・ヨンギル)、左打の四番打者である辺春男(ピョン・チュンナム)の二名である。
柳英吉は、身長183センチ、79キロ、取材当時は鉄道大学二年生の21歳であった(工藤 1991:106)。「なぜ野球に惹かれたのか?」との工藤の問いに「これは、つまり、男のスポーツだと思いました。闘志をつらぬく男の仕事としての憧れと言ったらいいのか……」(工藤 1991:106)と答えた。
辺春男は、取材当時第一師範大学三年生の22歳。中国での遠征試合で場外ホームランを打った選手であると紹介されている(工藤 1991:106)。「なぜ野球に惹かれたのか?」との問いには、「最初に野球を見た時に、自分もやってみたいと思いました。打つのが、自分の好みに合っていて、特に面白いのです」(工藤 1991:106)と語っている。
このときのエースと四番への取材中には、「ガールフレンドはいるか?」との問いに二人とも激しく首を振り、答えに窮する二人の選手にコーチが「新潟の試合に勝つまでは、ガールフレンドどころではないですよ」(工藤 1991:107)と助け船を出す……という一幕もあった。恋愛そっちのけで、真剣な表情で猛練習に明け暮れる北朝鮮代表チームの選手たちと、「商業ベースに染まってしまったような顔」(工藤 1991:107)の若者が多い日本の高校野球の選手とを比較しつつ、工藤は北朝鮮代表チームが今後強くなり、レベルも向上するであろうという強い期待を寄せている。
工藤が取材したときの北朝鮮代表チームの練習は、午前中3時間、午後3時間半、エースの柳は毎日200~250球投げるというものであり、24名の候補選手から17名を選抜して日本へ派遣する段取りとなっていた(工藤 1991:108)。ちなみに、日本での北朝鮮代表チームの練習拠点は駒澤大学であった(工藤 1991:108)。
また、コーチのほとんどが日本からの帰国者であり、基本的には日本式の野球をしているものの、選手の中にはキューバのスタイルでバットを寝かせている選手もいたことを工藤は指摘している(工藤 1991:108)。これは、代表メンバーの何人かがキューバに長期の合宿に行っていたことと無縁ではないだろう(工藤 1991:107)。
工藤の取材に応えて、ある野球関係者が、北朝鮮は従来弱いスポーツを国際試合に出さなかったが、最近は行ってみてとにかく勉強しなさいという姿勢に変わってきた(工藤 1991:108)と語っていたことに注目したい。このあと、実際に「第1回環日本海国際親善野球大会」に参加したことで、そうした柔軟な方針が少しずつ変化していく。
『週刊ベースボール』1991年6月10日号に載った北朝鮮野球関連記事は、工藤のルポだけではない。「シリーズ・世界野球紀行」の第2弾として、池田哲雄の取材による「北朝鮮の素顔と野球事情」と題したカラー写真付きの記事が掲載されている。この記事はマスゲームや「青春通り」スポーツ村の写真のほうが北朝鮮の選手の写真より大きく掲載されており、北朝鮮代表チームよりも北朝鮮という国そのものへの言及が多いなど、構成には不満も残るが、それでもカラー写真で北朝鮮代表チームを紹介した点で画期的であろう。
この記事では、投球練習をするエースの柳の姿や、キャプテンの鄭民主(チョン・ミンジュ)、エースの柳、四番の辺春男のスリーショット、河川敷のグラウンドでの打撃練習、グラウンドに集合した代表チームの集合写真が掲載されている。
これらの写真から、北朝鮮代表のユニフォームは、シャツは濃い緑色で首元と袖に白と赤のラインが入り、胸元には白い縁取りの赤い文字で、ハングルで大きく「平壌」と書かれていること、ベルトは赤色、パンツは薄い水色、そして帽子は緑色でつば部分が赤く、中央に赤色のロゴが入っている[注:印刷がつぶれていてロゴの形は判読不能である]ことが判明した(池田 1991:130)。なお、パンツの右腿には、ミズノのロゴが入っている。

引用元:『週刊ベースボール』1991年6月10日号
この記事では、工藤の取材とは若干異なる部分もある。それは、このときの代表チームが、1991年9月から中国の北京と天津で開催されるオリンピックアジア予選(アジア野球選手権大会)を目指して結成されたものであると明記されていることである(池田 1991:130)。また、1990年12月には中国に代表チームが遠征し、4戦全勝であったことも紹介されている(池田 1991:130)。この時の中国遠征はおそらく練習試合であろう。北朝鮮野球協会の金喜洙書記長の「野球を始めた初期のころは、とにかくキャッチャーに人材がいなかった。ランナーがひとり出ると走られっぱなしで、必ず1点は覚悟しなくちゃなりませんでした」(池田 1991:130)というコメントも興味深い。この談話は、「第1回環日本海国際親善野球大会」での北朝鮮代表の戦いぶりを様々な点で暗示している。
また、この記事にはもう一枚、興味深い写真が掲載されている。宿舎でベースボール・マガジン社発行の『科学する野球』のイラストを見ながら勉強するエースの柳の姿である(池田 1991:130)。
『週刊ベースボール』1991年6月24日号に、6月7日に新潟県の鳥屋野球場で開幕した大会の模様を伝える「第1回環日本海国際親善野球大会リポート」が掲載された。ただしこれは、大会の全日程を消化した時点のものではないことに留意する必要がある。
このリポートで目を見張るのは、北朝鮮代表チームが6月8日の対ソ連戦で19安打19盗塁を挙げ、22‐1で大勝したことだろう(著者不明 1991a:117)。記事には、盗塁を決める北朝鮮の李在成(リ・ジェソン)の姿をとらえた写真も掲載されている。6月10日号で北朝鮮野球協会の書記長が、代表チームについて「キャッチャーの人材難だった」という趣旨のコメントをしていたことを思い越せば、対ソ連戦で北朝鮮はソ連側の「キャッチャーの人材難」を突いたのである。
確実なミート、盗塁で相手のミスを誘うスタイルは日本の野球に近い……と指摘しつつ、この記事では北朝鮮の野球について「ルーツは日本ではなく、同じく社会主義国家のキューバから導入された。88、89年の2回にわたり現在のメンバーのほぼ全員がキューバに野球留学」(著者不明 1991a:117)と断言されている。また、金清吉監督の「キューバ、日本の両方のスタイルを学び、いろいろ考え迷ったが、野球は技術だということがわかった」(著者不明 1991a:117)という談話や、キャプテンの鄭民主の「今までは力の野球が基本だったが、考える野球をしたい」(著者不明 1991a:117)というコメントも掲載されている。野球留学があったにせよ、北朝鮮野球のルーツを日本ではなくキューバだと言い切っている点は、若干の取材不足の感もあるが、北朝鮮代表が挙げた「歴史的な初勝利」を詳しく紹介している点においては評価すべき記事であろう。北朝鮮代表チームについては、同じ6月24日号の他の記事でも「セーフティバントなどの小技をからめた野球を誇る」(著者不明 1991b:125)と紹介されている。
ちなみに、「第1回環日本海国際親善野球大会」に参加した日本代表は、実業団のニチエーを中心とした「オール新潟」チームであり、そのメンバーの内訳ははっきりしていない(著者不明 1991a:116)。なお、日本代表のユニフォームには「JAPAN」ではなく「NIIGATA」と書かれていた。
『週刊ベースボール』1991年7月1日号には、「社会人野球リポート」のページで「第1回環日本海国際親善野球大会」の全試合のスコアが掲載された。その内訳は下記のとおりである。韓国が全勝で優勝した。日本は韓国に敗れ、中国と引き分けるなど不振で2位に終わった。中国が3位、北朝鮮が4位、ソ連が最下位となった。
この大会の韓国代表チームは漢陽大学校、日本代表は先述の通り「オール新潟」、そして中国は北京体育学院と天津体育学院の学生を中心としたチーム、ソ連代表はハバロフスク地方選抜チームであった(相川 1991:104‐105)。ハバロフスクは、1986年からベースボール・マガジン社社長の池田恒雄らが訪問し、野球の指導に力を入れてきた街であった(相川 1991:105)。
6月7日
日本 19‐1 ソ連(7回コールド)/北朝鮮 1‐24 中国(7回コールド)
6月8日
ソ連 1‐22 北朝鮮(7回コールド)/韓国 13‐5 日本
6月9日
韓国 8‐1 中国/日本 15‐4 北朝鮮
6月10日
中国 10‐0 ソ連(7回コールド)/北朝鮮 1‐2 韓国(降雨ノーゲーム)
6月11日
ソ連 1‐28 韓国(7回コールド)/中国 4‐4 日本(9回引き分け)北朝鮮 1‐16 韓国(7回コールド)
6月10日の、野球史上初の南北対戦は降雨ノーゲームとなった。この大会の規定では、雨天ノーゲームは順延せず、消化済みの試合成績で順位を決定することとなっていたが、大会本部側が「せっかくの南北対戦をなくするのは忍びない」と両軍の監督に掛け合い、6月11日に急遽第3試合として改めて南北の試合が組まれた(相川 1991:104)。6月10日の試合で2回にソロホームランを放った北朝鮮の四番チ・バンソンは「この大会に参加している日本をはじめ、ソ連、中国の選手とは言葉も通じない。でも、南の選手とは話も出来たし、勝ち負けよりも、一つの民族が野球を出来たということに意義があった」(相川 1991:104)とのコメントを寄せた。また、両軍の監督は「南北統一チーム」の夢を熱く語った。
ちなみに、この大会での「南北対戦」については、正岡の研究をはじめ、6月11日に急遽組まれた南北の試合については言及がなく、なぜか6月10日の降雨ノーゲームで情報が止まっているものが散見される。
ベースボール・マガジン社常務取締役の田村大五は、7月1日号掲載の「白球の視点」においてこの大会の模様を紹介している。記者会見には、南北両軍の監督に加えて、選手を代表して韓国代表の投手である金容範(キム・ヨンボム)と、北朝鮮代表の四番チ・バンソンが同席した。2回裏、チが金から左翼席に放った特大ホームランについて、金が「ストレートをきれいに捉えられた」といえばチは「スライダーだった」と答えて会見場は笑いに包まれたという(田村 1991:24)。幹部や監督が緊張を隠せない中、両軍の選手は打ち解けた雰囲気であったという。なお、この記事では、北朝鮮代表が日本戦でトリプル・プレーを決めたことも触れられている(田村 1991:25)。
『週刊ベースボール』は、自社が後援する「第1回環日本海国際親善野球大会」において、とりわけ南北対戦の実現を強くアピールしたいという意図をもっていたらしく、7月1日号には、6月11日にようやく実現した南北の試合と交流に焦点を当てた「“統一”の願いを込めて……」という写真付きの記事も掲載された。両軍の選手が試合後に笑顔で言葉を交わす写真は、この大会の意義を伝える一枚であろう(著者不明 1991b:124)。また、この試合の応援に駆け付けた新潟朝鮮学校の女子学生は、統一旗を振り、韓国の選手にも声援を送ったという(著者不明 1991b:125)。
当時茨城朝鮮高級学校の英語教師兼サッカー部監督(正岡 2021:113)で、北朝鮮代表に投手として参加した尹台祚(ユン・テジョ)は、取材に応えて「ホテルに帰るとお互いの部屋に出入りしてましたよ。それは言葉が通じるということだけじゃなく、お互いに野球をやっているからなんですよ」「“南北対決”なんて悲しいですよ。同じ民族なのに。統一して一緒に出たいですよ」(著者不明 1991b:125)と語った。また試合後のパーティーでは南北統一の歌を北朝鮮ナインが壇上で歌い、韓国の選手が駆け寄っていく一幕もあった(著者不明 1991b:125)。
「第1回環日本海国際親善野球大会」でソ連相手に代表チームとしての歴史的な勝利を挙げた北朝鮮代表チーム。1991年4月1日の結成以来目標としてきた9月の第16回アジア野球選手権に向けて気合も十分……と思われたが、『週刊ベースボール』10月7日号の「社会人野球リポート」によれば、北朝鮮代表は開幕直前でアジア選手権大会への不参加を表明した(著者不明 1991c:122)。
北朝鮮代表にとって、現時点で最後の国際大会参加となったのは、1993年にオーストラリアのパースで開催された第17回アジア野球選手権大会であった。大韓野球協会会長などを歴任した、横浜商業出身の崔寅哲(チェ・インチョル)は、この頃にオーストラリアで会った北朝鮮野球協会の理事や監督は、下関商業の出身と名乗っていたと語っている(大島 2006:89)。
この時の日本代表メンバーは次の通りである(二階堂 1993:107)。これはまさしく、北朝鮮代表と対戦経験をもつ日本の野球人の名簿である。なお、選手の経歴については1993年以降のものも記載した。
投 手:杉浦正則(同志社大→日本生命)、高橋建(拓殖大→トヨタ自動車→広島東洋カープ→ニューヨーク・メッツ→広島東洋カープ)、山部太(八幡浜工高→NTT四国→ヤクルトスワローズ)、米正秀(西京高→神戸製鋼→横浜ベイスターズ)、渡辺秀一(作新学院高→神奈川大→福岡ダイエーホークス)、川村丈夫(立教大→日本石油→横浜ベイスターズ)、織田淳哉(早稲田大→読売ジャイアンツ)
捕 手:田嶋大三(龍谷大→熊谷組)、大久保秀昭(慶應義塾大→日本石油→近鉄バファローズ)、柳沢裕一(明治大→読売ジャイアンツ→オリックス・ブルーウェーブ→中日ドラゴンズ)
内野手:谷口英功(東洋大学→東芝)、旗手浩二(法政大学→本田技研鈴鹿)、松本尚樹(若山商業高→住友金属→千葉ロッテマリーンズ)、小久保裕紀(青山学院大→福岡ダイエーホークス→読売ジャイアンツ→福岡ソフトバンクホークス)、十河章浩(近畿大→日本生命)、仁志敏久(早稲田大→日本生命→読売ジャイアンツ→横浜ベイスターズ→ランカスター・バーンストーマーズ)
外野手:高林孝行(立教大→日本石油)、梶田茂生(筑波大→日本生命)、佐藤友昭(中央大→プリンスホテル)、大野倫(九州共立大→読売ジャイアンツ→福岡ダイエーホークス)
社会人野球のオールスターに、渡辺、川村、織田、柳沢、小久保、仁志、大野の大学生メンバーを加えた、まさにドリーム・チームというべき日本代表に対して、北朝鮮代表のメンバーに関する報道は無い。
北朝鮮代表の試合に絞ってそのスコアを列挙する。
中華人民共和国 17‐1 北朝鮮
中華民国(チャイニーズタイペイ) 22‐0 北朝鮮(7回コールド)
オーストラリア 4‐2 北朝鮮
北朝鮮 6‐2 フィリピン
韓国 11‐0 北朝鮮(7回コールド)
日本 17‐0 北朝鮮(7回コールド)
北朝鮮と日本の試合、日本の先発は高橋健-田嶋のバッテリーで、織田がリリーフで登板した。佐藤が2号ホームランを放った(江成 1993:105)。
この大会を最後に、北朝鮮代表は野球の国際大会から姿を消した。
鈴木の2013年の著作によれば、この頃の北朝鮮代表チームの状況は、朝鮮労働党の幹部が無断でグラウンドに立ち入り勝手に練習を仕切り始め、指導者たちも古臭い方法論にこだわっていて選手がついてゆけないなど、惨憺たるものであった(鈴木 2013:170)。
6勝8敗。北朝鮮代表が「二化杯」「環日本海国際親善野球大会」「アジア競技大会」という三つの国際大会の公式戦で残した全成績である。もっとも、6勝のうち4勝は「二化杯」で挙げたものであることに留意する必要はあろう。日本航空には大勝し、「全新潟」そして社会人野球の全日本チームには大敗した……ということから、当時の北朝鮮代表のレベルを推し量ることができるだろう。
北朝鮮代表が国際大会で「7勝目」を挙げる日を、楽しみに待ちたい。
その後の北朝鮮野球
代表チームは国際大会から姿を消したが、北朝鮮野球そのものは完全には表舞台から消えたわけではない。1996年のアトランタオリンピックの野球競技では、キューバ対オーストラリアの試合の球審を北朝鮮の審判イム・ジュンが務めた。(https://imnews.imbc.com/replay/1996/nwdesk/article/2005266_30711.html)
また、2013年10月24日には、北朝鮮の朝鮮中央通信の報道を引用する形で、聯合ニュースが北朝鮮の野球について報じた。北朝鮮最強の野球チームとして、内閣鉄道省所属の「機関車体育団」を紹介している。この報道によれば、機関車体育団は1947年創設で、卓球や重量挙げ、サッカーなど多数の種目を抱える強豪であり、機関車体育団に野球チームが出来たのは1980年代末のことであったとされている。この点、本稿で先述した、1974年から波山次郎が所属した平壌鉄道省体育団を「機関車体育団」と同一のチームと見做すかどうかについて、検討の余地があろう。
また、この報道では機関車体育団は共和国選手権大会で10年連続優勝していること、機関車体育団に所属していた脱北者の話として、北朝鮮には野球チームが4つあるが、黄海道、平安北道などの地方にあり、平壌にあるチームは機関車体育団だけであることなどが紹介されている。2013年の共和国選手権大会野球競技では、機関車体育団が優勝、大寧江体育団が2位、臥牛島体育団が3位となった。(https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20131023191200014)
ただ、この報道に添えられた写真は、木製バットを持った選手と金属バットを持った選手が室内で素振りをする…というものであり、チームとしての方針がよくわからない部分がある。
2016年にYouTube上にアップロードされた、朝鮮中央テレビが2014年に「共和国選手権大会」の野球競技の模様を報じた映像をご紹介しよう。南浦市野球場での試合に勝利し、機関車体育団が1位となったことが報じられている。(https://www.youtube.com/watch?v=8ONcQ3YbpwM)
追記:北朝鮮の野球場・ソフトボール場
北朝鮮の野球場・ソフトボール場については、2016年に自由アジア放送(ラジオ・フリー・アジア)が、衛星写真がとらえた南浦市野球場について、試合をする人々が写っていたことを報じている(https://www.rfa.org/korean/weekly_program/c704c131c0acc9c4-d558b298c5d0c11c-bcf8-bd81d55c/satellitenk-02172016122657.html)
この、自由アジア放送の報道に掲載された、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学韓米研究所のカーティス・メルビン研究員の解説によれば、北朝鮮にある野球場は南浦市野球場が唯一であり、平壌の牡丹峰区域と普通江区域にそれぞれソフトボール場がある、とされている。
北朝鮮は1991年に国際ソフトボール連盟に参加し、2006年に中国で開かれた世界選手権大会と同年12月に開かれたアジア大会などに参加した。2007年に開かれたアジア・オセアニア州オリンピック予選に参加したのを最後に、国際大会から姿を消している。
ただし、国内ではソフトボールは続けられており、2010年5月には牡丹峰区域のソフトボール場で行われた「万景台賞」という大会の女子ソフトボールの試合を朝鮮中央テレビが中継した。(https://www.youtube.com/watch?v=T8C1HTnzQ-w)
この報道などを受けて書かれた、ある個人サイトには、南浦市野球場(https://maps.app.goo.gl/re5YZCVhHobuFugf9)や牡丹峰区域のソフトボール場(https://maps.app.goo.gl/tkEP2PWGgH9tJu5f9)などの他に、平壌の万景台区域に客席を備えた野球場があったものの現在は取り壊され、「朝鮮人民軍武装装備館」(https://maps.app.goo.gl/tkEP2PWGgH9tJu5f9)が跡地に建っていることが紹介されている。(https://maman12.web.fc2.com/now/now3553.htm)
参考文献表
相川光康 1991 「社会人野球リポート」『週刊ベースボール』1991年7月1日号:104‐105 東京:ベースボール・マガジン社
池田哲雄 1991 「シリーズ・世界野球紀行② 北朝鮮の素顔と野球事情」『週刊ベースボール』1991年6月10日号:128‐130
江成康明 1993 「社会人野球リポート」『週刊ベースボール』1991年3月22日号:104‐105 東京:ベースボール・マガジン社
大島裕史 2006 『韓国野球の源流 玄界灘のフィールド・オブ・ドリームス』 東京:新幹社
工藤美代子 1991 「特別寄稿 ピョンヤンで出会った『男のスポーツ』」『週刊ベースボール』1991年6月10日号:106‐107 東京:ベースボール・マガジン社
鈴木昌樹 2013 『甲子園と平壌のエース 東北高校・波山次郎と幻の北朝鮮野球』 仙台:本の森
田村大五 1989 「白球の視点 走れ!ヨシヒコ!平和な時代のヒーローよ…」『週刊ベースボール』1989年12月4日号:24‐25 東京:ベースボール・マガジン社
田村大五 1991 「白球の視点 ベースボールで解け合った人たちに幸いあれ」『週刊ベースボール』1991年7月1日号:24‐25 東京:ベースボール・マガジン社
著者不明 1989 「ピョンヤンにも野球の火が灯る 日本海沿岸諸国での野球大会の開催を目指して」『週刊ベースボール』1989年11月20日号:128 東京:ベースボール・マガジン社
著者不明 1991a 「第1回環日本海国際親善野球大会リポート」『週刊ベースボール』1991年6月24日号:116‐117 東京:ベースボール・マガジン社
著者不明 1991b 「日本海を平和な海に…第1回環日本海国際親善野球大会が新潟・鳥屋野球場で開幕!」『週刊ベースボール』1991年6月24日号:124‐125 東京:ベースボール・マガジン社
著者不明 1991c 「“統一”の願いを込めて…『第1回環日本海国際親善野球大会』で目にした感動的なシーン」『週刊ベースボール』1991年7月1日号:124‐125 東京:ベースボール・マガジン社
著者不明 1991d 「社会人野球リポート」『週刊ベースボール』1991年10月7日号:122‐123 東京:ベースボール・マガジン社
二階堂昭雄 1993 「社会人野球リポート」『週刊ベースボール』1993年1月25日号:106‐107 東京:ベースボール・マガジン社
正岡大陸 2020 「北朝鮮野球史 1」『チュッペ』第15号:2‐5 甲府:宮塚コリア研究所
正岡大陸 2021 「北朝鮮野球史 2」『チュッペ』第18号:110‐114 甲府:宮塚コリア研究所
山本英一郎 1991 「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の野球との出会い」『週刊ベースボール』1991年1月28日号:126 東京:ベースボール・マガジン社
参考サイト
북한 야구 심판 임진, 쿠바.호주 야구 경기 심판[김주태]
(韓国・MBCニュース、1996年7月21日)https://imnews.imbc.com/replay/1996/nwdesk/article/2005266_30711.html (2024年6月29日閲覧)
北 야구 '명문'은 기관차체육단…10년째 우승 석권
(韓国・聯合ニュース、2013年10月24日)https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20131023191200014
(2024年6月28日閲覧)
북한의 야구·소트프볼 경기장
(韓国・自由アジア放送 2016年2月17日)https://www.rfa.org/korean/weekly_program/c704c131c0acc9c4-d558b298c5d0c11c-bcf8-bd81d55c/satellitenk-02172016122657.html
(2024年6月30日閲覧)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
