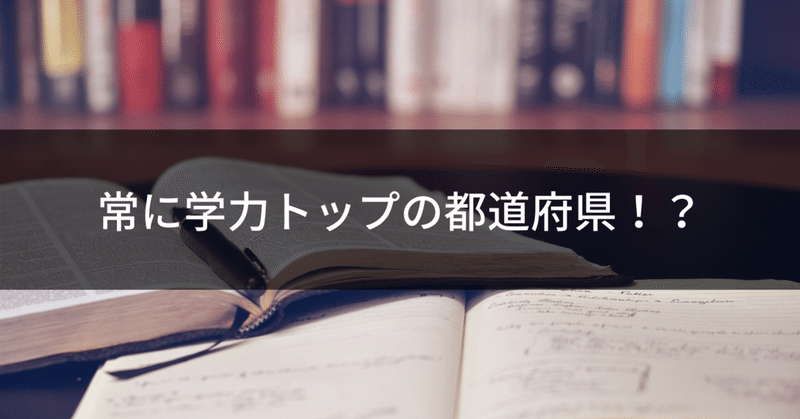
常に学力トップの都道府県!?
みなさん!
日本の中で学力の高い都道府県どこか気になりませんか?
東京や大阪などの都会の方が塾などの教育施設も充実してるし学力が高いんじゃないの、と私はそう思っていました。
しかし、実は、、、
秋田県
が日本でいちばん学力が高い都道府県なのです。
続いて北陸三県が入ります。
小学校 国語
1位秋田県 2位石川県・福井県
算数
1位石川県 2位秋田県・東京都
中学校 国語
1位秋田県 2位石川県・福井県
数学
1位福井県 2位秋田県・富山県・石川県
英語
1位東京都・神奈川県・福井県 4位石川県・静岡県・兵庫県
出所:国立教育政策研究所「平成31年度(令和元年度) 全国学力・学習状況調査【都道府県別】および【指定都市別】調査結果資料」を基に東洋経済作成
まず調べて驚いたことがあります。
秋田県は塾に通っている子が全国で一番少なかったんです。
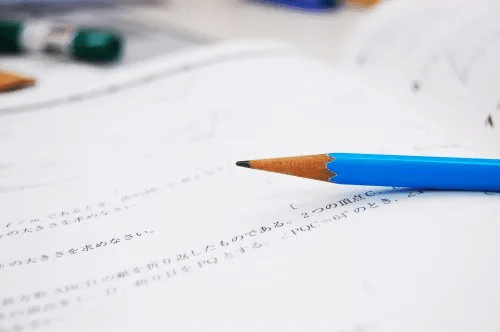
ますます僕の疑問は深まっていきました。
どうして学力が高いのだ。。。その理由について今回は紹介していきたいと思います。
今回はこちらの本「子ども格差の経済学」の本を参考に記事を創らせていただきました。
秋田県や北陸3県の学力が高い理由
①子どもを伸ばす授業づくりの特徴
◯「恥ずかしい」という感覚を無くす
秋田県の学校では、学校や家庭で何かを間違えたとしても、責めたり馬鹿にしたりすることは決してなく、間違えても良いと安心できる雰囲気や授業がつくられています。
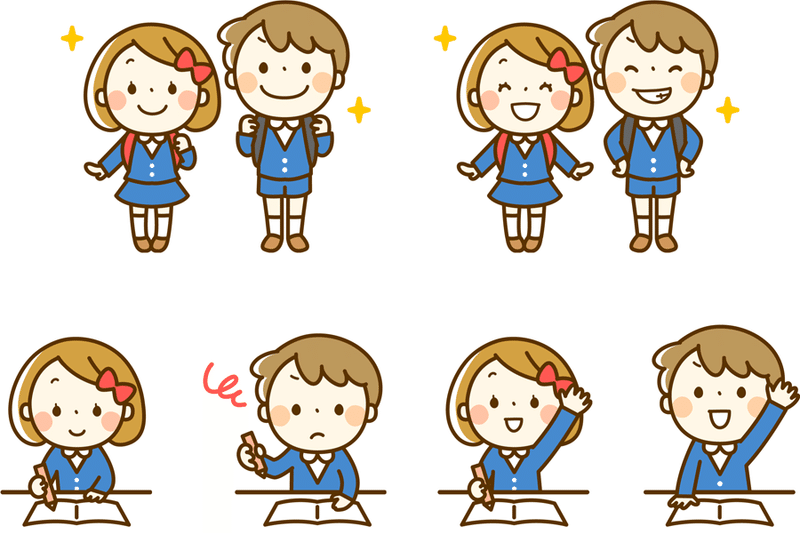
例えば、学校で誰かが発表して答えを間違えたとします。
よく見られるのは、「違います」と先生や周りの子どもたちに言われて終わりというパターン。しかし、秋田県の多くの学校では、もし誰かが間違えたら、それさえも授業の材料とし、みんなで正解を見つけていこうという姿勢で授業をしているのです。
そのため秋田県の子どもが間違いを恐れず、間違えることを「恥ずかしい」と思うことがなくなります。このことは、秋田県は全国的に見て圧倒的に無回答率が低いということがそのことを証明してくれています。
◯表現重視の授業づくり
秋田県では、ただこなすだけの授業ではなく、表現することを重視した授業づくりがされています。
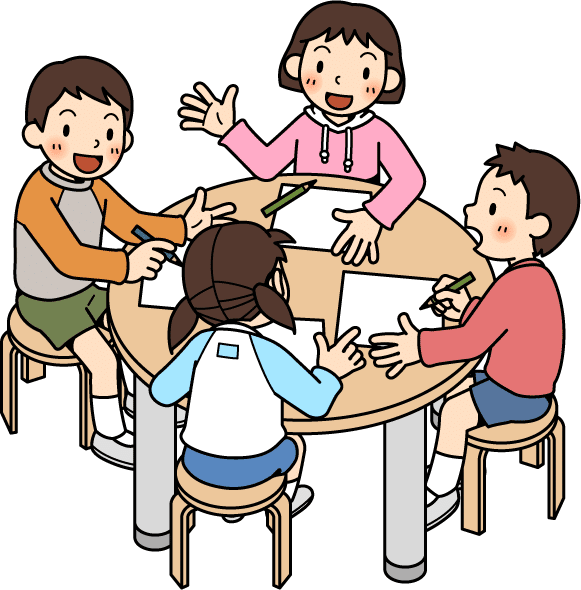
例えばかけ算の学習をするときに、九九をただ覚えるというのではありません。かけ算の計算の仕方はどうしたら解けるのか、九九はどんな仕組みになっているのかなどを、先生が教えるのではなく、子どもたちが考える授業を展開しています。
いろんなひらめきやアイデアを出して考えを練り合い、答えにたどり着くように工夫がされています。そのため、ただ聞く、こなすだけの授業ではなく、自分を表現する量が多くなります。
◯保護者も参加する家庭学習ノート
秋田県では、普段出される宿題以外にも、家庭学習ノートなどで自学をするようにしているところが多くあります。この家庭学習ノートは、自分で自分に問題を出す形で取り組まれています。内容は特に問われていないのが特徴で、自分の好きな教科、苦手な教科、予習、復習、漢字の練習、視写など、その日に自分がやりたい内容をなんでもして良いということになっています。
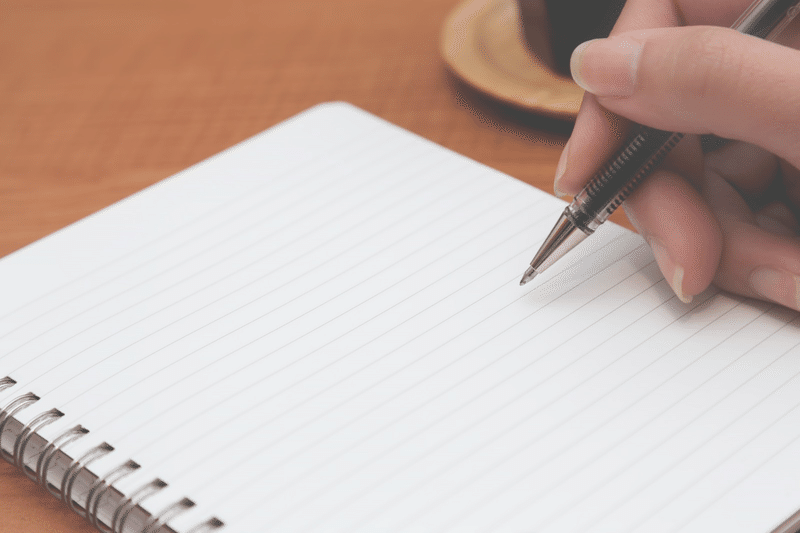
子どもが学習したノートには、保護者と担任がコメントを残します。全国的には、担任が子どもへコメントを残すというのはよく見られますが、秋田県では保護者もコメントを残すという点が他県との違いであり、ポイントでもあります。
家庭学習ノートは、やりたくない学習をするわけではありませんので、子どもも進んで取り組みます。また、自分が頑張ったことに対して、誰かが反応を返してくれるということは、見てもらえている、認めてもらえているという安心感や、次も頑張ろうというやる気につながっていきます。
さて、ここまで学校での取り組みについて話をしてきました。もちろんこれは学校や教師の血のにじむような努力と研究のおかげでしょう。しかし、それだけではありません。このような努力をおこなえたのはのは家庭とのつながり、地域との強いつながりがあったからなのです。ここからは、そのことについて紹介します。
②家庭の協力による学習習慣と生活習慣の改善
◯睡眠と朝ご飯がしっかりとれている
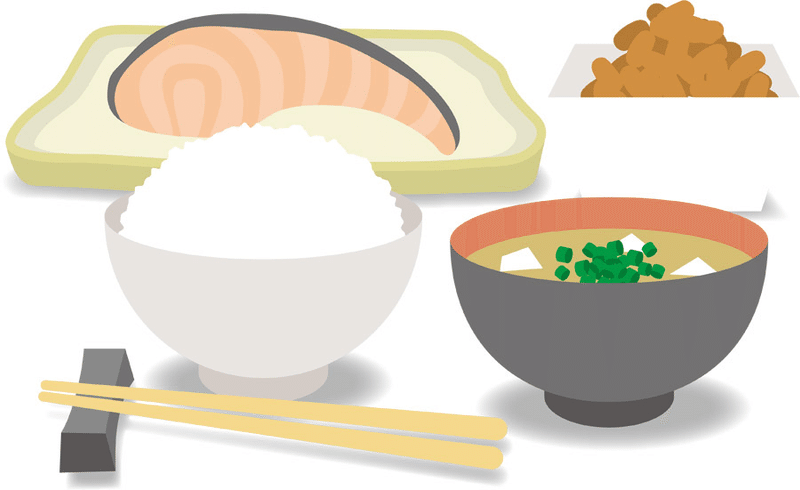
近年では、スマホやゲームが普及していることもあり、夜遅くまで起きていたり、時間がなく朝ご飯をしっかり食べなかったりする子どもが増えてきています。
しかし、秋田県ではアンケートなどの結果から、睡眠や朝ご飯が他県に比べてしっかりととれていることが分かっています。睡眠と朝ご飯をしっかりととれていなければ、当然学校で授業に集中することができません。授業に集中できないだけではなく、身体的にも成長が遅れてしまう可能性があります。

家庭での、生活リズムをきちんとつけることができている子が秋田県には比較的多く、授業に集中できる環境にあることも大きな影響ともいえるでしょう。
◯3世代住宅の安定性
秋田県は、3世代住宅の家庭がとても多いです。そのため、両親が共働きしていてもおうちにはおじいちゃんやおばあちゃんが見守ってくれる安心感があります。両親も安心して働け、子どもたちも一人で寂しい思いをしないことも大きな影響ともいえるでしょう。

③地域の教育力の高さと学校・地域のつながり
家庭、学校、先生、地域が一体となって教育に熱心
◯授業参観の保護者参加率が高い

秋田県の授業参観の保護者の参加率は、なんと120%にも及びます。120%とはどういうことかというと、両親のみならず祖父母や親戚、近所の方なども参加する。みんなで子どもを見守る文化が出来ているということですね。。
村全体で子どもを見守り、子どもは両親からももちろん、周りの大人たちからたっぷりの愛情を受け、劣等感を持たない自尊心の高い子どもに育っていく。
そのため、子どもは学習にやる気が出たり自信を持てます。
最後にはなりますが、学力が高いから一番良い教育をしているというわけではありません。全国各地の先生方は、毎日汗水たらして色んなものから圧力を受けながら素晴らしい教育を創ってくれています。なので、これはあくまで参考に、これからの未来の教育を創っていく一つの参考になればいいなと願い今回の記事を作成しました。
このブログでは「幸せに繋がる子育てのための知識」を発信していきます。論文、科学的根拠に基づいた情報を発信していくのでフォロー、いいね、コメント等をして頂けると有益な情報収集を加速させる事ができます。ご協力お願いします。
それではまたお会いしましょう!
参考文献
志水宏吉、前馬優策(2014)「福井県の学力・体力がトップクラスの秘密」、中公新書ラクレ
太田あや(2009)「ネコの目で見守る子育てー学力・体力テスト日本一!福井県の教育のヒミツ」、小学館
橘木俊詔(2017)「子ども格差の経済学」、東洋経済新報社
田中 博之(2011)「全国学力・学習状況調査において比較的良好な結果を示した教育委員会・学校等における教育施策・教育指導等の特徴に関する調査研究」、平成22年度文部科学省委託研究
北条常久(2017)「秋田県が学力日本一はなぜ」、あきた経済2017年5月号pp,21-22
渡邉剛(2014)「いい子供が育つ都道府県ランキング」、共立総合研究所、2021年5月5日最終閲覧
https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/04/153-research1.pdf
秋田県「全国学力テスト」成績上位常連のなぜ、東洋経済ONLINE、東洋経済新報社、2021年5月5日最終閲覧
https://toyokeizai.net/articles/-/385027
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
