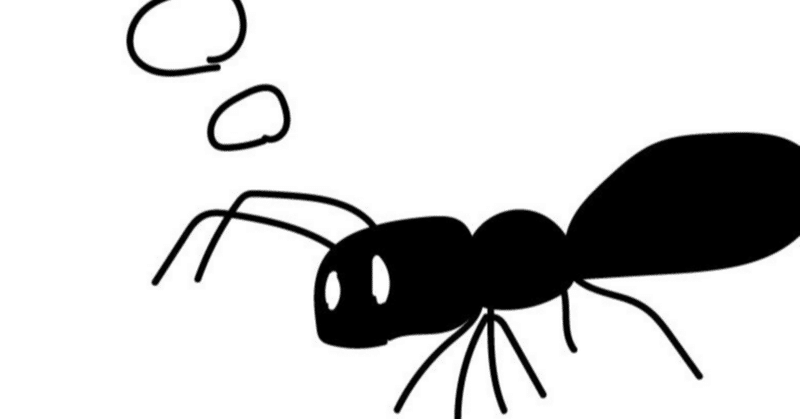
クソみたいに報われない仕事について。
しんどい。
シット・ジョブで働くってことは、とんでもなくしんどい。
まるでボクシングだ。
シット・ジョブというリングに立ったら最後、身も心も打ち砕かれる。
完膚なきまでに。
『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』(ブレイディみかこ著 KADOKAWA)は、読んでいるこちらまで真っ白に燃え尽きそうになってくる一冊だ。
シット・ジョブとは、クソみたいに報われない仕事のことをいう。
社会的ヒエラルキーがクソだったり、お給料がクソだったり(仕事のキツさに対して割に合わない)、人間関係がクソだったり・・・。
クソの種類は種々様々。
『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』は、タイトルの示す通り、主人公の「私」が世の中のありとあらゆるシット・ジョブを渡り歩くさまを描く。
容姿や年齢で容赦なく差別され、侮辱され、それでも笑って大金を稼ぐ「水商売」。
お手伝いさん、という名の下僕になる「ベビーシッター」。
人間でありながら機械になることに徹する「クリーニング屋」。
無資格・非正規に人権はないのか「保育士」。
金持ちにとっては自己満足な偽善ごっこの「ケアワーカー」。
どれも、誰かの毎日を支える大事なお仕事だ。
なにより、自分自身を支える糧でもある。
誰かの役に立てて、なおかつお金がもらえる。
うわあ、働くってサイコー!!!
・・・と、自分を洗脳できれば幸せなのかもしれない。
いやいや、洗脳なんてしなくても本来そうあるべきなんじゃないのか、仕事ってさ。
私の仕事は司書である。
カウンターでよく受ける相談が
「タイトルがわからないけど、こんな感じの本を探している」
というものだ。
利用者さんの話を注意深く聞いて、ヒントになりそうな言葉を探す。
右往左往して目当ての一冊を探り当てたとき、利用者さんも私も、声をあげて喜んでしまうのだ。静粛にすべき図書館で。
そんなとき、本当にこの仕事をしていて良かったな、と思える。
お給料は非常に少ないけど。
これが仕事であってほしい。
働く私も、その先にいる利用者さんも、お互いを支え合って、尊敬しあえる。そういう関係でなりたつものであってほしい。
だけど。
現実は厳しい。
本書で「私」が飛び込んだあらゆるシット・ジョブ。
そこで働く人々。その人々を取り巻く環境。その仕事につく経緯。
シット・ジョブの持つ背景みたいなものが、小説という形態で描かれているから我がことのように身につまされる。
そうやって、シット・ジョブを「経験」した結果、私が辿り着いたのが、
すべてのシット・ジョブをクソたらしめているのは、人々の偏見である
ということだ。
シット・ジョブという報われない仕事がまかり通っているのは、偏見があるからだ。
あの仕事は尊いけど、この仕事は卑しい。
そんな偏見が社会に染みついているからだ。
労働の対価としてお金を頂いているということは、その労働は社会にとって必要であるということである。
にもかかわらず、労働の種類によって貴賎が生まれるというのは、人々の偏見以外にありえない。(そもそも貴賎という概念は人間が作り出したものだし)
理不尽だな、と思う。
けれど、その理不尽に盾突いても、敵は社会そのものだから多勢に無勢。
勝てない戦をするよりも、少しでもお金を稼いだほうがまし。
そうやって理不尽に耐え、シット・ジョブに就いているうちに、いつのまにか自分自身が理不尽を受け入れてしまうようになる。
自分で自分を「シット・ジョブをしているクソな自分」だと思い込んでしまうのだ。
自分をクソだと思い始めると、人はすさむ。ひねくれる。歪む。
自暴自棄になる。
自分に優しくできないくらいだから、もちろん、人にも優しくできない。
自分より立場が弱いものを見つけて、攻撃し、憂さを晴らそうとする。
「あいつらに比べたら、私のほうがずっとマシ」。
そうやって自分を守っているつもりが、自分を傷つけているのだ。
生活を支えるための仕事が、自尊心を著しく損なう要因になっている。
それが、シット・ジョブだ。
しかし、救いはある。
シット・ジョブを生み出しているのが偏見なんだとしたら、私たちの意識しだいでシットをグッドに変えることだって出来るはずだ。
正直、すぐに変化を起こすための方法はわからない。
一筋縄ではいかないことは解っている。
そういうときのために、本があるのだと私は思う。
本は、考えるためのツール。
読んで、考えて、皆で意見を出し合えば、必ず変化は起こるはずだ。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。 新しい本との出会いのきっかけになれればいいな。
