
「インターなんて自分には関係ない」が終わる時代へ!教育のグローバル化に必要なこととは?ー年頭の挨拶に変えてー
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年は、立ち向かい乗り越える山が本当に多い一年になると思うのですが、この一年で方向性を明確にしたいと考えています。日本の子どもたちの未来をもう少し良くできることを、私にしかできないこととして実現します。
さて、全ての都道府県にインターナショナルスクールを設置することを提唱している私ですが、日本のインターナショナルスクールは、もっと身近であるべきだ、と思うようになったのは、息子が日本の高校を退学して、英国のインターナショナルスクールへ転校したのがきっかけでした。

英語が話せないのに、インターなんていけるの?
探せばある!選べばいける!
都内の私立高校に進学した息子は1年生でその学校を退学することにしました。片道90分の通学に疲弊していたことに併せ、日本語IB(国際バカロレア)カリキュラムでの学習と英語力アップの両立が難しいと判断したためです。もちろん、日本語IBと英語力の両立ができる生徒はいましたが、我が家の場合は、どちらも中途半端になることを危惧しての決断でした。 IB カリキュラムで学べて、ネイティブ同等の英語力も習得できるところ。 これが我が家の転校の条件でした。
日本国内で、IBカリキュラムで、かつ、帰国生でもないのに高校の途中から転入を受け入れている学校を探すと、インターナショナルスクールにいきつきました。しかし、日本にあるインターナショナルスクールには、高い英語力という壁が存在していました。残念ながら、当時の息子にはその壁を越えるほどの英語力はなく、また、英語力を伸ばしながら編入できるインターナショナルスクールは、2019年当時の日本では見当たりませんでした。
そこで、海外に目を向けたところ、英語力に不安があっても入学できるインターナショナルスクールがいくつか見つかりました。それらの学校は、ノンネイティブの学生のために、英語力アップのための語学習得コースなどを併設しており、一般の科目とは別にサポートが受けられるという学校です。
当時の彼は、英語はあまり話せず、英検2級を保有していたレベルでしたが、簡単な試験(英語インタビューやIELTSの模擬試験など)を受け、英国の全寮制インターナショナルスクールに転校を決めました。
知ればみんなも行きたくなる!
息子が英国のインターへ転校することを伝えると、「英語が話せないのにどうして英国の高校に行けるの?」という質問が何人もの友達からありました。彼はどうやったら海外のインターナショナルスクールに行けるか、次のような説明をしました。
〇海外には、留学生の受け入れを積極的に行っているインターナショナルスクールがある
〇そういったスクールでは、ネイティブではない留学生向けの英語補習クラスなどを履修できる
〇9月に新学年が始まる国に行けば、日本で3学期まで修了した後に留学が可能。しかも約半年間、英語補習クラスに集中できるので、正式修学の前に英語力がアップできる
〇留学生を受け入れているスクールには、母国での就学年齢が異なる学生もいるため、年齢差は気にならない
〇留学生専用の寮があるスクールもある。当然、24時間英語で生活ができるし、ネイティブではない生徒同士なので気後れせずに英語を使え、上達が早くなる
すると同級生が次々と退学を決意し、ニュージーランドや英国などのインターナショナルスクールに編入するという事態が起きたのです。
このことは、私に大きな気付きを与えてくれました。
みんな、インターナショナルスクールに興味があるのだ、と。
みんな、「自分には関係ない」と思っていただけではないのか、と。
だったら、もっと身近にあるべきではないか、と考えるようになったのです。

ニーズはあるのに、日本のインターには行けない!?
日本にあるインターの課題とは
日本にあるインターナショナルスクールが、あまり身近ではなく、希望する誰もが学ぶことができる場とならないのには、いくつか課題があると思います。
一つは、費用です。
日本のインターナショナルスクールは、コストが高すぎることが限られた人しか選択できない事態を招いています。調べたところ、年間学費は通学制で150~300万円、全寮制だと600〜1,000万円程となっています。近年では、名門のボーディングスクールも参入し、高額化はさらに進むものと考えられます。
公立校程度の学費で、とは言いませんが、せめて、私立校の平均的な学費で学ぶことができるインターが増えれば、身近な選択肢になるのではないでしょうか。将来的には、現在の私立高校無償化のように、インターナショナルスクールに対しても、地方自治体や政府が金銭的サポートしてくれる制度が整備されるのが理想です。
もう一つは、語学力です。
残念なことに、現在の日本では、学校の授業だけで、日常生活が送れるほどの英語力を身に付けることは難しいです。しかし、大多数のインターナショナルスクールが、英語を使用言語としており、ネイティブ並みの英語力が求められるなか、歴然たる語学力の差がとても高い壁となっています。ブータンやルワンダのように教育公用語が英語の国とは異なる日本だからこそ、ノンネイティブの生徒を対象とした「語学習得コース」などがセットになったようなインターナショナルスクールが、もっと必要なのではと思います。
そして、最後に数が少ないことです。
全都道府県に1インターの設置を実現してもっと身近になれば、
・外国人の行く学校
・有名人の子どもが行く学校
・帰国子女が行く学校
といったイメージが払しょくされ、教育の選択肢が広がると思います。
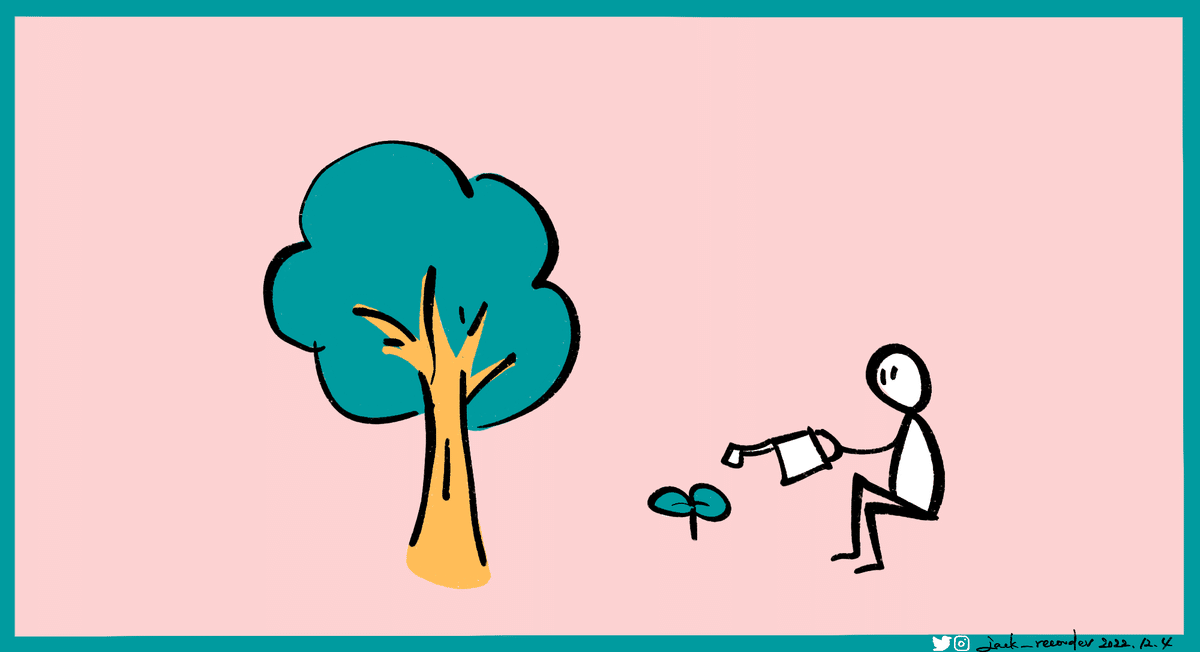
日本教育のグローバル化を後押しするために
私が、インターナショナルスクールを広めたい理由は、単に、英語が話せる日本人を増やしたいからではありません。日本の学校ではまだ追いつけていない国際基準の教育カリキュラムに注目をしているからです。
例えば、国際バカロレア(IB)カリキュラムです。IBは、スイスのジュネーブに本部を置く機関が提供する国際基準の教育プログラムです。世界159以上の国・地域、約5,500校で採用されています(2022年5月時点:文部科学省IB教育推進コンソーシアムより)。特に高校生が対象のDP(ディプロマ・プログラム)では、卒業時の世界共通試験のスコアを基準に世界各国の大学に入学することが可能となっており、世界中の大学を選択肢に考えている学生にとってのパスポート的な存在となります。
日本でも、グローバル人材育成の観点から、IBの普及・拡大を推進しており、IB認定校を2022年度までに200校以上に増やすことを目標としてきました。しかし、現在の国内のIB認定校は157校で、この中で日本の文科省が定める一条校(学校教育法第1条に規定されている学校、いわゆる日本政府が「学校と認める」学校)は61校にとどまっています。日本でIBカリキュラムを提供している教育機関としては、インターナショナルスクールが存在感があるのが現状です(※出典:文部科学省IB教育推進コンソーシアム)。
国際水準のカリキュラムは、IBだけではなく、ケンブリッジ国際認定などさまざまなカリキュラムがありますが、どんなカリキュラムだとしても、国の政策として普及させるには、時間がかかることでしょう。
国の動きを待っていたら、私たち親世代と同じ教育を受けた世代が増えてしまう。
そうなると、日本のグローバル化は、ますます遅れてしまう。
今の子どもたちの将来も、私たちと同様、日本国内に留まることになる。
この危機感こそ、私が全都道府県にインターナショナルスクールの設置を提唱している原動力となっています。
もちろんインターナショナルスクールが、”最高の教育機関”と言っているわけではありません。中には、成績の振るわない生徒に退学勧告したり、IBの単位取得を諦めるように促したりするインターもあり、子どもの成長を第一目標に運営されているとは言えないインターもあると耳にすることもあります。
ただ、プロジェクト思考の学びや対話で様々な課題を解決することを基本に学びを提供しているインターナショナルスクールが日本に増えることは、必ず、日本の学校教育現場を変革させることに繋がると思います。
大切なのは、子どもたちの未来を決める教育に、より多くの選択肢があること。
そして、その選択肢に、世界基準の学びがあること。
「インターなんて、私には関係ない」という時代が終わることこそ、日本教育のグローバル化に繋がり、日本の子どもたちが世界中で生きるための選択肢が広がると、私は信じています。

Illustrations by Jack (Morisaki Kyohei)
editorial support by Hara Tomoko
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
