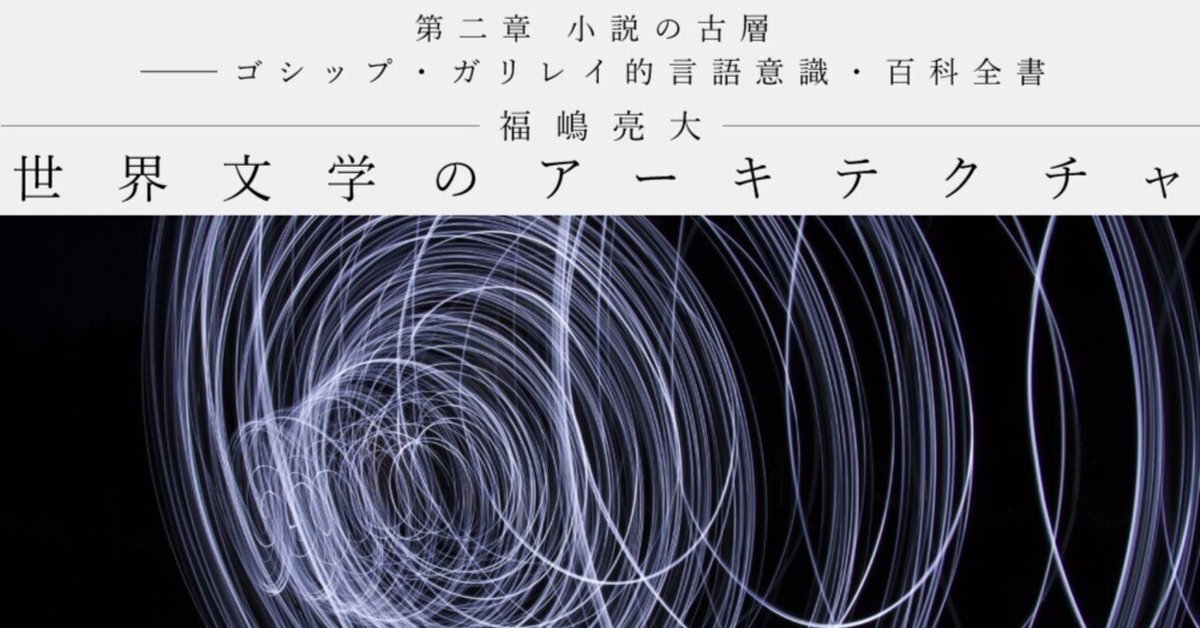
第二章 小説の古層――ゴシップ・ガリレイ的言語意識・百科全書|福嶋亮大
福嶋亮大 世界文学のアーキテクチャ
第二章 小説の古層――ゴシップ・ガリレイ的言語意識・百科全書|福嶋亮大
1、ゴシップの人類学的意味
小説の起源をいつ、どこに求めるかは難題である。ただ、人類史的な視点から言えば、ストーリーを語ろうとするコミュニケーションの意欲が人類に備わっていることが、あらゆる小説の必要条件であることは確かに思える。もし人間が「語る動物」でなければ、小説が生まれることもなかっただろう。
その一方、語る動物であるからといって必ず小説を生み出すわけでもない。どんな共同体にも物語はあるが、それが小説という形態をとるようになったのは、比較的最近の現象にすぎない。小説とは語りのコミュニケーションの大海に浮かぶ島嶼のようなものであり、ゆえに≪世界文学≫の進化を考えるには、まずは語りの条件を明らかにする必要がある。この点については、文学研究の外部に手がかりを求めるのがよい。
例えば、人類学者のロビン・ダンバーは、人間の言語的なコミュニケーションを猿の毛づくろいと類比している。霊長類の社会は多くの時間を毛づくろいに費やすことによって、集団的な結束や帰属感を高めてきた。しかし、群れが大きくなれば、毛づくろいに費やせる時間は限られ、社会の結合が保てなくなる。ダンバーの考えでは、この限界を突破するためにこそ、言語が必要とされた。対面の毛づくろいにかかる膨大な時間を省略しながら、それでも巨大な群れを維持するために、いわば音声的な毛づくろいとしての言語的コミュニケーション、とりわけゴシップ的な話題が求められた。ダンバーは大胆にも、人間に噂話をさせるためにこそ言語が進化したと結論づける[1]。
実際、ダンバーが言うように、人間の会話は知的・専門的な内容を含んでいたとしても、すぐに卑近な人間関係の話題へと転じてしまう。われわれは既知の人間も見知らぬ人間も遠慮なくゴシップの話題にのせながら、集団の結合を確保し、集団における自らの位置をもたえず確かめている。このような社会生活のあり方はインターネット時代になっても変わらないし、むしろ顕在化している。ネットのユーザーは誰某がこんな悪事を働いたとか、誰某と誰某が決裂したとか、その種のくだらない週刊誌的なゴシップに飢えている。このような性向は、人間の言語がそもそもそのような噂話の交換のために進化したことに基づく。
ゴシップはもっぱら人間の評価に関わるが、より広く言えば、人類はたえず環境の評価(アセスメント)をやるように仕向けられている。例えば、あの果実は食べられるのか、彼とは友人になれそうか、あの部族は敵対的か、明日の天候はどうなるか、狩猟にどれだけの労力が必要か――われわれの先祖はたえずそのような評価を下し、それを仲間に語りながら生存してきた。今日の大衆社会のゴシップは、そのような環境の評価を見ず知らずの他人にまで拡大したものである。
もとより、ゴシップの多くは有名人の評判の低下を狙っている。やっかみや嫉妬によって加速する大衆社会のゴシップは、たいてい下劣であさましい。にもかかわらず、ダンバーが示すように、われわれの噂話は恐らくその根底においては共同生活に資するもの、つまり協力的=利他的なコミュニケーションを促すものである。ひとが噂話に熱中するのは、それによって何らかの利益を他者と分かちあおうとするからである。
霊長類学者のマイケル・トマセロによれば、人間の幼児のやる指さしは、早くも情報のシェアの意欲を示している。幼児は大人たちが指さしに何とか反応しようとすることを知っており、だからこそしきりに対象を指示し、大人とその情報を共有しようとする。言葉を話す前から、手ぶりや身ぶりで外界を指示し、いわば大人を教育しようとする幼児のコミュニケーションは、他の霊長類と比較しても際立った特性を示している[2]。トマセロはこの前言語的なふるまいこそが、言語の進化の基礎にあると考えた。彼によれば、共同体に有益な情報を伝え、他者と「協力」するという「生活形式」(ヴィトゲンシュタイン)に深く依存して、言語は進化したのである。
逆に、言語がもっぱら「競争的」に、つまり他者を攻撃するために用いられるとしたらどうか、と想像してみるのも面白い。トマセロの考えでは、そのとき、言語の形式はわれわれの想像を絶したものになる。
さらに注意を引くのは、もしも協力でなく競争というコンテクストで進化していたなら、人間の「言語」はどんな風になっていただろうか――それを「言語」と呼びたいなら、の話だが――と想像してみることである。この場合、共同注意も共通基盤もないことになるから、指示するための行為を人間のようなやり方では行えなくなる。とくに視点や、その場に存在しない指示対象に関してはまず無理である。お互いに協力的であるという想定の下での伝達意図は存在しないし、それゆえどうしてある人が自分とコミュニケーションをしようとしているのかを一生懸命に見つけようとする理由もない――またコミュニケーションの規範もない。慣習とは人々が協力に基づく理解と関心を共有している場合にしか生じないものだから、慣習もないことになる。[3]
この空想上の「競争的」な言語は、今の言語とは似ても似つかないものになるだろう。トマセロによれば、それはフィクションも生み出せないし、協働の道具にもならない。そこからは慣習も発生せず、他者の意図を読み取ろうとする動機も生じない。この競争的な言語でもコミュニケーションは可能かもしれないが、それは協力的な言語によるコミュニケーションに比べれば、ひどく貧弱なものとなるに違いない。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
