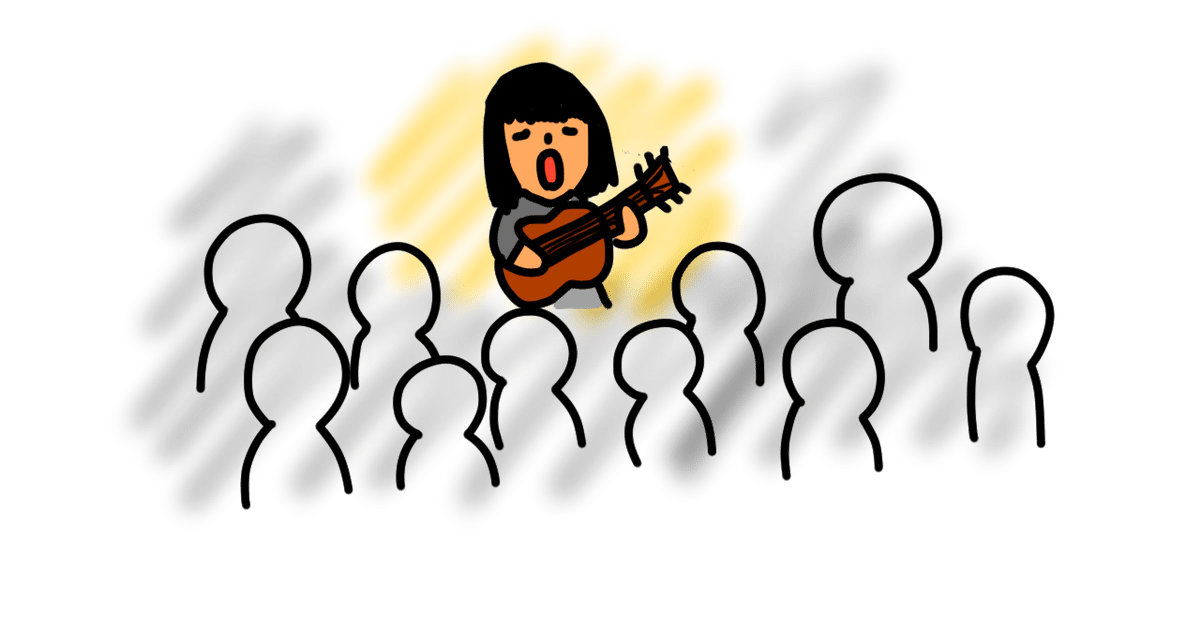
地方演劇を真面目に考える会 その9 【地域社会との関わり方 後編】
概要
2021年に和歌山市のクラブゲートと、オンラインで開催した「地方演劇を真面目に考える会」の記録です。以下のHPにて、開催した動画のアーカイブ、アンケートデータや、インタビュー動画をご覧になれます。ぜひご覧ください。
演劇以外の文化団体・芸術活動とのかかわり
今回は、まず演劇以外の文化団体や人とのかかわりを聞いてみました。地域に限らず、演劇以外の文化活動の関りも非常に重要な要素ではないでしょうか。

大体半々といった感じでしょうか。どちらがいい悪いではないと思いますが、演劇がやりたい団体と、文化活動がやりたい団体と、ちょうど半分に分かれたという感じかもしれません。演劇以外の文化活動と関りがあれば、活動に幅が出て、いろんなイベントなどに呼ばれる可能性も高くなってきます。特に音楽関係が地域社会でも非常に強い所が多いと思いますので、ライブハウスで音楽の間に演劇をするなどといったこともできるかもしれません。それだけ、演劇に興味がない層にもアピールをする可能性も広がります。演劇に興味がある観客層が少ない、非大都市圏では有効な活動方法といえます。逆にそれが煩わしいと思う時もあるかもしれません。そもそも演劇がやりたくてやっている団体であるので、そういうのがやりたくなければ演劇に特化するのも地域の劇団の在り方として、全然間違っていないと思います。いろんな所と、喧嘩しなければ! 仲良くはした方がいいですネ!
地方の演劇文化として抱えている問題
二つ目は前回のデメリットと似ているのですが、自由に書いていってもらいました。色々な意見がもらえてとてもありがたいです。
演劇だけでなく、地域の文化に興味がある人にはぜひ見てほしいです。
8・その他、地方の演劇文化として抱えている問題と思うことがあれば教えてください。46 件の回答
●人材不足
育てた役者が都市に出て行くこと。
若手がでてこない
芝居をやりたい人が都会へ出ていくため、人材確保が難しい。
何かやりたい演目があってもそれに合うだけの出演者数を確保できない。
団員が集まりにくい 練習場所の確保
演劇をやりたいと思っても、周りに誰もいない
特に地方の役者は、仕事としてやっていけるだけの仕事量がないので、本当に仕事として役者をやりたいと思う人間は、どんどんいなくなる。
少子化、人工流出による演劇人口の減少
スタッフ不足
お仕事をしながらなので、練習やリハーサルなどに全員がそろわないことがある。
地域に暮らす俳優という存在は、大きな財産であると思う。金銭的なことだけではなく、そこへの様々な支援があるべきだとも思う。
●活動環境
劇団のジャンルが少なくて、嗜好が偏りがち。基礎的な技術が低い。
少人数の劇場(ホール)が少ない
活動場所の選択肢の無さや稽古場所の無さ、それに尽きます
劇団の数が少ないため、文化として形成されていない。
稽古場が取りにくい、身分証明から登録から手間
活動の世界がどうしても狭くなりがち
やる方にも観る方にもお金がない、チケット相場の安さ
●活動する意識の違い
活動している人々の意識の違い
1)学生が多いため若い演出家、俳優、スタッフの新陳代謝が約3〜4年スパンで行われ定着しない。2)WSなど勉強する機会が少ないのはもちろんだがWSなどがあっても意欲的ではない
公演参加者の長期的な目で見たモチベーションの持っていき方(プロになりたかったり有名になりたい訳では皆さん無いので)
演劇関係で仕事になることが少ないため、プロ意識や自覚を持ちにくい。
高齢の世代が築き上げている「演劇ができればいい」という価値観のせいで、演劇の質向上を目指さない風潮が演劇界に感じられる。若手と呼ばれる人たちはその風潮に抗うように演劇活動しているものが多いものの、コンテスト形式の場になれば評価するのは高齢の層であり、趣味趣向だけで若手が評価される現場が痛々しく思えてくる。
ギャランティをもらう文化があまりないので、ギャランティをもらう人との間に意識の差がある気がする(どちらが良い/悪いではなく)
フリーの役者が増えている反面、劇団数は最盛期より減少している。団体や興行に責任を持たず、楽にやりたいという意見も聞いたことがある。
●周辺環境関係
アーツカウンシル的な仕事が出来る人が必要。自分たちがやりたいことができて満足ならそういう劇団はありだが、演劇文化をどうしていくか?という点については重要だと考えます。
公演する劇場施設が少ない。
交通網が不便
地方 < 都心 と思われる節がある
競合団体が少なく、表現を切磋琢磨しあえる環境でない。
とても閉鎖されたコミュニティーなので外との関わりが希薄
自治体間で温度差が激しい。文化芸術行政は担当者の好みや得手不得手で左右されることも多い。
『商業目的と勝手に見做されて活動場所を制限される』アマチュア団体なのですが、活動資金としてのチケット料金を取るだけで、それは商業活動と見なすという勝手なローカルルールがまかり通っているので、半分公共施設のコミュニティセンターの貸し館を断られたり、有料の使用を特別に求められたり、ポスターを貼らないなどの対応を慣例的にされる。いっそ全員有料にすればいいのに。条例には無い基準で活動を制限されるので、小さな団体にとって練習場所の確保だけで対人ストレスがすごい。
生計を立てられるような仕事がない。
他の業界との関わりが希薄
●観客
「観客」層を育てること。
同じ地域の中で長く活動していると、集客が一定化してしまったり、評価も含めて枯渇してきがちである。(これに関しては、地元劇団の市民団体を作り、合同で事業を行った事で、現在は交流や情報交換の効果が出てはいます)あとは、若い学生演劇人たちが卒業と共に就職で地域外へ出て行ってしまう事でしょうか。
地方意識高いわりに、大都市と比べがち
地方内で演劇が周知されていない
地方の方が活動する側にはやりやすいと思うが、観客側には見られる劇団数が少なくて選択肢がせまいと思う
プロと言われる以外の人の表現への理解
演劇と出会っていない人が多すぎる
新しい客層を呼び込めない。観客の固定化。
人口の少なさや宣伝媒体の弱さなども相まって、お客様がどの劇団・ユニットでもほとんど固定化されてきている。結果的に評価や動員に偏りが生まれている。
●その他
特に無し。無い畑を耕すのが面白い
名古屋は恵まれた大きな都市なので、問題があっても地方としてというよりは各劇団、個々人の問題かなと感じています。
色々な答えがあるのですが、やはり都市構造が大都市圏と圧倒的に違うのが、若年層の人口流出だと思います。進学によって大幅に若年層が流出する。しかし、就職などが都会より少なく、受け入れも少ない。出ていくだけで入ってくるようになっていない。こういう都市構造は、日本社会の問題なのでどうしようもありませんが、それでも演劇はやりたいので、その中でどうするかという問題は常に考えていかなければなりません。
また、モチベーションの違いも大きな問題としてあるようです。プロ志向の人達と、趣味志向の人達では大きな違いがあり、どちらがいい悪いではないのですが、選択肢がすくない地方では、一緒の団体で活動をすることになり、団体自体が混乱して衰退していってしまうという、本末転倒なことになりかねません。これをまとめあげられる人がいればいいのですが、そんなことができる人はなかなかいません。そもそも大都市圏の劇団でもありがちなことですが、地方で長期的な継続をする劇団があまり生まれてこない一番の原因かもしれません。そこで文化行政なり地域の演劇統括団体などがあれば、そこをフォローできるのでしょうが、それすらなければ、本当に辛いと思います。しかし、今やネット時代ですので、さがせば自分たちと気の合う他地域の劇団が見つかると思いますので、そういう交流が増やせる方法があればなと(すでにあるかもですが)思います。
周辺環境においては、個人的な意見ですが、行政側に文化行政ができる人がいれば話が早いのですが、そうはうまくいかず、役所の人に高望みばかりして不満を言っててもしょうがないかなと思います。(選挙は行くべきです!)自分ももう20年以上やっていて、環境を良くできなかった原因の一つなんだなと悲しい気持ちですが、まず文化行政と対話ができる環境を作る必要があると思います。文化行政の方も、支援がしたくないのではなく、むしろしたいと思っていると思います。ただ、向こうもやり方がわからない。その為には窓口が必要で、一つの劇団では、なかなかそれが難しいと思います。まずは、地域の劇団がまとまって、統括団体を作り、文化行政と対話ができる窓口を作るのがスタートラインかなと思います。
そして、一番深刻な問題は、大都市圏の演劇と比べてしまい、地域の文化を卑下してしまう状況だと思います。どうしてもメディアの力が強く、資金力もある大都市圏の演劇と見比べて見劣りしてしまうかもしれませんが、それは全くの別物だと自分は考えています。そもそも、そういうジャンルの演劇がやりたいなら、地域で演劇をやる理由は薄くなると思います。プロ野球と高校野球で、試合を見てどちらも感動できるのと同じように、本来、演劇には技術や資金は関係ないはず。そして草野球をやっている人達だって、楽しんでいるように演劇だって、やっても楽しいし、それが劣っているとは到底思えません。むしろ演劇は劇空間という、どうしようもない場所に囚われた芸術活動だからこそ、場所の強さがあると思います。それはそこで演劇を行う大きな魅力につながると思います。
劇団と地域とのかかわり方についての個人的見解
一個前でいろいろ書きすぎて、あまりいう事もないのですが、地域との関りについて、かなり個人的見解が強く出てしまって反省です。すいません。ひとつだけいえば、地域社会と関わるのが正義みたいなとられ方はしてほしくないなと思います。演劇を純粋に楽しめばそれで充分で、地域のためだとか、観客のためだとか、文化のためだとか、クオリティーが大事とか、そんなのはどうでもいいと思います。演劇は楽しい!これが一番重要で、他はどうでもいいとも思います。
つづきます。
その10はコチラ
劇作家 松永恭昭謀(まつながひさあきぼう)
1982年生 和歌山市在住 劇団和可 代表
劇作家・演出家
劇団公式HP https://his19732002.wixsite.com/gekidankita
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
