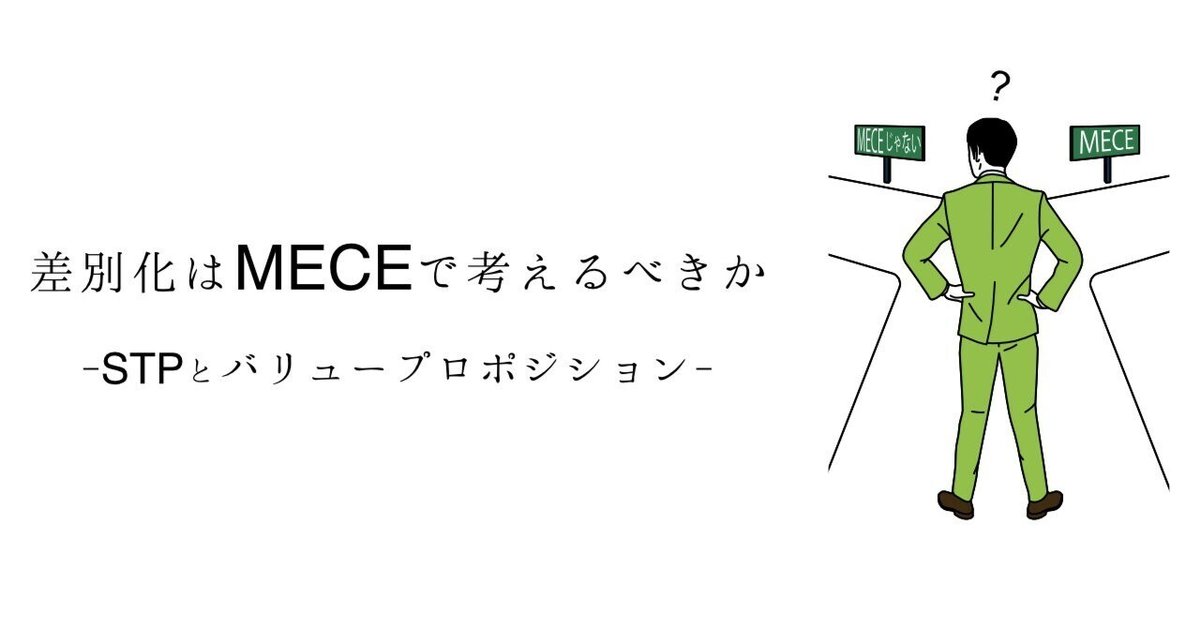
差別化はMECEで考えるべきか-STPとバリュープロポジション-
ウェブ解析士のnoteをご覧いただきありがとうございます。
早くも第4回目の投稿となります。そろそろ、ちゃんとマーケティングらしいことを書いていこうと思います。
今回は、差別化戦略の手法を検討してみたいと思います。
基本の”き”『STP』
マーケティング従事者なら必ず触れるのがSTPですね。
Segmentation → Targeting → Positioningという分析を行うことで、自社商品の独自イメージ(≒差別化)を顧客に知覚してもらうためのフレームワークです。
この時3つのステップの中で最も重要になるのは、Targetingの精度やPositioningの妥当性に影響する”Segmentation”です。
ウェブ解析士の公式テキストではSTP分析を行う際は6つのRを活用するとよいと記載されています。
6R
・十分な規模(Realistic Scale)
・成長性(Rate of Growth)
・競合状況(Rival)
・優先順位(Rank)
・到達可能性(Reach)
・測定可能性(Response)
Segmentationに絞って言えば、これら6Rに加え”差別化可能性”が重要になります。
差別化可能性とは、セグメント分けされた市場はそれぞれ別のニーズによって成り立たなければいけないという基準です。同じセグメント内に異なるニーズが混在したり、異なるセグメント間で同じニーズが混在したりしないようにセグメント分けをしましょうという考え方ですね。
お気づきですか?
差別化可能性=ニーズを起点にMECEで考えるべきということなのです。
MECEって?
MECE(ミーシー)とはMutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略語で、日本語にすると「漏れなく、ダブりなく」です。
「分析」は「わけて、さく」という字の成り立ちをしていますね。
「分ければ分かる」なんて言われるように、複雑な事象をシンプルに切り分けることで分かりやすくすることがビジネスでは求められます。
切り分けた際に、漏れがあると重要な課題の見落としにつながったり、ダブりがあると同じことを繰り返すことになったりと非効率です。
そのため、MECEであることは分析する上で非常に重要だと言われています。
MECEで考えられたセグメント例
STPを用いたマーケティングの成功事例と言えば、有名マーケターの森岡毅さんが手がけたUSJのV字回復劇でしょう。
その事例を覗いてみましょう。
下表はUSJ立て直しのために行われたセグメンテーションの考察です。

出典:(公社)日本マーケティング協会『ベーシック・マーケティング』同文舘出版 66p
開業当初はセグメントA,Eにしかリーチできておらず、開業初年度をピークに来場者数は伸び悩んでいました。
このセグメントをもとに、ステップに応じて【非映画ファン(B,F)の取り込み】【子供連れ(C,D)の取り込み】【非関西圏居住者(G~L )の取り込み】とターゲット層を拡大していったそうです。結果はみなさんご存知の通りですね。
Segmentation実行時の「差別化可能性」とは、競合と比較したときに差別化できるかではなく、ニーズの差別化(ターゲットセグメントのニーズと他のセグメントのニーズと差別化)ができているかが重要となります。
そのニーズの中からTargetとするセグメントを抽出し、Positioningを経て競合との差別化を図っていきます。
ダブりから考える差別化……?
さて、これまではMECEって大事だよね。っていう話をしてきましたが、差別化を考える方向性として、「ダブりから考える」というものもあります。
MECEの「漏れなく、ダブりなく」という方向性とは真逆の考え方のように聞こえますね。
それがバリュープロポジションというフレームワークです!
バリュープロポジションは事業分析に用いられる3C分析の延長線上にあります。
3C分析とバリュープロポジション
3C分析は「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Corporation)」という3つの要素に注目し、事業領域を分析するフレームワークです。
通常、3C分析では「顧客」を分析する際、デモグラフィックデータとサイコグラフィックデータを掛け合わせてターゲット顧客の特徴を抽出します。一方、バリュープロポジションは分析対象を「ニーズ」に絞って抽出していきます。ニーズを起点にするという考え方は、Segmentationの留意点と共通しますね。
「競合」や「自社」を分析する際、3C分析では強み・弱み・リソースなどを検討していきますが、バリュープロポジションでは「提供できる(している)価値」に分析対象を絞ります。
バリュープロポジションは下図のようにベン図で示されます。

顧客のニーズと自社が提供できる価値が重なるところ=ニーズがあっても他社では充足できないニーズがあれば、強力な差別化ポイントになりますね。
STPとバリュープロポジション
さて、差別化を考える際はMECEがいいのか。というタイトルの問いについて考えます。
これまでの記述をお読みいただいた方なら察しがつくと思いますが、ケースバイケースですよね。っていう無難な着地点になります。
ただ、STPを実行するにあたっては、少なくともSegmentationはMECEで考えるべきです。
「漏れなく、ダブりなく」抽出された市場セグメントのうち、どのセグメントを狙い、どんなポジションに勝ち筋があるのかを検討する際にはバリュープロポジションのようなダブり要素を検討するのが有効かもしれません。
あとがき
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
なんだか、テーマが変わると文体も変わっているようで統一感なくてごめんなさい(汗
「マーケティング分析はMECEだ!」という声が最近大きいような気がして、「いやいやダブらせる手法もあるよ」という天邪鬼な私が動き出した結果、こんなテーマで書いてみることにしました。
発想を広げるような段階では「こうでなければならない!」みたいに凝り固まることなく、いろいろな手法を試していくと、思わぬところに成功への道筋が見えてくるかもしれません。
なかなか難しいことではありますが、可能性を広げるためにも視野は広く持っていたいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
