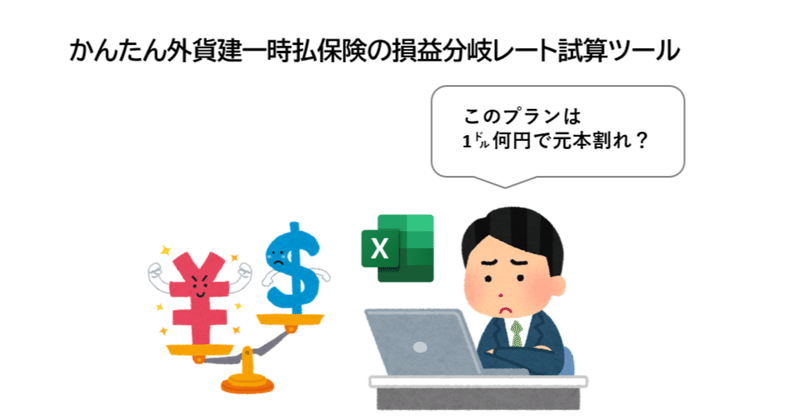
【FPA】保険試算ツール2「損益分岐レート」~外貨建一時払用🤝
※本記事の予測は為替や金利・株価などの将来の予測を保証するものではありません。一つの経済やニュースなどの見方として捉えてください。
投資・金融商品はあくまでも自己責任です。
ツールの公開が延び延びになっていましたが、やっと解説付きで公開になりました。一時払保険の試算ツール第二弾です。
前置き
為替が円安になると既に投資をしていた外貨建資産の価値が高くなる。
日銀黒田総裁が長期金利の変動幅を拡大するサプライズ的な発表をしたことで再び「日米金利差」に注目が集まっていますが、短期の為替の変動は誰にも予測が出来ません。
日米の金融政策が変更にならなければ、かつ為替介入や有事などが新たに起こらないという前提で考えると日銀の2023年最初の金融会合は1月17-18日。アメリカは1月31日-2月1日です。
この間の想定レートは個人的には127-140円ほどで一時期の150円台からはずいぶん落ち着いてきましたが、これは一過性の状況にすぎないでしょう。
何故ならFRBは利上げ幅を縮小しただけでまだ利上げを続けており、インフレの鎮静化もまだ短期金利と比べて高い所にあるためです。
本当に懸念があるとすれば日銀副総裁が3月に、総裁は4月に交代した後での金融政策がどうなるのかです。
これ次第で政策金利が見直されると住宅ローンを変動金利で借りている多くの人たちに影響が出ますし、日本の経済が本当に終わってしまう冷や水になってしまいかねません。
金融のセオリーは「借入は固定、運用は変動」。
そして債券は金利が高い時に買うのが必勝パターンです。
利下げを2023年どこかのタイミングですると明言している以上、こんなに余剰資金を手堅く運用できる市況もありません。
日銀のサプライズによって130円前後まで円高に振り戻った今は好機ではないでしょうか。
投資初心者の誤解
かつて戦後復興期、高度経済成長期には日米の経済格差が解消されていくために変動相場制に移行した1971年以降のドル円相場は円高基調が長く続いてきました。
しかしそれは今や昔の話。
2012年以降、長期的な視点で考えた場合に日本とアメリカの経済的な格差が将来に向かっている方向性は多くの人が考えている通りです。

何故なら2006年以降は総人口が減少に転じ、2012年以降は団塊世代の年金受給開始年齢到達によって日本経済の労働人口が減少に突入。
2025年にこの団塊世代は75歳以上の後期高齢者となり、日本の社会保障がこれまで以上に大きな社会的な負担となっていくためです。

また2035年には彼らの子ども世代である団塊ジュニア世代が65歳以上の年金受給開始年齢に到達。労働市場から退職する人が増えることで更に労働人口が減少していきます。
「日米金利差」は確かに為替の変動要因の一つではありますが、長期的には経済の基礎的条件が好転しない限り円の価値が高くなることを織り込むのはなかなか現実的ではないのではないでしょうか。

世間は2024年からの総合NISAの拡充に沸き立っていますが、投資をするのは今や当たり前の時代。
積立投資で本当に良いのか、安全なのか。
(ちなみに私は全くそう思っていない。特に米国株やACWIなどに積立投資をする場合は金持ちにはなれないと思っている。その理由は下記、有料セミナーで解説しています。)
どの制度を利用するのが良いのかに目が行きがちですが、多くの初心者投資家にとってもっと気になっている点は将来の自分の資産が取り崩そうとした時に毀損していないかどうか。
つまり将来、引き出す時に元本割れをしないかどうかです。

金融庁の資料によると株式投資は超長期で20年以上続ける事が、浮き沈みのある株式市場でも元本割れしないための重要な要素であると語っています。

金融庁のこうした説明もいい加減突っ込みどころ満載なのですが、そうした中で日米の経済の状況と将来を考えた時に、積極的に資産を増やしたい人は株式で長期運用が前提となってきますが、堅実に資産を増やしたい人に株式投資は向かないと常々思っています。
特に資金の換金性(流動性)に関しては投資初心者ほど甘く見積もりがちです。仮に想定と異なってしまったとして、途中売却をすることになってもその時に損をするような状態ではいけません。
つまり途中売却時におけるリスク、損益分岐の状況の理解もしておくことが重要です。
日本人の多くに向いているのは実は債券、それも劣後債や高利回りを謳いながら格付けはゴミ同然と呼ばれるジャンク債などではなく、保険会社が利率を満期まで保証してくれる「外貨建一時払保険」かもしれません。
資産規模の巨大な保険会社が高い利率を保証してくれるのですから、1つの民間の会社の社債よりもはるかに安心です。
ある程度の投資経験がある方であれば兎も角、投資は自己責任の本当の意味さえ理解していない素人の投資家に1社にリスクを背負わせる社債を買わせるIFAは色々な意味で本当に危険だと思う。特に債券投資の手数料を考えるとどの口で保険の募集手数料を否定しているのかと思う。
彼らは顧客が投資した債券の償還が延期される特約付きとか劣後債とか、実際に起きた時にどう責任を取るつもりなのだろうか。
この辺りは顧客の投資性向、つまり投資目的によって変わってきます。
私は安全性重視な運用を好む人には2010年以降一貫して外貨建保険を提案してきました。
(資産を積極的に増やしたい人には変額保険や投資信託での運用を勧めてきたが、その比率もほぼ半分ずつ)

2023年も、その先も恐らくそれは変わらないでしょう。
何故なら、損益分岐点と債券の仕組みを考えるとディフェンシブな運用は今後益々重要になってきます。

特に10年超の利回りを保証してくれる場合、私の20年超の投資経験を踏まえてもこんなに利率の高い時代が今後果たして来るのだろうかも分からない。
短期的には再び円高に振れることがあっても、長期的には円安トレンドが是正されるとは現在のところ考えづらいと考える人が少なくないからです。

ということで、顧客にその目安と考え方を伝える前に、FP・保険募集人がその損益分岐レートを試算するためのツールを作成しました。
※顧客に印刷して提示する場合には保険会社・代理店のルールに基づいて自己責任でご利用ください。
本ファイル・資料はFP・IFA・保険募集人が使用するための参考ツールであり、顧客に提示をするための販売資料を原則として想定していません。
使い方解説動画
利用ルール
メンバーシップ登録者以外に共有、二次利用されているのが発覚した場合にはメンバーシップの解除、データ・ファイルの提供の停止をします。
当ファイルで作成するのは価格・金利データの過去の推移であり、参考データです。将来の価格・金利を保証するものではありません。
ファイル共有URL
GoogleDriveでファイルを共有します。(Gmailアカウント推奨)
(メンバーシップ参加者以外に共有URLを共有しないでください。)
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
