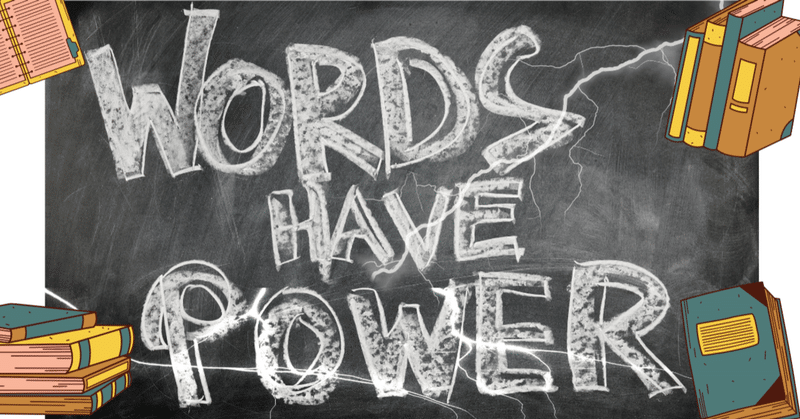
【多義語研究】多義語の研究はどのように進んできたのか?(認知言語学のはなし)
<はじめに>
この記事は、もともと多義語について学んでいる学部生にプリントとして配布することを予定していたものを、このアカウントの記事用としまして、再編集したものになっています。同じ研究室の学部生を対象にしておりますので、やや専門用語が入っています。ですが、そこは追って解説しています。
①多義語を知っている≠多義語の『意味』を知っている
多義語という言葉は、文字通りに解釈すれば「複数の意味がある言葉」ということですね。多義性というのは、これも文字通りに解釈すれば「たくさんの意味を持つという性質のある言葉」になります。ここでは、多義語の性質という意味で「多義性」という言葉を使います。
多義性というのは「たくさんの意味があるという性質」ということ。ですので、「たくさんの意味を覚えること」が多義性を持った単語を覚えることになるのでしょうか。意味を覚えれば、その単語を知っているということになるのでしょうか。
いや、それは違うと思います。つまり、世の中の単語はーそれが日本語であれ英語であれー意味を知っていればその単語を「知っている」ということにはならないと思います。
②文法の知識とかさまざまなものを「知っている」
例えば、英語の動詞を例に取ります。主語が「彼」とか、そういう三人称単数で、かつ、現在時制として使われている時は、動詞の活用が変わる。それは「動詞の活用」という『文法的側面』を知っているからです。また、同志を会話によって使い分けられるのは「使い方」という「誤用的側面」を知っているからです。このように、1つの言葉を知っていると言っても、意味だけを知っているからといって、知っていることにはならないのです。
それに、僕のような非ネイティブでも、多義語を瞬時に使います。会話では条件反射でそのような単語が出てきます。それはその単語の「日本語訳」から産出しているのでしょうか。それも違うでしょう。
ということは、意味を使い分けなくても、使っているということは「日本語訳」以外の知識があって、それを英語という形で産出している。そう考えた方が得策です。
では、その辞書に書かれていないであろう「日本語訳以外の知識」とはなんのことを言うのでしょう。ということになりますよね。それが研究者を惑わせてきた問題です。特に、僕や指導教員の先生(大堀壽夫先生)が研究している認知言語学は、確かにまだできて半世紀も経っていないのですが、その問題に真剣に取り組んできました。
③認知言語学における多義語の研究の流れ
認知言語学ができた最初は、研究にする道具立てもなかったので、まず「多義性」という概念があるということを普及させるところから始まります。
そして、言語学的に多義性という理論を包括する動きが起こった。次に、教育的示唆を含む研究が行われるにつれて、意味のカウントについて考える研究が出てきました。そうすると、教育的妥当性と言語学的妥当性を考えられるような、その両面を包括できるような理論を考察しましょう、ということになります。それが今です。
③「多義語」の言語学的な定義って?
多義語は言語学的には「単一の言語形式に複数のニュアンス的に関連した意味のある言葉」という定義があります。単一の言語形式?複数?辞書の意味のカウントの仕方さえも各々の辞書で異なるのに?関連したニュアンスの定義は?という感じで、この言語学的定義を教育に応用しようとすると、さまざまな問題が出てきてしまうのが事実です。
僕は卒論で『多義語の言語学的定義は無意味である』という結論を出しました。多義語かそうではないかの線引きをするのは良いけれど、多義語の言語学的定義に従う必要はなく、あくまでも個々の学習者が線引きすれば良いという結論です。これは多くの言語学者にとって残念なことですが言語というのは「実際の使用の中で」使われます。その言葉単体で使われるわけではないのです。
しかし。辞書や言語学的定義には「意味論」、すなわちその単語単体で考察されます。そこのところお負のパラドックスをなんとかしていきたいということです。それこそが、日本人が英語に対して持っている「多義」の知識を解明することにつながるのではないか。それを他の短義ごとは何が異なっているのか。ではその知見を教育へ応用するなら?それについて一定の結論を出すのが博士論文の研究になります。
幸い、僕はそこについて、修士論文であくまでも一部分に関しては結論を出しました。言語は実際の使用の中で教えた方が教育効果があるということでそれが修士論文です。つまり、人間の言語使用の原理に則って教えた方が、その言葉単体で教えるよりも(今、流行りの「確信を築けば一瞬で解決」という言葉にはじまっているような)一定期間で単語の定着率が上がったということです。
④目指すべき博士課程での研究
この修士論文で行った研究を拡大させていくこと。辞書の話をすると、辞書の大半の言葉の定義は「多義語」に分類されます。そうではない、実際の母語話者と非母語話者でどんな多義語とそうではない言葉の境界線について線引きが行われているのか確かめること。これが博論になりそうですねえ。
つまり、単語を覚える原理に、多義のメカニズムを当てはめるということになります。まあ、そんな感じで支離滅裂に書きました。上のことについてですが、夏休みに文献の整理をしてみる必要があるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
