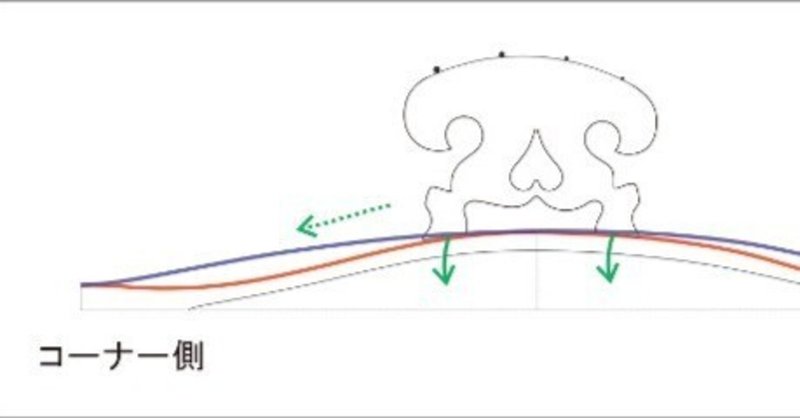
風Vn2024:表板土台の理想的なふくらみ方とは
今回は、下リンク記事の続きのお話で、
表板の理想的なふくらみ、について書いていきます。
まず、下図を見て欲しいのですが、
ヴァイオリンの表板が、弦の張力を支える場所は、
基本的には、①魂柱(裏板)と②表板土台
この2つだけです。

「ほんまでっか?」 と思うかもしれませんが、
①も裏板に乗っかっているだけなので、
実質は②の表板土台だけです。
いや、そう作るのです。
こう作ることで、他は弦の張力を支えないことで、
表板は上にふくらんだ形をしているのもかかわらず、
裏板の作る優しい音を出せるようになります。
例えるなら、表板は仮面のようなもの。
赤ずきんちゃんにオオカミの仮面をかけても
やっぱり本質は、赤ずきんちゃんですよね。
あれ、なんか、話が違ってる?
例えば、弦楽器の展示会に行って、
目の前のヴァイオリンがどのように作られているかは、
②表板土台のふくらみ方(以降アーチと呼びます)を
観察することでかなり判別できます。
まあ、手っ取り早くは、横から見て
コーナーの押し下がり具合を見てもよいですけどね。
1年以内の新作楽器の場合は、コーナーが押し下がる特徴が
まだ出ていないものもあるのです。
このため、アーチを見ることで、将来性の判断に使えます。
ここからは、この表板土台のアーチについて
実際に考えてみましょう。
下図のように、駒が直接、表板土台の上にのっているイメージで、
アーチの中腹を押し下げて、コーナー方向を押し出すのです。
さて、Aの赤線とBの青線のアーチの形を比較して、
どちらがコーナー側をうまく外に押し出せそうですか?

アーチを重ねて比較すると、下図のようになります。
はっきりと違いがわかります。

そして、答えは、、、
コーナー方向にくぼませないという意味で、
Bだと私は思っています。
このアーチは、「風Vn2022」の図面上のアーチをのせています。
実際には下図のような風景になります。

Aのアーチ(赤線)のように、
コーナー手前でアーチがくぼんでいると、
表板を強く下方向に押せてしまいます①。
結果として、コーナーのふちは、
上方向に持ち上がってしまいやすい②
と考えられます。
コーナーを外に押し出すためには、
力を横方向に多く伝えていく必要があるのです。

ここからは、製作道具や都合などが少し出てきます。
普通の人には単語がピンとこないかもしれません。
残念なことですが、一般的には、
Aのアーチの作品の方が多く感じます。
しかし、そうなる理由もあるのです。
まず、Aのアーチの方が、見た目に「かっこいい」こと。
これが、性能と相反する一番の問題なのかもしれない。
装飾とかも考えると、
「ヴァイオリンの表板は、キャンバスだ」という人は、
別に無理をしてBのアーチにする必要はありません。
そして、もう一つは 製作過程において、
パフリングを表板アーチ作成の初期の段階で入れる場合、
アウトラインのふちから10mmぐらい5mm厚で平面な部分を作りますよね。
その後、パフリングを入れ、表板アーチの内側を正確に作り、
仕上げに、パフリング近辺を少し掘り込むと
大抵の場合、Aのアーチが出来上がってしまいます。
問題の根底には、パフリングカッターの2枚の刃で、
一度に2本の切れ込みを入れたいという、気持ちがあります。
今後、アーチ重視で製作するのであれば、
パフリングの切れ込みは、1本ずつ作業することをお勧めします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
