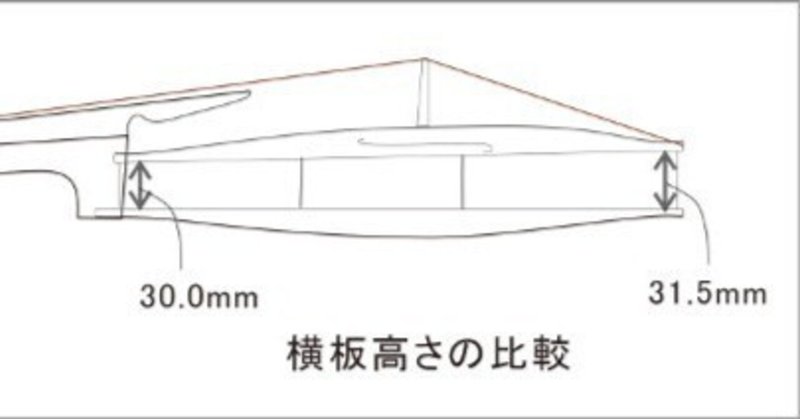
風Vn2024:表板-裏板間インターフェース(横板の高さ)
今回の記事では、表板コーナーが押し出される力①を
スムーズにUpper方向②に伝えるための工夫を紹介します。

上図、①→②の力でやりたいことは、下図は極端に表現していますが
横板をほんの少しづつ、外に傾かせたいのです。
これにより、裏板「ねじれの入口」に表板ふちの力を
加えることができるようになります。
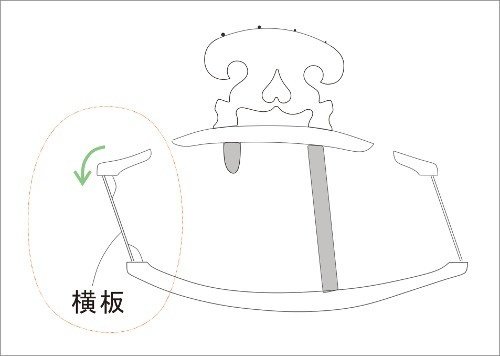
イメージを伝えるために、できるだけ簡単に説明します。
下図Aのように、コーナーからUpper方向の横板が、同じ高さだった場合、
①②は下方向に押し曲げますが、距離が離れて曲がりが少なくなると③、
①②の押し曲げを引き戻す力になります。

これじゃ、あかんのです。
Bのように①②③全てにおいて、
裏板「ねじれの入口」を上から押し下げて欲しいのです。
このためには、③は①②よりも低い場所にする必要があります。
実はこれは、ヴァイオリン製作の教本にものっているのですが、
なんでこうするのか、は書かれていなかったように覚えています。
習慣的に横板の高さは、ネック方向に低く作ります。
一般的なヴァイオリンの場合だと、横板の高さは
エンドピン位置が31.5mm、ネック付近は30mmで、
1.5mmの差がついています。

何をしようとしていたか、を知ることで、
製作者の人が、なんで横板に傾斜をつけるのか、
その意味が少しでも見えたなら、
私が頑張って書いた苦労が報われます。
ただ、これまではやっている理由がはっきりしなかったので、
積極的に会話にしたい内容ではなかったのですが、
理由がわかったからといって
どのぐらい横板の高さに差をつければいいかは、
楽器のスペックによっても違ってくるので
やっぱり、会話に出てくることは少なそうです。
演奏者の人には、伝わりにくい話ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
