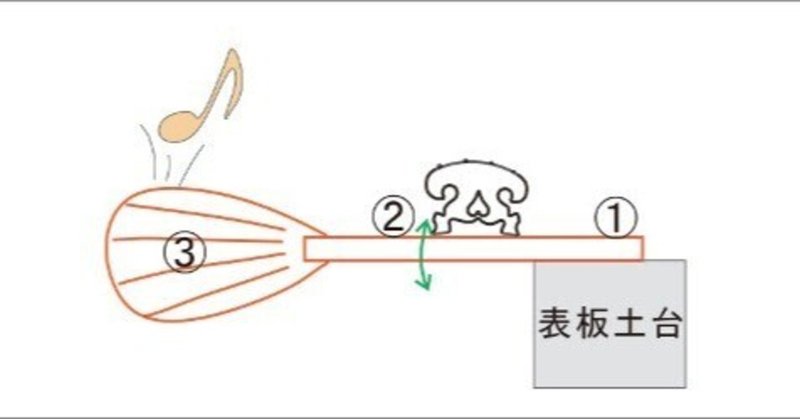
風Vn2024:聴き手とのインターフェース
前回記事のVnを人に見立てた会話形式が、
表現しやすかったので採用することにしました。
一応簡単に登場者紹介、
(1) 細2012:ストラディバリモデルとして製作、一般的なVnに近いです。
(2) 風2022:「風時代Vn」の初号機。既に欠点はいくつか、、、。
(3) 風New:風Vn2022の欠点を対策しつつ、今年生まれるはずの新作です。
(4) 私(設計):水瓶座、55才、独身の男やけど、ここではVnの生みの親。
こんな登場者で行きます。
さて、今回は、ヴァイオリンの音を作る全体像から、
聴き手に届ける音の作り方を説明してみます。
表板、裏板のしなりをそのままでは表現しにくいので、
バネの強さと長さに置き換えてみました。
各バネには、飛び込み台がついていて、駒がのっています。
バネの長さ(高さ) = 板の振動
バネの線の太さ = バネの強さ
駒の大きさ = 弦の張力
飛び込み台の長さ = 回転力
回転力は難しく考えずに、バネから遠いほど、
少ない力でバネを縮められると考えてください。

風New:「うまいこと表現したやん。」
私: 「ふっふーん。まあね。
この仕組みで音を飛ばす時、何が大切か解るかな?」
風New:「連携?」
私: 「おっ、正解や。バネは1つが頑張っても意味がないねん。
全てのバネがタイミングよく動いて、初めて機能するんや」
細2012:「その前に、あんた、私を作った時は
①だけしか考えて無かったでしょ。」
風2022:「私にも①、②までしか入ってへんよね。」
私: 「そう言われても、③、④に気付いたんは、最近やねんで」
風New:「ちゃんと入れてや、でも③、④は、まだみんな知らんやろ。」
私: 「そや、はよ説明せんと。」
ということで、③、④を説明したいのですが、
先に、この4つのバネ全体の時間的な感覚を知ってほしい。
たぶん、みんなの想像力の圏外やから。
下図は、「細2012」でD線を弓で弾いた時の振動波形です。
D線開放を294Hzとして、おおよそ1つの周期が1000分の3秒で、
その中で、1つの上下(基音)を作っているのは10000分の3秒。

つまり、バネ全体が、押し下がり、伸び上がって、元に戻るまでを
なんと、10000分の3秒で完結しないといけないのです。
なんか、感覚が違うでしょ。
例えば、バネ①の裏板土台(魂柱位置)は、押し下げてから、
遅くても10000分の1秒で押し戻しが必要なのです。
これまでは、「音程が作れてるから大丈夫」でよかったけど、
4つのバネの伸び縮みタイミングの連携をとるためには、
10000分の1秒という世界での仕組み作りが必要なのです。
ここからバネ③、④の話に入ります。
聴き手にとって「優しい音」をどのように作るのか、
手段として下図のような、表板の「うちわ」で作ります。
ちょっと絵が下手で、「しゃもじ」「筆」っぽいですが。

下図に、「うちわ」で音を出すイメージを抽出しました。
①「うちわ」の持ち手の端を表板土台に固定して
②駒足で持ち手を上下に揺らし、
③「うちわ」の羽先で、音を出します
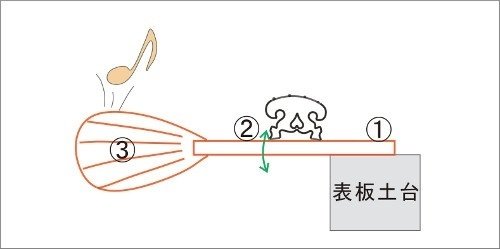
どうですか? 優しい音色が聴こえそうですか?
「うちわ」を持ち手の端①だけで支えていることがポイントで、
②の駒足の力加減で、力みの無い羽先の音③が聴けます。
バロック駒が、バスバー側の足の力を軽めにしているのは、
②の力加減を作るためなのです。
最後に、もし今回の記事を読んで、
表板「うちわ」の作る優しい音色を、
ぜひ「聴いてみたい」と思った人は、
強く願ってみてください。
その願いを聞いた誰かが「作ってもいいよ」と受けてくれれば、
実際に「作りたい」という人が現れます。
そうやって、現実が創られていきます。
聴き手に「優しい音」を届けるための仕組みは、
10000分の3秒という短い時間の中で
表板、裏板の動きをどう連携させるか、という難題です。
仕組みを理解できても、物質化できる人は少ないはずで、
もちろん、私にとってもハードルは高いのです。
多くの人が、願ってくれることを祈ります。
私的には、早く「風時代Vn」を使った
弦楽四重奏を聴いてみたいのですが、、、。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
