
風Vn2024:トラップを自分で作って、自らはまった私
今回の話は、風Vn2024:表板「視覚的なトラップ」の続きです。
表板に、音を出す仕組みを「うちわ」という名前にしたことで
強く「扇ぎたい」という欲を作り出していることに気が付きました。
理解のしやすさから「欲」が生まれた
という失敗事例です。
先に、新しく登場する単語を1つ、
下図の紫色エリア(f字孔上部分)のふくらんだ形を
「FTアーチ」(f字孔Topアーチの略)として、
以降説明を進めます。

「うちわ」を強く扇ぎたい、音を飛ばしたい。
だから、FTアーチを柔らかく、大きく動けるように作る。
一見、何も問題はなさそうだけど、
得たい結果を求めて行動すると
欲しい結果は得られず、思考の迷路に迷い込んでしまうのです。
私の失敗は、
「うちわ」の扇ぎ方を工夫して、表板で音量を大きくしよう、
と考えてしまったことにあります。
「風2024」:それのどこが問題なん?
「私」:表板はね、裏板「しなり」が生み出す振動を
そのまま、音にするだけでいいんだ。
表板のふくらんだ形で、音を大きくしようとすると、
どうしても、耳当たりにきつい音になってしまう。
「細2012」:私にも付いている、一般的な長いバスバーも、
音を大きくしたい、という欲だよね、きっと。
「私」:ヴァイオリンの19世紀の改良は、
大きなホールでの演奏のための音量欲しさが理由だから、
みんなが迷路の中に案内されたんだ。
だけど、それは「土の時代」のお導きとして、
仕方のないことだったと考えている。
「風2022」:私はバスバー短いけど、最近は音量も出てるよね。
「私」:そう、直近の駒の改良で、音が広がるようになったんだ。
バロック駒の性能を引き出すテクニックやね。

「風2024」:ほんで、私はどう作ってくれるの?
「私」:「うちわ」を扇ぐという表現をやめて、
裏板「しなり」を表板「うちわ」に伝えて音にする
という表現に変更します。
今のモダンヴァイオリンの音って、
自分が病気とかで体が弱っている時に、
耳元で演奏聴きたいと思う?
「風2024」:思わへんね、たぶん。
そうか、本物の「癒やし」の音やね。
最後に、私がヴァイオリン製作を始めた頃に、
何度もやったFTアーチのやったらあかんパターンを紹介します。
下図を参考に、表板FTアーチの作り方を想像してください。
①→②と進めて、アーチを適当につなげると
③の場所に急なカーブ、強さができてしまうのです。
タップ音を聴けばわかりますが、
急カーブができると、板厚を薄くしても柔らかくなりにくいです。
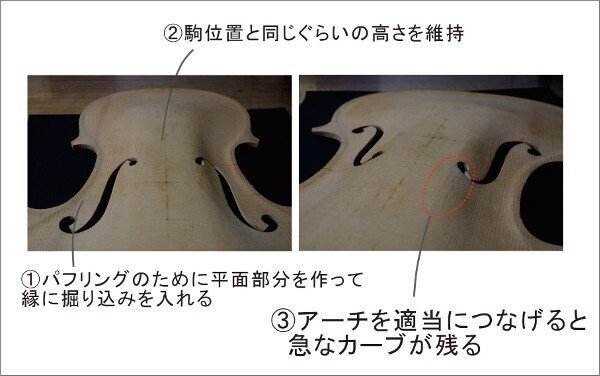
このことから、次のことがわかります。
調整でタップ音を下げたい時は、
板厚を減らすよりも、アーチのカーブを緩くすること
なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
