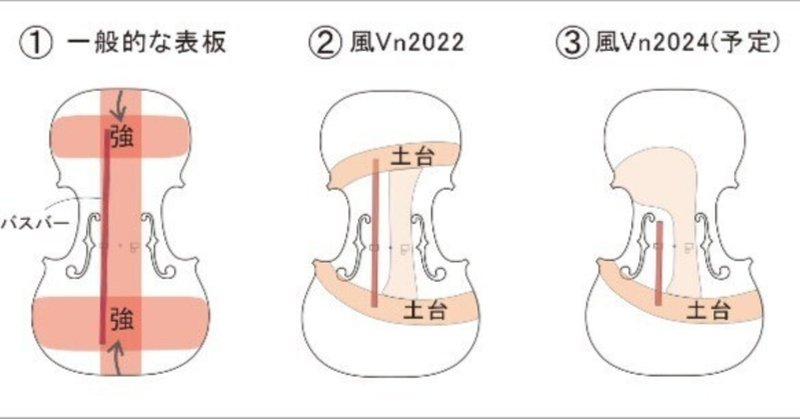
風Vn2024:ヴァイオリンの性能を決めるインターフェース
私の屋号「Violin Interface Design」にも使っている
インターフェースという言葉、
パソコン好きの人以外は、馴染は薄いと思うけど、
今後、使いたい単語なので、登場させます。
インターフェースとは、AとBの「つなぎ方」で、
AとBの間で取り決めたルールをプロトコルと、、、。
これじゃあ、あかん、伝わらん。
頑張って、もっと簡単な説明に、
では、もう一度。
ヴァイオリンの中で、Aを4本の弦として、Bを表板とする。
AとBをつなぐのは「駒」で、これがインターフェース。
AとBの間で仲介的な役割りをする物と言える。

ヴァイオリンの中には、様々なインターフェースがあって、
顎当て、肩当てのように、AがヴァイオリンでBが人間の
ようなパターンもある。
そして、今回紹介するのは、ヴァイオリン内部で
Aが表板、Bが裏板というパターンで
「魂柱」というインターフェース。
「魂柱」を使う上での取り決め事は、
「表板は駒を支えずに、裏板に動きを委ねること」

簡単に言えば、「表板さん、勝手な動きしないでね」と。
しかし、これって、言うほど簡単じゃなくて、
表板はf字孔があって、「魂柱」がある場所は
柔らかそうに見えるかもしれないが、
下図の①一般的な表板には、縦横の赤ラインのように、
立派に上にふくらんだ形(アーチ)が在り、
さらに、長いバスバーで強さを橋渡ししている。

あまり他人事ではないのが図②の「風Vn2022」で、
このころの考え方では、表板土台は上下に2つあり、
バスバーはその間にかけていた。
①よりは、柔らかくなったが、まだ強い。
そして、図③の「風Vn2024」の表板は、
土台を1つにして、バスバーを短くすることも含めて、
こんな感じに作ろうとしています。
実は、一般的なヴァイオリンが、
なんで強度を上げたい気持ちになるのか、
理由があるのです。
気付いてほしいのは、
スチールのE線をVnに取り付けて、調弦する時、
とても強い力でペグを回す必要がある上に、
弦が切れないか、楽器が壊れないか、
「怖さ」を感じませんか?
この「怖さ」は、体が覚えているのですよね。
だから、スチール弦を張ったヴァイオリンは、
製作者も、「表板を弱く、柔らかく作ろう」なんていう
発想をしないと思うのです。
私は仕方がないことなのかも、と受け止めていますが、
皮肉な話、だとも思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
