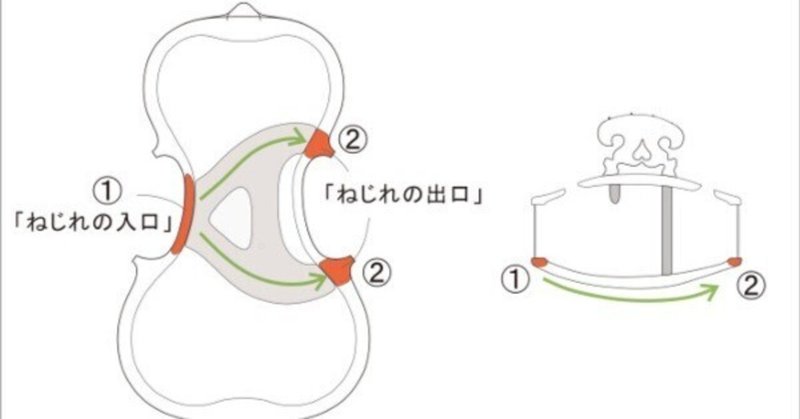
風Vn2024:表板-裏板間インターフェース(概要)
ここから、難所に入ります。
理解するのも難しいけど、説明も厄介なのです。
前回記事で、表板-裏板間のインターフェースの1つとして
「魂柱」を紹介しながら、表板の概要をお伝えしました。
今回は、裏板について、ざっくりと説明しています。
まずは、下図赤点線エリアから始めます。
これまで、表板土台を押し広げて、
コーナーを押し出すことは説明してきました。
バスバーが表板土台を駒側に押し下げるので、
C部側にねじる力が入ります(緑線)。
この力を受け取るのは、横板です。

下図のように、表板がコーナーを押し出す力は、
横板を経由して、裏板「ねじれの入口」に伝えます。
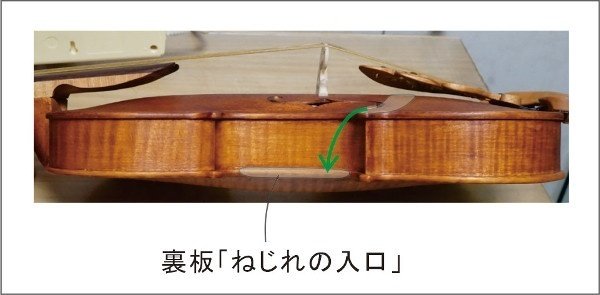
はい、新しい単語が出てきましたね。
ここで裏板「ねじれの入口」をもう少し具体的にします。
下図のように、「ねじれの入口」は、裏板フレームの一部分です。
フレームとは、横板を接着するための平坦な場所で、
ふち全体から内側に、ぐるっと約7mm~10mmぐらいになっています。

横板はこの「ねじれの入口」を真上から押します。
では、押した力は何処にいくのでしょうか。
この行き先が、下図の「ねじれの出口」②です。
裏板の「ねじれの入口」①を押し下げられた力を
裏板の反対側のコーナー「ねじれの出口」②に伝えます。

上図の、灰色の部分を、今後「裏板土台」と呼びますが、
この形、何かに似てませんか?
そう、「バロック駒」です。
私が、ヴァイオリンを研究を続けて見えてきたのは、
ヴァイオリンという楽器は、
「バロック駒」をモチーフとした変奏曲
のような景色だったのです。
仕組みの上にも、美しさを感じました。
このまま終わると、私らしくないので、
照れ隠しのようでもありますが、
裏板土台の形って、「パンツ」にも見えますよね。
具体的に「バロック駒」に重ねてみました。
正しいイメージは、下図の右側なのですが、
両方とも、透明度50%でスケスケ。
「ビキニ」か、または「ズロース」なのか、
不協和音が聴こえてきそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
