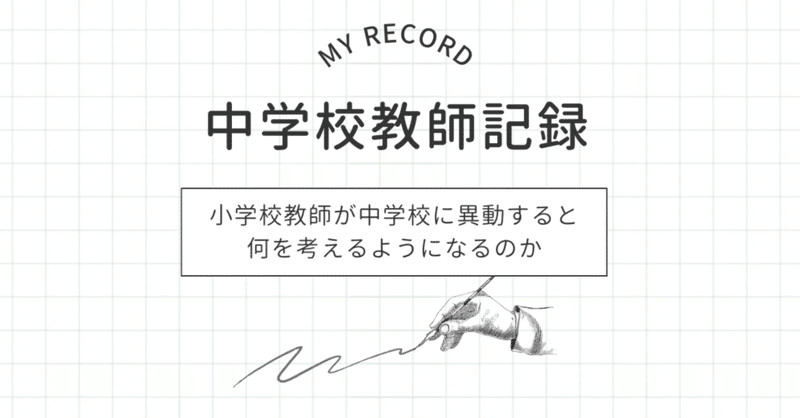
中学校教師 #35 学級が崩れている
4月から中学校で勤務しています。
いずれは小学校に戻ることを考え、この経験を記録に残そうと思います。
異動の経緯や考えは下記参照
学級経営・授業づくり 実はうまくいっていません
3週間前、教育相談員の先生からのご指摘
・「対話はあって、学びはない」と言われた授業
・授業、学級経営のフレームが大事
・リーダーを生かした学級経営ができているのか?
詳細は以下を参考に。
壊れた学級での授業
週1回程度、来校するこの教育相談員。
また、授業を参観していただくことができました。
中2数学「三角形・四角形」章の導入の授業。
前回の反省を生かし、力を入れてみる。
・情動を動かすような授業の導入。
・存在感を示すように、声をきちんと出す。(遠慮しすぎと言われ…)
・まず、規律を整えるために一斉指導の形で授業を進める。
→章の導入、知識を定着させたいので、教える部分が大きいのもある。
私の学級の隣の学級だったのですが、まぁ崩壊しかけているのです。この学級が。
・授業中の離席(一部生徒)
・ワークシートに書こうとしない。
・授業とは関係ない話を広げようとする。
→席が離れていても目を合わせて、話を広げようとする。
こんな状況でも授業は進めます。
生徒の声を拾いながら、大事な場面では手を止めて、規律を整えながら学習を進めました。課題に対するまとめもして、あと少し進めたかったなぁと思ったあたりで終了。
授業後、空きコマだった私は相談員の先生のもとへ。
そして、また価値のある話をたくさんいただきました。
話していることは素晴らしい、でもトーンが同じ
学級の状態が良くないことは承知の上で、授業の振り返りをいただきます。数学という学習内容に対する私の進め方、生徒の声、反応を振り返ると、前向きにとらえてよい要素が多くありました。
「音声を記録して、文章化したらスーパーティーチャーと一緒だよ。いいことだよ。でもね、1時間ずっと同じトーンで話しているんだ。学習の核心に迫ることも、雑談も、生徒への注意や指導も。」
この言葉に一番ハッとしました。
恥ずかしながら全然意識していなかったことです。
ずっと同じトーンで話していると、結局何が大事なのか分からない。そして、授業に集中できないような生徒は「またこの調子か。」と自らの言動を振り返ることができないと感じました。
★すぐに改善★
次の授業では、声のトーンを意識しました。
・あえて私が反応せず、生徒が声を挙げやすい空気をつくる。
→ある発問に対して「辺の長さが等しくない?ここは垂直じゃない?」と生徒がつぶやきました。そこで、すぐに反応せず、様子を見守ります。その後の反応次第で、
①班で話合い(フレームを整えた上で活動)
②全体を止めて教師が進める(反応が続かなかった場合)
・重要な部分は、言霊として伝える
→ただ、教科書の内容を伝えるのではない。学習内容を越えた学習の価値について私の思いも加えながら伝える。言葉+思い=言霊を意識しました。
・注意や指導はあえて小さな声
→その生徒の席に向かい、小さな声で端的に。
この方が全体としては落ち着き、指導された生徒はハッとしていました。メリハリをつけることができた点が良かったと思います。
思っているような中学生ではない
「中学生は小学生とは違う」
心の中で思っていたことが、態度として表れてしまっているようです。
「変に大人扱いしている」
こんな指摘をもらいました。
小学生とは違って、より多面的に、批判的に物事を考えることができるから、教師としての振る舞いや発言は気を付けなければいけないと考えていました。どこか丁寧すぎて、かしこまりすぎていたのかもしれません。
しかし、実際に目の前にいる中学生は、小学生とはそんなに大きく変わるわけではありませんでした。だから、時には強く指導し、熱く思いを語るべきなのだと感じました。小学校からの異動、「中学校の勤務を経験している」という感覚がありました。これではダメですね。今、自分がこの中学校の一員として全力で学校を良くするんだ!という思いが足りないのではないかと思いました。
学級を壊すような態度をとる生徒、結局は学習が分からないのです。しかし、分からないからといって「分からない。」と表現できず、関係ない話をしたり、ふざけた言動をとったり、寝てしまったりするのです。
つまり、こういった生徒に真正面から「ちゃんとやれ!」と言っても、それは知恵のない対応で、生徒が感じている「分からない」に対して適切な支援をしなければ根本は変わりません。おそらく、私の目の前だけ学習したフリをして、別の教師の前では態度が変わってしまいます。
小学校では、学習に困り感を抱いていた児童への支援をたくさん実践してきました。
・授業の導入の工夫
・ワークシートの工夫
・写真、動画等の視覚的支援
・班活動のメンバー構成
・問題量や質の調整
教師としての指導技術的なことだけでなく、その児童が安心して教室で学ぶことができるような空間づくりも意識して実践してきました。
だからこそ、私が中学校に異動して、ここでその経験を生かすべきなのだと考えました。(気付くのが遅い…)
授業の前半で、学習のレールに乗せてあげるような支援をすることで、まず前半だけでも学習に参加できるように授業づくりを改善してみたいと思います。そうすれば、その勢いのまま学び続けることができるかもしれないです。
正直、「早く小学校に帰りたい」とずっと思いっていました。
しかし、今週、「中学校も面白いかも」とちょっとだけ感じることができました。
それは、私の学級で班長を中心としたリーダーが主体的に周囲に働きかけている姿、そのリーダーの働きかけに反応し、ともに努力しようとする生徒の姿を見ることができたからです。
もちろん、こんなところで満足してはいけないのですが、中学校現場での学級経営の面白さを垣間見ることができたのだと思います。
リーダーシップを生かした学級経営については、後日まとめてみます。
厳しい現状の話を記事にまとめました。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
【「えがお」を大切に 焦らず、誠実に、前向きに】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
