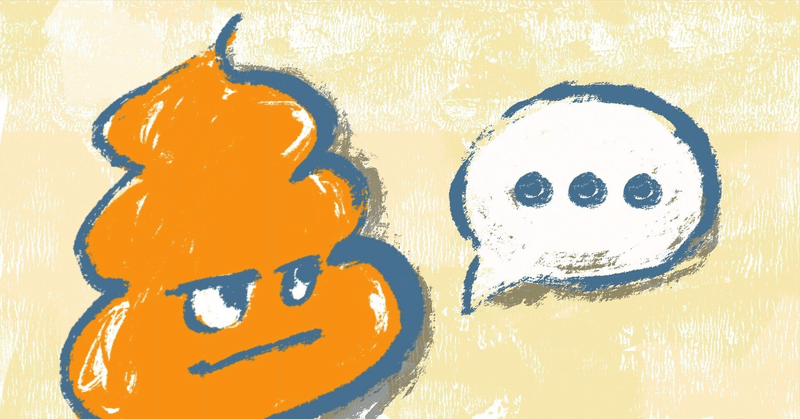
ブルシット・ジョブ「クソどうでもいい仕事の理論」
こんばんは、今日は知人のコーチが熱く紹介してくださった上記の本についての読後感想。
いや~このタイトルを聞いて
「はははーわかるわかる」「思い当たる」
という方多いのではないでしょうか。
人によっては
「え、私の仕事のことですか?」なんていう方もいるかもしれないですね。
私も漏れなくこのブルシット・ジョブを経験したことがあるな~と思いました。
この本、まじめに「クソどうでもいい仕事」がなぜ世にはびこっているのか、そして世界でも約40%近くの人がこの手の仕事はあると答えているのに、「ブルシットジョブ廃絶運動」が起きないのはなぜか、など真剣に議論が展開されています。
中世の封建主義時代にまでさかのぼっていたり・・・
タイトルはカジュアルなのに中身はしっかりとした学術書のような印象でした。
「ブルシット・ジョブ」とは
被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある雇用の形態である。
と定義されています(笑)
雇用形態までいくとやばいけど、少なからず「これやる意味まじでないだろ!」と叫びたくなる仕事って、やっぱり会社員だとつきものですよね?
もう少し具体的に言うと、
1.取り巻きの仕事
(誰かを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせるというただそれだけのため、もしくはそれを主な理由として、存在している仕事)
2.脅し屋の仕事
(脅迫的な要素を持っている仕事。軍隊が代表例。)
3.尻ぬぐいの仕事
(組織に欠陥が存在しているためにその仕事が存在しているに過ぎない雇われ人。必要もないのに散らかしをする人間の後片づけ)
4.書類穴埋め人の仕事
(実際にやっていないことをやっていると主張できることが主要ないし唯一の存在理由であるような被雇用者)
5.タスクマスターの仕事
(自分の仲介が不要で、他人への割り当てからだけなる仕事。また他者がなすべきブルシットジョブを作り出すこと)
私個人としては、「5」の話はよく聞くし自身も経験あるなぁと思います。
いかに作り出されないか、「管理対象」にならないかにめちゃくちゃ頭を回したことがあります。それでも回ってしまうと、
「なぜ?いらないよね?なぜ??????」と発狂したくなるもの。
この本にもあるのですが、どうにも現代の私たちには
「仕事をしていないと怠惰でだめなやつ」
という意識があるようで。これは別に日本に限らない話らしい。
なので「仕事をしない有閑階級への憧れ」よりも「ワーカホリックで働きまくるCEOへの憧れ」の方が強い傾向にあるという著者の指摘も確かに納得。
やっぱり、自分の役割、その先の目的や意義を全うするということが欲しいわけで、
別に「仕事(=業務、作業)」が欲しいわけではない。
んですよね。だから強烈にムカつくんですよね。
かといって超暇な仕事が最高か?というと、そこで別のことをするのも難しいという話。
わかりますよね、業務中にちがうことやっているとちょっとうしろめたさがありませんか?
それは「時間を売る」という考えが背景にあるから。だそうです。
(ここでも「モモ」の話につながって個人的にちょっとびっくり。)
そもそも「時間を売り買いできるもの」という概念ができあがったのも数世紀の間にできあがった比較的新しい概念だそうです。
私たちは経営者(会社)に時間ごと売り渡してしまってきたのか・・・
何で働いてたときに辛かったのかな~と色々説明された感じがして、少しこれまで見えなかったものの正体がちょっと見えた気分でした。
これという解決策があるわけでもなく、特にこの本は「問題提起」をしている本であり、ベーシックインカムの話はちらりと書かれていますが、少しだけという感じです。
そっか。
やっぱり人のマインドや認識の問題だけではないんだよな。
「じゃあどうしていこうか?」
歴史・構造から語られると一瞬諦めそうになるんですけど、だからだめと決まったわけではない。
こういう発想で、この先もコーチングや研修、自分のジョブに取り組んでいきたいと思いました!
働いている皆さんと一緒に考えながらやっていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
