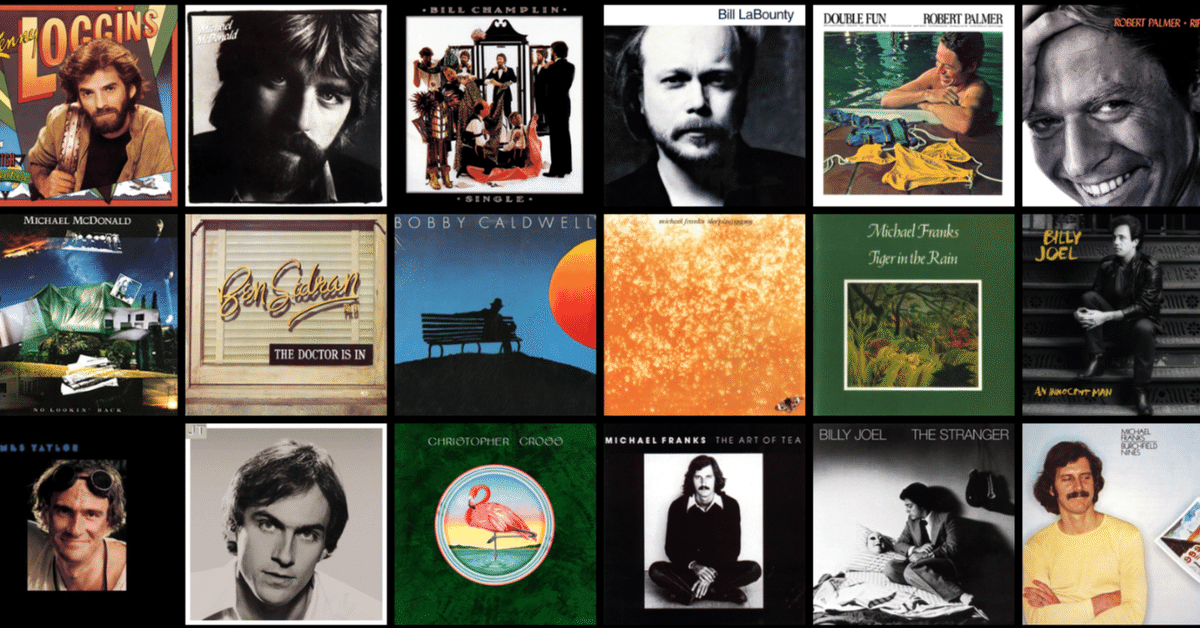
AOR玩味之記
今年の6~7月頃にAORを集中的に聴いていたので、そのときの感想をまとめた。そのあとオルタナを聴くようになって、また気候がかなり暑くしんどくなってきて、現在はあまり聴いていないのだが、暑さの盛りを過ぎた今日この頃、これらのアルバムのことを思い出し、また取り出してみてもいいかもな、という気持ちになってきたので、記事にすることにした。
これらのアルバムについて私は、一昨年のことだったか、友達の家でAORの名盤本を読んだことで知った。その頃私は、AORはおろか、80sの音楽すら明るくなく、70年代のハード・ロックにどっぷり浸っていたので、全く知らない世界があるのに驚いた。確かその本は、金澤寿和、福田直木『AORライトメロウ プレミアム 01 Legends & Pre-AOR』(シンコーミュージック、2020)だったと思う。
このとき友達の家でアルバムをメモし、ずっと自分のライブラリーにあたためていた、というわけだ。また、こうやってアルバムの感想をつらつら書き始める前に既に、スティーリー・ダンやドゥービー・ブラザーズの諸作や、ボズ・スキャッグスの『シルク・ディグリーズ』、ドナルド・フェイゲンの『ナイトフライ』などは聴いてしまっていたので、ここには出てこない。
なので他の記事と同様、ほとんど日記に過ぎないわけだが、ある程度の枚数の感想がまとめられているので、この種の音楽をこれから聴くという方も、これまでの人生で好んで聴いてきたという方も、よければ読んでいってくれると嬉しい。
AORについての覚書
さてこの記事を投稿するにあたり、AORについて簡単に書いておいた方がいいのではないかと思う。
英語版Wikipediaの“Album-oriented rock”の記事を参照にAORの成立について簡単に記述する。
AORという文字列は、アメリカにおいては「アルバム・オリエンテッド・ロック(Album-Oriented Rock)」の略語であるが、これはそもそも、60年代後半のアメリカにおいて、アルバム主体でオン・エアするFMラジオの放送形態が確立し、その形態を当時シングル曲をかけることが主流であったことに対して「アルバム・オリエンテッド・ラジオ(アルバム指向のラジオ)」と呼んだことに由来している。
この放送形態は、ロックがシングル曲のヒットではなく、アルバム全体での完成度を優先するようになった事実と深い関係を持っている。(ビートルズの『サージェント・ペパーズ』が1967年である。アーティスト側の指向とラジオ局(産業としての供給側)の形態変化、どちらが先に起こったのかはわからないが、まあこういうものは大体どちらが先というのでもなく、相互影響的に隆盛していくものだ。)
そこではヒット云々にかかわらず、DJがリコメンドするアーティストの曲やアルバムがオンエアされた。つまりリスナーにとっては、まだ知られていない新しいロックを聴くことができる場所だったわけだ。プログレッシブ・ロックなど様々なジャンルの音楽がここで紹介され、人気を博していく。
しかし人気を博したコンテンツが消費者の思う通りにならないのはいつの時代も同じことであり、70年代半ばにはディレクターが放送楽曲を管理するようになる。そこではアルバムから数曲がえらばれるようになり、従来の芸術性云々でなく、より「売れる音楽」に焦点が当てられるようになった。レコード会社としてもこのチャンネルの普及率に気づいてしまい、対する放送局も音楽産業のビジネスとしての巨大化に気づいてしまったのだろう。
そして70年代後半を通じて、かつてアルバム・オリエンテッド・ラジオで流されていたプログレやファンク、R&Bなどが「売れる音楽」、商業的なロック結びついていく。こうしてできたのがAORという音楽ジャンル、というわけだ。
一方、日本においてAORは「アダルト・オリエンテッド・ロック “Adult-oriented rock”」、すなわち「大人向けのロック」という言葉の略語として一般的に用いられている。
この「アダルト・オリエンテッド・ロック」という言葉は和製英語らしいが、要するに上記の過程で成立したAORという音楽が、60sのサイケや70sのハード・ロックのような、エネルギーを発散したりひねくれていたりする、若者的なサウンドとは違っていて、落ち着いた雰囲気をもった大人向けと思われるサウンドを持っていたから、そう呼ばれるようになったのであろう。
ちなみに本土アメリカでは、60年代頃からの落ち着いた雰囲気を持ったロックの名称として「ソフト・ロック」があり、また70年代半ば以降のその種の音楽(ソフト・ロックに比べジャズやディスコなど新たな方法論が加えられた落ち着いた雰囲気のロック)を「ヨット・ロック」と呼ぶ。ソフトはそのまま柔らかい雰囲気の、みたいなニュアンスだろうが、ヨット・ロックというのは当時そういう音楽を聴くのがヨットを所有するような裕福な若者である、という偏見に基づいた呼び名だ。だからヨット・ロックという言葉には多少批判的な意味が込められているのだが、いつの間にかそのジャンルの音楽を指すニュートラルな言葉として定着した。(「印象派」とか「シューゲイザー」なんかと同じだ。)
しかし日本においては、ソフト・ロックやヨット・ロックよりも、AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)という言葉の方が一般的ではないかと思う。それは恐らく70年代後半から80年代にかけて、アメリカと同じく日本の音楽産業も巨大化していったという背景があるのではないか。
ここからはそんなAORという言葉、そして成り立ちから連想した、私の簡単なAOR観をひとつ記したく思う。
そもそもロックとは、アメリカにおけるアフロ・アメリカンの音楽であるブルースやドゥーワップ、そしてそれらをもとにした50年代後半のロックンロールを、60年代のイギリスの若者たちがバンドを組んで、自分たちで実践しだしたことによって生まれた。だから、ロックとはすなわち若者の音楽であった。
イギリスの若者たちによって生みだされたロックは、1963~64年にアメリカに上陸、またたくまにアメリカの若者たちの心をもガシッと掴むようになる。アメリカにおいてロックという音楽は、ある意味では巷に溢れていた従来の産業音楽への反抗、カウンターとして流行したものでもあった。いつの時代も若者は反抗する生き物だ。
しかしその60年代にロックを聴いていた反抗的な若者たちも、社会に出、仕事に就き、家庭をもつことによって、大きなシステムの中に組み込まれていった。そこで彼らが求めるのは、かつて自らが熱中していた、激しく世の中に異を唱える音楽ではなく、そのような疑問符は宙吊りにして、それよりもまず日々の心労を癒してくれる、優しく豊かな音楽であっただろう。そしてそこに、かつて彼らが身を投じたロックの断片を、音響として聴きとることができるのならば尚良い。
そういった事情で誕生し、広く聴かれるようになったのがAORという音楽なのだと私は認識している。そのように考えるとAORを、よく言われているように商業主義として退けるべき音楽とは、私は別に思わない。なぜならこの音楽を聴いていた人々には、避け得ない生活(つまり、生きることの困難さ)に由来する、切実な欲求があったはずだからだ。
ロックを知った普通じゃない(と思っていた)若者が、結局普通の大人になってしまった、そんなハッピーエンドともバッドエンドともとれるストーリー(平凡というのは良い悪いを越えたところにある)が、AORを聴いていると頭の中に湧き出てくる。
・・・以上ごちゃごちゃ書いたが、すべて忘れて、ただ「良い音楽」として聴いてよい、いやそのように聴くべきだ、という声が、以下のアルバムたちから聞こえてもくる。産業音楽というのはやはり面白い。
Bobby Caldwell / Bobby Caldwell
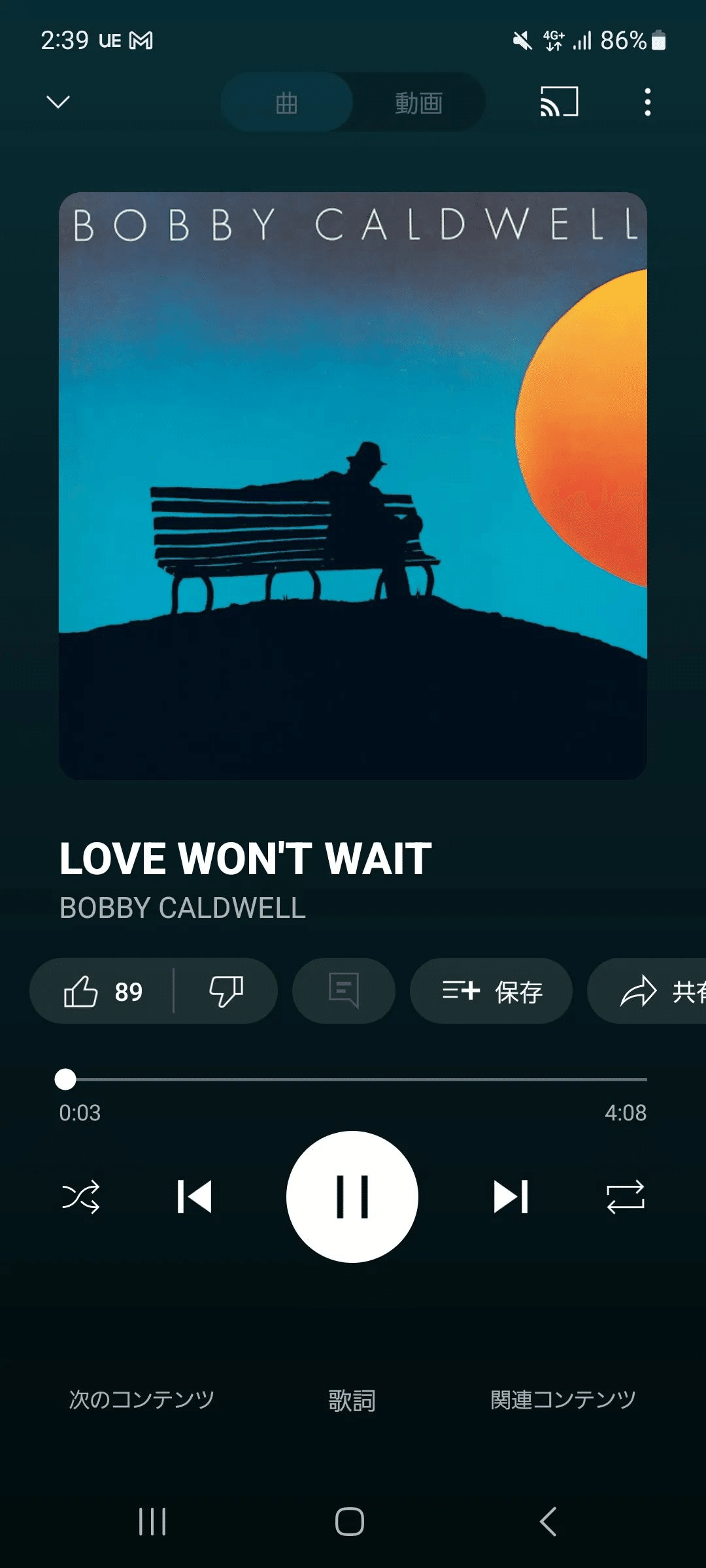
1978年作。コールドウェルはニューヨーク、マンハッタンの生まれ。他のAORアーティストに比べ、特に日本で人気を博した。4thアルバム『August Moon』は日本でのみ発売されている。
これはそんな彼の1stアルバム。ソウルフルな歌い方だが声を張り上げすぎず、しつこくない。甘辛いタレに漬けてふんわりと焼き上げた鰻の蒲焼きに、ピリッと山椒が効いてる感じ?(ダサい喩え…)
音像もふわーっとしたものではなく、シンプルで硬質。エレピの良さが出ている。タイトな雰囲気が日本でウケたのだろうか?
M3“Love Won't Wait”はヤマタツのラジオのOPですな!
(2024.6.10)
Christopher Cross / Christopher Cross

1979年1stアルバム。クロスはアメリカ南部のテキサス州はサンアントニオ生まれ。このアルバムに収録された“Sailing”は、ヨット・ロックの代名詞ともなった。
エレガントで美しく、爽やかで滑らかで心地よい、うーん、良い音楽… クロスは少し鼻にかかった、(もちろん彼らがこのジャンルを作っていったんだけれども)AORのお手本のような歌声。曲ごとにサウンドが少しずつ異なっているのもポイントが高く、さながら70s後半の音の見本市。M2“I Really Don't Know Anymore”でのラリー・カールトンのギター・ソロ、M4“Never Be the Same”でのジェイ・グレイドンのギター・ソロなど、ボーカル以外の聴きどころも満載。 名曲として名高い“Sailing”は、ストリングスとエレピに乗って、水平線の彼方へと雄大に出航していく。
(2024.6.10)
Michael McDonald / If That's What It Takes
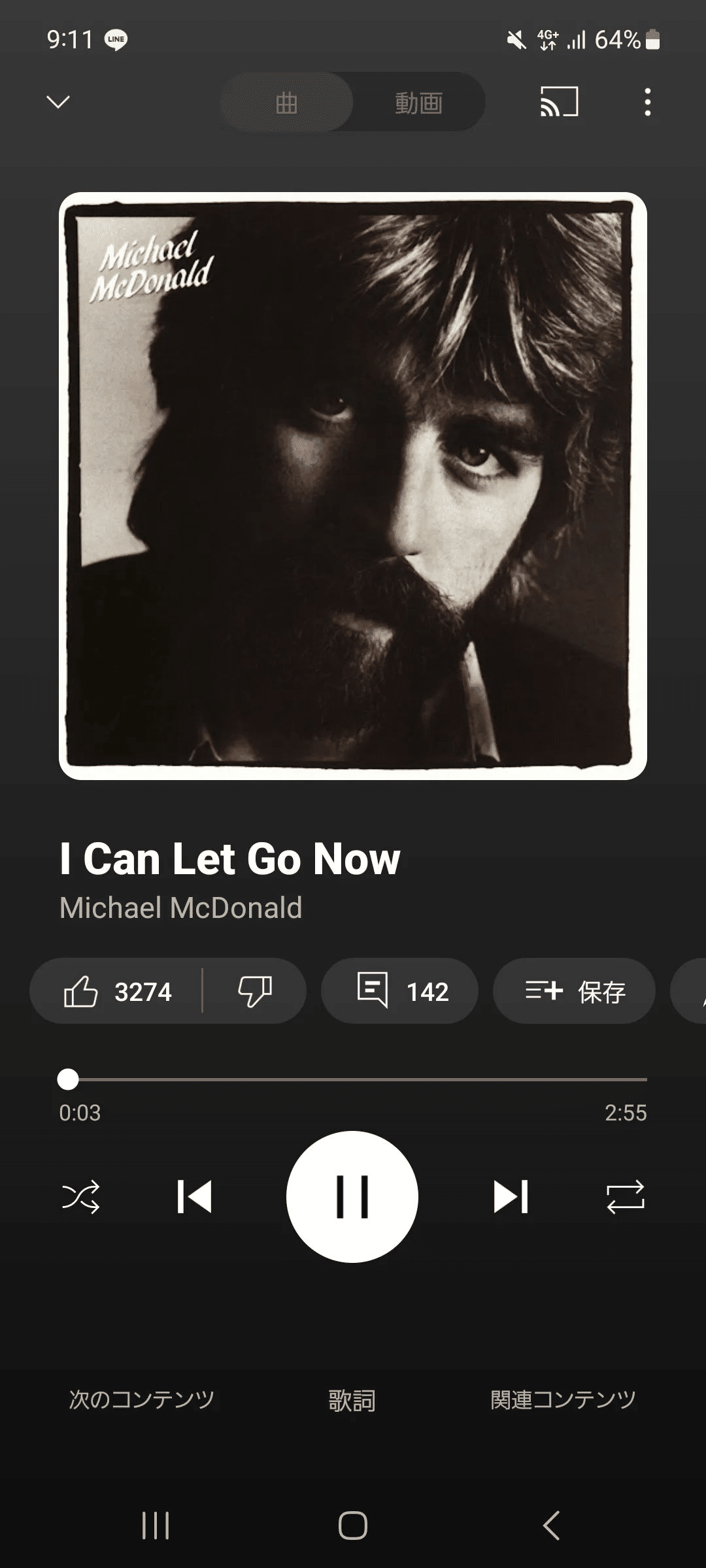
1982年作。マイケル・マクドナルドは1975年にウェスト・コースト・ロックの雄であるドゥービー・ブラザーズに加入、ドゥービーが活動を停止した1982年からソロ活動をスタートさせる。このアルバムはソロ・デビュー・アルバムだ。
AORと思って再生したが、厳しさがあり、「ムーディーでオシャレなAORを恋人と…」みたいな謳い文句で売り出されるそこら辺のソフト・ロックとは一線を画す音楽への妥協なき姿勢があると思った。バックのサウンドは一定で、プロダクションに甘えるところがないところにもまた、ロックの精神が垣間見られ、やっぱりドゥービーやスティーリー・ダンと通ずるものがあるように感じる。 ストリングスが入るM5“I Can Let Go Now”でも、歌声に圧倒される。サラっと歌ったとは思えない、マイケル・マクドナルドのこだわりが聴こえる。 何か他の音楽を否定する気は毛頭ない!が、「こうでなくっちゃね!」と私は思う。バックのメンバーも一流揃いで、そりゃそうだよね、と納得。優れたアルバムに出会えて良かった。
(2024.6.10)
Michael McDonald / No Lookin' Back

1985年2ndアルバム。80sの音だ。だがやかましくはない。マイケル・マクドナルドの声は抑制されており、バックのサウンドを形作る西海岸のミュージシャン連中の演奏も落ち着いている。
ジェフ・ポーカロのドラムが快適な鼓動を打つ。スティーリー・ダン、トトの音だ。M9“Don't Let Me Down”でのロベン・フォードのギターも見事。
先入観もあると思うが、ロック小僧が80年代になり、仕事をして家庭をもって、若者の音楽も変わってしまい、さぁて何を聴いたらよいものか、なんてレコード屋に久しぶりに入ってみたところでこのアルバムを手にとって、これならちょっと聴いてみようか、なんて思って購入、帰途につく…そんな光景が思い浮かぶ。仕事に疲れた日の帰り道に似合いそうだ。
タイトル曲はケニー・ロギンズとの共作、カーステレオで聴きたい
(2024.6.20)
Bill Champlin / Single
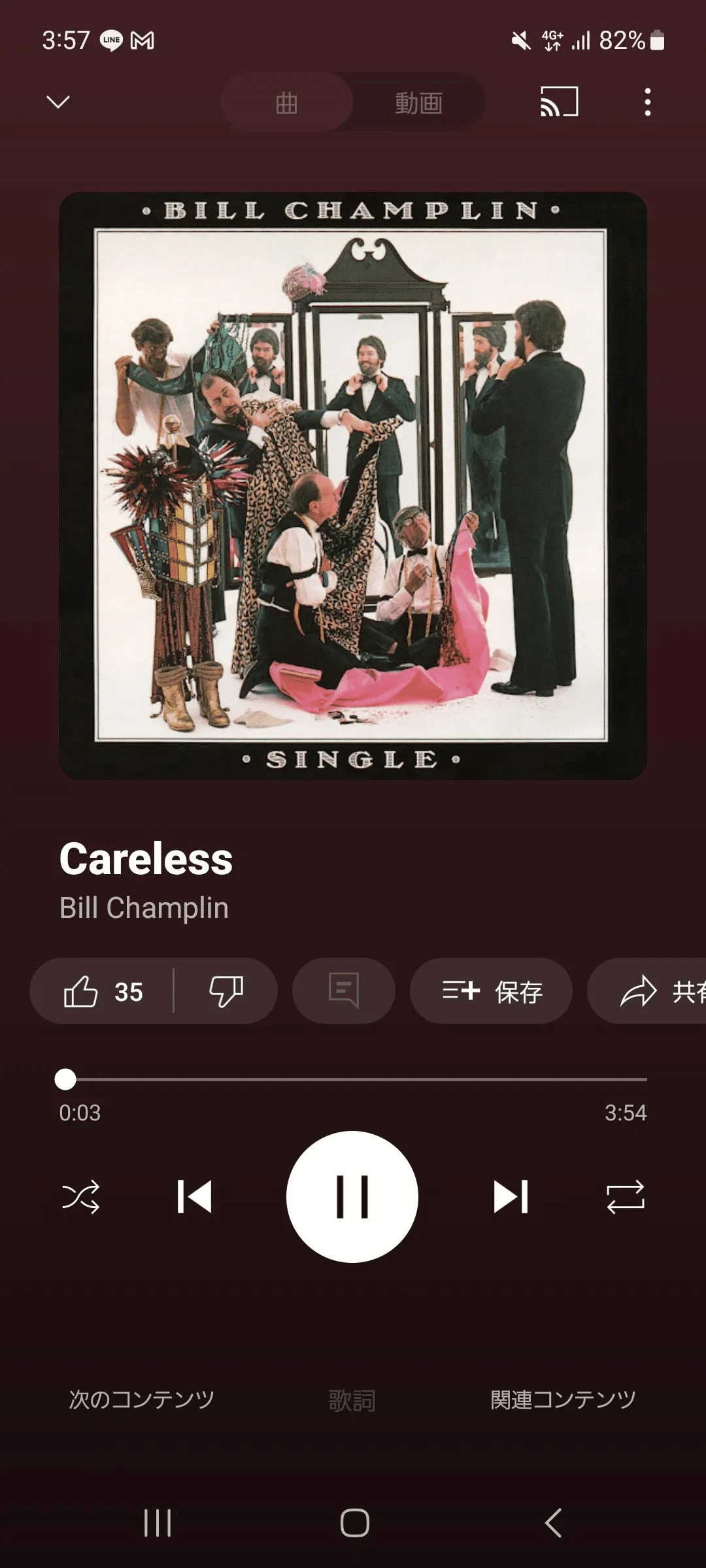
1978年1stアルバム。ビル・チャンプリンは60年代から売れないサイケ・バンドの一員として活動するが同バンドは1977年に解散。そこへセッション・ミュージシャンでありプロデューサーであったデヴィッド・フォスター(1980年にジェイ・グレイドンとエア・プレイを結成する、これもAORの名バンドだ)に見出され、ソロ・デビューを果たす。
このアルバムでは、そんなデヴィッド・フォスターの名プロデュースを得たチャンプリンが、壮年の元気を体現するかのようなボーカルを聴かせる。 M1“What Good Is Love”のギターはまさしく70年代後半の軽快な音。M2“I Don't Want You Anymore”のようなファンキーでノリの良いナンバーと、M3“We Both Tried”のような大きく弧を描いて伸びやかに歌うバラードとがバランスよく収録されていて、快適に聴ける。歯切れは良いのだが少しウェットなサウンドも心地よい。まさにアダルト・コンテンポラリー。 そしてM7“Careless”でのチャンプリンの楽しそうなこと!ロックスターでもシンガーソングライターでもない「ロック歌手」としての最高の表現がここにある。それはロックが大人になったことによって生まれたものなのだろう。
(2024.6.20)
Kenny Loggins / High Adventure
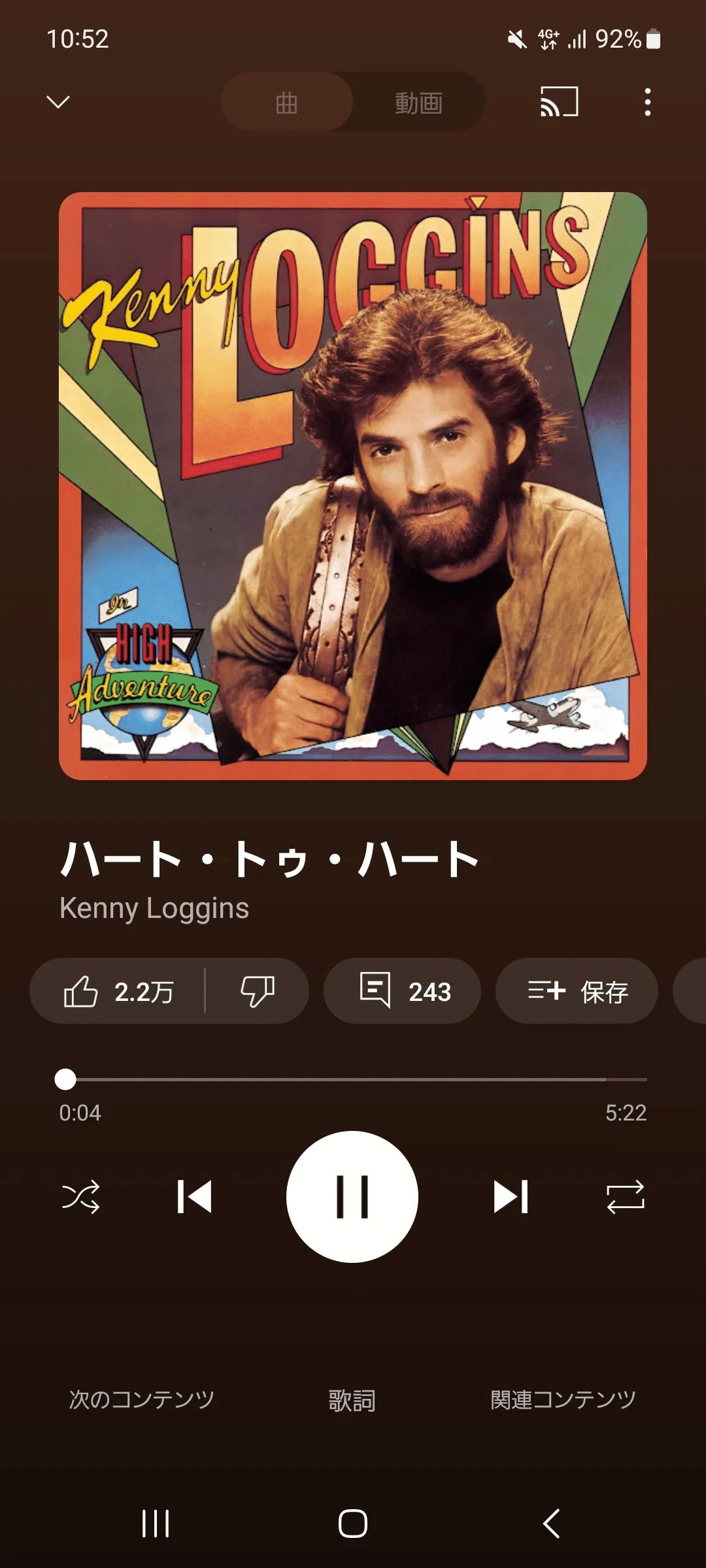
1982年4thアルバム。ケニー・ロギンズは西海岸北端のワシントン州はエヴェレット出身。1971年に旧友ジム・メッシーナとポップ・フォーク・デュオであるロギンス&メッシーナを結成。1977年からソロ活動も行っていく。
一曲目からハード。ソフト・ロックだと聞いていたので、おお!と思った。ロギンズの声はまさに80sって感じ。ハードな曲はクイーンみたいな一方、メロウ/グルーヴィーなナンバーはAOR・フュージョン的サウンド作りが施されている。
ヒットシングルであるM6“Heart to Heart”でマイケル・マクドナルドが弾くフェンダー・ローズが素晴らしい。
(2024.6.20)
Michael Franks / The Art of Tea
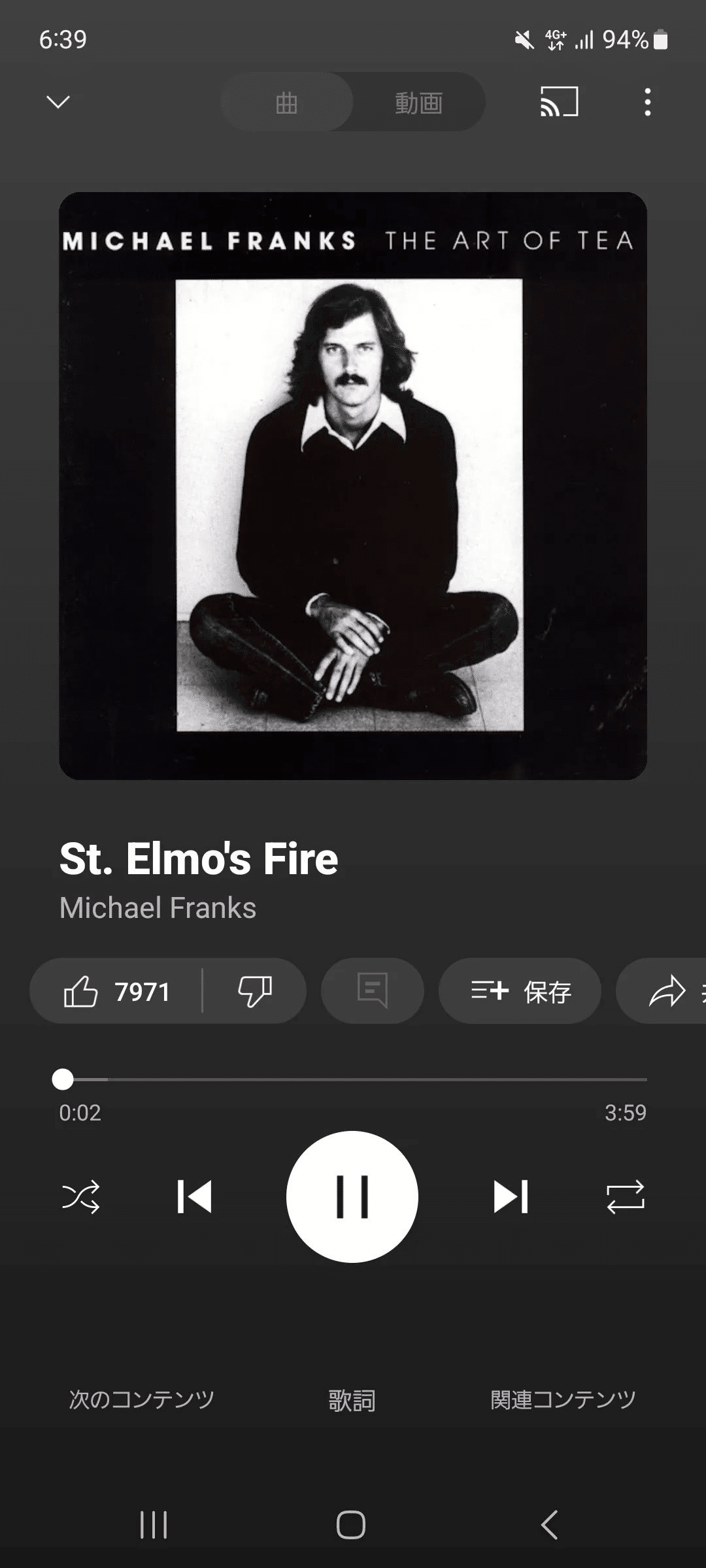
マイケル・フランクスはカリフォリニア州ラホヤ出身で、1970年前後から音楽活動を開始。ジャズ、フュージョン系のミュージシャンと関係が深く、この2ndアルバムは1976年作で、ワーナー・レコードからリリースされた。
フュージョンの名手たちによる簡素なサウンドを背景に、フランクスが穏やかで小気味良いボーカルを聴かせる。もちろんリズムやサウンドとしては70sのポップスという地点に立っている訳だが、たちのぼる音楽の雰囲気は間違いなく“ジャズ”だ。
随所で肩を叩くかのように登場するマイケル・ブレッカー(ts)とデヴィッド・サンボーン(as)も勿論良いが、恒常的に演奏しているリズム・セクションの素晴らしさたるや。メンバーはジョー・サンプル(p)にウィルトン・フェルダー(b)、ジョン・ゲラン(ds)といった面々。ウェスト・コースト・ジャズが持っていた洗練された簡潔さの継承者ここにありといった感がする。特に耳が惹き付けられるのはジョー・サンプルのエレピ。これが有るのと無いのとではボーカルの印象が天と地ほども違うだろうに、それを思わせないさりげなさ。いやぁ、スバラシイ!
(2024.6.18)
Michael Franks / Sleeping Gypsy

1977年3rdアルバム。
ブラジル音楽のエッセンスをAORに昇華させた名作。マイケル・ブレッカーやデヴィッド・サンボーンの熱演、ジョー・サンプルの心地よいエレピも去ることながら、フランクスの優しい声を包むクラウス・オーガーマンの、温かなオーケストラ・サウンドが素晴らしい。 ジョビンのCTIの諸作を思い起こさせる、しかしソフト・ロックのタイトさ心地よさもしっかりと感じれる素晴らしい音楽。
(2024.6.4)
Michael Franks / Burchfield Nines
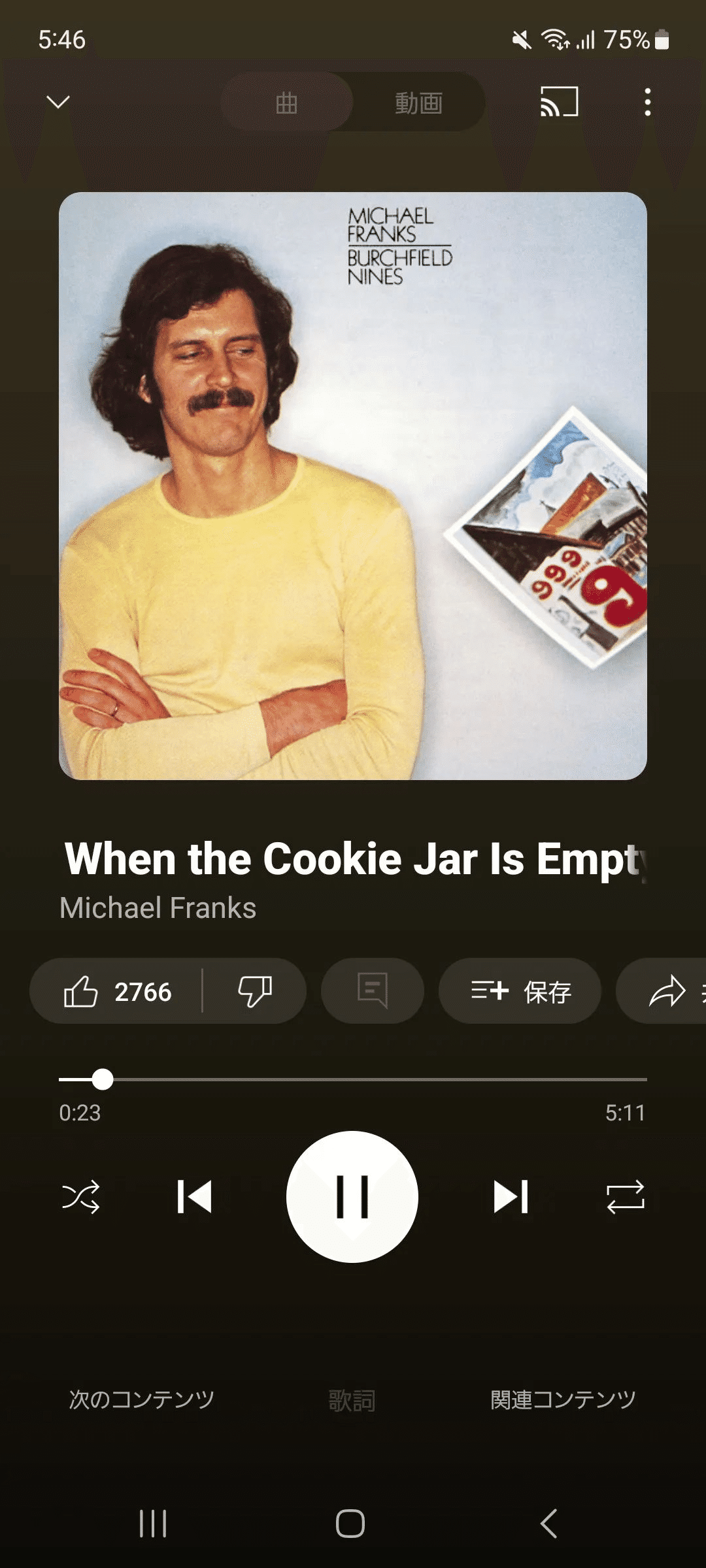
1978年4thアルバム。
ジョン・トロペイのギターとデオダートのアレンジが特徴的。
前作のラテン的優しさを引き継ぎつつ、少しファンキーで乾いた空気がプラスされている。ここら辺がデオダート節って感じ。そのバランスの良さは、この時代の“フュージョン”という音楽を体現しているように思える。良質でナイスな音楽。バド・シャンクのアルトはさりげない。
(2024.6.19)
Michael Franks / Tiger In The Rain

1979年5thアルバム。
フランクスの美声は保たれながら、プロデューサーのジョン・サイモンによって、新たなサウンドが導入されている。
全体的にはボサノバ風味の穏やかなラテンロックといったところか。フローラ・プリムの参加も印象的だし、マイク・マイニエリのヴァイブも良い。ボサノバを感じるのはサウンドというよりフランクスのボーカルなのかもしれないが、まさしく彼の歌声にマッチするサウンドを、従来のフュージョン/スムース・ジャズの文脈とはまた違うところから組み立てているように感じられる。
私的にはアルバムのラストを飾るザ・バンド風の二曲、M8“Satisfaction Guaranteed”とM9“Lifeline”が素晴らしい。後者でルー・ソロフのトランペットにエコーをかけてるのなんかタマラン。70sの終わりを感じさせる名盤。
(2024.6.19)
Ben Sidran / The Doctor Is in

1977年6thアルバム。ベン・シドランはイリノイ州シカゴの生まれ、ウィスコンシン州ラシーン育ち。60年代後半には英文学の博士号取得のためにイギリスのサセックス大学へ入学、同地でセッション・ミュージシャンとして多くのブリティッシュ・ロックにおけるキーボードを弾いた。
そんなベン・シドランの達者なピアノは聴いているだけで楽しい。ジャズ的カンファタビリティに加え、レオン・ラッセルのようなルーツ・ロック的軽快さもある。ボーカルは穏やかながら、ピアノの存在感(それは大仰なものではなく、居ると気付かないのだけど、居ないとすぐにわかる種類の存在感)を考えると、ビリー・ジョエルなんかに近いと思った。 B面ではストリングスが入る。アレンジはニック・デカロ。さすが。 おや、良いトランペットだなと思って確認したら、ブルー・ミッチェルだった。こっちもさすが。
(2024.6.28)
James Taylor / JT

ジェームス・テイラーはマサチューセッツ州ボストン出身のシンガーソングライターで、70年代前半におけるシンガーソングライター(SSW)ブームにおける代表的な人物のひとりだ。これはそんな彼が1977年にリリースした第8作目。
ジェームス・テイラーの美声を堪能できるというその一点が素晴らしいアルバムだと言える。アレンジもとても控えめ。彼の初期の傑作『スウィート・ベイビー・ジェイムス』を思わせる。この人はやっぱり穏やかに音楽と向き合いたい人なのか。
(2024.6.30)
James Taylor / Dad LovesHis Work

1981年10thアルバム。
『パパはこの仕事が好き』というタイトルは、テイラーが家庭を省みなかったために、子どもを置いて出ていってしまった当時の奥さん、カーリー・サイモンに向けられたもの。なかなか大変な結婚生活だったみたいですね、二年後には離婚してしまうし… それはそれとして、このアルバムは、パパが自信をもって答えるだけのことはある作品。M2“Her Town Too”を筆頭に、エレピを中心としたアダルトな夜の雰囲気に、心地よいグルーヴネスが加えられたサウンドが存分に楽しめる。 プロデューサーのピーター・アッシャー、彼はジェームス・テイラーと長く付き合っているけれど、ウェスト・コースト・ロックの重要人物なんですね。要チェックだ。
(2024.7.2)
Robert Palmer / Double Fun
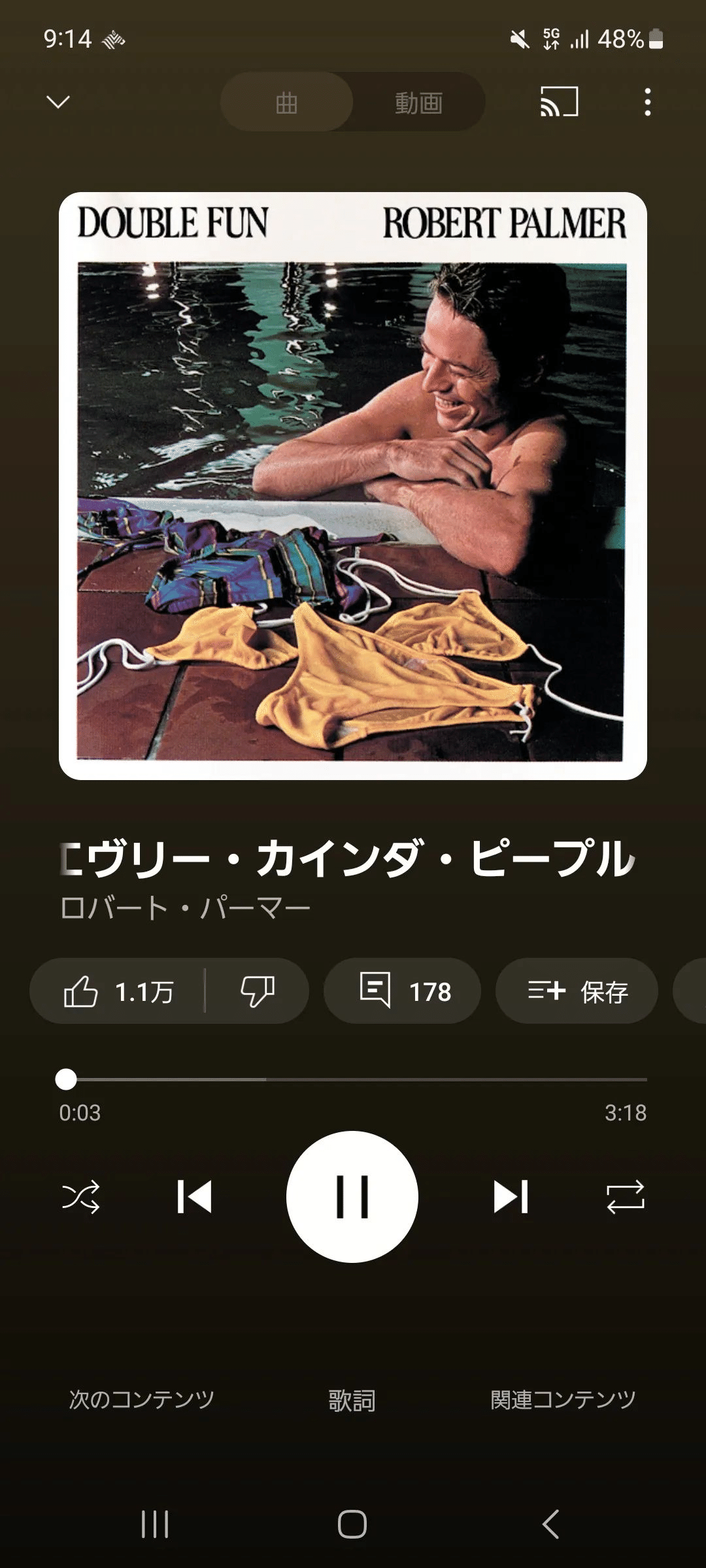
イングランドのウェスト・ヨークシャー出身、ロバート・パーマーの1978年4thアルバム。
音が充実してて良い!バックで吹いているブレッカー・ブラザーズのおかげかも。あとはマイケル・マクドナルドに近いところがある気がする。スウィートなところもあるんだけど、根底にあるのはハードな音像。 特にファンキーなナンバーが良い。例えばシングル曲のM1“Every Kinda People”。キレが良いだけでなく、ストリングスも加わったゴージャスなサウンドだ。スティール・パンも良い味出してる。ソウルフルな歌い方も私好みだ。ナイスなアルバム。
(2024.7.2)
Robert Palmer / Riptide
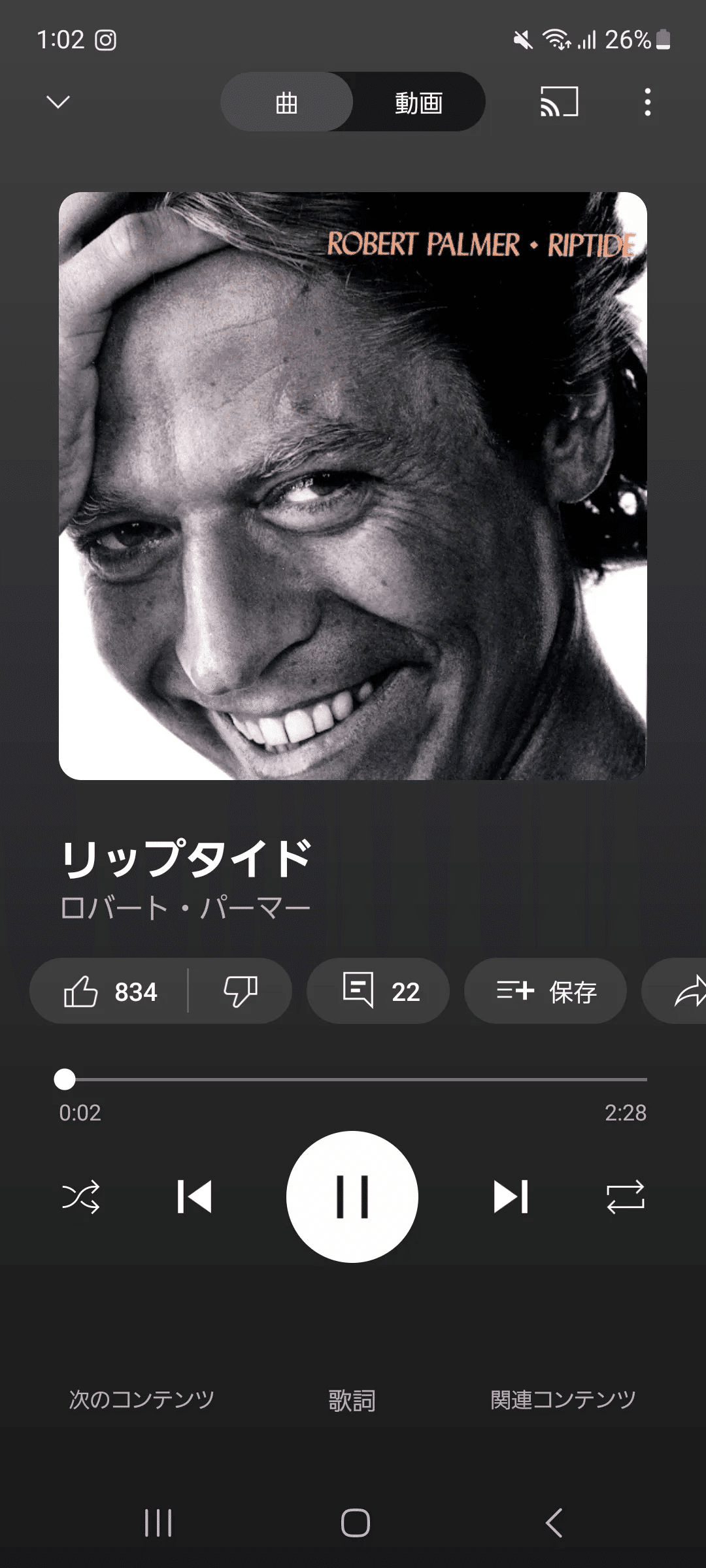
1985年8thアルバム。
M2“Hyperactive”とM3“Addicted to Love”は80sらしいマッスルなハード・ロックなのだが、M1“Riptide”とM4“Trick Bag”は不思議なサウンド。
M5“Get It Through Your Heart”はフワフワしたバラード、M6“I Didn't Mean to Turn You On”はニューウェーブ風、スピーディーでカッコいい。M7“Flesh Wound”はエアロスミスみたいなリフがカッコよく、M8“Discipline of Love”はネオ・ロマンティックって感じ。そしてM9“Riptide”のリプライズで〆る。
こう書くと散らばってるようだけれど、80sの音楽が存分に鳴らされていて楽しい。
なんというか、一筋縄ではいかないのがイギリス人らしいというか…
(2024.7.3)
Bill LaBounty / Bill LaBounty

AORの巨匠(?)、ウィスコンシン州出身のビル・ラバウンティによる1982年4thアルバム。
ここ最近、AORのアルバムをいろいろ聴いてきたけれど、これはかなり良いアルバムだと思った。よくある、エレピや8ビートの軽快なドラムが耳に残りやすいがために強調され、その中にあるべきはずの他の楽器の音がスカスカな、羊頭狗肉なサウンド(それでも別に悪くはないのだけれど、そういうのばかり続けて聴いていると、その「こういうのでいいんでしょ?」的な金太郎飴感にいささかイラッとしてくる)ではなく、エレピとドラムの間に、芯のあるエレキギターの音と分厚いホーン・セクションのサウンドがしっかりと詰まっており、それらが一糸乱れぬグルーヴを奏でているので、すごい迫力が生まれる。しかしそれが押し付けがましくなく、あくまで「心地よさ」に主眼が置かれている。素晴らしい!
(2024.7.2)
Billy Joel / The Stranger

アメリカのニュー・ヨーク出身のシンガーソング・ライター、ビリー・ジョエルを、一躍スターダムに押し上げた1977年の5thアルバム。
このアルバムは久しぶりに聴いた。以前聴いたときは、エルトン・ジョンと比べてしまい、何だか暗いなぁとピンと来なかったけれど、まさしくその天性の翳りと、ジャズのフィーリングに溢れたソングライティングとピアノのプレイングこそが、彼の穏やかなる魅力なのだと解った。これからも聴き続けたいアルバム。
(2024.3.6)
Billy Joel / An Innocent Man

1983年9thアルバム。
R&BやR&Rの先達に捧げたホットなナンバーを、ビリー・ジョエルがノリノリで歌いまくる!アツいアルバムだ。 個人的にはM4“This Night”が好き。ああ、彼は自分の生まれた時代を心から愛しているんだな、というのが伝わってくる。ベートーヴェンの《悲愴》を使っているのも、効果的だし面白い。やっぱりこのメロディーは、美しい想い出に浸りながら、昔を懐かしんでいる感じだよね。 表現力ゆたかなボーカルが素晴らしいのは勿論のこと、加えて本気でオールディーズに取り組んでいる80sのスタジオの、俺たちこんだけやれるんだぜ、という心意気もバシバシ伝わってくる。全員があの時代の音楽に、最大の敬意と共感を抱きながら、明るく楽しく屈託なく演奏している。ビリー・ジョエルを筆頭に、まさしく彼らは「無邪気な男」たちだ。
(2024.7.6)
Level 42 / Level 42

1979年に結成されたイギリスのジャズ-ファンクバンドの1981年1stアルバム。
ホーンが無くシンセの存在感が強いため、テクノとかディスコっぽいなと思った。ファンク色を担うのはベース兼ボーカルのマーク・キングか。バシバシチョッパーも行うし、AOR的な歌声も聴かせる。ただ、一般的なフュージョンに聴こえるファンキーチューンよりも、そうじゃない、シンセの和音が、80年代らしく響く曲の方が、このバンドの独自性が出ていて好きだ。そればかりでは売れていなかっただろうけど…
ジャケットのもつ異世界的なイメージからか、筒井康隆『旅のラゴス』のBGMにぴったりだった。
(2024.6.2)
Fourplay / Fourplay
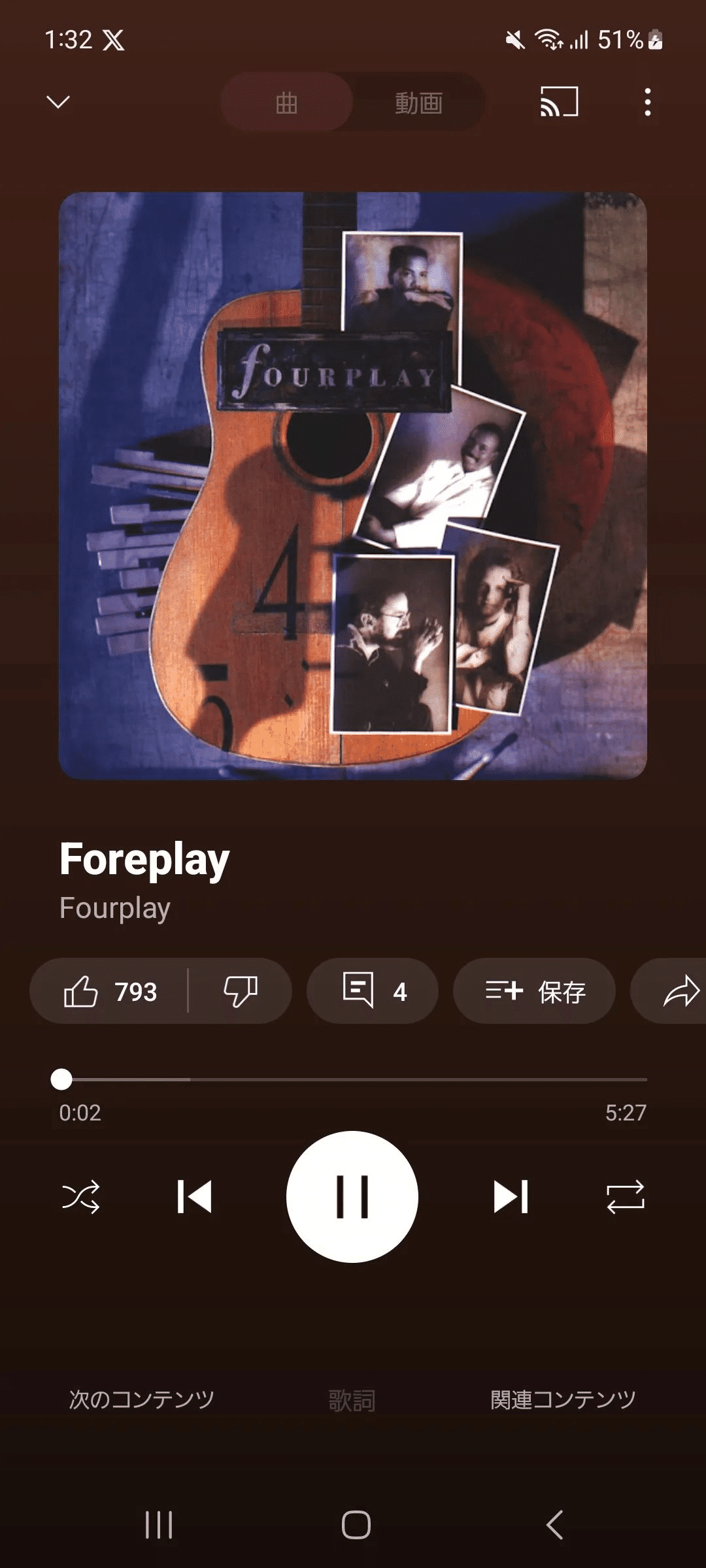
ピアニストのボブ・ジェームス、ギタリストのリー・リトナー、ベーシスト兼ボーカルのネイザン・イースト、ドラマーのハービー・メイソンという、ラヴ・アンリミテッド・オーケストラのメンバーであったネイザンと、70~80年代のフュージョン界におけるスター・プレイヤーたちによって1990年に結成されたバンド「フォープレイ」の1991年作。
イージーリスニング的ながら、瑠璃色の輝きを静かに放つ素晴らしいアルバム。最年少のネイザン・イーストは余計なことをせず背景の一部と化し、ハーヴィー・メイソンも、静かに、しかし着実なドラミングを聴かせる。彼もトシを取ったのだな。そしてリー・リトナーの美音。思えば彼は、サイドに居た方が引き立つタイプの人間だ。そのリトナーの個性は、ボブ・ジェームスの思い描くサウンドの方向性(おそらくこのバンドを操縦しているのは彼だ)と、この上なくマッチしている。彼の70~80sを経た、極上の「アダルト・コンテンポラリー」が、ここにある。どんな音楽にも、最盛期を過ぎた時に枯れた味わいが生まれるとすれば、フュージョンという音楽の枯淡の境地のひとつがこのアルバムであると言えるのではないか。大人向けのマスターピースだ。
(2024.6.3)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
