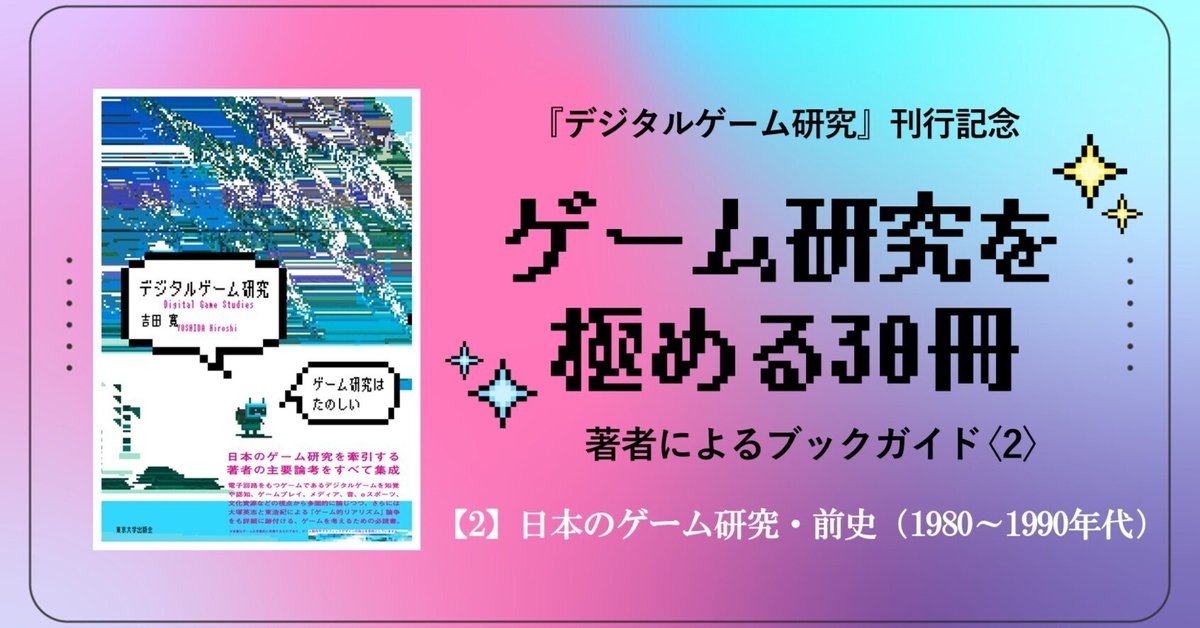
ゲーム研究を極める30冊〈2〉/吉田寛
(2)日本のゲーム研究・前史(1980~1990年代)(7冊)
日本では1980年代から、テーブルトークRPGのムーブメントを担った安田均や多摩豊が優れたゲーム論を書いていた。また、1990年代には学者や評論家によるゲーム論やゲーム産業論、ゲームクリエイターによるゲーム論が登場する。それらは「ゲーム研究」というディシプリンを意識して書かれたものではなく、なかには「研究」とは呼べないようなものもあるが、ゲームについての深い思索や鋭い洞察を含むものとして、今なお読むに値する。
(2-1)安田均『SFファンタジィゲームの世界』(青心社、1986年)
デジタルゲームを(その一部として)扱った日本語の単独の出版物は、これが最初かもしれない。海外SFの翻訳家・批評家として出発した安田均は、本書出版の翌年にグループSNEを立ち上げ、テーブルトークRPGを日本に紹介する役割を一身に担った。本書でいう「SFゲーム」は、ウォーゲーム(シミュレーションゲーム)、ロールプレイングゲーム、ファンタジーゲームなどを含むが、本書で実際に扱われているゲームはボードゲームやカードゲーム、ゲームブックが中心であり――さらに「郵便ゲーム」(PBM=プレイ・バイ・メイル)も扱われている!――デジタルゲーム(コンピュータゲーム)に割かれるページはごくわずかである。この時代に「ロールプレイングゲーム」といえば、もっぱら『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』(1974年)に代表されるテーブルトークRPGを指し、『ウルティマ』や『ウィザードリィ』などコンピュータ上で遊ばれるものは、それらから区別するために、わざわざ「コンピュータ・ロールプレイングゲーム(CRPG)」と呼ばれたりしていたわけだが、ボードゲームとしてのウォーゲーム(シミュレーションゲーム)やテーブルトークRPGの流行やコミュニティがまず先に存在しており、コンピュータゲームは後からそこに加わった後発のジャンルであった、という前後関係を見誤ってはならない。安田はこの後、『神話製作機械論』(1987年)や『幻夢年代記:コンピュータ・ゲームの世界』(1989年)を通して、コンピュータゲームの批評家・紹介者としての実績と知名度も積み上げていく。
(2-2)テレビゲーム・ミュージアム・プロジェクト編『テレビゲーム:電視遊戯大全』(ユー・ピー・ユー、1988年)
デジタルゲームの歴史を日本語で初めて詳細に論述した本。本書でいう「テレビゲーム」には、家庭用ゲーム機で遊ばれるゲーム(コンソールゲーム)だけでなく、コンピュータゲームやアーケードビデオゲームも含まれており、当時はこの語が(今でいうデジタルゲームのような)総称として使用されていたことが分かる。(アナログを含む)ゲーム一般の歴史、ブラウン管の歴史、コンピュータの歴史、デジタルゲームの技術と文化、主要なゲームクリエイターとゲーム会社、歴史的に重要なゲームタイトル200本を網羅的かつ体系的に叙述した本書は、ゲームが今や「研究対象」となった(歴史が分からなければ今のことが分からないという意味で)ことを強烈に印象づけた。ウィリー・ヒギンボーサム、スティーブ・ラッセル、スペースウォーといった歴史的な人名やタイトルに、本書を通じて初めてふれた日本の読者は筆者だけではないはずだ。また本書は、特殊な製本技術を用いており、大半のページの紙が、物理的に2つまたは3つに切り分けられている。それによって、「テレビゲームの歴史」「テレビゲームの制作者」「テレビゲーム200選」「クリエイターズ・インタビュー&コラム」という4つのパートを、まるで別々の本のように、それぞれのページをめくって見比べながら読み進めることができる仕組みになっている。編者の言葉を借りれば、これは「テレビゲームの歴史を見ながら、テレビゲームの制作者のことを知り、同時にそのテレビゲームの遊び方や、面白さが分かる」ように「マルチタスク化」された本であり、「ページをめくるという時間軸が複数ある」本なのだ。また各項目には関連項目のインデックス(いわばリンク先)が示されており、それ自体がゲームにも類比可能な「サイバーテキスト」(オーセット)となっている。いわば「遊戯についての遊戯的書物」である本書の存在は、当時のデジタルゲームが、文学という形式(書物という物体)の限界を打破したいという欲望を引き受けていたことの証拠となっている。
(2-3)多摩豊『コンピュータゲームデザイン教本』(ビジネスアスキー、1990年)
著者は、安田均と共にテーブルトークRPGを日本に紹介することに尽力した編集者、翻訳者、批評家であり、日本で初めてとなるデジタルゲームのデザインに関する体系的著作がそのような人物の手で執筆されたという事実は重要である。むろん彼はコンピュータゲームについても当時日本国内でトップクラスの見識をもっており、本書では、クリス・クロフォード(『バランス・オブ・パワー』)やリチャード・ギャリオット(『ウルティマ』)、アンドリュー・グリーンバーグとロバート・ウッドヘッド(『ウィザードリィ』)、ウィル・ライト(『シムシティ』)らへの取材を通して彼が咀嚼したゲームデザインの極意が要所要所で配置されている。インタラクティビティ、インテリジェンス性、柔軟なグラフィック表現能力、シミュレーション性、リアルタイム性といった、コンピュータゲームの基本特性についての彼の考察は、同時代のグローバルな水準のなかでも決して見劣りしていないどころか、明らかに突出している。1997年に惜しくも夭逝した彼が、もしももう少し長く生きていれば、日本のゲーム研究の黎明期の風景もだいぶ違っただろうと思わざるをえない。「ログイン・ブックス(LOGiN BOOKS)」シリーズの1冊として、攻略本や資料集に取り混ぜて、このような理論的著作をもさりげなく刊行していた出版社アスキーの貢献も多大である。
(2-4)藤井雅実・澤野雅樹編『人はなぜゲームするのか:電脳空間のフィロソフィア』(洋泉社、1993年)
今は無き(2020年に宝島社に吸収合併)洋泉社から出ていた「キーワード事典」シリーズの1冊として、映画、音楽、アートといったジャンルに混ざって、ゲームの本が出ていたことは、ゲームがいわゆるポストモダン思想と相性がよかったことを示している。編著者の藤井雅実は、リンダ・ニード『ヌードの反美学』の翻訳などで知られる美術批評家であり、澤野雅樹はドゥルーズをはじめとするフランス現代思想研究で知られる(ただしこの本のなかでは「社会学者」を自称している)。思想家や評論家がゲームを取り上げる時代(テレビゲームはもはや小学生のおもちゃではない!)は、中沢新一や高橋源一郎によってすでに幕を開けていたが、(当時は)比較的無名だった若い書き手による高密度でハイテンションの論考を集めた本書は、ゲームがいよいよ誰にとっても無視できない対象になっていることを読者に知らしめた。なかでも澤野は1人で5本もの論考(オープニングと対談を除く)を寄稿する大活躍であり、タルドやジラール、レヴィ=ストロース、ドゥルーズ、ラカン、デリダ、ジジェクの理論や術語を自在に駆使しながら、『ドラゴンクエストIV』、『女神転生II』、『プロ野球ファミリースタジアム』、『ストリートファイターII』を縦横無尽に論じている。その着眼と議論の切れ味は、今読んでも十分刺激的である(とくにファミスタ論とトルネコ論とシューティングゲームの平面論は、未読なら必読だ)。「ゲーム的発想がなければ世界は読めない!」「90年代はゲームの時代である」など表紙を飾るキャッチコピーも、すでに当時からそういわれていたことを知れば、今後無自覚に反復するのは慎まれるだろう。
(2-5)田尻智『新ゲームデザイン:TVゲーム制作のための発想法』(エニックス、1996年)
ゲームクリエイターによるゲームデザイン論の嚆矢となったのが本書である。ゲーム系同人誌の発行やライター活動から出発した著者は、同人誌を母体としたゲーム制作会社「ゲームフリーク」を設立し、その第1作として『クインティ』(ナムコ、FC、1989年)をリリースした。執筆・出版活動からゲーム制作へと参入した著者は、理論に裏打ちされたデザイン実践を行い、しかもそのプロセスを明瞭に言語化できるという、ユニークで稀有なクリエイターとなった。著者は冒頭で、高校時代に美術の授業で高階秀爾の『名画を見る眼』を読んでうけた感銘を振り返り、「TVゲームの世界も、しっかりとした裏付けと言葉による表現を使って、同じような読み取る行為が可能ではないか」と述べる。それに続いて本編では、ハードウェア、モチーフ(題材)、ルール、ジャンル、グラフィック、音楽の順序で、ゲームデザイン論が展開される。今日、田尻と「ゲームフリーク」といえば、真っ先にあげられるのは「ポケットモンスター」シリーズだと思われるが、ゲームボーイ用に作られたその初代作『ポケットモンスター 赤・緑』(1996年2月発売)は、本書刊行の時点(1996年1月刊行)ではまだ発売されていなかった。しかし著者は本書で、『ポケットモンスター』が発売されている(皆が遊んでいる)ことを前提にした議論を展開しており、しかも本書ではその発売年が「1995年」と表記されている。おそらく著者は、ゲームと本の同時発売を目論んでいたのだろう。だが周知のように、このゲームは、当初予告されていた発売予定日(1995年12月21日)が、デバッグなどの遅れにより最終的発売日(1996年2月27日)に変更された経緯があり、1996年1月発売の本書は結果的にその両者の間に挟まる格好になってしまった。『ポケットモンスター』を遊びながら読まれる「副読本」として書かれた本書は、著者の意図に反して、ゲームに先行して単独で世に出てしまい、そのため皮肉なことに、さほど注目されずに(少数部数が刊行されただけで)終わってしまった。しかし『ポケットモンスター』のデザイン理念(通信、ギャザリング、交換)と、そこに至るまでの著者の遍歴を理解するために、今も真っ先に読まれるべき本である。
(2-6)平林久和・赤尾晃一『ゲームの大學』(メディアファクトリー、1996年)
テレビゲームに関する初めての日刊連載記事として『日本工業新聞』に掲載された平林久和「ゲームの大学」(1994年9月~1995年1月)および赤尾晃一「ゲームの経済学」(1995年2月~7月)を再編成したもの。ゲーム業界のビジネスモデルや流通を扱った産業論と、ゲームの本質や技術の問題まで踏み込むゲームデザイン論(そのなかでホイジンガ、カイヨワ、チクセントミハイの理論も紹介されている)が組み合わさっており、全体としては「ビジネス書」の体裁を取りながら、研究書としても十分読み応えのある本となっている。本書に頻出する当時のゲーム業界のキーワードは、マルチメディアやCD-ROM、次世代機、3DリアルタイムCG、インターネットなどであり、単行本書き下ろしの部分では、発売直後のウィンドウズ95(日本では1995年11月発売)がゲーム業界に与えるだろう影響や、発売直前に迫ったNINTENDO64(1996年6月発売)の将来性が論じられている。「ゲームのことが分からなければ、これからは産業のこともビジネスのことも分からない」という一貫した論調をもっており、あとがきでは、本書の題名によせて、「相変わらずゲーム(そしてエンタテインメント)を研究対象として扱うことさえも異端視して」いる「日本のアカデミズムの世界」への批判も見られる。すなわち本書は、総合的な「ゲーム学」の構想の日本における先駆的事例であるが、それが産業論をベースにしていたことが、今日でもなお日本のゲーム研究に影を落としているといっても過言ではない。やがてヨーロッパで登場する「ルドロジー」(人文学をベースとする)との違いを考えれば、なおさら興味深い。
(2-7)『大人のためのテレビゲーム学概論』(アスペクト、1999年)
(旧)アスキー系の出版社であるアスペクトから、「特集アスペクト」の1冊として出された、いわゆる「ムック本」であるが、こういう題名をもつ以上は、ここで取り上げないわけにはいかないだろう。バーチャルリアリティ、物語とルール、育成シミュレーション、デジタルヒーリング、恋愛シミュレーション、ゲーム音楽といったテーマをもつ各章ごとに、学者や評論家による論考が収録され、そのテーマに関連するゲームタイトルが紹介される。その際には、歴史的意義や先駆性の観点から、今ではプレイすることができない1980年代のタイトルも取り上げられるなど、明らかに「商業寄り」ではなく「学術寄り」の編集方針をとっている。また本書をそれ以前の類書から区別する最大の特徴は、中村光一(チュンソフト)、飯野賢治(ワープ)、薗部博之(パリティビット)、飯田和敏(パーラム)、田中公平(『サクラ大戦』シリーズ音楽監督)などゲームクリエイターのインタビューが、要所要所に挟まっていることだ。堀井雄二や遠藤雅伸のような「例外」は1980年代から存在していたが、ゲームクリエイターが時代を代表する「発言者」として急速にメディアに露出するようになるのは、この頃からである。この時期を境に、ゲームクリエイター(少なくともその表象)は、いわば「会社員(雇われ職人)」から「アーチスト」へと変身するのである。

ゲーム研究を極める30冊〈1〉/吉田寛|東京大学出版会 (note.com)
ゲーム研究を極める30冊〈3〉/吉田寛|東京大学出版会 (note.com)
ゲーム研究を極める30冊〈4〉/吉田寛|東京大学出版会 (note.com)
ゲーム研究を極める30冊〈5〉/吉田寛|東京大学出版会 (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
