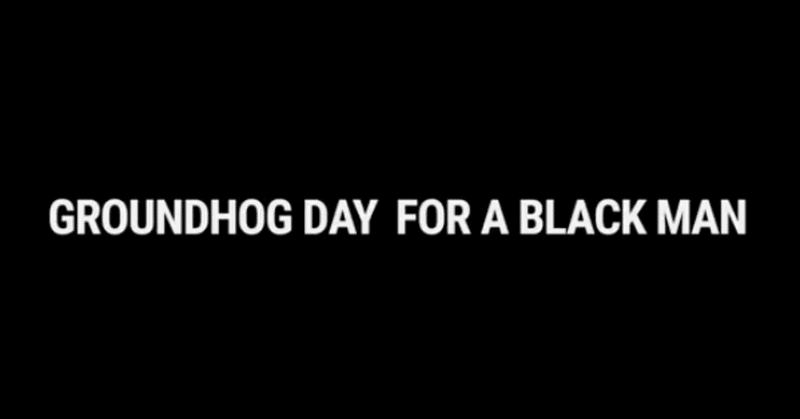
無意識の差別とイギリス教育〜英語記事紹介③〜
Black Lives Matter、この標語がいま世界中を席巻していますね(*1)。知り合いの小学生2人も「ニュースで見た!」と少なからずの関心を寄せていました。
そこで今回はイギリスの放送局、Channel 4による3部作ドキュメンタリー「人種差別を終わらせようとした学校」(The School That Tried to End Racism)を紹介します。(最後に人種差別を描くあるコメディも紹介します!)
とはいえ3部作を違法視聴するわけにもいかないので、このシリーズで話題となったシーンを紹介してくれているこちらの記事をとりあげます。
この記事には4分ほど本編の動画が埋め込まれているので、そちらも紹介したいです。
番組の舞台となっているのは南ロンドンのグレンソーン高等学校です。この生徒の割合としてはBAME(黒人、アジア人、マイノリティ民族系)はちょうど50%に届かないくらいで残りは白人系です。
そしてこの学校で3週間の特別授業がYear 7(小学6年生)向けに開講されました。グレンソーン学校はアメリカ発であるこの特別授業をイギリスにも導入するトライアルに参加し、24人の生徒が志願しました。教師陣はニコラ・ロロック博士とリアノン・ターナー教授の協力のもと特別授業向けの訓練を受けました(*2)。
この授業の目的はもちろん人種差別に対処するためですが、中でも肌の色への意識をあげることが核にあります。もともと人種差別政策として肌の色に目を向けない(colour-blindness)姿勢が重要視されましたが、これは機能しておらず社会の構造的な差別を根絶できないとされています。そのため今回の特別授業はむしろ肌の色という差異に正面から向き合おうとする試みの一環なのです。
この特別授業を通して生徒たちは肌の色に応じて類似グループ(affinity groups)へと分類されます。グループは白人系、黒人系、ブラウン系と全部で3つあり、生徒たちはそれぞれのグループ内で人種(race)について議論します。
授業の最初のタスクとして、無意識なバイアスの有無を測るゲームを行いました。これはハーバード大学教授陣によって開発されたもので、今では広く採用されています。
生徒たちは肯定的・否定的な言葉のリスト、そして黒人・白人の顔を見せられます。そこでまず、否定的な言葉を黒人の顔に、肯定的な言葉を白人の顔に結びつけるよう言われます。しかし途中から今度は、否定的な言葉を白人の顔・肯定的な言葉を黒人の顔へ、と作業をスイッチします。そして前半、後半での所要時間が測定されます。
ほとんどの生徒が自分に人種的なバイアスがないと思っているのに対して結果は全く逆のものでした。24人中18人が白人への好意的なバイアスを見せていたのです。黒人に好意的バイアスを抱くのは2人、バイアス無しとされたのは4人でした。
生徒たちはどのようにこの結果を受け止めたのでしょうか?
参加メンバーの一人であるヘンリーは実験の後、友人のブライトに「先生たちが悪く思う必要はないって言ってたけど、僕はまだ、悪いことをしちゃった気分だよ」と告げていました。

(左がヘンリー、右がブライト)
次に先ほどのグループに戻って人種に関する経験をみんなで議論します。非白人系グループの生徒たちは笑顔を浮かべて、踊ったり歌ったりしながら自らの民族性を話しているのに対して、白人グループはお通夜状態でした。
そこで先生が次のように質問します。
「白人であることが何を意味するか、これまで考えたことはありますか?」
これに対して、ある女子生徒は
「白人ってことはあんま重要じゃないです」
と答えました。
最初のゲーム後に困惑していたヘンリーは、楽しそうな非白人系集団とお通夜状態の自分のグループを比べて、また自問自答していました。
ヘンリー:「あっちのグループは、みんなとっても楽しそう...でもそれは僕たち(白人)がそのグループにいないからなのか、それとも別の理由があるのか....わかんないよ.....」
この後グループは解散して生徒たちは集合し、感想を共有しました。
しかしこのセッションで、ヘンリーは「ちょっとうらやましいよ」と涙ながらに述べ、教室から出て行ってしまいました。

両親の前でヘンリーは少しづつ自分の感情を説明してくれました。
「白人であることが何を意味するのか、これをみんなで話したんだ。でも、すごい変な感じがしたんだ。話してて嫌な気分だったんだ」
「もし選べるなら、僕は友達と一緒に過ごすよ。人種とかじゃなくてね。だってそれってすごいひどいことだもん」
さらにヘンリーは取材陣にこう述べてくれました。
「これまでずっと、人種なんて関係ない。人としてどうあるか、それが大事だって言われてきたんだ」
「人種ではなく、人としてどうあるか」というヘンリーの言葉は、まさにこの特別授業が覆したかったこれまでの政策の影響が露見した瞬間でした。
生徒たちはその後、自身の文化的背景を反映したモノを持ってくるよう言われて再び同じグループに分けられました。しかしこれに対してヘンリーは自分なりの考えがありました。
「類似グループはない方がいいと思うんだ。僕のグループのほとんどみんなが、こっちだと落ち着かないって言うんだ」
そこで教師が白人系の生徒たちに、人種を議論するのがどうしてそれほど難しいのか尋ねると、生徒たちは他の人を怒らせてしまうのではないか不安だったことを認めました。ヘンリーも同様でした。
しかしヘンリーは他のセッションも体験した数日後には、人種の議論をすることがまだ楽になったと述べています。
「人種が僕が思っていたよりももっと大事なことだってのが分かったよ。それに人種がまだ十分に議論されてないってことも分かったよ」
記事自体は、尻切れトンボですが、ここで終わります。皆さんももしNetflix等で配信された際にはぜひ視聴して見てください!
記事内にある本編の紹介動画ではヘンリー以外にも2人、紹介されています。
一人目は白人系とブラウン系のハーフであるファウラです。

彼女は類似グループでどっちに行くべきか分からず、結局白人ではなくマイノリティ側に行ったと両親に説明しました。そして「ハーフだから自分は白人とは別の生き方をしていて、白人系の中だと落ち着かないのよ」と述べました。
両親によると彼女は幼少期から自分のアイデンティティに悩まされており一時はブロンドになりたいとも言っていたようです。
このように類似グループに戸惑いを隠せない生徒たちがいた一方で、そうではなかった子もいました。

黒人系のマカイは自分たちの経験を共有し合うことでいい時間が過ごせた、と母親に告げました。ただ母親がその経験、差別の経験の内容に関して尋ねると「教えたくない」と口を閉ざしてしまいました。
最後に、3年ほど前に話題になったある短編コメディを紹介します!これは黒人への偏見に基づく差別を描いたもので、黒人が日常を普通に生き抜くことの難しさが浮き彫りにされています。ぜひご覧ください!
(Groundhog Day For A Black Man, 2016) (監督: Cynthia Kao)
Black Lives Matterで問題となっているような、人種への偏見に基づく構造的な差別問題に立ち向かうためにこの特別授業が有効であるのかどうか、それはまだ判断はできません。
しかし黄色人種で黒髪のいわゆる「日本人」としてこの番組を見たとき、ヘンリーが体験したような人種という色に立ち向かう困難で苦しい姿勢は、日本社会のマジョリティが身に付けねばならないものであると感じました。
それというのも見た目が外国人だから警察に在留カードを提示するよう呼び止められた、というような体験談を友人からよく聞くからです。
肌の色に目を向けず(colour-blind)、能力のみを評価軸とすることで平等な社会が実現しているフリをした社会は、偏見に基づく構造的な差別そして差別の歴史を明らかにする可能性に閉ざされている。そのように考えさせられました。
(文責: D)
*1: Black Lives Matterの始まりは2020年5月25日に起きた白人警官(当時)デレク・ショービンがアフリカ系アメリカ人のジョージ・フロイドの首を過度に膝で圧迫して殺害した事件ではありません。この標語自体は2012年に起きたアフリカ系アメリカ人のトライヴォン・マーティンが射殺されるも、2013年の裁判で発砲したジョージ・ジマーマンが無罪判決を言い渡されたことをきっかけとしています。
https://blacklivesmatter.com/about/
*2: ニコラ・ロロック博士(Dr. Nicola Rollock)はロンドン大学ゴールドスミスカレッジに所属しており人種関係の研究をしています。リアノン・ターナー教授(Professor Rhiannon Turner)はクイーンズ大学ベルファストに在籍しています。
当団体は、学生メンバーの自費と会報の売上によって運営されています。更に活動の幅を広げるには、みなさまからの応援が不可欠です。 あなたの思いを、未来の人文学のために。 ワンクリック善行、やってます。
